| 佐屋街道 熱田伝馬町追分-(約24km)-佐屋宿 | ||
| 2022年10月20日(木) 晴れ | ||
| 佐屋(さや)街道 天保4年(1647年)佐屋街道の宿場は、岩塚 / 万場 / 神守 / 佐屋 があった。 熱田伝馬町追分~金山新橋交差点の南西の角にある佐屋街道道標までは、美濃路との重複区間になる。 |
||
 |
金山新橋交差点の南西角に文政4年(1821年)造立の佐屋(さや)街道道標がある。「東 右 なこや 木曽 海道」「右 宮海道 左 なこや道」 |
|
| 佐屋街道道標 | ||
 |
 |
佐屋街道道標から西に進むと、すぐに堀川に架かる尾頭橋(おとうばし)を渡る。堀川は名古屋城築城のために造られた運河で、熱田の七里渡し付近へ流れている。 |
| 朝日を浴びて伸びる影 | 津島街道一里塚石標 | |
 |
津島街道一里塚石標から10分ほどすると、左手の中川福祉会館前に、佐屋街道石標 / 案内板 がある。 |
|
| 佐屋街道石標 | ||
|
中川福祉会館5分足らずの長良橋東交差点の手前左手に、明治天皇御駐蹕(ちゅうひつ)之所碑がある。 |
||
 |
 |
豊国通6交差点から15分ほどの左手に、八幡社 / 隣接して光明寺 がある。神社の向かい側に岩塚宿の本陣があった。 |
| 八幡社 | 光明寺 | |
 |
すぐに庄内川の堤防に突き当たったところは万場の渡し跡で、往時は渡し船で渡っていた。 |
|
| 庄内川の河川敷 | ||
 |
 |
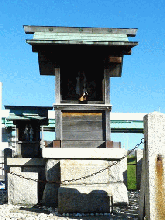 |
| 庄内川 | 秋葉神社 | |
| 迂回して庄内川に架かる万場大橋を渡り、すぐに長い階段を下る。庄内川方向に道なりに進むと、すぐ左手の土手に秋葉神社 / 万場宿案内板 がある。万場宿は万場の渡しを挟み、岩塚宿と一宿と見なされ、月の上半月を万場宿
/ 下半月を岩塚宿 が交代で人馬継立の役務を行った。 |
||
|
[迷い道] |
||
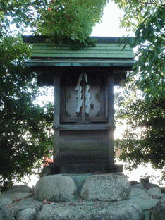 |
万場宿の町並みを進む。宿場の規模が頭に残り、宿場の長さを誤っている。また久々の街道歩きで、勘が鈍っていたことも要因。 |
|
| 天神社 | ||
 |
 |
万場宿を進むと、右手に覚王院観音寺(ちちの観音) / 隣接して国玉神社・八剣社 がある。覚王院観音寺は境内にある乳の木の実を食べたら、乳の出が良くなったと云われている。国玉神社は尾張大国霊神社より勧請したと云われ、「延喜式神名帳」に記載されている式内社。 |
| 覚王院観音寺 | 国玉神社・八剣社 | |
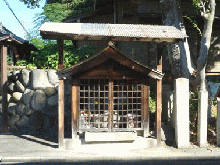 |
 |
 |
| 不明の祠 | 常夜灯 | 光圓寺山門 |
 |
 |
国玉神社・八剣社の角に祠があり、街道は大きく右に曲がる。すぐ左手に大きな常夜灯が見え、 光圓寺がある。山門は織田信長と斎藤道三が会見した聖徳寺から移築したもの。 |
| 光圓寺本堂 | 光圓寺三重塔 | |
 |
 |
5分ほどの万場交差点を渡って北西へと進むと、すぐ右手に浅間神社がある。 |
| 浅間神社 | ||
 |
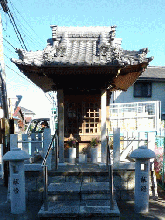 |
浅間神社から佐屋街道は左折する。道なりに新川に平行する道を北に進み、新川に架かる砂子橋を渡る。新川は川幅のあり、 |
| 十二所神社鳥居 | 地蔵堂 | |
 |
 |
 |
| 常夜燈 / 題目塔 | 不明の祠 | 稲荷社 |
 |
十字路を佐屋街道は左折する。街道を西へと進むと、すぐ右手に常夜燈と南無妙法蓮華経題目塔 / すぐ右手に不明の祠 / すぐ右手に稲荷社 / 佐屋街道 従是馬嶋明眼院道 標識 と続く。祠は道路工事のため、覗き込むことができなかった。明眼院は尾張国海東郡馬嶋村(現:愛知県海部郡大治町)にあり、日本最古の眼科専門の医療施設として知られる。 | |
| 佐屋街道 従是馬嶋明眼院道 標識 | ||
| すぐに東名阪自動車道を潜る。 |
||
 |
佐屋街道に戻り、しばらくすると狐海道東交差点に出る。往時のこの付近は家一軒ない淋しい所で、狐に化かされたという伝承がある。狐海道東交差点を左折して北西に進む。 |
|
| 黒板塀の屋敷 | ||
 |
秋竹西橋から30分ほどの神守町交差点を過ぎると、すぐ右手に神守の一里塚がある。佐屋街道で残る唯一の一里塚であるが、右側しか残っていない。椋(むく)の木が植えられている。 | |
| 神守の一里塚 | ||
| 5分足らずの神守町下町交差点を右折すると神守宿となる。 |
||
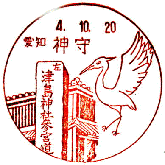 |
神守町下町交差点 |
|
| 神守郵便局風景印 | ||