| 宇治 | |
 |
|
| 宇治川 | |
| 宇治の地は、応神天皇が離宮(桐原日桁宮)を造営したところである。京都と奈良を結ぶ交通の要所であり、琵琶湖から宇治川や木津川に木材を運ぶ水運が盛んだった。 |
|
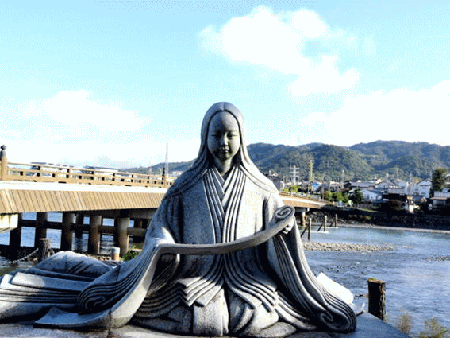 |
|
| 宇治橋 / 紫式部像 | |
| 源氏物語五四帖の最後の宇治十帖の舞台であり、主人公の光源氏が亡くなった後の恋物語である。 |
|
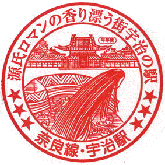 |
 |
| JR奈良線・宇治駅のスタンプは、源氏ロマンの香り漂う街 宇治の駅 / 平等院 / 十二単 の図柄になっている。宇治駅南口の東側、観光案内所前に茶壺ポストがある。なお、宇治で最初にお茶の栽培が始まったのは鎌倉時代である。 |
|
 |
|
| 宇治橋 | |
| 駅前の15号線を北東に進むと、10分足らずのところに宇治橋がある。 |
|
 |
|
| 宇治神社 | |
| 宇治橋を渡り、東詰交差点を右折する。すぐのY字路を左方向に“さわらびの道”を道なりに進む。道は登り坂となり、右手に宇治神社がある。 | |
 |
|
| 宇治上神社拝殿(国宝) | |
| さらに坂を登ると、右手に宇治上神社がある。 朝日山の山裾にある宇治上神社と宇治神社は対をなす式内社で、応神天皇が離宮(桐原日桁宮)を造営したところである。 平安時代後期造営の宇治上神社本殿(国宝)は、神社建築で日本最古とされる。拝殿(国宝)は鎌倉時代前期の造営、寝殿造りになっている。 |
|
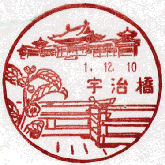 |
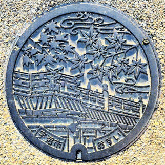 |
|
宇治橋まで戻る。宇治橋西詰交差点を右折して平等院参道を進むと、すぐ左手に宇治橋郵便局 がある。風景印は、平等院 / 茶の花 / 宇治橋 の図柄になっている。 |
|
 |
|
| 平等院表門 | |
 |
|
| 鳳凰堂(国宝) | |
 |
|
| 観音堂(重文) | |
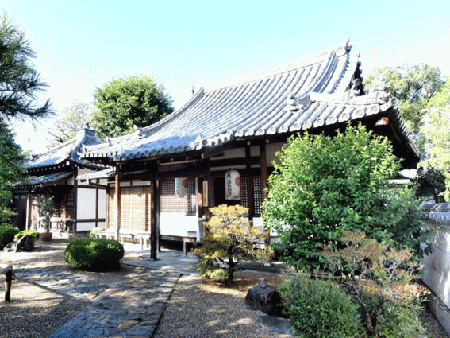 |
|
| 最勝院不動堂 | |
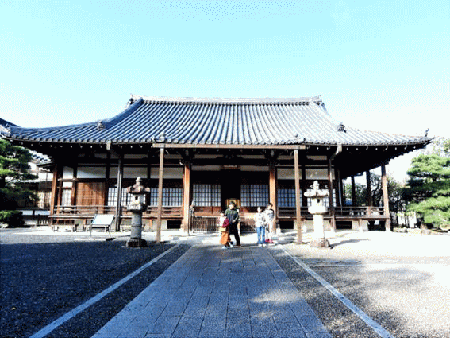 |
|
| 浄土院 | |
| 宇治は、平安時代初期から貴族の別荘があったところである。 陽成天皇→宇多天皇→朱雀天皇と渡り、離宮・宇治院となった。さらに宇多天皇の孫・源重信を経て、長徳4年(998年)摂政・藤原道長の別荘・宇治殿となった。 鳳凰堂(ほうおうどう / 国宝)は、天喜元年(1053年)に建立された阿弥陀堂である。往時は、阿弥陀堂あるいは御堂と呼ばれていた。 源氏物語が完成したと推測される寛弘5年(1008年)には、未だ阿弥陀堂はなかった。 |
|