| 紫式部墓所 / 紫式部供養塔 | |
| 藤原為時の次女・藤式部は、寛弘8年(1012年)頃まで宮中で奉仕したと云われている。藤式部が何所で何時亡くなったのか解っていない。源氏物語が評価されていたのに、解っていないのは不思議なことである。 寛仁3年(1019年)頃に死去したとされるが、誕生年が天禄元年(970年)の場合は49歳 / 天延元年(973年)の場合は46歳 / 天元元年(978年)の場合は41歳 で亡くなったことになる。 藤式部の娘・大弐三位は長和6年(1017年)18歳頃に母の後を継ぎ、彰子(上東門院)に女房として出仕している。 |
|
 |
|
| 京都市営地下鉄烏丸線・北大路駅の南側を通る北大路通を西に進む。すぐに北大路通は南西に曲がる。堀川北大路交差点を左折して堀川通を南に進むと、すぐ右手に小野篁(おのの たかむら) / 墓紫式部 墓所入口がある。北大路駅から10分ほどである。 入口左側に小野篁卿墓 石柱 / 右側に紫式部墓所と彫られた自然石がある。 |
|
 |
 |
| 短い参道を進むと、右手に小野篁墓 石柱 / 奥の塚に五輪塔 / 傍らに小野篁の顕彰碑がある。小野篁(802年〜853年)は、平安時代初期の公卿 / 文人。 | |
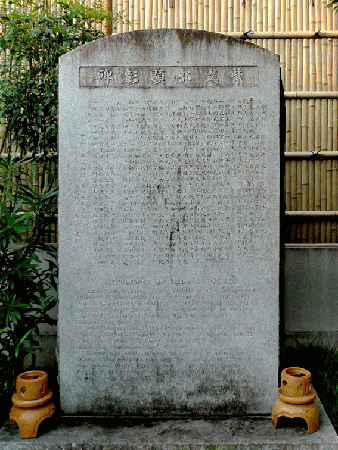 |
|
 |
|
 |
|
| 次いで左手に平成元年(1989年)造立の紫式部顕彰碑 / 右手に紫式部墓 石柱 / 奥の塚に高さ約80cmほどの五輪塔 がある。 |
|
|
この地は、雲林(うりん)院の末院・天長元年(824年)創建と云われる白毫(びやくごう)院があったところ。紫式部の墓に関しては、正平年間(1346年〜1370年)に編纂された河海抄に記載されたのが初見である。 |
|
 |
|
| 紫式部墓所入口から堀川通を北に進む。すぐの堀川北大路交差点を左折して北大路通を西に進む。15分ほどの千本北大路交差点を左折して千本通を南に進むと、10分ほどの右手に寛仁元年(1017年)創建の引接(いんじょう)寺がある。閻魔大王を祀っていることから、千本ゑんま堂で知られている。引接とは、仏が生きる者を浄土に往生させることをいう。 |
|
 |
|
 |
|
|
本堂右手横の回廊を奥に進むと、右方向に紫式部像と高さ6mの紫式部供養塔(重文)がある。 |
|