| 石光山・石山寺 |
|
藤原為時の次女は寛弘2年(1006年)頃に、一条天皇中宮の彰子(藤原道長の長女 / 後の上東門院)の女房(家庭教師)として仕える。寛弘8年(1012年)頃まで奉仕したと云われている。
当時の慣習から、藤式部と呼ばれていたと云われている。宮中の女房は、氏と父や兄弟の官職名を組み合わせて呼ばれていた。
中宮の彰子が新しい読物を読みたいとのことで、藤式部は石山寺に7日間詣でて構想を練ったと云われている。
藤式部は宮仕えをしながら、藤原道長の支援の下で物語を完成させたと云われている。支援=紙で、往時の紙は貴重品であった。 寛弘5年(1008年)には完成していたと推測されている。 |
|
 |
| 石坐神社鳥居 |
|
 |
| 石坐神社拝殿 |
|
| 一条院から石山寺の行程は、越前国府の往復に歩いた行程だったと思われる。大津から江戸時代に整備された旧東海道を進む。瀬田唐橋までの街道沿いには、天智天皇(626年〜672年)の頃創建と云われる石坐神社がある。社殿は文永3年(1266年)に建立されたもの。御霊殿山の大岩上に祠があったことが、石坐の由来となっている。 |
|
 |
| 瀬田唐橋 |
|
 |
| 琵琶湖遠望 |
|
瀬田川に架かる瀬田唐橋から琵琶湖が見える。瀬田唐橋は琵琶湖から流れ出る瀬田川に架かる橋。奈良時代からの橋で、瀬田川に架かる唯一の橋として交通の要衝であった。鎌倉時代に架け替えられたとき唐様になったため、唐橋と呼ばれる様になったと云われている。
瀬田唐橋は短い唐橋を渡ると中州で一旦途切れ、再度長い唐橋を渡る。 |
|
 |
| 石山寺駅ロータリー |
|
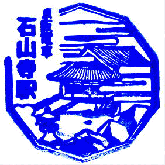 |
唐橋西詰交差点を右折して422号線を南へ進む。15分ほどすると、右手に 京阪電鉄・石山寺駅がある。 |
| 京阪電鉄・石山寺駅スタンプ |
|
 |
| 朗澄大徳ゆかりの庭園 |
|
 |
10分ほどすると、右手に朗澄(ろうちょう)大徳ゆかりの庭園がある。朗澄大徳は鎌倉時代の石山寺屈指の名僧で、中興の祖とされる。朗澄大徳ゆかりの庭園は、朗澄大徳朗澄律師が死後に鬼の形になって現れたところと云われている。 |
| 朗澄大徳像 |
|
 |
| 東大門(重文) |
|
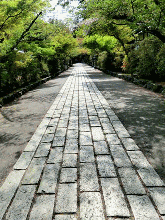 |
 |
| 参道 |
珪灰石 |
|
 |
| 本堂 |
|
 |
| 多宝塔(国宝) |
|
| 朗澄大徳ゆかりの庭園からすぐの右手に、天平19年(747年)創建の石光山・石山寺がある。琵琶湖の南端近くに位置、琵琶湖から流れ出る瀬田川の左岸に位置する。永長元年(1096年)再建された本堂(国宝)は珪灰石(国の天然記念物)という巨大な岩盤の上にあり、これが寺名の由来にもなっている。石山寺は兵火に遭わなかったため、東大門(重文)や源頼朝の寄進と云われている建久5年(1194年)建立の多宝塔(国宝)なども残っている。西国三十三所観音第13番札所
/ 江州三十三観音1番札所 / 近江三十三観音3番札所 となっている。蜻蛉日記 / 更級日記 / 枕草子 などにも登場する。 |
|
 |
月見亭 / 芭蕉庵 からは、瀬田川が眺望できる。
元禄2年(1689年)に奥の細道を終えた芭蕉は、翌年に京阪電鉄・石山寺駅の西にあった幻住庵(げんじゅうあん)に3ヶ月半滞在した。石山寺には度々訪れ、「石山や石にたばしる霰かな」と詠んだ。
|
| 月見亭 / 芭蕉庵 |
|
 |
| 瀬田川眺望 |
|
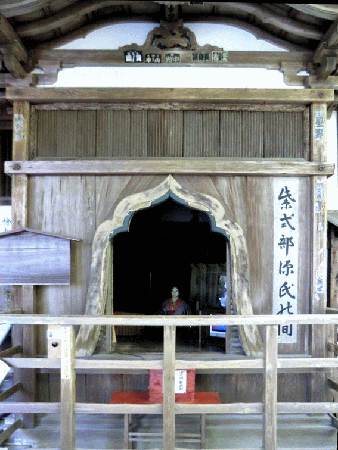 |
| 紫式部源氏の間 |
|
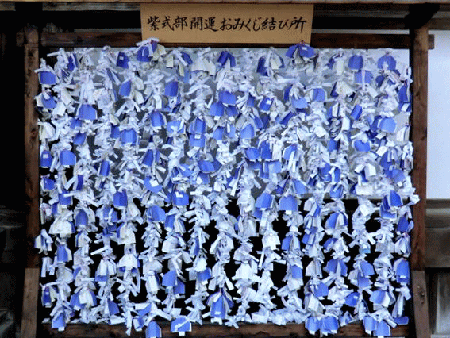 |
| 紫式部開運おみくじ結び所 |
|
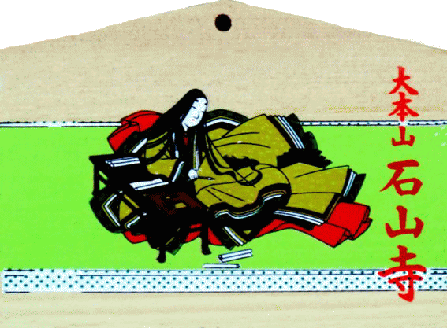 |
| 石山寺絵馬 |
|
本堂内に紫式部源氏の間がある。ただし藤式部が石山寺に7日間詣でたころの本堂は、承暦2年(1078年)落雷によって消失している。
現本堂(国宝)は、 永長元年(1096年)の再建である。源氏物語が完成していたと推測されている寛弘5年(1008年)以降である。 |
|
 |