| 長崎街道 木屋瀬宿 |
|
| 長崎街道・木屋瀬宿 |
|
小倉常盤橋から2番目の宿場で、東構口(消滅)から西構口(現存)まで約1100mにあった。構口(かまえぐち)は宿場の門にあたるところ。道路と直角に石垣を組み、その上に白壁の練塀を築いたもの。構口は方位に関わらず、上り方面を東 / 下り方面を西 としていた。本陣付近で「くの字」に曲がり、家並みは“のこぎり歯”状に建てられていた。これは“矢止め”と呼ばれ、敵が攻めてきたときに隠れたり不意をついて攻撃したりするためと云われている。宿場のほぼ中間に、代官所
/ 本陣 / 脇本陣 / 郡屋 / 人馬継所 があった。筑前国 / 筑後国 / 肥前国 / 肥後国 / 薩摩国 の参勤交代の大名、多くの旅人が利用した。旅籠は14〜15軒あり、ドイツ人医師・シーボルトやケッペル
/ 測量学者・伊能忠敬 / 白象 が泊まった記録がある。赤間街道の起点でもあり、遠賀川の水運でも栄えた。
|
|
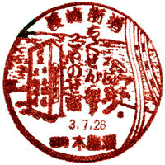 |
筑豊電鉄・木屋瀬駅で下車する。下りホームの南側を通る道を東に進むと、すぐの右手に木屋瀬郵便局がある。風景印は、追分道標 / 遠賀川 / 宿場踊り
の図柄になっている。 |
| 木屋瀬郵便局風景印 |
|
 |
 |
下りホームの南側を通る道を西に、すぐの交差点から右方向に進む。5分足らずの左手に須賀神社がある。永享年間(1429年〜1441年)に勧請、江戸時代までは祇園社と称していた。
|
| 須賀神社鳥居 |
須賀神社社殿 |
|
 |
 |
すぐ右手に天正10年(1582年)妙奇庵を結んだのが始まりの西元寺がある。 |
| 西元寺山門 |
西元寺本堂 |
|
|
西元寺からすぐに長崎街道と交差する。東構口はここから北に約300mの岡森用水路の傍らにあったと云われている。すぐ北側の変則十字路辺りから西構口まで散策する。
|
|
 |
 |
 |
| 町並み |
永源寺楼門 |
永源寺本堂 |
|
|
変則十字路から永源寺小路を西に進むと、突き当りに永源寺がある。かつて金剛寺として北九州市八幡西区金剛にあったが、兵火により大栄3年(1523年)現地に移転して永源寺に改称した。
|
|
 |
 |
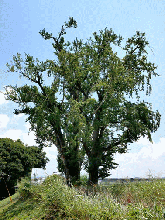 |
| 町並み |
長崎街道 木屋瀬宿プレート |
大銀杏 |
|
| 変則十字路から南に進み、すぐの十字路近くに“長崎街道 木屋瀬宿プレート”が道路に埋め込まれている。十字路を右折して西に進むと、左前方に往時は舟着き場の目印だった大銀杏がある。 |
|
 |
 |
 |
| 町並み |
問屋場跡 / 正面:木屋瀬宿記念館 |
里程標「福岡 十三里三十四町二十五間」 |
|
| 十字路まで戻り宿場通りを進むと、5分足らずで左手に問屋場跡がある。長崎街道は“くの字”に曲がり、正面に長崎街道木屋瀬宿記念館 / 里程標「福岡
十三里三十四町二十五間」 がある。福岡まで52.3kmである。 |
|
 |
 |
すぐ左手に木屋瀬でも古くからの寺と云われる長徳寺がある。安元元年(1175年)頃は天台宗だったが、嘉禎元年(1235年)浄土宗に代った。慶応2年(1866年)小倉藩騒動のとき、佐賀藩の宿陣となった。 |
| 長徳寺山門 |
長徳寺本堂 |
|
 |
 |
 |
| 船庄屋跡(梅本家) |
愛宕山護国院 |
旧高崎家(伊馬春部生家) |
|
 |
 |
 |
| 村庄屋跡(松尾家) |
西構口跡(西側) |
西構口跡(東側) |
|
| すぐの交差点を越えると、右手に船庄屋跡(梅本家) / 右手に明応2年(1493年)北九州市八幡西区香月の聖福寺の末寺として創建された愛宕山護国院/
右手に旧高崎家(伊馬春部生家) / 右手に村庄屋跡(松尾家) / 西構口跡 と続く。 |
|
 |
西構口の南西側に追分道標(複製)があり、赤間街道の起点になっている。「従是 右 赤間道 左 飯塚道」と彫られている。元文3年(1738年)造立の道標は、木屋瀬宿記念館に展示されている。赤間道は渡し舟で遠賀川を渡り、植木宿〜猿田峠〜吉留(よしとめ)を経て赤間宿に至る。
|
| 追分道標(複製) |
|
 |
 |
 |
| 興玉神社 |
73号線手前からの遠賀川 |
中島橋からの遠賀川 |
|
|
赤間道を西に進むと、すぐ右手に正徳5年(1715年)創建の興玉神社がある。旅の安全を守る猿田彦神が祀られている。 突き当たる遠賀川の土手を越えて川原に降りると、渡し場があった。73号線は交通量が多いため、河川敷には降りていない。
|
|
 |