| ディーゼル機関車 |
|
 |
| DD13 11(新宿駅) |
|
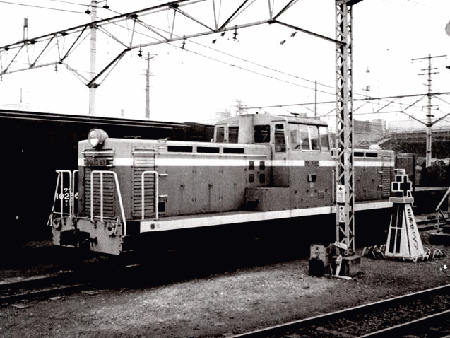 |
| DD13 32(新宿貨物駅) |
|
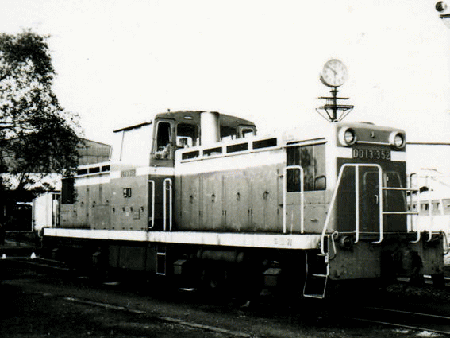 |
| DD13 352(吹田機関区) |
|
 |
| 入換作業中の前照灯2灯のDD13後期型(新小岩操車場) |
|
DD13形は、貨物の入換作業を主目的として開発された液体式ディーゼル機関車。昭和33年(1958年)〜昭和42年(1967年)に416両が製造された。DD13形の登場までは、明治 / 大正 / 昭和のから戦前 に製造された蒸気機関車が使われていた。DD13形の登場によって、山手線でも見られた蒸気機関車による入れ替えは見られなくなった。
110号機までは、前照灯が前後に1個ずつ設置されていた。新宿駅ホームに停車中の初期型DD13 11は茶色に黄色帯の旧塗装 / 新宿貨物駅の初期型DD13 32は新塗装 になっている。 |
|
 |
| DE10 64(佐倉機関区) |
|
 |
| DE10牽引の普通客車列車(内房線) |
|
|
DE10形は、昭和41年(1966年)〜昭和53年(1978年)に708両製造された液体式ディーゼル機関車。ローカル線の貨客列車牽引 / 貨物の入換作業
を主目的として開発され、日本各地のローカル線で蒸気機関車を置き換え動力近代化を促進した。
製造数708両は、国鉄のディーゼル機関車としては最も多く製造された形式である。
|
|
 |
| 入れ替え作業中のDE11(吹田機関区) |
|
| DE11形は、昭和43年(1968年)〜昭和54年(1979年)に116両製造された重入換専用液体式ディーゼル機関車。1960年代後半からの高度経済成長により、鉄道貨物輸送量は増大した。DD13形では牽引力や制動力が不足、引き続き蒸気機関車を使用せざるを得ない状況となっていた。これらを解消したDE10形が、さらにこれを基に入換用途に特化したDE11形が製造された。
|
|
 |
| 旧塗装のDF50 504(吹田機関区) |
|
DF50形は、昭和32年(1957年)〜昭和38年(1963年)に138両製造された電気式ディーゼル機関車。旅客列車 / 貨物列車 とも運用が可能な最初のディーゼル機関車で、特急列車から貨物列車まで幅広く運用された。暖房用のボイラー(蒸気発生装置)を搭載している。蒸気機関車牽引の貨物列車列車の置き換えには性能的に不足していた。
昭和60年(1985年)までに全車廃車になった。 |
|
 |
| DD51 18(吹田機関区) |
|
 |
| DD51牽引の急行・うち房(両国駅地平ホーム) |
|
 |
| DD51 804牽引の急行・うち房 |
|
| DD51形は、昭和37年(1962年)〜昭和53年(1978年)に649両が製造された液体式ディーゼル機関車。昭和32年(1957年)から運用されたDF50形は、幹線では出力不足であった。DD51は速度面では旅客列車用蒸気機関車C61形を、牽引力では貨物列車用蒸気機関車D51形を上回る性能になっている。 |
|
 |