| 戦後の貨物列車用直流電気機関車 |
|
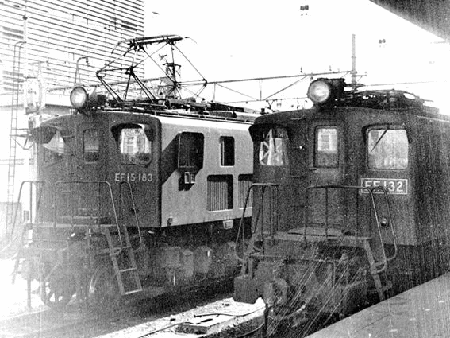 |
| EF15 183 / EF13 2(新宿駅) |
|
EF15形は、昭和22年(1947年)〜昭和33年(1958年)に202両が製造された貨物列車牽引用の直流電気機関車。旅客用のEF58形とは台車や電気機器など主要部品が共通化された標準型。直流電化の東海道本線 / 山陽本線 / 東北本線 / 高崎線 / 上越線などで貨物列車を牽引した。昭和61年(1986年)春のダイヤ改正でEF60形に置き換えられ、秋には紀勢本線の貨物列車が廃止されて営業運転が終了した。158号機はJR西日本)に引き継がれて車籍を残したまま保存されていたが、平成23年(2011年)に車籍抹消された。
保存機は全て昭和27年(1952年)以降に製造された改良型であるが、初期型の形態を残すEF16 28(旧EF15 31)が保存されている。
|
|
 |
| EF16
28 |
|
|
[参考]キヤノン・ダイヤル35 & オリンパス・ペンFで撮影した画像ではなく、デジタルカメラである。
EF16形は昭和26年(1951年)〜昭和33年(1958年)にEF15形から24両が改造された貨物列車用直流用電気機関車である。勾配区間に対応するため、回生ブレーキを搭載している。国鉄の電気機関車で初回生ブレーキ形式であ る。EF64形1000番台に置き換えられ、昭和57年(1982年)までに全車廃車になった。
水上駅近くの道の駅・水紀行館に、EF16唯一の28号機が保存されている。EF15 31から改造された。屋根はあるが保存状態はよくなく、錆止めの様な塗装になっている。
|
|
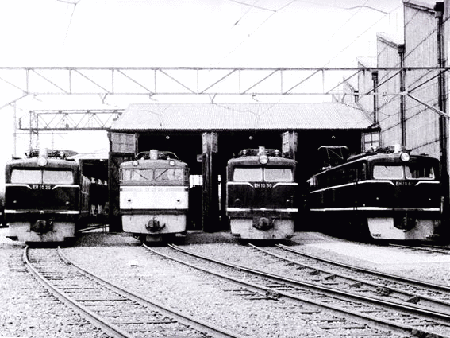 |
| EH10 25 / EF60 / EH10 56 / EH10 69(吹田第二機関区) |
|
 |
| EH10 60(吹田第二機関区) |
|
| EH10形は、昭和29年(1954年)〜昭和32年(1957年)に64両が製造された8動軸式の貨物用直流電気機関車。東海道本線 / 山陽本線
で運用された。昭和34年(1959年)から東京・汐留駅〜大阪・梅田駅間で運行開始されたコンテナ特急貨物列車“たから号”でも活躍した。昭和57年(1982年)までに全車廃車になった。 |
|
 |
| 前照灯が異なるEF60 (吹田第二機関区) |
|
|
EF60形は昭和35年(1960年)〜昭和39年(1964年)に143両が製造された貨物用直流用電気機関車。昭和39年(1964年)製造車からは、前照灯が2灯シールドビームになっている。500番台は、昭和38年(1963年)〜昭和39年(1964年)に20系客車寝台特急(ブルートレイン)牽引のEF58形置換え用として14両が製造された。令和元年(2019年)までに全車廃車になった。
|
|
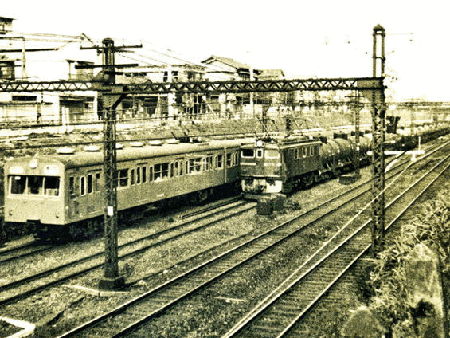 |
| ED61形(市ヶ谷駅付近) |
|
|
ED61形は、昭和33年(1958年)〜昭和34年(1959年)に18両が製造された貨物列車用直流用電気機関車である。急勾配が連続する中央本線・八王子駅〜甲府駅間の輸送力増強
/ 私鉄買収機関車や大正時代の輸入機関車などの置き換える のために製造された。基本的にED60形と同じ構造で、急勾配区間を走行するため電力回生ブレーキが装備されている。昭和49年(1974年)〜昭和54年(1979年)に18両全車がED62形に改造され、形式消滅した。ED62は平成14年(2002年)までに廃車となった。
|
|
 |