| 戦前の貨物列車用直流電気機関車 |
|
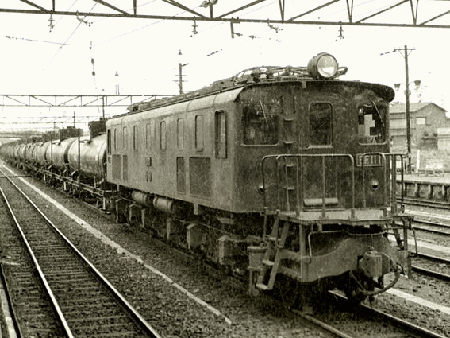 |
| EF11 1(拝島駅) |
|
| EF11形は、昭和10年(1935年)〜昭和12年(1937年)に4両が製造された貨物列車用直流電気機関車。1号機〜3号機は角型の車体になっている。昭和49年(1974年)全車廃車されたが、保存機はない。 |
|
 |
| EF13 5(新宿駅) |
|
EF13形は、昭和19年(1944年)〜昭和22年(1947年)に31両が製造された貨物列車用直流電気機関車。第二次世界大戦中に製造が始まったため、戦時設計の凸型車体で登場した。昭和28年(1953年)〜昭和32年(1957年)凸型車体を箱形車体に載せ換えられた。これはEF58形の箱形車体を半流線型車体に載せ換えたときに余剰になったもの流用である。昭和54年(1979年)までに全機廃車されたが、保存機は残っていない。
画像は客車を連結してホームに停車中のEF13 5。新宿駅発の中距離列車にも使用され、大菩薩峠に登ったときに利用している。暖房が必要な時期には、蒸気暖房用の蒸気を発生させるためのボイラーを搭載した暖房車が連結されていた。 |
|
 |
| EF14 2(吹田機関区) |
|
| EF14形は昭和3年(1928年)〜昭和6年(1931年)に9両が製造された旅客用直流電気機関車EF52形を、昭和19年(1944年)に1号機
/ 昭和20年(1945年)に2号機 が貨物用に改造された直流電気機関車。昭和35年(1960年)吹田機関区に配置され、大阪駅構内の入換機となった。昭和49年(1974年)に廃車となった。 |
|
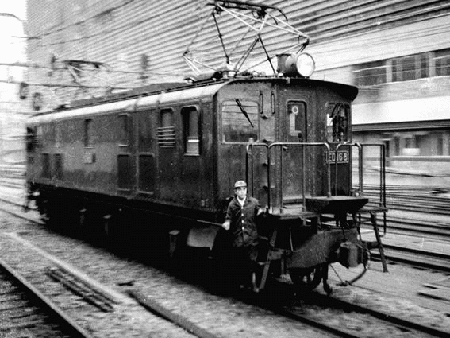 |
| ED16(新宿) |
|
ED16形は、昭和6年(1931年)に18両製造された直流電気機関車。水上機関区と甲府機関区に配置され、上越線 / 中央本線 で旅客列車 / 貨物列車 に運用された。昭和45年(1970年)18両全機が立川機関区に集められ、奥多摩駅〜浜川崎駅間などで石灰石列車を牽引していた。青梅線の改良によりEF15形やEF64形が入線可能になり、置き換えられた。昭和59年(1984年)全車廃車となった。旧型電気機関車として53年間も運用された。
背景は、昭和39年(1964年)開業の新宿ステーションビル。 |
|
 |
交流電気機関車ED91 11 / 直流電気機関車ED17 21
(作並機関区) |
|
| 直流電気機関車ED17 21は、大正14年(1925年)東海道本線・国府津駅迄の電化に際しイギリスから輸入されたED52形が種車。昭和6年(1931年)から昭和10年(1935年)中央本線・新宿駅〜甲府駅用として、歯車比を変更してED18形(初代)に改称する。さらに 昭和24年(1949年)〜昭和25年(1950年)装備改造により、ED17形に編入される。 |
|
 |
|
|
昭和45年(1970年)は、安保闘争 / 鉄道のスト があった頃である。千葉鉄道管理局は動労が強いところで、スローガンがペンキで書かれた機関車や電車が走っていた。
画像の状態がすこぶる悪く、形式は判別できない。
|
|
 |