| 戦後の旅客列車用直流電気機関車 | |
 |
|
| 113系 / EF58 122(東京駅) | |
| EF58形は、旅客列車用直流電気機関車である。 昭和27年(1952年)〜昭和33年(1958年)に自動式のSGを搭載するため車体が延長され、半流線型となった。 機器類の多くは貨物用のEF15形と共通化されていた。 1980年代にほとんどが営業運転から撤退、令和5年(2023年)お召し機の61号機が除籍されたことにより形式消滅した。 |
|
 |
|
| EF13 5(新宿駅) | |
| EF58形の箱型車体は、昭和28年(1953年)〜昭和32年(1957年)に後期型と同じ半流線型車体となり仕様も統一された。 |
|
 |
|
| 東京駅に到着する夜行急行列車牽引のEF58 113 | |
 |
|
| 東京駅に到着の夜行急行列車 | |
 |
|
| 後部に連結されたEF58 132 / 中線の11番線(東京駅) | |
 |
|
| 東京機関区 | |
| 東京駅で見られたEF58は、夜行列車や荷物列車牽引が多かった。 平成3年(1991年)東北新幹線は東京駅に乗り入れるが、その工事のとき中線は撤去された。 |
|
 |
|
| EF58重連(日暮里駅付近) | |
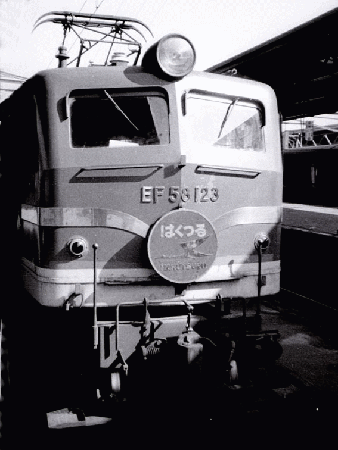 |
|
| F58 123(上野駅) | |
| 東京駅発着のブルートレインはEF60 500番台であったが、上野駅発着の はくつる はEF58 / 常磐線経由の ゆうづる は、EF80形交直流電気機関車 牽引だった。 | |
 |
|
| EF58 153(上野駅) | |
| はくつるが到着するとEF58を切り離して機回しして後部に連結、尾久機関区に回送していた。 |
|
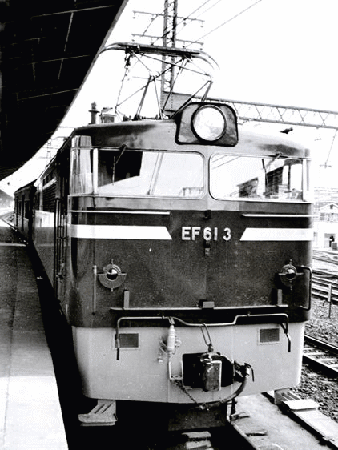 |
|
| EF61 3 | |
 |
|
| EF61 2牽引の荷物列車(東京駅) | |
|
EF61形はEF58形の後継として設計され、昭和36年(1961年)から製造された旅客列車用直流電気機関車である。EF60形の1次形をベースにしており、冬期の客車牽引に対応するSG1B形暖房用蒸気発生装置を搭載している。 |
|