| 戦前の旅客列車用直流電気機関車 |
|
 |
|
| EF53 16(上野駅) | |
 |
|
| EF53 16(上野駅) | |
| EF53形は、昭和7年(1932年)〜昭和9年(1934年)に19両が製造された旅客列車用直流電気機関車である。 EF52形をベースにしており、省形電気機関車の完成形とされる。 昭和38年(1963年)山陽本線・瀬野駅〜八本松駅間(瀬野八)の急勾配区間の補助機関車を無煙化するとき改造され、EF59形に改番された。最後まで残っていた3両が昭和43年(1968年)に改造され、EF53形は形式消滅した。 |
|
 |
|
| EF56 7(上野駅) | |
| EF56形は、昭和12年(1937年)〜昭和15年(1940年)に12両が製造された旅客列車用直流電気機関車である。 EF53形をベースにしており、暖房用の蒸気発生装置(SG)を搭載している。冬季の暖房車の連結を不要とした。 昭和50年(1975年)に全車廃車された。 |
|
 |
|
| EF57 1(上野駅) | |
| EF57形電気機関車は、昭和15年(1940年)〜昭和18年(1943年)に15両が製造された旅客列車用直流電気機関車である。 EF57 1号機はEF56形13号機として完成する予定の車体に、強力な主電動機を搭載した。 |
|
 |
|
| EF57 6(上野駅) | |
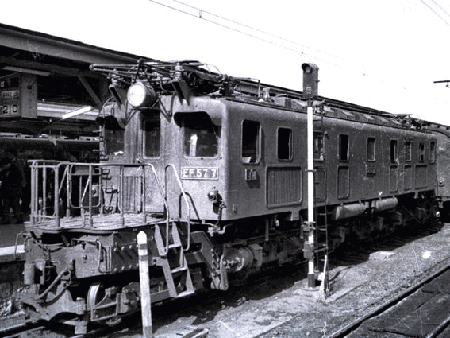 |
|
| EF57 7(上野駅) | |
|
EF57 2号機以降は、屋上のパンタグラフ2基を車体両端一杯に寄せている。 |
|