| 総武本線 新小岩機関区
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
| 新小岩機関区は明治27年(1894年)錦糸町駅に開設された総武鉄道本所機関庫が始まり。明治40年(1907年)鉄道国有法により国有化された後、昭和4年(1929年)に新小岩操車場に移転した。 |
|
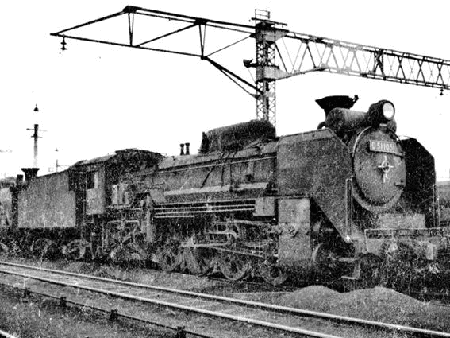 |
| D51 1051 |
|
 |
| 新小岩操車場を爆走するD51 507牽引の貨物列車 |
|
| 新金線を介して他線区と接続、貨物列車運行拠点として貨物列車牽引の主力・D51形蒸気機関車も配置されていた。
|
|
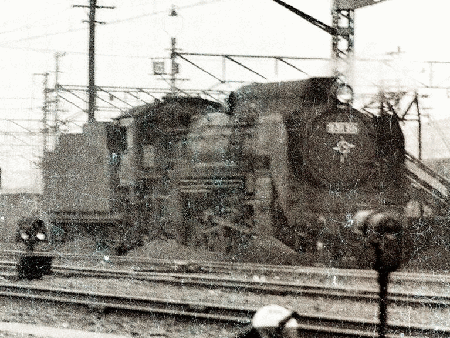 |
|
D51形蒸気機関車は主に貨物輸送のために第二次世界大戦中に大量生産された。国鉄所属数は1115両で、ラストナンバーは1161である。ディーゼル機関車 / 電気機関車 など日本の機関車1形式の両数で最大となっている。
初期製造の95両は、煙突とボイラー上の砂箱の間に給水加熱器を置いて一体化されていた。形状から「ナメクジ」 / 汽車製造会社製の22 / 23は覆いが運転台まで延びているため「スーパーナメクジ」
と呼ばれていた。 |
|
 |
| C58 261 / D51 |
|
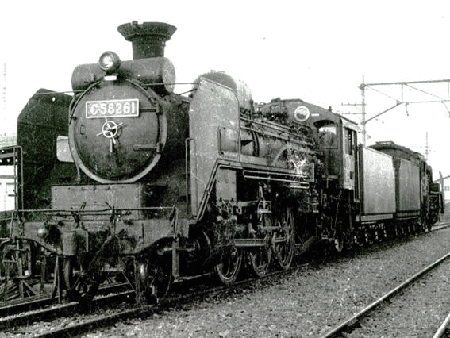 |
|
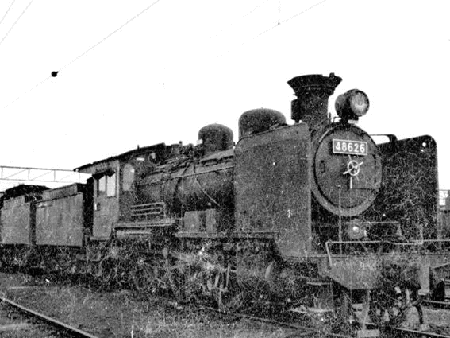 |
|
昭和39年(1964年)の時点で、D51形が10両 / 区間用のC58が9両 / 入換用の8620が6両 が配置されていた。
千葉鉄道管理局の蒸気機関車の煙突に取り付けられていた皿式火の粉止めは、かっこ悪く残念なものであった。 |
|
 |
|
| 旧型直流電気機関車 / D51形蒸気機関車初期型 / C58 / 旧型客車 が連結されていた。旧型客車と言うよりはオハ31形の様な古典的客車で、「新小岩機関区救援車 」の文字が見える。 |
|
 |
| 操車ヤード |
|
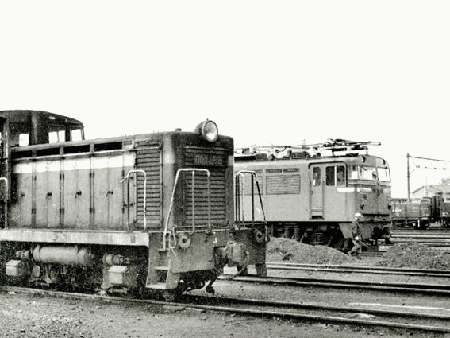 |
| 前照灯1灯のDD13初期型 / EF80 |
|
| 新小岩操車場には入換用のDD13 / 新金線を介して常磐線の交流区間に乗り入れる交直流機関車EF80 も見られた。 |
|
 |
| 前照灯1灯のDD13初期型 |
|
 |
| 入換作業中の前照灯2灯のDD13後期型 |
|
| 昭和44年(1969年)両国駅から蒸気機関車の運用がなくなり、昭和45年(1970年)には越中島貨物線用に残っていたD51の運用がなくなる。蒸気機関車王国だった千葉鉄道管理局は無煙化された。 |
|
 |