| 吹田機関区 |
|
|
往時は蒸気機関車とディーゼル機関車が所属する吹田第一機関区 / 電気機関車が所属する吹田第二機関区 に分かれていた。昭和31年(1956年)東海道本線全線電化に伴い、蒸気機関車とディーゼル機関車の基地は吹田第一機関区に改称、電気機関車の基地として吹田第二機関区が新設された。昭和44年(1969年)または昭和45年(1970年)夏に撮影。
|
|
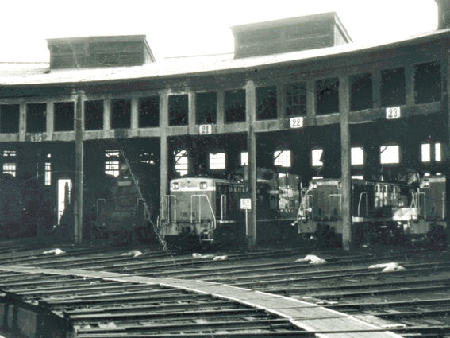 |
| 吹田第一機関区 機関庫 |
|
 |
| D51 754 |
|
| D51形は昭和11年(1936年)〜昭和20年(1945年)に国鉄向けだけで1115両製造された貨物用蒸気機関車。 |
|
 |
| D51 78(ナメクジ) |
|
| 初期に製造された95両は、砂箱と給水加熱器を覆う半流線形で“ナメクジ”と呼ばれている。また、かまぼこ形ドームの戦時形も製造された。 |
|
 |
| 入れ替え中のD51 115 |
|
| 入れ替え用になったD51は、デフが外されて手すりが追加されている。 |
|
 |
| DF50 504(旧塗装車) |
|
|
DF50形は昭和32年(1957年)〜昭和38年(1963年)に138両製造された電気式ディーゼル機関車。昭和60年(1985年)までに全車廃車になった。
|
|
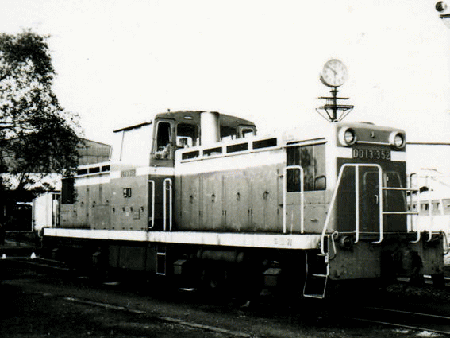 |
| DD13 352 |
|
| DD13形は昭和33年(1958年)〜昭和42年(1967年)に416両が製造された液体式ディーゼル機関車。貨物入換作業を主目的として開発された。 |
|
 |
| DD51 18 |
|
| DD51は昭和37年(1962年)〜昭和53年(1978年)に649両が製造された液体式ディーゼル機関車。昭和32年(1957年)から運用されたDF50形は、幹線では出力不足であった。速度面では旅客列車用蒸気機関車C61形を、牽引力では貨物列車用蒸気機関車D51形を上回る性能になっている。 |
|
 |
| 入れ替え中のDE11 |
|
| DE11形は、昭和41年(1966年)〜昭和53年(1978年)に708両製造された貨車入換ディーゼル機関車。老朽化のため、後継機に置き換えられる予定になっている。
|
|
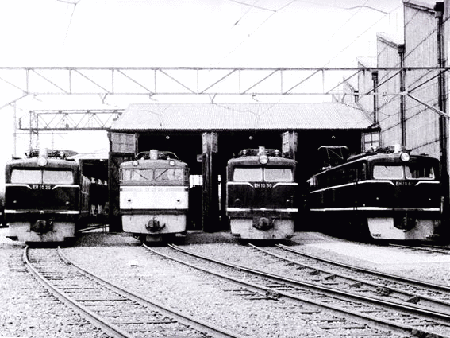 |
| 吹田第二機関区 機関庫 |
|
 |
| EF14 2 |
|
| EF14形は昭和3年(1928年)〜昭和6年(1931年)に9両が製造された旅客用直流電気機関車EF52形を、昭和19年(1944年)に1号機
/ 昭和20年(1945年)に2号機 が貨物用に改造された直流電気機関車。EF14 2は昭和35年(1960年)吹田機関区に配置され、大阪駅構内の入換機となった。昭和49年(1974年)に廃車となった。
|
|
 |
| EH10 60 |
|
| EH10形は、昭和29年(1954年)〜昭和32年(1957年)に64両が製造された8動軸式の貨物用直流電気機関車。東海道本線 / 山陽本線 で運用された。昭和34年(1959年)から東京・汐留駅〜大阪・梅田駅間で運行開始されたコンテナ特急貨物列車“たから号”でも活躍した。昭和57年(1982年)までに全車廃車になった。 |
|
 |
| 前照灯が異なるEF60 |
|
|
EF60形は昭和35年(1960年)〜昭和39年(1964年)に143両が製造された貨物用直流用電気機関車。昭和39年(1964年)製造車は、前照灯が2灯シールドビームになっている。500番台は、20系客車寝台特急(ブルートレイン)牽引用に14両が製造された。令和元年(2019年)までに全車廃車になった。
|
|
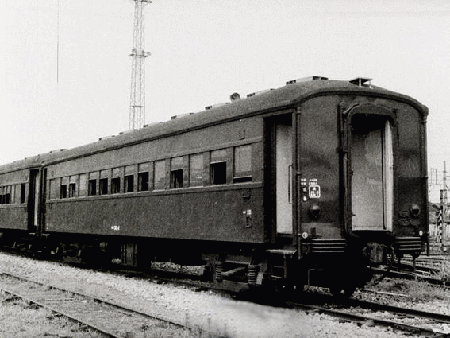 |
| オヤ30 4 |
|
|
オヤ30 4は昭和2年(1927年)オロ41 723として製造→昭和3年(1928年)の改番でオロ30653→昭和16年(1941年)の改番でオロ31
52→昭和16年(1941年)の改造でオハ27 52→昭和38年(1963年)職員通勤用に改造されオヤ30 4 となった。吹田工場などの職員通勤用に運用され、昭和58年(1983年)に廃車になった。
|
|
 |