| 美濃路 No.05 名鉄竹鼻線・須賀駅-(約14km)-大垣宿本陣跡 |
|
| 2018年 1月 9日(火)07:15 雨 |
|
 |
 |
 |
| 須賀駅 |
及が橋 |
天満神社 |
|
|
07:00を過ぎても暗い雨の日、名鉄竹鼻線・須賀駅から美濃路を北へ進む。すぐに足近川の支流・及川に架かる及が橋を渡る。及が橋を渡った左手に、及が橋案内板がある。上流に鎌倉街道が通っており、及が橋が架けられていた。江戸時代に街道が美濃路に付け替えられたが、橋の名前は引き継がれたと云う。すぐに変則十字路があり、北西方向に道なりに進む。すぐ左手に天満神社がある。
|
|
| [迷い道]天満神社からすぐに水路と平行する道に突き当たる。左方向に見える羽島中学校の建物を、足近小学校の建物と勘違いする。足近小学校の北側に出たと勘違いして、突き当たりを左折して南に進んでいる。さらに突き当りを右折して西に進み、水郷ハナミズキ街道の足近小学校西交差点の南側に出ている。右折して北へ進むと、5分足らずのところに足近小学校西交差点がある。 |
|
| 正しい美濃路は、2018年3月6日に歩き直しました。 |
|
 |
天満神社からすぐに水路と平行する道に突き当たり、右折して北へ進む。すぐの突き当りを左折して北西へ進むと、すぐ右手に、美濃路案内板 / 親鸞聖人が滞在した西方寺への道標
がある。正面に「親鸞聖人御舊跡」 / 右側面に「寺田山渋谷院西方寺」と彫られている。ここは旧南宿村で、かつては南宿と北宿の間に鎌倉街道の宿駅があった。美濃路が整備されると宿場は役目を終えるが、旧南宿村の南西側に間の宿が置かれた。 |
| 西方寺への道標 |
|
 |
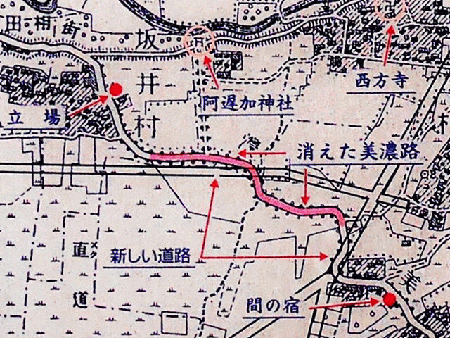 |
| 地蔵の祠 |
|
 |
| 町並み |
美濃路案内板からの抜粋 |
|
| 美濃路案内板 / 西方寺への道標 から北西に道なりに進むと、すぐ左手に地蔵の祠がある。すぐに足近小学校西交差点の北側で水郷ハナミズキ街道に突き当たり、美濃路が途絶える。 |
|
|
[迂回路]水郷ハナミズキ街道を北東へ進み、すぐの足近町2交差点を左折して西へ進む。北側の道、7本目辺りから美濃路が復活する。この道は北へ少し進んでから北西に曲がっているのが目印となる。通り過ぎた2本目のところに坂井バス停がある。美濃路を北西に進むと地元の方に出会い、美濃路の入口で迷ったことに苦笑されていた。美濃路は標識が欲しいところが多い。
|
|
 |
 |
美濃路が復活してから5分足らずで境川の土手に突き当たり、左折して土手道を西へ進む。すぐの鎌倉街道と美濃路が合流する右手の三角地帯に「親鸞上人御舊跡」と彫られた親鸞聖人が滞在した西方寺への道標がある。 |
| 土手道に登る坂 |
西方寺への道標 |
|
 |
 |
 |
| 地蔵の祠 |
街道寸景 |
普明院への道 |
|
 |
 |
10分足らずの東境川橋南詰手前右手に地蔵の祠がある。5分ほどすると美濃路案内板があり、すぐに普明院が見えてくる。普明院にはすぐのY字路を左に進み坂を下る。Y字路まで戻り、美濃路を北西に進む。普明院裏を過ぎたすぐ左手に西小熊の一里塚跡がある。
|
| 普明院 |
西小熊の一里塚跡 |
|
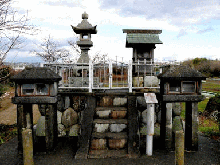 |
10分足らずの右手に秋葉神社がある。 |
| 秋葉神社 |
|
| 5分足らずのところにY字路がある。美濃路は左方向に直進するが、すぐに突き当り途絶える。往時は境川を小熊の渡しで越えていた。境川は尾張国と美濃国の境であった。 |
|
 |
ここからは迂回路になり、突き当りを右折して北へ進む。すぐに境川を渡り、すぐの置江五十石交差点を鋭角に左折する。すぐに右折して水門脇を通り、道なりに西へ進む。すぐに土手に突き当たり、階段を登り土手道を北へ進む。すぐ左手の河川敷に茶屋新田運動場があり、美濃路はこの辺りに繋がっていた。さらに長良大橋のすぐ北側にある日置江公園辺りから墨俣の渡しで対岸に通じていた。土手道を北に進んでから10分ほどすると、長良大橋東交差点がある。
|
| 水門 |
|
 |
| 長良大橋 |
|
 |
長良大橋東交差点を左折、長良川に架かる昭和8年(1933年)竣工 / 延長382.7m の長良大橋を渡る。長良大橋西交差点を右折して北へ進むと、前方に墨俣城模擬天守(墨俣一夜城歴史資料館)が見える。すぐのT字路右手に渡船場からの道が通じていた。 |
| 墨俣宿への橋 / 墨俣城模擬天守 |
|
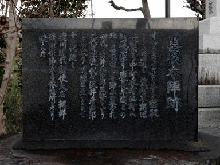 |
 |
T字路を左折して橋を渡ると墨俣宿札の辻で、左手の本陣跡に金比羅大権現と彫られた常夜燈 がある。往時は渡船場近くにあった常夜燈を復元したもの。右手に、美濃路石柱
/ 社 / 墨俣宿碑 がある。 |
| 本陣跡 |
復元常夜燈 |
|
 |
 |
 |
| 美濃路石柱 |
社 |
墨俣宿碑 |
|
|
鎌倉街道の墨俣(すのまた)宿は南側の上宿付近にあったが、美濃路が整備され移設された。揖斐川と長良川に挟まれた立地で、重要な宿場であった。長良川には墨俣の渡しがあった。北側に墨俣城がある。天保14年(1843年)には、本陣:1 / 脇本陣:1 / 問屋場:1 / 旅籠:10軒 の規模であった。
|
|
 |
墨俣宿札の辻から北へ進むと、5分ほどのところに平成3年(1991年)大垣城天守を模して建てられた墨俣城模擬天守(墨俣一夜城歴史資料館)がある。尾張から美濃へ侵攻する重要拠点であることから、度々合戦になっていたと云われている。信長公記には永禄4年(1561年)洲俣要害の攻防があり攻略、改修して在陣したことが記されている。永禄9年(1566年)織田信長の稲葉山城攻略の際、木下藤吉郎が一夜にして城を築いた逸話がある。信憑性に乏しく、江戸時代の創作であるとも云われている。天正12年(1584年)池田恒興の家臣・伊木忠次が改修、天正14年(1586年)木曽三川(木曽川・長良川・揖斐川)の氾濫で木曽川の流路が変わり、墨俣城は戦略上の重要性を失ったと云われている。 |
| 墨俣城模擬天守 |
|
 |
名古屋転勤3年間に撮影した画像。初期のデジタルカメラに搭載されたレンズは、上部がかなり湾曲している。 |
| 墨俣城模擬天守からの眺望 |
|
|
 |
 |
 |
| 宿場通り |
脇本陣跡 |
|
| 宿場通りを進むと、すぐ左手に脇本陣跡がある。明治24年(1891年)濃尾地震で倒壊したが、ほぼ同様の構造で再建された。 |
|
 |
 |
すぐ右手に津島神社・秋葉神社がある。鳥居右手に「琉球使節通行記念燈篭」標柱がある。寛政2年(1790年)琉球使節が墨俣宿を通行したとき、天王社(現:津島神社)石燈籠に「琉球国儀衛正毛延柱」と彫った。
|
| 津島神社・秋葉神社 |
「琉球使節通行記念燈篭」標柱 |
|
 |
本陣跡から5分ほどの突き当りを右折して北へ進む。すぐの十字路から東に延びる道は、墨俣遊郭跡。すぐ左手に、八幡神社 / 参道に晴れた日でも滑り落ちそうな太鼓橋
がある。 |
| 八幡神社 |
|
 |
 |
八幡神社から左へ、土手に登る道を進む。すぐのY字路を左へ、道なりに西に進む。すぐに23号線を陸橋で越える。10分ほどすると瑞穂市標識があり、瑞穂市に入る。5分ほどすると安八(あんぱち)町に入る。標識の手前右手に地蔵がある。
|
| 土手に登る道 |
地蔵 |
|
 |
 |
 |
| 米の宮之跡 |
公園 |
町屋観音堂 |
|
|
10分ほどすると、すぐ右手に「米の宮之跡」石柱がある。5分足らずの右手に池を配した公園 / すぐ右手に町屋観音堂 と続く。町屋観音堂は照手姫伝説の地の1つで、ここでは十一面観音の頭上に照手姫の守本尊が載せられている。
|
|
| 町屋観音堂のところはY字路になっており、美濃路は直進して揖斐川に突き当たる。往時は佐渡(さわたり)の渡しで揖斐川を渡っていた。雨が強くなり、揖斐川までは行っていない。 |
|
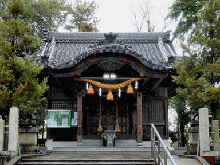 |
 |
| 結大明神 |
新揖斐川橋から南側の眺望 |
|
 |
 |
 |
| 八幡神社 |
浄勝寺 |
大師寺 |
|
|
ここからは迂回路になり、町屋観音堂から北へ進む。すぐ左手に嘉応年間(1169年〜1171年)創建と云われる結(むすぶ)大明神がある。縁結びや諸願成就にご利益があると云われている。すぐのY字路を左へ進む。21号線に突き当たり、左折して揖斐川に架かる新揖斐川橋を渡る。最初の道を左折して南へ進むと、すぐ右手に八幡神社がある。道なりに東へ進むと、すぐ右手に長享3年(1489年)創建の浄勝寺がある。南へ進みすぐの突き当りを右折すると、すぐ右手に大師寺がある。
|
|
|
大師寺から道なりに南に進むと、突き当たる道が美濃路になる。左折して東へ、揖斐川方向に進む。
|
|
 |
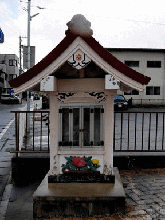 |
東町児童公園がある揖斐川の土手近くから西へ進む。すぐ右手に宮脇酒造がある。10分ほどの小野交差点を越えると、10分足らずの右手に地蔵の祠がある。 |
| 宮脇酒造 |
地蔵の祠 |
|
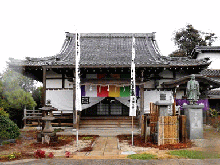 |
 |
 |
| 宝光寺 |
八幡神社 |
社 |
|
|
10分ほどすると、直進方向にJR東海道本線の線路が見える変則十字路がある。左折すると、すぐ左手に宝光寺 / すぐ右手に八幡神社 / すぐ左手に社
と続く。雨が強くなり、八幡神社で雨宿りと遅めの昼食を摂る。
|
|
 |
 |
すぐの交差点を右折して西へ進む。10分ほどすると、右手に神明社 がある。すぐの伝馬町交差点の右手(北東側)に、鐘が置かれている。
|
| 神明社 |
鐘 |
|
 |
 |
 |
| 宝相寺 |
秋葉神社 |
本顕寺 |
|
 |
 |
伝馬町交差点を越えると5分足らずの伝馬町西交差点まで、右手に宝相寺 / 右手に秋葉神社 / 右手に本顕寺 . 右手に順念寺 / 右手に東本願寺大垣別院 と続く。 |
| 順念寺 |
東本願寺大垣別院 |
|
 |
 |
| 稲荷神社 |
|
 |
| 変則十字路 |
貴船神社 |
|
|
伝馬町西交差点からすぐに変則十字路があり、ここから城下町特有の曲がりが続く。右手に稲荷神社ある。左手に美濃路標識があり、左折して南へ進む。美濃路標識裏面には地図がある。ところどころに同様な地図があり、迷うことはない。すぐ右手に元和2年(1616年)〜寛永12年(1635年)の間に創建された貴船神社がある。
|
|
 |
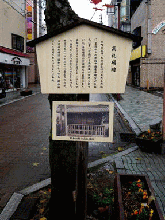 |
すぐの突き当りを右折する。すぐに十字路がある。右折して北に進むと、すぐ右手に高札場跡がある。 |
| 古民家 |
高札場跡 |
|
 |
美濃路は十字路を左折して南へ進む。5分足らずで237号線と交差する。交差点を左折すると、すぐ左手に山門が閉ざされた乗蓮寺がある。 |
| 乗蓮寺 |
|
 |
 |
交差点まで戻り、南へ進む。すぐ左手に昭和48年(1973年)復元の本町道標がある。美濃路と竹鼻街道との分岐点に建てられており、「左 江戸道」「右 京道」と彫られている。すぐの十字路を左折して南へ進り、右折すると、すぐの十字路の北西側に問屋場跡がある。
|
| 本町道標 |
問屋場跡 |
|
 |
 |
 |
| 大垣宿本陣跡 |
明治天皇行在所跡 |
|
 |
美濃路は右折して西へ進む。すぐ右手に大垣宿本陣跡がある。美濃路に面したところに明治天皇行在所跡 石柱 / 敷地に社 がある。大垣は、大垣藩10万石の城下町 / 美濃路の宿場として賑わっていた。
|
| 社 |
|
 |
 |
すぐに57号線に突き当たる。美濃路はさらに西へ進む。 |
| 古商家 |
57号線に突き当たる |
|
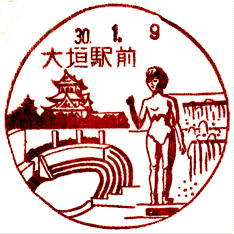 |
57号線を右折して北へ進む。10分ほどのところにある高屋町交差点の1本手前の道を右折すると、すぐ右手に大垣駅前郵便局がある。風景印は、水の広場 / 女神像 / 大垣城 の図柄になっている。
|
| 大垣駅前郵便局風景印 |
|
| 高屋町交差点のすぐ北側にJR東海道本線・大垣駅がある。 |
|
 |