| 美濃路 No.04 名鉄尾西線・萩原駅-(約9km)-名鉄竹鼻線・須賀駅 |
|
| 2017年 3月 6日(火)09:00 晴れ |
|
 |
 |
 |
| 町並み |
萩原商店街アーケード |
秋葉神社 |
|
|
名鉄尾西線・萩原駅北側の踏切から、美濃路を西へ進む。すぐ右手に秋葉神社があり、この辺りから萩原宿に入る。萩原宿は、本陣:1 / 脇本陣:1 / 問屋場:2 / 旅籠:17 / 家数:236 / 人口:1002人 と美濃路では最も小規模だった。宿の中央でL字になっていた。日光川の東に位置、毎年5月には萩原宿チンドン祭りが行なわれている。
|
|
 |
 |
秋葉神社からすぐ左手に地蔵堂がある。すぐの萩原下町交差点を左折すると、すぐ右手に萩原郵便局がある。風景印は、万葉公園の図柄になっている。 |
| 地蔵堂 |
萩原郵便局風景印 |
|
 |
 |
萩原下町交差点まで戻り西へ進む。すぐのT字路左手に正端寺がある。往時は高札場があった。
|
| 古民家 |
正端寺 |
|
 |
 |
 |
| 古民家 |
馬頭観音の祠 |
地蔵の祠 |
|
 |
 |
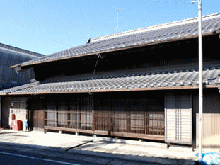 |
| 問屋場跡 |
萩原商店街アーケード |
古民家 |
|
 |
T字路を右折して北に進む。すぐ左手に馬頭観音の祠 / 左手に地蔵の祠 / すぐ右手に問屋場跡 / 萩原商店街アーケード / すぐ右手に神社 と続く。美濃路はすぐの十字路を直進、名神高速道路を潜った先の“天神の渡し場”で日光川を越えていた。 |
| 神社拝殿 |
|
 |
 |
 |
| 日光川 |
社 |
寂雲寺 |
|
| ここからは迂回路になる。十字路を左折して日光川に架かる萩原橋を渡る。往時の川幅は現在よりも広かった。Y字路を道なりに右方向に進むと、すぐ右手に社がある。名神高速道路を潜ると、すぐ左手に寂雲寺が見える。 |
|
 |
 |
 |
| 八幡神社石柱 |
地蔵の祠 |
秋葉神社 |
|
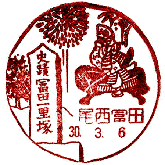 |
すぐに道は北西方向に曲がる。この辺りに天神の渡し場があった。美濃路を北西に進む。10分ほどすると、右手に八幡神社石柱 / すぐ左手に地蔵の祠 / 反対側に秋葉神社 / 尾西冨田郵便局 と続く。風景印は、花火 / 騎馬の武士 / 冨田一里塚 の図柄になっている。
|
| 尾西冨田郵便局風景印 |
|
  |
| 冨田一里塚(西塚 / 東塚) |
|
 |
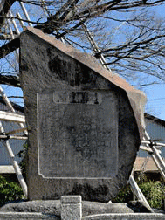 |
尾西冨田郵便局からすぐに、冨田一里塚がある。美濃路に設置された13の一里塚で、唯一両側に原形を留めている。葉の生い茂る榎の木が見たくなる。西塚側に、トイレやベンチがある。 |
| 冨田一里塚石柱(西塚) |
冨田一里塚碑(東塚) |
|
 |
冨田一里塚からすぐ左手に、慶応3年(1867年)再建の「左 駒塚道」道標がある。 |
| 道標 |
|
 |
 |
| 起宿脇本陣 / 問屋場跡 |
|
 |
| 脇本陣 |
古民家 |
|
|
道標から15分ほどすと、左手に起宿(おこしじゅく)脇本陣 / すぐ右手に起宿脇本陣と問屋場跡 と続く。起宿は、尾張国と美濃国の境にあたる木曽川の東岸側にあった。木曽川に設けられた起渡船場は、定渡船場(じょうわたしば) / 宮河戸(みやごうど) / 船橋河戸(ふなばしごうど) の3ヶ所が設置されていた。船橋河戸は船橋の架設位置で、将軍の上洛や朝鮮通信使の通行の際に利用された。天保12年(1841年)には、本陣:1
/ 脇本陣:1 / 問屋場:2 / 旅籠:22 / 家数:230 / 人口:1033人 規模だった。起村は小村であったため、冨田 / 東五城
/ 西五城 / 小信中島 の村々を加宿として、伝馬役 / 人足役 の宿駅を負担した。脇本陣は明治24年(1891年)濃尾地震で倒壊、翌年に建て直したもの。江戸時代後期の建築がほぼ残り、尾西市歴史民俗資料館別館となっている。
|
|
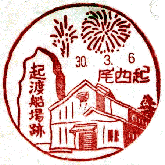 |
起宿脇本陣 / 問屋場跡 からすぐに変則十字路がある。右折して東に5分ほど進むと、左手に尾西起郵便局がある。風景印は、花火 / 起渡船場跡 /
尾西市歴史民俗資料館本館 の図柄になっている。 |
| 尾西起郵便局風景印 |
|
 |
 |
 |
| 町並み |
満開の梅 |
本誓寺 |
|
 |
 |
 |
| 宮河戸跡 |
銀杏 |
大明神社 |
|
 |
変則十字路まで戻り北に進む。5分足らずの右手に本誓寺 / 隣接して室町時代初期創建の大明神社 がある。大明神社の美濃路沿いに宮河戸跡石柱がある。宮河戸跡は、主に荷物の揚げ降ろしを業務とした湊だった。大型船が木曽川を上下、物流の中継拠点としての機能を果たしていた。境内に推定樹齢350年の銀杏 / 長い鳥居のトンネルを進むと大福稲荷神社 がある。
|
| 大福稲荷神社 |
|
 |
大明神社すぐに18号線を潜ると、5分足らずのところに交差点がある。往時は北東に直進する道はなく、北西に進路を変えて定渡船場に繋がっていた。東角地にある旧湊屋主屋は、明冶24年(1891年)濃尾地震で倒壊をまぬがれた建物。元治元年(1864年)以降に建てられたと云われている。
|
| 旧湊屋主屋 |
|
 |
 |
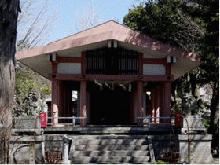 |
| 起渡船場跡 |
常夜燈 |
金刀比羅社 |
|
|
十字路を左折すると、すぐ右手に金刀比羅社がある。境内に、起渡船場跡碑 / 天保14年(1843年)造立の常夜燈 がある。起渡船場は3ヶ所があったが、定渡船場は広く使用されて両岸に常夜燈が設けられていた。昭和31年(1956年)濃尾大橋が竣工するまで利用された。
|
|
 |
 |
| 木曽川 |
濃尾大橋 |
|
| 金刀比羅社から北西に進むと、すぐの土手道を潜ると木曽川河川敷に出る。南西方向に、木曽川に架かる全長777.7mの濃尾大橋が見える。 |
|
 |
 |
 |
| 顕彰碑 |
起渡船場石灯台 |
|
| 木曽川河川敷を南西に進み、土手道に登る。濃尾大橋東交差点を右折して濃尾大橋を渡る。風が強く寒さが堪える。途中に休憩施設が欲しいほどの長さがある。濃尾大橋を渡り終えると、正木町三ッ栁交差点の北西側に昭和13年(1938年)造立の“正木の本堤の顕彰碑”がある。木曽川沿いに184号線を北東に進むと、すぐの中央分離帯に明和7年(1770年)造立の起渡船場石灯台がある。 |
|
 |
 |
 |
| 大浦(三ツ屋)の道標 |
大浦金比羅神社 |
|
 |
起渡船場石灯台辺りで歩道が途切れる。184号線は車の往来が多く危険なため、正木町三ッ栁交差点まで戻り西へ進む。正木町新井交差点手前をUターンして、184号線に平行する下の道を進む。10分ほどすると、右手に大浦(三ツ屋)の道標案内板がある。寛延3年(1750年)造立の道標は。角地の個人宅門前に移されている。正面に「右いせみち」 / 左側面に「左おこし舟渡」 と彫られている。西に進むと、すぐ右手に大浦金比羅神社がある。定渡船場跡からの渡船は、大浦金比羅神社の西に上陸していた。すぐに突き当たる土手の手前右手に、起渡船場跡案内板がある。
|
| 突き当たりの土手 |
|
 |
 |
 |
| 秋葉神社 |
大浦の子守地蔵堂 |
地蔵の祠 |
|
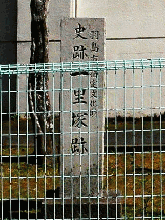 |
大浦(三ツ屋)の道標案内板から北へ進む。10分足らずの右手に秋葉神社 / すぐの三角地帯に大浦の子守地蔵堂 / すぐ左手に地蔵の祠 / すぐ右手の正木小学校に美濃路街道案内板と不破一色一里塚跡 と続く。
|
| 不破一色一里塚跡 |
|
 |
正木小学校角の変則十字路を右折する。さらに左折すると、すぐ左手に貴船神社がある。
|
| 貴船神社 |
|
 |
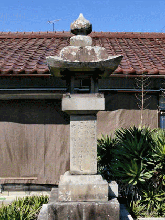 |
変則十字路まで戻り北へ進む。垣根で遮断されている貴船神社境内横を通る。10分足らずの右手に法啓寺がある。さらに5分足らずの左手に、移設された文政9年(1826年)造立の及が橋灯籠がある。足近川が氾濫して美濃路が水没したときは、渡船を利用していた。渡河の安全祈願のために、輪中堤防上の松並木にあったもの。
|
| 法啓寺 |
及が橋灯籠 |
|
 |
及が橋灯籠から5分ほどすると、名鉄竹鼻線踏切を越えた右手に須賀駅がある。美濃路を完歩する。 |
| 名鉄竹鼻線・須賀駅 |
|
 |