| 水戸街道ぶらり旅 No.06 藤代駅-(約10km)-牛久駅 |
|
| 2017年 2月14日(火)10:00 晴 |
|
| 藤代駅 |
→ |
慈眼院観音堂 |
→ |
水神神社 |
→ |
金龍寺 |
→ |
星宮神社 |
→ |
成井一里塚 |
→ |
正源寺 |
→ |
牛久駅 |
|
|
 |
 |
 |
| 古民家 |
八坂神社 |
小貝川土手 |
|
| JR常磐線・藤代駅から北へ、すぐのT字路を右折して旧水戸街道を北東へ進む。旧宮和田宿の町並みに、往時の面影はない。また宮和田宿本陣があった場所は、解らなくなっている。10分ほどすると、旧水戸街道は小貝川の土手に突き当たる。突き当たる手前左手に、八坂神社がある。往時、小貝川は宮和田の渡しで越えていた。 |
|
 |
 |
| 文巻橋からの小貝川 |
慈眼院観音堂 |
|
| 小貝川の土手に登り、小貝川沿いに北へ進む。すぐに208号線に突き当たり、右折して小貝川に架かる文巻橋を渡る。すぐに右折してY字路を左へ進むと、すぐ左手に天慶年間(938年〜947年)平貞盛が父・国香の菩提を弔うために建立したのが始まりの慈眼院観音堂がある。現観音堂は享保2年(1717年)に再建されたもの。
|
|
 |
 |
 |
| 左:旧水戸街道 / 右:迂回路 |
治水之碑 |
水神神社 |
|
| 慈眼院観音堂の南側を東へ進む。5分ほどすると、旧水戸街道は谷田川で途切れる。手前のY字路を右に進み、すぐのJR常磐線の踏切を渡る。すぐに左折してすぐの谷田川に架かる往還橋を渡った辺りで旧水戸街道が復活、すぐ左手に治水之碑
/ すぐ左手に水神神社 と続く。 |
|
 |
水神神社から10分足らずで5号線に合流する、すぐの馴芝小入口交差点を左折して、北へ進む。すぐに関東鉄道・竜ヶ崎線の踏切りを渡る。5分ほどの突き当り手前右手に、文政9年(1826年)造立の道標がある。道に迷う旅人が多かったため、村人の寄付で造立されたと云う。正面に「水戸十六里」/
左側面に「布川三里」/ 右側面に「江戸十三里」と彫られていると云う。「布川三里」しか判読できなかった。
|
| 道標 |
|
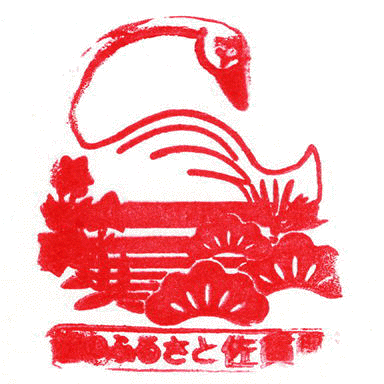 |
突き当りと左折して北へ進むと、5分ほどのところに佐貫駅東入口交差点がある。左折して西へ進むと、5分ほどの突き当りにJR常磐線・佐貫駅がある。スタンプは、白鳥の図柄になっている。使用限界を超えた状態になっている。 |
| JR常磐線・佐貫駅スタンプ |
|
 |
 |
佐貫駅東入口交差点から5分ほどすると、右手に「大坂 これより旧若紫宿」標識 / すぐ右手に八坂神社 と続く。若柴宿はこの辺りから始まっていた。
|
| 「大坂 これより旧若紫宿」標識 |
八坂神社 |
|
| 水戸街道 8番 若柴(わかしば)宿 |
| 所在地:茨城県龍ヶ崎市 |
|
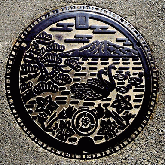 |
藤代宿と牛久宿間に、それぞれ一里ほどの近さにあった。本陣は置かれていなかった。明治19年(1886年)の大火で、宿場のほとんどが焼失している。長屋門などを構えた家並で、宿場らしい雰囲気がある。龍ケ崎市のマンホールは筑波山を背景に、牛久沼に泳ぐ市の鳥・白鳥 / 市の木・松 / 市の花・桔梗(ききょう)のデザインになっている。牛久沼はJR常磐線・佐貫駅北西側にあり、全域が龍ケ崎市になっている。牛久沼の東岸に沿って、JR常磐線と6号線が通っている。
|
| 龍ヶ崎市マンホール |
|
 |
 |
 |
|
 |
八坂神社から10分足らずの突き当りに、金龍寺がある。新田氏の菩提寺で、新田義貞の四男・貞氏が応永24年(1417年)に上州太田に創建したのが始まり。寛文6年(1666年)移転する。本堂は安政5年(1858年)に再建されたもの。参道の梅が咲き始めていた。
|
| 金龍寺 |
|
 |
旧水戸街道は、突き当りを右へ進む。5分ほどすると、左手に延長2年(924年)創建と云われる星宮神社がある。社殿は江戸時代に再建されたもの。 |
| 星宮神社 |
|
 |
 |
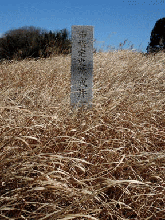 |
| 左:旧水戸街道 |
地蔵の祠 |
成井一里塚 |
|
  |
| 成井一里塚 |
|
| 5分ほどの若柴配水場入口交差点を越え、すぐのY字路を左へ進む。10分足らずの右手に地蔵の祠 / すぐに成井一里塚がある。左側は草木が生い茂り、右側は上部が平になっている。 |
|
| 成井一里塚から10分ほどするとY字路があり、左へ進む。すぐに左に大きく曲がるところは、JR常磐線で途切れているところ。旧水戸街道は真直ぐ続いていた。道なりに南西に進み、迂回する。JR常磐線を銅像山踏切で渡り、すぐに突き当たる6号線を右折して北へ進む。 |
|
 |
銅像山踏切北交差点から斜め左への道が、旧水戸街道になる。すぐの北浦坂を登ると牛久宿に入る。
|
| 銅像山踏切北交差点から約100mm |
|
| 水戸街道 9番 牛久(うしく)宿 |
| 所在地:茨城県牛久市 |
|
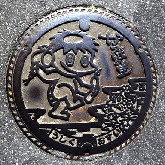 |
牛久宿は水戸街道19宿中間の宿場で、上町と下町で成り立っている。公用荷物の業務は、次の荒川沖宿と合同で行う合宿であった。大名行列が到着すると両宿だけでは対応しきれず、助郷制度に頼っていた。助郷制度は農民にとって過酷な負担であったため、牛久一揆に発展した。正源寺手前辺りに本陣が置かれていたと云うが、脇本陣はなかった。旅籠は15軒ほどだった。牛久市マンホールは牛久沼の河童伝説に因む図柄で、「かっぱの里」も文字がある。 |
| 牛久市マンホール |
|
 |
 |
銅像山踏切北交差点から10分足らずの交差点手前左手に、「芋錢河童碑道」石標がある。小川芋錢(うせん)の墓に通じる道。すぐ左手に、明治天皇牛久行在所碑がある。
|
| 「芋錢河童碑道」石標 |
明治天皇牛久行在所碑 |
|
 |
 |
明治天皇牛久行在所碑から5分ほどすると、左手に文禄元年(1592年)創建の正源寺がある。鐘楼門から下ったところに本堂がある。 |
| 正源寺鐘楼門 |
正源寺本堂 |
|
 |
正源寺から10分ほどすると6号線に合流、すぐ左手に地蔵の祠がある。 |
| 地蔵の祠 |
|
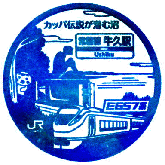 |
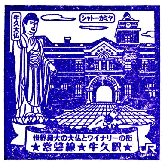 |
すぐの牛久駅西出口交差点を右折すると、突き当りにJR常磐線・牛久駅がある。スタンプ(右)は、牛久沼と河童 / E657系 の図柄になっている。スタンプ(右)は、牛久大仏 / ワイナリー の図柄になっている。 |
| JR常磐線・牛久駅スタンプ |
|
| [寄り道]牛久郵便局 |
 |
牛久市内の郵便局で風景印が置いてあるには、牛久郵便局だけである。牛久駅から北東方向、1.5kmほどのところに牛久郵便局がある。筑波山を背景に、牛久沼 / 河童 の図柄になっている。
|
| 牛久郵便局風景印 |
|
 |