| 水戸街道ぶらり旅 No.02 小菅駅…水戸街道入口-(約13km)-松戸駅 |
|
| 2017年 1月10日(火)09:00 晴 |
|
| 小菅駅 |
… |
水戸街道入口 |
→ |
小菅神社 |
→ |
蓮昌寺 |
→ |
宝蓮寺 |
→ |
新宿日枝神社 |
→ |
浄心寺 |
→ |
葛西神社 |
→ |
松戸神社 |
→ |
宝光院 |
→ |
西蓮寺 |
… |
松戸駅 |
|
|
 |
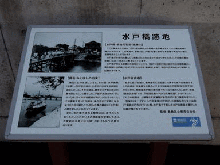 |
 |
| 水戸街道入口 |
水戸橋案内板 |
水戸橋からの下流 |
|
| 東武鉄道・小菅駅から、首都高速中央環状線の下を通る荒川沿いの道を南東へ進む。10分足らずの交差点を左折して、旧水戸街道(308号線)を東へ進む。標識もなく解りづらい。首都高速中央環状線が左に大きく曲がる手前の交差点になる。5分足らずで綾瀬川に突き当たる。往時は水戸橋が架かっており、案内板がある。この橋のたもとに妖怪が出没したが、元禄8年(1695年)水戸光圀がこれを退治した。「二度と悪さをしないように」と、この橋に水戸光圀の名前をとり「水戸橋」と命名したとの伝承。北側の水戸橋を渡り、迂回する。
|
|
 |
 |
綾瀬川対岸の交差点を南へ進むと、すぐ左手に小菅神社がある。明治2年(1872年)に小菅県が設置されたとき、庁内に創建され、小菅村の鎮守であった田中稲荷神社境内に移された。
|
| 小菅神社 |
田中稲荷神社 |
|
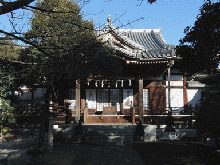 |
 |
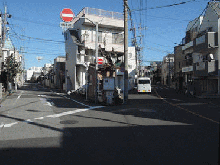 |
| 蓮昌寺 |
旧水戸街道標識 |
勘違いし易いY字路 |
|
| 旧水戸街道に戻り、綾瀬川対岸の交差点を東へ進む。5分ほどすると、左手に正安3年(1300年)創建の蓮昌寺がある。すぐの小菅3丁目交差点で川の手通りと交差する。すぐの変則交差点から左方向に進む。ここには、旧水戸街道(旧水戸佐倉街道)標識がある。さらにY字路を右方向に進む。ここは勘違いし易いところで、ここに標識が欲しい。 |
|
| 5分ほどすると交差点があり、常磐線高架下に平行する道を進む。すぐの交差点から南東方向に弓なりに進む。5分ほどすると、西亀有3丁目交差点で467号線(江北橋通り)と合流する。 |
|
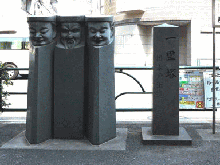 |
467号線(江北橋通り)の合流から10分ほどすると、左手に亀有の一里塚跡 / 助さんと格さんを従えた水戸黄門のモニュメント がある。亀有の一里塚は、千住宿から1里
/ 江戸日本橋から3里 に位置する。明治の末頃までは塚の跡が残っていた。
|
| 亀有の一里塚跡 |
|
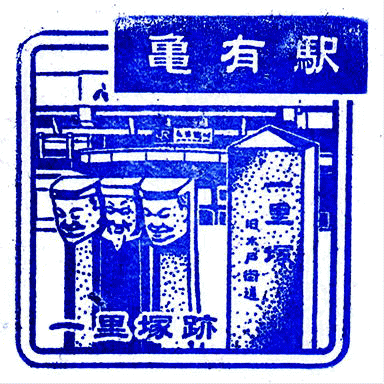 |
すぐの交差点を左折して北へ進むと、5分ほどの突き当りにJR常磐線・亀有駅がある。スタンプは、亀有の一里塚跡碑 / 助さんと格さんを従えた水戸黄門のモニュメント
が図柄になっている。
|
| JR常磐線・亀有駅スタンプ |
|
 |
467号線(江北橋通り)に戻り東へ進む。5分ほどすると中川橋を渡る。中川橋東詰から左方向に立増寺が見える。渡り切って左折すると、すぐ右手に不明の社がある。立増寺とは塀で遮断されている。 |
| 不明の社 |
|
 |
 |
中川橋東詰に戻り東へ進むと、すぐ左手に昭和8年(1933年)竣工の中川橋親柱 /
東詰にあったタブホの木 が保存されている。往時は新宿の渡しがあったところで、明治17年(1884年)中川橋が架けられた。通行料を徴収したため、賃取橋とも呼ばれていた。現在の中川橋は平成20年(2008年)の竣工。タブホの木は、架け替え工事により伐採された。
|
| 中川橋親柱 |
タブホの木 |
|
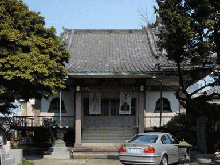 |
T字路交差点の手前を左折する。すぐの突き当りを右折すると、すぐ左手に永正年間(1504年〜1521年)創建の立増寺がある。
|
| 立増寺 |
|
 |
旧水戸街道はすぐのT字路交差点を右折して南へ進み新宿に入る。交差点を直進して東へ進むと、すぐ左手に天文元年(1532年)創建したと云われる宝蓮寺がある。
|
| 宝蓮寺 |
|
水戸街道 2番 新宿(あらしゅく)
所在地:東京都葛飾区新宿2丁目 |
|
| 新宿は千住宿から次の宿場町。往時は“あらしゅく”現在は“にいじゅく”と読む。交差点を右折して南へ進むと、上宿〜中宿〜日枝神社付近で屈曲して東に向う下宿からなる。下宿の東端(現:6号線中川大橋東交差点)付近には、佐倉街道(成田街道)の追分があった。小規模な宿場町で、本陣は置かれず問屋があるのみであった。明治17年(1884年)中川橋が架けられたとき通行料を徴収、町の主要な財源となった。明治30年(1897年)常磐線が開通する際に、通行料が取れなくなるために反対運動があった。新宿は鉄道から外れ、寂れていった。 |
|
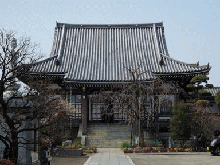 |
T字路交差点を右折して南へ進む。5分足らずのほど進むと右手に、文禄2年(1593年)麹町清水谷に服部半蔵正成によって創建された西念寺がある。寛永11年(1634年)移転した。 |
| 西念寺 |
|
 |
旧水戸街道はすぐに大きく東へ曲がる。直進して小道を南へ進むと。すぐの突き当たりに永禄2年(1559年)に創建と云われる新宿日枝神社がある。江戸時代には新宿町の鎮守だった。
|
| 新宿日枝神社 |
|
 |
 |
 |
| 浄心寺山門 |
浄心寺 |
金阿弥橋親柱 |
|
| 旧水戸街道に戻り東へ進む。すぐ左手に慶長19年(1619年)創建の浄心寺 / すぐ左手に金阿弥橋親柱 と続く。 |
|
 |
金阿弥橋親柱から左方向へ進む。すぐに6号線の交差点から北に伸びる道と合流、すぐの交差点を北東方向へ進む。すぐのY字路を旧水戸街道は右へ進む。三角地帯の旧水戸街道際に、平成10年(1998年)旧水戸街道道路拡張工事などにより、移転してきた石仏石塔群がある。神号碑「八大龍神」 / 記念碑 / 大乗妙典 入魂開眼 / 地蔵 / 地蔵 / 地蔵 / 青面金剛と台座に三猿が彫られた庚申塔
/ 日本廻国六十六部供養塚 / 日本廻国六十六部供養塚 / 六地蔵 と並び、少し離れて帝釈道道標がある。 |
| 三角地帯 |
|
 |
 |
| 石仏石塔群 |
帝釈道道標 |
|
| 石仏石塔群からすぐに浜街道踏切を越える。JR総武線と常磐線を繋ぐ貨物線で、1日数本の貨物列車が通過する。10分ほど6号線に平行する道を進む。京成電鉄・金町線の踏切がある金町3丁目交差点手前で、6号線の合流する。 |
|
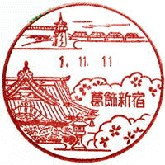 |
途中5分ほどのところにある十字路を右折して南に進むと、6号線の南側に葛飾新宿郵便局がある。風景印は、江戸川の取水塔 / 柴又帝釈天 / 江戸川堤の桜
の図柄になっている。
|
| 葛飾新宿郵便局風景印 |
|
 |
踏切から京成電鉄・金町に停車中の電車が見える。京成電鉄・金町線の金町〜柴又間は、人が車両を押して動かす人車軌道を運行していた帝釈人車鉄道が始まりである。明治30年(1897年)日本鉄道・金町駅が開業、柴又帝釈天への参詣者が増加した。交通の便を図るため、明治32年(1899年)に設立された。全線複線で、折り返しのため柴又駅と金町駅の終端部はループ線になっていた。1両6人乗りで64両あり、通常1人で押していたと云う。明治42年(1909年)成田山や柴又帝釈天の参詣客輸送を目的に設立された京成電気軌道に譲渡された。大正2年(1913年)人車の運行を終了、単線電化された。 |
| 京成電鉄・金町駅 |
|
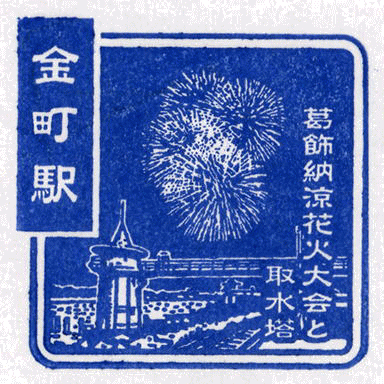 |
京成電鉄・金町線の踏切を渡り、すぐに左折する。すぐ左手に京成電鉄・金町駅 / 突き当りにJR常磐線・金町駅がある。スタンプは、葛飾納涼花火大会
/ 江戸川の金町浄水場取水塔 の図柄になっている。 |
| JR常磐線・金町駅スタンプ |
|
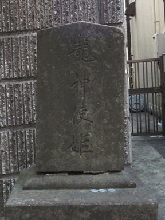 |
 |
金町3丁目交差点からすぐの金町広小路交差点を北へ進む。常磐線ガードを潜り、すぐに右へ北東に進む。すぐ右手に龍神使姫と彫られた石塔がある。すぐの三差路右手に、ガードレールに隠れる様に青面金剛と台座に三猿が彫られた庚申塔がある。 |
| 龍神使姫 |
庚申塔 |
|
 |
 |
三差路右方向に、元歴2年(1185年)創建の葛西神社がある。葛西清重が、上葛西と下葛西33郷の総鎮守として、香取神宮を勧請したと云われている。葛西囃子発祥の地として知られている。 |
| 葛西神社 |
絵馬 |
|
 |
| 江戸川土手道から葛西大橋眺望 |
|
 |
葛西神社辺りには間の宿・金町宿があった。葛西神社〜金町関所跡は、江戸川の河川改修によって旧街道筋はほとんどが河川敷に取り込まれ失われている。葛西神社からすぐに江戸川沿いの451号線に合流する。451号線には歩道がなく、土手道の江戸川堤サイクリングロードを北東へ進む。10分ほどすると、中央を東京外環自動車道が通る葛西大橋交差点を越える。 |
| 葛西大橋 |
|
 |
葛西大橋交差点からすぐの葛飾橋西詰交差点を越える。ただし直進できる横断歩道はなく、逆コの字型に横断歩道を3回渡る。江戸川堤サイクリングロードの切れ目で、直進する自転車が多い。葛西橋西詰交差点を渡ってからすぐ左手に、東金町ポンプ所の建物が見える。その手前に背を向けた「金町関所跡之記」碑がある。金町関所は、水戸街道が江戸川(江戸時代の利根川)を渡る地点に置かれた関門。関所は堤防下の河川敷一帯にあった。往時は松戸へ渡し船を利用していた。徳川将軍が鷹狩りに出かける際には、川に高瀬舟を並べて仮設の船橋が架けられた。
|
| 金町関所跡之記碑 |
|
|
|
| [寄り道]金町浄水場取水塔 / 矢切の渡し |
 |
 |
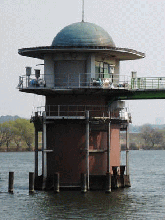 |
| 江戸川河川敷 |
第2取水塔 |
第3取水塔 |
|
|
葛西大橋から江戸川の土手を南西へ進む。20分ほどすると、金町浄水場の取水塔がある。とんがり帽子の第2取水塔は昭和16年(1941年) / 麦わら帽子の第3取水塔は昭和39年(1964年)の竣工。
|
|
 |
| 矢切の渡し |
|
|
| 取水塔から10分ほどすると柴又公園に案内板があり、左折すると矢切の渡しがある。江戸初期、江戸川の両側に田を持つ農民が関所を通らずに江戸と往来したことから「矢切の渡し」が始まった。矢切の渡しから柴又帝釈天は近い。
|
|
|
|
 |
 |
葛飾橋西詰交差点から江戸川を葛飾橋で渡る。交差点を左折して土手道を北東へ進む。5分ほどすると、右下の車道に「是より御料 松戸宿」石柱がある。往時は木製の傍示杭で、位置も異なるとのこと。
|
| 土手道からの上流 |
是より御料 松戸宿 |
|
中山道 3番 松戸宿
所在地:千葉県松戸市松戸本町
天保14年(1843年)水戸佐倉道宿村大概帳
家数:436 本陣:1 脇本陣:1 旅籠:28 |
|
| 江戸川に面しており、松戸宿は物資の中継地として賑わった。脇往還でありながら松戸宿までは道中奉行の管轄で、よく整備されていた。南北に約1kmの範囲に広がり、運河としても使われた坂川が市街地を横切っている。 |
|
 |
 |
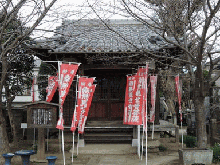 |
| 松龍寺山門 |
松龍寺本堂 |
観音堂 |
|
|
東へ進むと、すぐに流山街道に突き当たる。左折して北へ進むと、すぐ右手に慶長18年(1613年)創建の松龍寺 / 境内に観音堂 がある。山門は創建当時のものと云われている。観音堂の聖観音は、天明4年(1784年)籾殻(すくも)塚稲荷境内の籾殻から現れたもの。籾殻(もみがら)とは、籾の最も外側にある皮の部分のこと。
|
|
 |
 |
 |
| 松戸郵便局風景印 |
松戸市マンホール |
松戸市マンホール |
|
|
角町交差点からすぐ左手の脇本陣跡に、松戸郵便局がある。松戸郵便局風景印 / 松戸市マンホール ともに、同じ市内にある矢切の渡しが描かれている。また松戸市マンホールには、ユーカリとコアラ親子がデザインされているものもある。松戸市は昭和46年(1971年)にオーストラリア・ボックスヒル市(現:ホワイトホース市)と姉妹都市提携を結んでおり、ユーカリを市の木に制定している。
|
|
 |
すぐの宮前町交差点を左折すると、すぐ左手に本陣跡がある。
|
| 本陣跡 |
|
 |
 |
宮前町交差点に戻り北へ進むと、すぐ右手に寛永3年(1626年)創建の松戸神社がある。松戸の総鎮守となっている。宿場らしく、境内に社殿が同じ位の秋葉神社がある。 |
| 松戸神社 |
秋葉神社 |
|
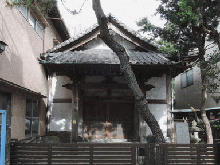 |
宮前町交差点から3本目を左折して小路を進むと、すぐ右手に妙晃寺がある。
|
| 妙晃寺 |
|
 |
 |
 |
| 松戸宿提灯が架かる古民家 |
古民家 |
宝光院 |
|
|
春雨橋を越えると、すぐ左手に宝光院がある。剣豪千葉周作の実父・浦山寿貞の墓と、周作の剣の師である浅利又七郎の供養碑がある。宝光院と北側にある善照寺との間は、千葉周作が修行した浅利道場があったところ。
|
|
 |
 |
 |
| 善照寺 |
古民家
|
西蓮寺 |
|
|
宝光院からすぐの左手に慶長16年(1611年)に移転してきた善照寺 / 左手に西蓮寺 と続く。善照寺は。西蓮寺は文禄3年(1594年)下総矢喰村に創建され、慶長18年(1613年)に移転してきた寺。
|
|
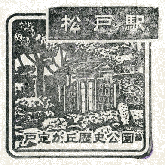 |
西蓮寺からすぐの本町の交差点を右折すると、突き当たりにJR常磐線・松戸駅がある。スタンプ は、戸定が丘歴史公園の図柄になっている。 |
| JR常磐線・松戸駅スタンプ |
|
 |