| ���B�X���Q�P���@�m��.�P�T�@��|�\����-�i��Q�R�����j-����h�c����w |
|
| �Q�O�P�T�N�@�V���Q�V���i�j�O�X�F�S�O�@�� |
|
 |
 |
��|�����_����k���i�ށB�����_��n��������ɉ���V�N�i�P�U�V�X�N�j�����̐���n�� / �E��ɉB���l�ɕs���̐Γ�������B
|
| ����n�� |
�s���̐Γ� |
|
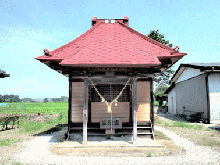 |
 |
 |
| ����_�� |
�_����u���s�_�v |
�m�ԋ�� |
|
| ��|�����_����T�����炸�̍���ɔ���_�Ђ�����B�����ɁA�_����u���s�_�v / �����T�N�i�P�W�O�W�N�j��|�h�̔o�l�ɂ�葢�����ꂽ�u������� �n�����ނ��� �قƁT�����v�m�ԋ�� ������B�N���̎s�����s�Ŏs�_���J���A���N��������o����𗬂̏�ƂȂ��Ă����B |
|
 |
 |
�אڂ��Ė����N�ԁi�P�S�X�Q�`�P�T�O�O�N�j�n���̐��ώ�������B�R��͓�|�h�{�w�̖�Ɖ]���Ă���B |
| ���ώ��R�� |
���ώ� |
|
 |
 |
 |
| ������ |
�߉ϐ�̒ސl |
�������ˋ��L�O�� |
|
 |
���ώ����炷���ɕ�����B�V�Q�����͍��Ȃ��邪�A�����B�X���͒��i����B���̕ӂ�͏h��̊O��ŁA�e�`�ɂȂ��Ă���B�����̓˂���������܁A�����ɂV�Q�����ɓ˂�������B�E�܂��āA�߉ϐ�ɉ˂��鏺������n��B�����͓k���n��ŁA��������ƏM�n���ɂȂ��Ă����B�]�ˌ���ɂȂ�ƁA�M����y�����˂���ꂽ�Ɖ]���Ă���B�߉ϐ�ɒސl������B��������n��ƁA�����E��ɏ������ˋ��L�O��
/ ��������ɂ��������ˋ��L�O�肪�Q�� ������B
|
| �������ˋ��L�O�� |
|
| ���������炷���̓˂���������܂���ƁA�z�@�h�ɓ���B�z�@�h�̐����́A���ۂR�N�i�P�U�S�U�N�j�ƒx�������B�Q�Ό��ō]�˂Ɍ��������˂́A�߉ϐ�̐엯�߂ɑ����Ə��������Ĉ�����̂�҂����B���ꂪ�h�̎n�܂�Ɖ]���Ă���B�{�w�F�P
/ �e�{�w�F�P / ���āF�P�P �������B�h��͖����̑�ŏĎ����Ă���B |
|
 |
 |
 |
| ��� |
���`�̒n�� |
�����Q |
|
| �˂���������܂���ƁA�����E��ɏ�� / �E��̉z�@���������ٕ~�n�Ɂu���̒n ���B�X���z�@�h ���`�̒n�v�� / �E��ɐΕ��Γ��Q / �E��ɖh�ΐ��H�{�L�O�V�� �Ƒ����B��ɂ͓߉ϐ�̉z�@�h���ɂ������u�]���쒆�����H�́v���H�˗̊E���ڒz����Ă���B�Ε��Γ��Q�́A�s���̐Γ� / �n�� / ���a�P�R�N�i�P�X�R�W�N�j�����̐��n�V��
/ ���a�U�P�N�i�P�X�W�U�N�j�����̏}���R�n�V�� �̂S��B |
|
 |
 |
 |
| ���v�����̕�W�� |
�ɐ���_�{�y�q�� |
���K�Q��ƐΕ��Γ��R�� |
|
| �h�ΐ��H�{�L�O�V������T���قǂ̍���̋u�ɁA���v�����̕�W��������B���v�����i���������������j�́A�����W�N�i�P�V�X�U�N�j���n�y�Ő��܂ꂽ���l��ƁB�V�ۂP�S�N(�P�W�S�R�N�j�]�˂ŖS���Ȃ�B�u�̏�ɂ͍��v�Ɛ�c��X�V��ȂǕ����̕悪������B�����E��̐��n�y�����ٕ~�n�ɁA�ɐ���_�{�y�q�� / �w��ɐ��K�Q��ƐΕ��Γ��R�� ������B |
|
 |
 |
���n�y�����ق���E�֑傫���Ȃ��鍶��ɁA�_���� / �ېΓ��c�_���K������ł���B |
| �_���� |
�ېΓ��c�_ |
|
 |
 |
�ېΓ��c�_���K����T���قǂ���ƁA����ɔ_���V�L�O�� / ����ɔn���ω����Q�� �Ƒ����B�_���V�L�O��ӂ肩�炫���Ȃ����́A�T���]��ŕx�m�����i�W���Q�X�T.�Tm�j�̒���ɒ����B�����͕x�m�����]�ł����Ɖ]���A�������������B���݂͎G�ؗтşT���Ƃ��Ă���B����������ƁA�����E��ɓ|��������ʂĂ��u���q�ꗢ�˂̗��v�W��������B |
| �n���ω� |
�����ʂĂ��u���q�ꗢ�˂̗��v�W�� |
|
 |
 |
| �n���ω� |
|
 |
| �������ꂽ���q�ꗢ�� |
���i�S�N�����̔n���ω� |
|
|
�����ʂĂ��u���q�ꗢ�˂̗��v�W������T���]������q�����_��O�E��ɁA���q�ꗢ�ˌ���������B�������ɂ͕������ꂽ���q�ꗢ�� / �n���ω� / �x�m�����ɂ��������W�����˂����i�S�N�i�P�V�V�T�N�j�����̔n���ω� ������B���q�ꗢ�˂͔��͊���T�O���̂Ƃ���ɂ��������A�w�Z�J�݂Ɠ��H�̊g���ɂ���Ď��ꂽ�B�x�m�����ɂ��������W�����˂��n���ω��́A�E���ʂɁu���a�R�Z�\�Z�� ���\�� ��Ó�\�l�� �ߐ{�����ܗ��v / �����ʂɁu�����R�\�Z�� �]�ˎl�\�ꗢ
���˓�\�� ���a�R�ܗ��v�ƒ����Ă���B
|
|
 |
 |
 |
| ��O�� |
�]���쌩���炵���� |
�]���� |
|
|
���q�ꗢ�ˌ�������T�����炸������ɁA���T���N�i�P�T�V�O�N�j�n���̉�O��������B�����B�X���͉�O������ߍ��ɓ��邪�A�����P�O�N�i�P�X�X�W�N�j�]����̔×��ŋ����q���͗������Ă���B�����͋�����������Ɛl���n���ƂȂ��Ă����B�]����ɉ˂��鎛�q����n���O�E��ɁA�]���쌩���炵����������B
|
|
 |
 |
| �����Q / �{�Y�� |
�̔� |
|
| �]����ɉ˂��鎛�q����n��A�����̏\���H�����܂���B�����ɋ����q������̋����B�X���ɓ˂�����A�E�܂���B�����ɂV�Q�����ƍ�������O�p�n�тɁA�Ε��Γ��Q
/ �{�Y�� / �u��Ƌ��ɔɂ�s�� �݂̂�L�� �S�䂽���Ɂv�̔� ������B |
|
 |
�V�Q�����ƍ������Ă���P�O���قǂ���ƁA����ɔ_�ƍ\�����P���ƋL�O��������B |
| �_�ƍ\�����P���ƋL�O�� |
|
 |
 |
| �s�����K |
�����Q |
|
 |
�_�ƍ\�����P���ƋL�O�������P�O�����炸�̉E��ɕs�����K / ����ɐΕ��Γ��Q / ����ɉ����ɑ����Ă��邩�s���̓��U �Ƒ����B�Ε��Γ��Q�͔n���ω��T��Ɠ�\�O�铃�i�E�[�j�B
|
| ���U |
|
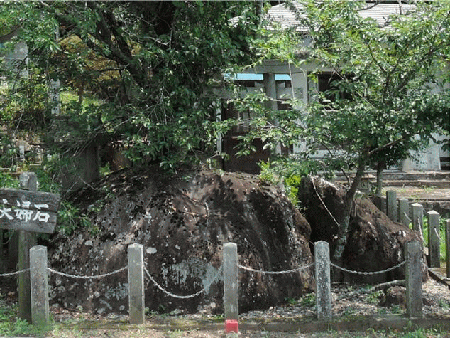 |
���U����P�O�����炸�����싴��O�ɕ�����B�����B�X���͉E�i�ނ��B����ɓ˂�������r��Ă���B�����͋�����������Ɛl���n���ƂȂ��Ă����B�V�Q������i�݁A����ɉ˂��鍕�싴��n��B�V�Q�����͉E�ɋȂ���A����ɍ��ɋȂ���Ƃ���ӂ�ɋ����B�X�����q�����Ă����B���싴�����T���]��̉E��ɕv�w������B�퍑����ɓG�ɒǂ�ꂽ�j�����A���̐̊���ڂɐg���B�����B�ǎ肪�߂Â��Ɣ��ւ�������������̂ŁA�G������ē������Ɖ]���Ă���B
|
| �v�w�� |
|
 |
 |
| �v�w�Έꗢ�ˁi�k���j |
�v�w�Έꗢ�ˁi�쑤�j |
|
|
�v�w����T���قǂ���ƁA�v�w�Έꗢ�˂�����B�k���̒˂͓��H�g���ō���Ă���B
|
|
 |
 |
 |
| �n���ω� |
�_���� |
�n�� |
|
 |
�v�w�Έꗢ�˂���T���قǂ̂x���H���A�����B�X���͍��i�ށB�����E��ɔn���ω� / �E��ɐ_���� / �E��ɒn�� / �E��ɔn���ω��Q�� �Ƒ����B�����ɂV�Q�����ɍ�������ƁA
|
| �n���ω� |
|
 |
�����E��ɕޏꐮ���v�H�L�O��������A�����ɂQ�W�����ƌ�������B�������ޗǐ��n��ƈ���h�ɓ���B����h�͓ޗǐ�ɉ����Đ݂����Ă���B����ɋ��ۂP�Q�N�i�P�V�Q�V�N�j�����̒n��������B���̒n���͍�����O�ɏo���Ă��邱�Ƃ��獿��n���ƌĂ�Ă���B����h�͏鉺���Ƃ��Ĕ��W�A�{�w�F�P / �e�{�w�F�P / ���āF�Q�T �������B
|
| �n���� |
|
 |
 |
�n�������炷���ɖ��`�ɂȂ�A�˂���������܂���B�����̉�����E�킪�L���ꂽ���ĕ��̐Α���������������B�Q���B�e�����Ƃ���ŁA���܂�ɑ����̂Ŏ~�߂�B�����̓˂�����Ȃ�ɉE�i�ށB�삩��̓��ƍ����A�����B�X���͖k�i�ށB |
| ���܉� |
�{�c�� |
|
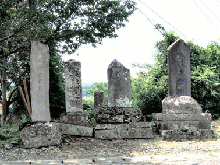 |
 |
���Ε����i��j�ɐi�ނƁA�����E��ɂT��̐Ε��Γ��Q / �����̍���ɓ��{�O�吹�V�i���傤�Ă�j���O���� ������B |
| �����Q |
�O���� |
|
| �g�O��Ȃ�Ƃ��h�́A���G�ɂȂ�ꍇ�������B�����s�䓌��E�{���@�i�ғ��R���V�j���ޗnj�����s�E��R���i����V�j�͊m��ŁA��ʌ��F�J�s�E����@�i�ȏ����V�j / �É������R���E�����R���V���i�������V�j / �O�d���K���s�E�啟�c���i�K�����V�j / ���Ɍ��L���s�E���y���i�L�����V�j �̂����ꂩ��������̂���ʓI�ȗl�ł���B |
|
 |
 |
 |
| ���� |
�Z�g�� / ���B���� ����h �ΕW |
���q�� |
|
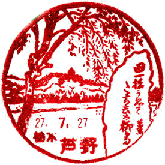 |
 |
 |
| ����X�Ǖ��i�� |
�̔��p�� |
�̔��p�� �s������ |
|
| �����B�X���ɖ߂�A�k�i�ށB�����E��Ɂu���B���� ����h�v�ΕW / ��������ɍ]�ˎ��㏉���n�ƂŌ����ẲV�����E���q�� / �����E��Ɂu�n�����Q���v�Β� / �����E��ɔԏ��ՂɌ��Ă�ꂽ����X�� / ��������ɖ{�w�ՂɌ��Ă�ꂽ�̔��p�� �Ƒ����B����X�ǂ̕��i��́A�V�s�� / �u�c�ꖇ �����ė������� �����ȁv�m�ԋ�� �̐}���ɂȂ��Ă���B |
|
 |
 |
| ������ |
�n�� / ��\�O�铃 / �O�E�ݗ쓃 / �s���̐Γ� |
|
|
�̔��p�ق���T�����炸�̉E��Ɍ�����������B���{�E���쎁���̕悪����B���쎁�́A�n���Ƃ��Ă��̒n�����߂Ă����B�]�ˎ���͂R�O�O�O�̊��{���������A�ߐ{�ꑰ�̂��߂P���Έȏ�̑ҋ����ĎQ�Ό����s���Ă����B ���������Ȃ����O����ɁA���ۂQ�N�i�P�V�P�V�N�j�����̒n�� / ��\�O�铃 / �O�E�ݗ쓃 / �s���̐Γ� ������ł���B����������h�̖k���ɂȂ�A�e�`�ɂȂ��Ă���B
|
|
| �����ɓޗǐ��n��ƁA�Q�X�S�����ɍ�������B
|
|
|
|
| �m��蓹�n�V�s�� |
|
 |
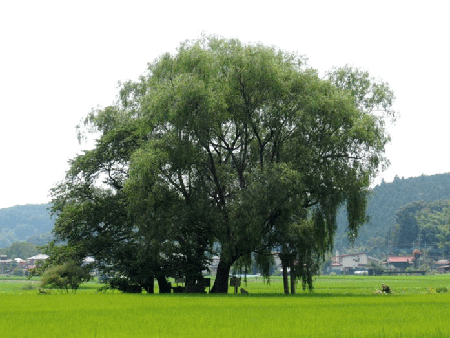 |
| �����̍ד��V�s���W�� |
�V�s�� |
|
 |
 |
 |
| ���s�̔� |
�m�ԋ�� |
������� |
|
|
�Q�X�S���������f����ƁA����ɗV�s���i�H���j�△���x�e��������B�k���̏��H�Ɂu�����̍ד��V�s���v�W��������A���i�ށB�����̏\���H�����܂���ƁA�E��ɗV�s����������B�V�s���͐̂����X�̋I�s���ɋL�ڂ���A���s / �����m�� / ���蓡�� �Ȃǂ��K�ꂽ���Ƃł��m���Ă���B�u���ׂ̂� ��������� ������ �����ƂĂ���
�����ǂ܂���v���s�̔� / �u�c�ꖇ �����ė������� �����ȁv�m�ԋ�� /�u���U ������ �Ώ��X�v������� ������B
|
|
|
|
 |
 |
 |
| �s���̕����� |
�����_�� |
�ׂ��ΖT��̕s���̐Γ� |
|
| �����B�X���ɖ߂�k���i�ނƁA��������Ɂu�S��L���v�� / �s���̕����� �Ƒ����B�ߍ��̋����ɓ���B�s���̕���������T�����炸�̍���Ɉ����_�� / ��������Ɂu�ׂ��̔�v�ē��� �Ƒ����B�`�����ނƉE��ɑ������B�Éi���N�i�P�W�S�W�N�j�����������̂ŁA�I�����������Ă���Ɖ]���B���̌`�ɂ͌����Ȃ��Ǝv��������A�T��ɂ������s���̐Γ��݂̂��B�e���Ă����B |
|
 |
 |
| ��������c�c |
�����Q |
|
 |
�ׂ��̔肩�炷���̂s���H���E�܂���ƁA�Q�X�S�����ɓ˂����荶�܂���B�����ɕ�����A�����B�X���͍��i�ށB����̎O�p�n�тɑ��ɖ�����Ă��镶���Q�N�i�P�W�P�X�N�j�����́u��������c�c�v / ��������ɐΕ��Γ��Q
/ ��������ɐ_����u�o�H��_ ���R��_ ���a�R��_�v / ��������ɕ�ُ݊]�R�ҔV�� �Ƒ����B��ُ݊]�R�ҔV��́A��C�푈�̂Ƃ��ɍ��H�˓��̔_������݊قŗm�������̌P�����e�n�Ő����������������B |
| �o�H��_ ���R��_ ���a�R��_ |
|
 |
 |
 |
| �����Q |
�n���ω�
|
�����^�� / ��\�O�铃 |
|
 �@ �@  |
| ���ꗢ�� |
|
|
�����ɂQ�X�S�����ɍ�������ƁA��������Ɍ����^���S�ݕՋ��{�� / �s���̐Γ� / ���� / �n�� ������B�����ɕ�����A�����B�X���͉E�i�ށB�T���قǂ���ƁA�E��ɔn���ω��S�� / �����E��Ɍ����^���Ɠ�\�O�铃 / ����������_����@����傪�����Ă���Ɖ]���@�_�̔� / �����ɔ��ꗢ�� �Ƒ����B���ꗢ�˂͗��˂��c���Ă��邪�A���H���@�艺����ꂽ���߂Ɉʒu�������Ȃ��Ă���B�����̒˂ɖ������l�ɁA�s���̐Γ� / ��断�T���{��
/ �n���ω� ������B
|
|
 |
 |
 |
| �n���ω� |
�n���ω� |
�n���ω� / �s���̐Γ� |
|
 |
 |
 |
| �����B�X�� |
������ |
|
|
���̈ꗢ������T�����炸�̉E��̋u�ɁA�n���ω��S�� / �E��ɔn���ω��Q�� / �n���ω��ƕs���̐Γ� �Ƒ����B�P�O�����炸�̉E��ɉi�\�P�O�N�i�P�T�U�V�N�j�n���̍�����������B��������ɂ��铰�̉A�ŋx�e����B
|
|
 |
 |
���������炷���̉E��ɐΕ��Γ��Q������B��i�͔n���ω��Q��ƕs���̐Γ� / ���i�͔n���ω��R��B�����E��ɔn���ω��T�� / �����ω��i�E�[�j������B |
| �����Q |
�n���ω��T�� / �����ω� |
|
 |
| �s���̐Γ� / �n�� / �n�� / �s���̐Γ� |
|
 |
 |
�Ε��Γ��Q����T���قǂ���ƁA�Q�X�S�����ɍ�������B�����E��̋u�ɐΕ��Γ��Q / �E��Ɍܗ֓� �Ƒ����B ����ɂT���قǂ���ƁA�E��ɐޓX�̓���������B |
| �ܗ֓� |
���� |
|
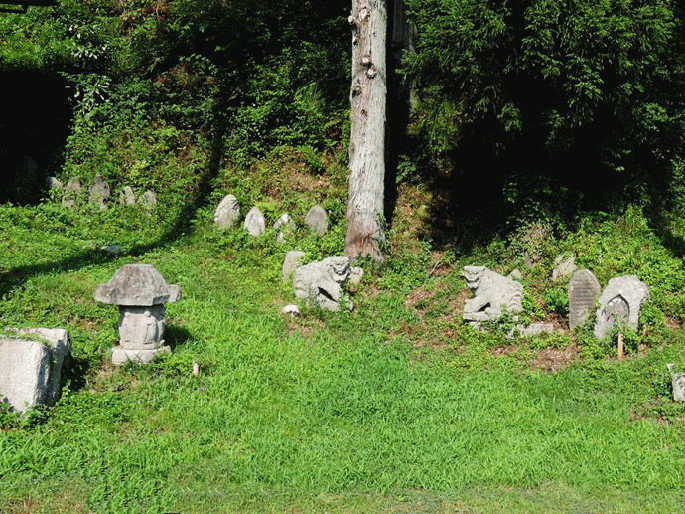 |
| �����Q |
|
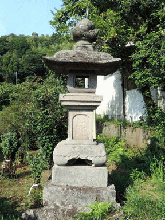 |
 |
 |
| ��铕 |
���y�� |
���y���ω��� |
|
| �ޓX�̓��Ă���P�T�����炸���E��ɁA���� / �Ε��Γ��Q ������B�����ɕ�����A�����B�X���͍��ւP�W�U������i�ށB�����E��ɏ�铕������B�����̕�����E�i�ނƁA�����E��ɋ��y�� / �����ɓߐ{�O�\�O���ω��P�O�ԎD���̊ω���
������B |
|
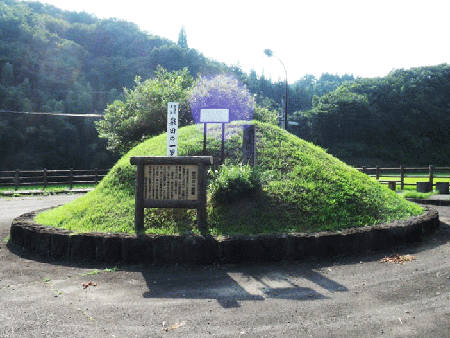 |
���y������T���قǂ���ƁA�Q�X�S�����ƍ�������B��������ɐ�c�ꗢ�˂�����B���썑�Ŗk�[�̈ꗢ�˂ɂȂ�B |
| ��c�ꗢ�� |
|
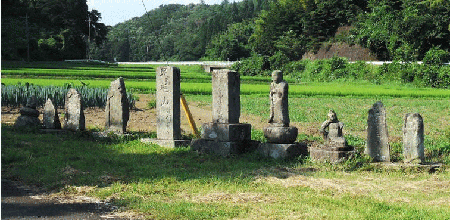 |
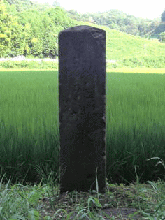 |
| �����Q |
���Ԑ����� |
|
 |
��c�ꗢ�˂���T���قǂ̂Ƃ�������܂���B�����Ɂu���̐�R�O�O�����Ԑ����v�W��������E�܂���B�����E��ɐΕ��Γ��Q / �����E������Ԑ����� �Ƒ����B�̕���E���������Q�i������j�w���́A�I�q�ˎm�E�я����ܘY�ƍȁE���Ԃ����������i������j���w������������B�w��T���Ă�����ɑ���a�я����ܘY�́A���̒n�ŗ×{����B���Ԑ����͏��Ԃ��p���������ŁA�я����ܘY���R���ɍ��̂��Z���i�ӂ��ׂ����j�B�����̂Q�X�S�����ƍ�������Ƃ���̍�����A�s���̐Γ� / �Z�Δ�u�Z�� ���ܘY���� ���Ԑ����]���v / �Z�� ������B |
| �s���̐Γ� / �Z�Δ� / �Z�� |
|
|
�Z���炷���ɓޗǐ�ɉ˂���˔���n��B�����ɋ����B�X���͉E�i�ނ��A�Q�X�S������i��ł���B
|
|
 |
 |
 |
| �n���ω� |
�n�� / �n�� / �s���̐Γ� |
�n�� / �����^���O�S�Ջ��{�� |
|
|
�˔���n���Ă��炩��T���قǂ���ƁA�E��ɖL���̔�������B�T�����炸�ŋ����B�X���ƍ�������B�T���قǂ���ƉE��ɔn���ω�������B�����̕���������B�X���͍��i�݁A�����ɂQ�X�S�����ƍ�������B��������ɒn���Q��ƕs���̐Γ� / ����ɒn���ƌ����^���O�S�Ջ��{�� �Ƒ����B
|
|
 �@ �@  |
| ���̖��_ |
|
| �Ε��Γ��Q����T���قǂ���Ɖ���i�Ȗ،��j�Ɖ��B�i�������j�̍����i�����j�ŁA�����̗����ɋ��̖��_������B���쑤�E���̖��_�͓V�쌳�N�i�P�O�T�R�N�j�n���B�����R�X�N�i�P�X�O�U�N�j�̉ЂŏĎ��A�����S�P�N�i�P�X�O�W�N�j�Č����ꂽ�B���B���E���̖��_�͕��\�S�N�i�P�T�X�T�N�j�n���B�×���荑������������ۂɂ͗��_�Ђ��Q�q�A�����̈��S���F�肵���Ɖ]���Ă���B�����m�Ԃ͌��\�Q�N�i�P�U�W�X�N�j�ɋ��̖��_�ɎQ�q���Ă���B�u������ ���₨���� �c�A�����v�m�ԁB |
|
 |
 |
���B���E���̖��_���炷������Ɂu�߂����̐����v�W��������B�O�@��t���߂���Ɖ]���Ă���B�Q�O�P�T�N�t�ɋ��b�B�X���ŕ����H�ɗ����������Ƃ�����A���[���Ƃ���ɂ͓��ݓ���Ă��Ȃ��B
|
| �߂����̐����W�� |
���[���� |
|
 |
 |
 |
| �s���̐Γ� |
�R�̐_�_�В��� |
���{�� / �s���̐Γ� / �n���ω� |
|
 |
 |
 |
| �吨���� |
�s���̐Γ� |
���䌳�V��펀�̐� |
|
 |
�u�߂����̐����v�W������T�����炸�̉E��ɕs���̐Γ�������B����ɂT�����炸�̍���ɎR�̐_�_�В��� / ����ɐΕ��Γ� / �吨����F / ����ɕs���̐Γ� / ����Ɂu��C�������_�ˎm ���䌳�V��펀�̐Ձv�ƈē��� / �� �Ƒ����B�c���S�N�i�P�W�U�W�N�j��C�푈�̉�Îᏼ�U�߂̑O����ŁA���͏�U�h�킪�W�J���ꂽ�B��_�ˏe�����E���䌳�V��́A�G�̏e�e�����ɎĐ펀����B |
| �� |
|
 |
����h�́A����h�Ɣ��͏h�̊Ԃ����߂���ׂɐ݂���ꂽ�h��B�{�w�F�P / �e�{�w�F�P / ���āF�Q�V �������B�u�J���~���Ă��P���炸�v�Ɖ]����قnj���A�˂Ă����B |
| ������ |
|
 |
 |
�����ɉE�ɕ��铹�͊��h���ŁA�����m�Ԃ͊��h����ʂ蔒�͂̊Ղ�K��Ă���B�Ђ���T�����炸�̉E��ɕs���̐Γ��Q�� / ����ɉ��i�P�T�N�i�P�S�O�W�j�n���Ɖ]�����ω��� �Ƒ����B�ω����ɂ���C�푈�Ő펀������_�ˎm�̕悪����B |
| �s���̐Γ� |
�ω��� |
|
 |
�ω�������P�O�����炷�̉E��ɁA���a�T�V�N�i�P�X�W�Q�N�j�����̋����ω� / ���v���N�i�P�W�U�P�N�j�����̔n���ω� ������B
|
| �����ω� / �n���ω� |
|
 |
�����ω� / �n���ω� ����P�T���قǂ̂Ƃ���Ɍ����_������B���ɂ������甒�͏h����܂ł͕����Ă���A�����_�����܂���B�������y���Ȃ�A�P�T���قǂłi�q���k�{���E����w�ɒ����B
|
| ����w |
|
 |