| 甲州街道 No.10 甲府駅-(約13km)-韮崎駅 |
|
| 2014年 5月20日(火)08:10 晴 |
|
| 南口に武田信玄像のあるJR中央本線・甲府駅から、52号線を南へ進む。 |
|
 |
 |
 |
| 道標 |
天然寺 |
法輪寺 |
|
 |
 |
10分ほどの相生交差点を右折して、旧甲州街道(52号線)を西へ進む。すぐの丸の内郵便局東交差点南西側に、昭和50年(1975年)に復元された「南
みのぶみち」「西 志んしうみち」道標がある。すぐの青沼児童公園前交差点を越えると、すぐ右手に天然寺 / 文治2年(1186年)創建の法輪寺 と続く。法輪寺境台にある“かんかん地蔵”は、甲斐源氏6代・武田有義の墓。 |
| 法輪寺かんかん地蔵 |
|
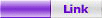 身延山・久遠寺 身延山・久遠寺 |
|
|
|
| [寄り道]穴切大神社 |
|
 |
 |
法輪寺からすぐの県民文化ホール北交差点から、二本目の小路を右折して北へ進む。5分ほどの左手に和銅年間(708年〜715年)創建と云わる穴切大神社がある。延喜式神名帳記載の式内社。貞享4年(1687年)と明和2年(1765年)に修築が行われている本殿は重文。随神門は寛政6年(1794年)の建立。 |
| 穴切大神社随神門 |
穴切大神社拝殿 |
|
|
|
 |
 |
旧甲州街道に戻り、西へ進むとすぐに寿交番前交差点がある。左折すると、すぐ右手に文殊神社がある。境内に「物言えば 唇寒し 秋の風」芭蕉句碑 / 不明の神号碑 / 素堂治水碑 / 不明の石塔 が並んでいる。素堂治水碑は「目には青葉 山ほととぎす 初がつお」で知られる甲府藩士・山口素堂が、近くを流れる濁川の治水事業に携わった業績を讃えた顕彰碑。 |
| 文殊神社 |
素堂治水碑 |
|
 |
寿交番前交差点まで戻り北へ進むと、すぐ右手に光雲寺がある。 |
| 光雲寺 |
|
 |
 |
寿交番前交差点まで戻り、旧甲州街道をに西へ進む。すぐに荒川橋東詰交差点がある。右折して北西へ分岐を右へ進むと、すぐ左手に丸石道祖神 / 妙豊寺
と続く。 |
| 丸石道祖神 |
妙豊寺 |
|
 |
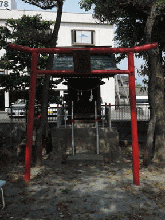 |
荒川橋東詰交差点まで戻り、旧甲州街道を南西へ進む。すぐに荒川に架かる荒川橋、続いて貢川(くがわ)に架かる貢川橋を渡る。貢川橋西詰交差点の分岐を右へ、美術館通り(52号線)を進む。すぐの上石田町バス停前から左へカーブする右手に“上石田のサイカチ”がある。昔この辺りまで貢川があり、川岸にあったサイカチを残したもの。右手奥に秋葉神社がある。 |
| 上石田のサイカチ |
秋葉神社 |
|
 |
 |
“上石田のサイカチ”からすぐの貢川交番前交差点で5号線と交差する。15分ほどすると、左手に山梨県立美術館 / 山梨県立文学館 がある。10分足らずの中央自動車道高架手前に甲斐市標識があり、甲府市から甲斐市に入る。中央自動車道高架を潜ると、すぐ左手に題目塔「南無日蓮大菩薩」と「南無妙法蓮華経
南無日蓮大菩薩」が並んでいる。10分足らずの真福寺入口交差点手前右手に、真福寺がある。 |
| 題目塔 |
真福寺 |
|
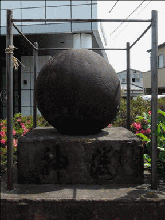 |
真福寺入口交差点から5分ほどの竜王新町交差点から52号線と分れ右へ進む。すぐ右手に古跡保存標識案内板 / 丸石道祖神 がある。ここは江戸時代に「寄り合い場」があったところ。 |
| 丸石道祖神 |
|
 |
丸石道祖神のある手前を右折すると、すぐ右手に新町不動堂 / 新町下公民館 がある。 |
| 新町不動堂 |
|
 |
 |
 |
| 蔵 |
称念寺 |
くり抜き石枠井戸 |
|
| 旧甲州街道に戻り北西へ進む。すぐ左手に慶長11年(1606年)創建の称念寺 / 境内に1枚岩で加工された“くり抜き石枠井戸”がある。上水道ができるまで、付近集落の生活用水だった。往来する旅人が休憩したことから、お休み井戸とも呼ばれていた。 |
|
 |
 |
 |
| 道祖神 |
道祖大神 |
赤坂 |
|
 |
 |
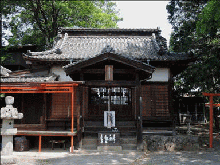 |
| 馬頭観音 |
諏訪神社 |
赤坂稲荷神社 |
|
|
称念寺からすぐにJR中央線踏切を渡る。すぐ左手に道祖神、5分足らずの左手に道祖大神がある。赤坂を登ると、すぐ左手に馬頭観音 / 右手に諏訪神社
と続く。諏訪神社境内に赤坂稲荷神社がある。
|
|
 |
 |
諏訪神社から10分ほどすると、右手に小さな鳥居のある小屋がある。供養塔の様な石塔 / 不明の石仏 / 不明の石塔 がある。すぐに「下今井(横町)ここから双葉町」標識があり、甲斐市竜王新町から下今井へ入る。右手のコンビニ駐車場は三軒茶屋跡。すぐ左手に廿三夜塔がある。
|
| 石塔群 |
廿三夜塔 |
|
 |
 |
 |
| 町並み |
庚申供養塔 |
道標を兼ねた庚申塔 |
|
|
 |
 |
 |
| 不明の石塔 |
町並み |
丸石道祖神 |
|
 |
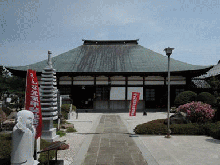 |
 |
| 自性院参道 |
自性院 |
町並み |
|
 |
廿三夜塔からすぐの分岐を分岐を左へ、ゆるい下りの坂を進む。廿三夜塔から10分ほどの左手に庚申供養塔 / 左手に道標を兼ねた庚申塔が新旧2基 と続く。左の古い方は判読できない。右の新しい方には「庚申 右市川駿河 左甲府江戸」と彫られているが、“河”と“戸”は地面に埋もれている。道の反対側に不明の石塔がある。すぐ右手の自性院前に丸石道祖神がある。自性院は、旧塩崎村山本坊沢百坊にあった慈勝院が始まりと云われている。本堂は明和2年(1765年)の建立。参道は、明和2年(1765年)敷設の石畳。旧甲州街道を北西に進むと、すぐ右手に双体道祖神がある。 |
| 双体道祖神 |
|
 |
 |
| 丸石道祖神 |
泣石 |
|
|
双体道祖神からすぐの下今井上町交差点で6号線と合流する。双体道祖神から5分ほどの左手に丸石道祖神があり、すぐにJR中央本線のトンネルを潜る。すぐの下今井交差点手前を右折してJR中央本線沿いを進む。丸石道祖神から5分ほどの右手に泣石がある。天正10年(1582年)武田勝頼の異母弟・仁科盛信が守る高遠城が落城する。武田勝頼は新府韮崎城に自ら火を放ち落のびる途中、勝頼の妻がこの地で燃える城を振り返り落涙したと云われている。鉄道開通までは、岩の中央部から水が流れていた。
|
|
 |
 |
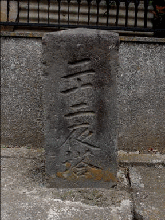 |
| 丸石道祖神 |
三界萬霊塔 |
二十三夜塔 |
|
 |
 |
泣石から10分ほどすると、右手に丸石道祖神 / 右手に寛政年間(1789年〜1801年)造立の三界萬霊塔 / 右手に二十三夜塔 / 右手に不明の石塔
と続く。 |
| 町並み |
不明の石塔 |
|
 |
 |
 |
| 町並み |
船形神社石鳥居 |
船形神社 |
|
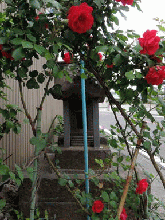 |
不明の石塔から10分足らずの右手に応永4年(1397年)造立の船形神社石鳥居がある。旧甲州街道を西へ進むと、すぐ左手に社がある。すぐの宇津谷バス停先の小路を右折すると、すぐ左手に「昼みれば首すじ赤き蛍かな」芭蕉句碑がある。 |
| 社 |
|
 |
 |
旧甲州街道を西へ進むと、すぐに田畑交差点がある。5分ほどの分岐を左へ進む。左手に二十三夜塔 / 不明の道標 / 二十三夜塔 がある。
|
| 町並み |
二十三夜塔 / 道標 / 二十三夜塔 |
|
 |
 |
 |
| 町並み |
JR・E351系スーパーあずさ |
鰍沢横丁 |
|
|
石塔群からすぐの分岐を道なりに左へ、すぐに6号線と合流する。5分ほどの塩川橋西詰交差点手前左手に韮崎市標識があり、甲斐市から韮崎市に入る。塩川橋西詰交差点を右折、すぐ左折してJR中央本線沿いに進む。韮崎市標識から10分ほどの下宿(しもじゅく)交差点を越えて左折するのが鰍沢横丁。峡北地方や諏訪・佐久地方の江戸納めの年貢米を馬背に積んで、鰍沢河岸(船山河岸)まで運んだ道。この辺りから韮崎宿へ入る。韮崎は甲斐武田家発祥の地で、守護神の武田八幡宮
/ 武田勝頼が真田昌幸に命じて築城した新府韮崎城 があった。韮崎宿は、甲府街道と富士川水系水運の物資の集散地として賑わった。信州の蔦木まで約28km続く七里岩が韮の葉に似て細長く、その先端にあるので韮崎と付けられたと云われている。.本陣:1
/ 旅籠:18 だった。
|
|
 |
 |
 |
| 大蓮寺 |
町並み |
馬つなぎ石 |
|
|
鰍沢横丁から旧甲州街道を北西に進むと、すぐ左手に大蓮寺がある。5分たらずの左手に“馬つなぎ石”がある。
|
|
 |
 |
馬つなぎ石からすぐの理容店と眼科医院の間を右折すると、すぐに一橋陣屋跡がある。一橋家は、徳川吉宗の四男・宗尹を家祖とする。租税 / 訴訟 /
断獄 などの民政を行ったところ。田安徳川家(田安家) / 清水徳川家(清水家) とともに御三卿として、徳川将軍家に後嗣がないときは後嗣を出す役割を担った。第11代将軍・家斉
/ 第15代将軍・慶喜 は一橋家の出身。
|
| 一橋陣屋跡 |
|
 |
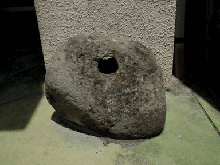 |
旧甲州街道に戻り、北西へ進む。眼科医院前に平成5年(1993年)造立の韮崎本陣跡碑がある。すぐ右手に“馬つなぎ石”がある。韮崎本陣跡碑は、町並みを撮影しているときに偶然撮影したもの。後で見つけた画像。 |
| 韮崎本陣跡碑:右手の石柱 |
馬つなぎ石 |
|
 |
馬つなぎ石からすぐに本町交差点がある。旧甲州街道は西へ進む。右折して、27号線を北東へ進む。5分ほどのJR中央本線のガードを潜り、すぐに線路沿いに右折するとJR中央本線・韮崎駅がある。27号線の左手方向、七里岩南端に昭和36年(1961年)造立の平和観音が見える。
|
| 平和観音 |
|
 |