| 旧青梅街道(成木街道)ぶらり旅 | ||
| 03 東大和・青梅橋-(8km)-横田基地界隈 | ||
| 東大和・青梅橋-(13km)-箱根ヶ崎交差点 | ||
 |
西武拝島線・東大和市駅南口から線路沿いに東へ進む。すぐの青梅橋交差点を左折して北へ進む。すぐの西武拝島線を潜った辺りから、青梅街道は二つの道筋に分れる。 | |
| 東大和市駅北口広場 | ||
| 東大和・青梅橋〜残堀〜横田基地界隈 | ||
 |
東大和市駅北口広場を横切り北西へ進む。慶長8年(1603年)に整備された頃の道筋で、残堀を経由して箱根ヶ崎に通じていた。最短距離で、石灰を運ぶだけなら都合が良かった。何もない原野の道で、追いはぎも出た物騒な道だったと云われている。この道筋は、横田基地界隈で分断されている。 |
|
| 多摩モノレール・桜街道駅 | ||
 |
多摩モノレール・桜街道駅から30分ほどすると、55号線の榎交差点に突き当たる。旧青梅街道は、少し北側の小路を北西へ進む。すぐに交差点があり、この先の旧青梅街道は商業施設で途絶えている。 |
|
| 稲荷神社 | ||
| 東大和・青梅橋〜奈良橋〜箱根ヶ崎交差点 | ||
 |
青梅橋交差点から北へ進む。20分ほどの奈良橋庚申塚交差点で新青梅街道と交差する。往時には庚申塚があったが、新青梅街道建設の時に取り壊されている。享保16年(1731年)造立の庚申塔は台座が道標を兼ねていて、「東
江戸道 北 くわんおん道 南 府中道 西 中藤 左 青梅」と彫られているとのこと。 |
|
| 新庚申橋からの空堀川 | ||
 |
奈良橋庚申塚交差点から10分ほどすると、奈良橋交差点がある。左折して西へ進むのが青梅街道、右折して東へ進むのが志木・引又河岸(ひきまたかし)に至る旧志木街道になる。何時の頃から、寺社や集落がある狭山丘陵の南側を通る道筋になった。青梅街道は慶長8年(1603年)整備された成木街道が始まりであるが、正徳3年(1713年)には青梅から奈良橋を経由して引又河岸に石灰が運ばれた記録が残る。石灰は新河岸川(しんかしがわ)の舟運を利用して江戸へ運んでいた。 | |
| 奈良橋交差点 | ||
 |
 |
 |
| 雲性寺山門 | 雲性寺本堂 | 雲性寺観音堂 |
 |
奈良橋交差点から西へ、すぐの交差点から北西方向へ道なりに進む。5分足らずの右手に、永享11年(1439年)創建と云われる雲性寺がある。狭山三十三観音 |
|
| 石仏石塔群 | ||
 |
雲性寺から西へ、すぐに青梅街道・郷土博物館交差点からの道に突き当たる。右折して北へ進むと、すぐ左手に奈良橋八幡神社 / 左手に東大和市郷土博物館 と続く。奈良橋八幡神社の創建年は不明であるが、天正3年(1575年)領主・石川太郎衛門の寄付により社殿が再興されたと云われている。 | |
| 奈良橋八幡神社 | ||
 |
 |
 |
| 熊野神社 | 蔵敷高札場跡 | 蔵敷高札場跡 |
 |
青梅街道まで戻り西へ進む。すぐに郷土博物館交差点から5分足らずの右手に熊野神社 / 右手に蔵敷高札場跡 / 右手に厳島神社 と続く。都内に残っている高札場は、蔵敷高札場と府中高札場のみとなっている。 | |
| 厳島神社 | ||
 |
 |
厳島神社からすぐの蔵敷公民館北交差点を左折して、芋窪街道を南へ進む。すぐ左手に蔵敷公民館がある交差点を鋭角に右折すると、すぐ右手に狭山三十三観音19番札所のはやし堂 / 左手に地蔵の祠 がある。 |
| はやし堂 | 地蔵 | |
| [寄り道]蓮華寺〜慶性院 | ||
 |
 |
青梅街道に戻り、西へ進む。すぐの芋窪交差点を左折して、43号線を南へ進む。5分ほどの左手に大正11年(1922年)村山貯水池(多摩湖)に沈んだ狭山三十七薬師37番札所の蓮華寺がある。次の交差点を右折すると、すぐ右手に住吉神社がある。 |
| 蓮華寺 | 住吉神社 | |
 |
 |
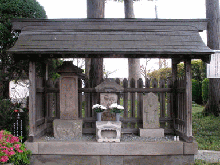 |
| 慶性院本堂 | 慶性院観音堂 | 庚申塔 / 水天 / 庚申塔 |
| 住吉神社からすぐの交差点を左折すると、すぐ右手に慶長年間(1596年〜1615年)創建の慶性院がある。村山貯水池(多摩湖)下貯水池の取水塔付近にあったが、大正11年(1922年)村山貯水池(多摩湖)が造られたときに移転した。狭山三十七薬師36番札所になっている。 |
||
 |
趣きのある山門(慶性門)は、村山貯水池(多摩湖)中堤の北側に保存されている。 | |
| 慶性院山門 | ||
 |
 |
 |
| 豊鹿島神社拝殿 | 豊鹿島神社境内社 | 豊鹿島神社休憩所 |
| 青梅街道の芋窪交差点まで戻り、青梅街道を西へ進む。すぐのT字路を右折すると、慶雲4年(707年)創建と云われる豊鹿島神社がある。室町時代建立と云われる本殿は、都内で現存する神社本殿で最古のものとされている。 | ||
 |
青梅街道まで戻り西へ進む。5分足らずの交差点を左折、すぐの奈良橋川を渡った左手に享保13年(1728年)造立の大橋の地蔵がある。 | |
| 大橋の地蔵 | ||
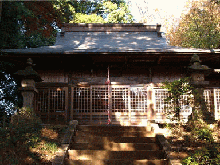 |
青梅街道まで戻り西へ進む。5分足らずの交差点を右折して北へ進むと、すぐ右手に八坂神社がある。 | |
| 八坂神社 | ||
 |
 |
青梅街道まで戻り西へ進むと、すぐに南西へ大きく曲がる。直進してすぐに右折して北へ進むと、左手に熊野神社がある。 |
| 熊野神社 | 熊野神社 | |
 |
青梅街道まで戻り南西へ進む。すぐの十字路に真福寺への標識があり右折する、すぐ右手に入り天満宮がある。明治維新の神仏分離までは真福寺に属する天満宮だった。 | |
| 入り天満宮社 | ||
 |
 |
 |
| 不明の石塔 / 馬頭観音 | 真福寺山門 | 真福寺本堂 |
 |
入り天満宮社から道なりに進むと、左手に永禄11年(1568年)創建の真福寺がある。途中右手に不明の石塔 / 馬頭観音 がある。安永7年(1778年)建立の本堂天井には、天保10年(1839年)に描かれた200枚を超える格天井花鳥画がある。 |
|
| 晩秋の真福寺 | ||
 |
 |
青梅街道まで戻り南西へ進む。青梅街道はすぐの大曲り交差点を右折して西へ進む。すぐの交差点の先を右折して北へ進むと、原山神明社 / 六ツ指地蔵
がある。江戸時代初期にこの地を治めていた前島十左衛門の娘は、手の指が6本あったと云う。身の不幸を悲しみ自害、村人が哀れんで六ツ指地蔵を造立したと云われている。。 |
| 原山神明社 |
六ツ指地蔵 |
|
 |
青梅街道まで戻り西へ進む。すぐの交差点を右へ進む。標識があり右折すると、狭山三十三観音21番札所の原山観音堂がある。 | |
| 原山観音堂 | ||
 |
 |
 |
| 萩ノ尾薬師堂 | 地蔵の祠 | 庚申塔 |
 |
青梅街道まで戻り西へ進む。5分足らずの右手に、天正18年(1590年)創建の萩ノ尾薬師堂がある。狭山三十七薬師2番札所になっている。薬師堂左手に地蔵の祠 / 庚申塔 / 延文元年(1356年)造立の宝篋印塔 がある。宝篋印塔は基壇 / 塔身 / 笠 / 相輪からなるが、基壇 / 笠 のみとなっている。銘文には「歿故了意禅尼」という被葬者名が彫られている。庚申塔 / 宝篋印塔 は、青梅街道沿いにある。 | |
| 宝篋印塔 | ||
 |
 |
萩ノ尾薬師堂からすぐの左手に武蔵村山市役所がある。すぐの「かたくりの湯入口交差点」を右折して55号線を北へ進む。すぐ左手に熊野神社がある。境内の北側の小路を北へ進むと、5分ほどのところに七所神社がある。武蔵村山市歴史民族資料館が近い。 |
| 熊野神社 | 七所神社 | |
 |
 |
 |
| 長円寺山門 | 長円寺本堂 | 大辨財尊天 |
| 青梅街道まで戻り西へ進む。すぐの交差点に標識があり右折すると、永禄11年(1568年)創建の長円寺がある。天保年間(1830年〜1843年)と嘉永5年(1852年)の火災により、山門を除き焼失した。本堂は明治4年(1871年)に再建されたもの。境内には大辨弁財天がある。 | ||
 |
長円寺の東側に、八坂神社がある。 | |
| 八坂神社 | ||
 |
 |
青梅街道まで戻り西へ進む。すぐの変則十字路を右折すると、すぐ右手に社がある。さらに5分足らずのところに色鮮やかな滝の入不動がある。 |
| 社 | 滝の入不動 | |
 |
 |
青梅街道まで戻り西へ進む。すぐの交差点を過ぎた右手に、和銅年間(708〜713年)創建と云われる十二所神社参道がある。江戸時代の三ツ木村の鎮守。 |
| 十二所神社 | 阿弥陀堂 | |
 |
青梅街道まで戻り西へ進む。すぐに峰交差点があり、すぐに右へ進む。すぐに右折して北へ道なりに進む。突き当たりを左折して道なりに進むと、狭山三十三観音23番札所の慈眼寺がある。 | |
| 慈眼寺 | ||
 |
 |
 |
| 赤稲荷神社 | 宿薬師堂 | 宿子育地蔵 |
| 青梅街道まで戻り西へ進む。5分足らずの右手に嘉永2年(1849年)創建の赤稲荷神社がある。再三の移転を経ている。すぐの交差点の右手に 慶長年間(1596〜1614年)創建の宿(しゅく)薬師堂がある。現在の本堂は昭和15年(1940年)に再建されたもの。狭山三十七薬師3番札所になっている。境内に宿 |
||
 |
 |
 |
| 禅昌寺 | 観音堂 | 須賀神社 |
| 宿薬師堂から5分足らずの岸交差点に標識があり、右折して道なりに北へ進む。5分ほどすると、正長元年(1428年)創建と云われる禅昌寺がある。本堂は文化14年(1817年)に再建されたもの。観音堂は文禄3年(1594年)建立と云われている。狭山三十三観音24番札所になっている。丘陵沿いに北西方面へ進むと、すぐに寛政2年(1790年)創建の須賀神社がある。岸の天王様と呼ばれ、境内の杉や樫の葉を門に吊るすと伝染病に掛らないと云われている。 | ||
 |
岸交差点まで戻り、青梅街道を北西へ進む。すぐの阿豆佐味(あずさみ)天神社前交差点手前右手に、阿豆佐味天神社参道がある。寛平4年(892年)桓武平氏の祖・高望王が創建したと云われ、延喜式神名帳では武蔵国多摩郡八座に数えられている。阿豆佐味天神社の総本宮。 |
|
| 阿豆佐味天神社 | ||
 |
阿豆佐味天神社から左手へ、坂道を登って行くと須賀神社がある。 | |
| 須賀神社 | ||
 |
 |
阿豆佐味天神社参道まで戻り、青梅街道を北西へ進む。すぐの殿ヶ谷交差点の南東側に、殿ヶ谷地蔵 / 不明の石塔 / 火の見櫓がある。 |
| 殿ヶ谷地蔵 | 不明の石塔 | |
 |
 |
 |
| 福正寺三門 | 福正寺本堂 | 福正寺観音堂 |
 |
殿ヶ谷交差点からすぐの交差点に標識があり、右折する。道なりに5分ほど進むと、左手に文保2年(1318年)創建の福正寺がある。本堂前に天然記念物のタラヨウがある。古来、葉は写経に用いられていた。観音堂は天保12年(1841年)に再建されたもの。狭山三十三観音25番札所になっている。小振りな五重塔は、奈良・興福寺五重塔を1/7で建立されたもの。 | |
| 福正寺五重塔 | ||
 |
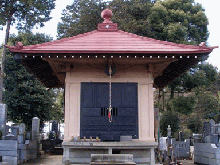 |
福正寺から青梅街道に戻る途中にある十字路を右折する。すぐの変則十字路を右折して北へ進むと、すぐ左手に阿弥陀堂 / 左手にたち山地蔵 と続く。 |
| 阿弥陀堂 | たち山地蔵 | |
 |
 |
青梅街道まで戻り北西へ進む。すぐの交差点を右折して北へ進む。3本目のT字路を左折すると、神明神社がある。青梅街道なで戻り北西へ進むと、すぐ右手に文久3年(1863年)創建の吉野岳地蔵堂がある。総欅(けやき)造りの地蔵堂で、堂内に享保4年(1719年)造立の地蔵がある。 |
| 神明神社 | 吉野岳地蔵 | |
 |
 |
吉野岳地蔵からすぐの交差点を右折して北へ進むと、左手に御嶽神社がある。境内に、推定樹齢350年 / 樹幹42m / 樹高176mの欅(けやき)がある。 |
| 御嶽神社 | 御嶽神社 | |
 |
青梅街道まで戻り北西へ進む。5分ほどすると、分岐がある。三角地帯に箱根ヶ崎時計台がある。昭和6年(1931年)に建てられた木造の箱根ヶ崎時計台があったが、老朽化のため昭和30年代後半に解体撤去された。箱根ヶ崎のシンボルとして、平成15年(2003年)に復元されたもの。 |
|
| 箱根ヶ崎時計台 | ||
 |
左への道は、旧青梅街道の道筋。すぐ右手に稲荷神社 |
|
| 稲荷神社 |
||
 |
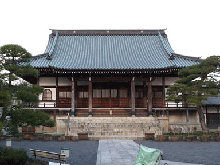 |
 |
| 円福寺三門 | 円福寺本堂 | 円福寺観音堂 |
| 箱根ヶ崎時計台まで戻り、西へ進む。すぐの旧日光街道交差点を越えると、すぐ右手に天正元年(1573年)創建の円福寺がある。狭山三十七薬師 |
||
| 青梅街道は、箱根ヶ崎交差点を直進して西へ進む。 | ||
 |
 |
 |
| 杉山稲荷神社 | 加藤神社 | 加藤塚 |
| 箱根ヶ崎交差点を左折すると、すぐ右手に享和2年(1802年)創建の杉山稲荷神社がある。すぐの交差点を右折すると、JR八高線・箱根ヶ崎駅がある。交差点を直進すると、すぐ右手に加藤神社がある、加藤神社は、天正10年(1582年)箱根ヶ崎で討死した武田氏家臣・加藤景忠を祀り村民により八幡社が創建された。明治35年(1902年)加藤神社と改称した。加藤神社境内に、加藤景忠を埋葬したと云われる加藤塚がある。 | ||
| [寄り道]狭山神社 / 元狭山神社 | ||
 |
箱根ヶ崎交差点を右折して166号線を北東に進む。すぐの交差点から、斜めの小路に進む。道なりに川沿いの道を進むと、すぐの狭山池公園に弁才天がある。 | |
| 弁才天 | ||
 |
 |
166号線まで戻り北東に進む。すぐの交差点を左折すると、すぐ右手に狭山神社の鳥居がある。参道を進み108段を登る。源義家が奥州征伐の永承年間(1046年〜1053年)に箱根権現を勧請したと云われている。境内に、狭山茶創業の沿革が記されている狭山茶場の碑がある。 |
| 狭山神社 | 狭山茶場之碑 | |
 |
166号線まで戻り北東に進む。すぐの狭山神社下交差点を過ぎ、10分足らずの駒形富士山交差点を右へ進む。10分足らずの交差点を右折して道なりに進む。交差点からすぐの左手に、2基の祠が並んでいる。右側が狭山三十七薬師6番札所の池谷庵薬師堂。 | |
| 池谷庵薬師堂 | ||
 |
 |
 |
| 福泉寺 | 萱戸石薬師 | 駒形水天宮 |
| 交差点まで戻り北東へ進むと、すぐ左手に文安年間(1444年〜1448年)創建の福泉寺がある。狭山三十七薬師5番札所になっている。すぐの高根下交差点の北東側に、狭山三十七薬師7番札所・萱戸石薬師がある。5分足らずの左手に駒形水天宮がある。 | ||
 |
狭山神社下交差点を左折して北へ進む。20分ほどの瑞穂三小前交差点手前左手に |
|
| 元狭山神社 | ||