| 旧青梅街道(成木街道)ぶらり旅 |
|
| 01 新宿追分-(約24km)-田無町交差点 |
|
 |
新宿3丁目交差点から北西へ進む。5分足らずのJR新宿駅東口広場に、馬水槽がある。ロンドン水槽協会から東京市に寄贈され、明治39年(1906年)東京市役所前(現:東京国際フォーラム)に設置され大正初期までは荷馬車を曳いた馬が利用していた。大正7年(1018年)麹町・東京市水道局守護門前に移された。大正12年(1923年)関東大震災後は各地を転々、昭和39年(1964年)に移された。赤大理石で造られた水槽で、前面の上部が馬用 / 下部が犬猫用の水飲み場 / 裏面が人間の水飲み場 になっている。
|
| 馬水槽 |
|
 |
旧青梅街道はJRで分断されている。地下道を潜り西口側に出ると、右手に思い出横丁がある。昭和21年(1946年)頃にできた闇市が始まりで、しばらくはションベン横丁と呼ばれていた。交差点手前左手に旧青梅街道標識がある。 |
| 旧青梅街道標識(西口側) |
|
 |
 |
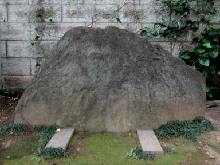 |
| 春の常円寺山門 |
常円寺本堂 |
便々館湖鯉鮒狂歌碑 |
|
 |
 |
 |
| 常泉院本堂 |
水かけ菩薩 |
鬼子母神堂 |
|
|
交差点を越え小田急ハルクの裏を通り、新都心歩道橋下交差点で青梅街道(4号線)に合流する。すぐ右手に天正13年(1585年)渋谷区幡ヶ谷近辺より移転したと云われる常円寺 / 境内を接して寛文年間(1661年〜1672年)創建の常泉院
がある。常円寺の参道入口右手に、文政2年(1819)造立の便々館湖鯉鮒(べんべんかんこりふ)狂歌碑がある。常円寺の山門や境内には春には桜が咲き、春の山門は趣きがある。
|
|
 |
 |
5分足らずの右手に延喜3年(903年)創建の成子天神社がある。すぐの淀橋交差点で302号線と合流、すぐに新宿区と中野区の境の神田川に架かる淀橋を渡る。 |
| 成子天神社 |
淀橋親柱 |
|
 |
淀橋からすぐの中野坂上交差点で、山手通りと交差する。右折して北へ、中野区立第十中学校沿いの小路の左手に白金龍昇宮がある。 |
| 白金龍昇宮 |
|
 |
 |
中野坂上交差点まで戻り、青梅街道を西へ進む。すぐ右手に中本稲荷神社がある。鳥居を潜り狭い階段を登ると社殿がある。
|
| 中本稲荷神社鳥居 |
中本稲荷神社 |
|
 |
 |
 |
| 宝仙寺仁王門 |
宝仙寺本殿 |
宝仙寺三重の塔 |
|
 |
中本稲荷神社から10分足らずの宝仙寺前交差点を右折すると、突き当りに宝仙寺がある。寛治年間(1087年〜1094年)源義家が後三年の役(1083〜87年)を平定して京へ凱旋の途中、護持していた不動明王を以って創建した。再建された三重の塔は、飛鳥様式の純木造建築。中野区立第十中学校の敷地にあった。臼塚は機械化により使われなくなった臼を供養するために、捨てられていた臼を積み上げた塚。
|
| 臼塚 |
|
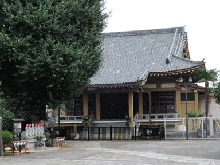 |
宝仙寺前交差点から20分足らずの右手に、門が閉ざされた慈眼寺がある。
|
| 慈眼寺 |
|
 |
慈眼寺からすぐの鍋谷横丁交差点を越えると、すぐに所沢道(ところざわみち)が北西へ分岐する。所沢道は、青梅街道・中野村追分と所沢を結んでいた古道。5分足らずの杉山公園交差点で、中野通り(420号線)と交差する。5分ほどすると、右手に西町天神社 がある。
|
| 西町天神社 |
|
 |
 |
 |
| 旧試験場正門 |
妙法寺青銅製燈籠(東側) |
妙法寺青銅製燈籠(西側) |
|
|
西町天神社から10分足らずの左手に蚕糸の森公園がある。 明治44年(1911年)に開設された農商務省原蚕種製造所が始まりの蚕糸試験所があったところで、昭和55年(1980年)茨城県つくば市へ移転した跡地。煉瓦造りの旧試験場正門が残る。角の小路は妙法寺旧参道で、青銅製燈籠が対に並んでいる。
|
|
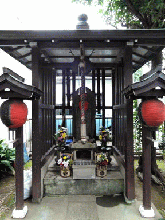 |
 |
蚕糸の森公園からすぐに環七通りと交差する。5分ほどすると五日市街道入口交差点がある。五日市街道は、五日市や檜原から木材・炭などを運ぶために整備された街道。往時の分岐は100mほど西の交差点で、大法寺前で新旧の道が合流している。5分ほどすると、左手に寛永年間(1624年〜1645年)創建の清見寺 / 入口に清見寺地蔵堂 がある。
|
| 清見寺地蔵堂 |
清見寺本堂 |
|
 |
清見寺から 15分ほどの天沼陸橋交差点から、旧青梅街道は左へ進む。JR荻窪駅北口にあった地図を見ると、東京メトロ丸の内線が地下を通っている。すぐに旧青梅街道はJR中央線で分断され、地下道で北側に出る。線路沿いに西へ進み、JR荻窪駅北口を通り青梅街道に合流する。
|
| JR荻窪駅北口の案内地図(抜粋) |
|
 |
荻窪駅北口から20分ほどの荻窪警察署前交差点の手前右手に、元禄時代(1688年〜1704年)以前の創建と云われる薬王院薬師堂がある。慶長2年(1597年)創建された観音寺が始まりの観泉寺に、明治維新に併合される。観泉寺は杉並区今川にある戦国大名・今川氏末裔の菩提寺。
|
| 薬王院薬師堂 |
|
 |
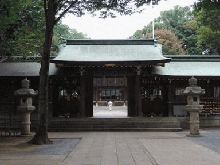 |
 |
| 荻窪八幡神社鳥居 |
荻窪八幡神社神門 |
荻窪八幡神社拝殿 |
|
 |
薬王院からすぐ左手に寛平年間(889年〜898年)創建と云われる荻窪八幡神社がある。永承6年(1051年)源頼義が奥州征伐のとき宿陣、戦勝祈願したと云われている。本堂手前左手に、道灌槇(どうかんまき)と呼ばれる御神木がある。文明9年(1477年)太田道灌が石神井城を攻めるに当たり、故事に倣い植えたもの。 |
| 道灌槇 |
|
 |
 |
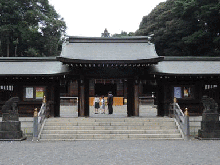 |
| 井草八幡宮北参道大鳥居 |
井草八幡宮楼門 |
井草八幡宮神門 |
|
 |
荻窪八幡神社から15分足らずの左手に、井草八幡宮東参道大鳥居がある。青梅街道を北西に進んだ井草八幡前交差点左手には、井草八幡宮北参道大鳥居がある。境内に「頼朝公御手植の松」がある。源頼朝が文治2年(1186年)奥州藤原泰衡征討の際、戦勝を祈願して植えたと云われている。昭和48年(1973年)に枯れ、2代目となっている。
|
| 井草八幡宮拝殿 |
|
 |
井草八幡宮北参道大鳥居からすぐ左手に文政9年(1826年)造立の三山供養塔 / 享保14年(1729年)造立の江戸向き地蔵 / 善福寺200m標識 / 善福寺公園460m標識 がある。
|
| 三山供養塔 / 江戸向き地蔵 |
|
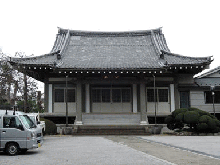 |
左折すると、すぐ右手に福寿庵が始まりの善福寺がある。地名の由来となったとされる善福寺は、善福寺池のほとりにあった。江戸時代に災害により壊滅、そのまま廃寺になったため現存しない。 |
| 善福寺 |
|
 |
青梅街道に戻り北西へ進む。10分足らずの左手に、江戸時代中期の創建と云われる竹下稲荷神社がある。
|
| 竹下稲荷神社 |
|
 |
 |
| 社 |
勢至菩薩 / 関のかんかん地蔵 / 大日如来 |
|
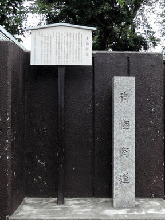 |
竹下稲荷神社から5分足らずの関町1丁目交差点を越えた左手に社がある。さらに5分足らずの右手に、寛保元年(1741年)造立の勢至菩薩 / 江戸時代中期造立の関のかんかん地蔵 / 享保14年(1729年)造立の大日如来 がある。すぐの石神井西小学校前に、青梅街道案内板 / 青梅街道石標
がある。
|
| 青梅街道案内板 / 青梅街道石標 |
|
 |
 |
青梅街道案内板 / 青梅街道石標 から20分ほどすると、右手に文政9年(1826年)建立の大日如来堂がある。すぐ右手にある保谷東伏見郵便局手前辺りから西東京市東伏見5丁目歩道橋辺りまで、北にに孤を描く旧青梅街道のなごりの様な道が道がある。 |
| 大日如来堂 |
東伏見5丁目歩道橋から見た道 |
|
 |
 |
 |
| 東伏見稲荷神社鳥居 |
東伏見稲荷神社神門 |
東伏見稲荷神社拝殿 |
|
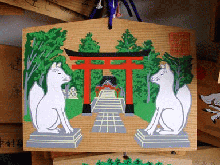 |
保谷東伏見郵便局から5分ほどすると、東伏見交差点がある。東伏見交差点を右折すると、すぐ左手に昭和4年(1929年)創建の東伏見稲荷神社がある。東伏見の地名は、神社創建されてから付いた地名。昭和2年(1927年)開業の西武新宿線・上保谷駅は、昭和4年(1929年)東伏見駅に改称する。
|
| 東伏見稲荷神社絵馬 |
|
 |
 |
 |
| 柳沢寺 |
弘法大師供養塔 |
柳沢庚申塔 |
|
|
東伏見交差点まで戻り、青梅街道を西へ進む。10分足らずの右手に柳沢寺がある。すぐの西武新宿線を潜ると、すぐ右手に道標を兼ねた弘法大師供養塔 / 左手に享保8年(1723年)造立の柳沢庚申塔 と続く。
|
|
 |
|
 |
| 絵馬 |
|
 |
| けやき / 田無神社拝殿 |
茅の輪くぐりの津島神社 |
|
| 柳沢庚申塔からすぐの田無町1丁目交差点を左折する。直進は所沢街道(4号線)で、5分ほどの北原交差点で新青梅街道と斜めに交差している。田無町1丁目交差点からすぐ右手に、正応年間(1288年〜1292年)谷戸の宮山に尉殿(じょうどの)大権現として創建したのが始まりの田無神社がある。青梅街道が整備されて宿場町が形成されると、寛文10年(1670年)住民とともに移転させられる。明治5年(1872年)田無神社と改称する。 安政5年(1858年)建立の本殿は、柴又帝釈天や川越氷川神社を手がけた名工・嶋村源三の装飾彫刻で知られている。拝殿は明治8年(1875年)の建立。津島神社や室町時代創建の野分初稲荷大社など、境内社が多い。 |
|
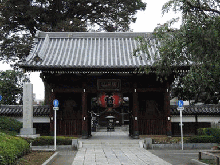 |
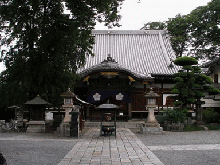 |
 |
| 総持寺山門 |
総持寺本堂 |
けやき / 総持寺妙見堂 |
|
|
田無神社からすぐの総持寺・田無神社前交差点を越えると、右手に元和年間(1615年〜1623年)西武池袋線・ひばりが丘駅に近い谷戸に西光寺として創建したのが始まりの総持寺がある。青梅街道が整備されて宿場町が形成されると、慶安年間(1648年〜1651年)住民とともに移転させられる。江戸時代には尉殿権現社(現:田無神社)の別当寺だった。明治8年(1875年)密蔵院
/ 観音寺 と合併、総持寺と改称した。境内には、けやきが多い。妙見堂には、妙見菩薩 / 不動明王 / 安政6年(1859年)造立の下田半兵衛木像 がある。下田半兵衛は田無村名主で、尉殿大権現(現:田無神社)の拝殿再建や福祉行政の先駆けともいえる善政を行った人物。御用勤勉により苗字を許された。
|
|
 |
総持寺山門前は四季の花が咲いている、白い曼珠沙華を後に青梅街道を西に進むと、すぐに田無町交差点がある。左折すると、すぐの踏切の右手に西武新宿線・田無駅がある。 |
|
 |