| 旧志木街道 |
|
| 04 野火止交差点-(志木街道)-新河岸川 |
|
| JR武蔵野線・新座駅から254号線を東へ進む。5分足らずの野火止交差点で志木街道(40号線)と交差する。 |
|
|
|
| [寄り道]平林寺 |
|
 |
 |
| 総門 |
|
 |
| 佛殿 |
山門 |
|
 |
 |
 |
| 中門 |
本堂 |
半僧坊 |
|
| 野火止交差点から254号線を東へ進む。10分ほどの新座警察署交差点を右折して南へ進むと、5分足らずの左手に新座市役所 / 道を挟んだ反対側に平林寺(有料施設)がある。山門までは、さらに5分ほど掛かる。永和元年(1375年)現:さいたま市岩槻区に創建される。寛文3年(1663年)
川越藩主・松平信綱の遺志により、松平輝綱が菩提寺として野火止に移転する。境内林は武蔵野の面影を残す雑木林として、国の天然記念物に指定されている。山門は寛文4年(1664年)建立 / 佛殿は寛文3年(1663年)の建立 / 本堂は明治13年(1880年)の再建。 |
|
 |
 |
 |
| 松平信綱の墓 |
松平信綱五輪塔 |
松平信綱夫人五輪塔 |
|
| 大河内松平家歴代の墓 / 松平信綱夫妻墓 がある。松平信綱五輪塔には「河越侍従松平伊豆守信綱 松林院殿乾徳禅梁大居士 寛文二壬寅年三月十六日」
/ 松平信綱夫人五輪塔には「源姓井上氏 隆光院殿太岳静雲大師 寛永十三年丙子三月七日」 と彫られている。 |
|
 |
 |
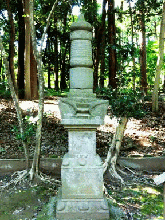 |
| 増田長盛墓 |
島原の乱供養塔 |
見性院供養塔 |
|
| 増田長盛墓 / 島原の乱供養塔 / 見性院供養塔 などもある。増田長盛墓は豊臣政権五奉行の一人で、元和元年(1615年)大坂夏の陣後に自害させられた。平林寺移転に伴い、移された。島原の乱供養塔は、寛永14年(1637年)〜寛永15年(1638年)島原の乱戦没者を供養するため文久元年(1861年)に造立された。見性院(けんしょういん)は武田信玄の次女で、武田家親族衆・穴山信君(梅雪)の正室。天正10年(1582年)織田信長・徳川家康連合軍の甲州征伐のとき、穴山信君(梅雪)は織田・徳川方に味方する。本能寺の変のとき上方にいた穴山信君(梅雪)は、宇治田原において殺害される。見性院の子・穴山勝千代が跡を継ぐが、天正15年(1587年)早世して穴山氏は断絶する。見性院は、江戸幕府2代将軍・徳川秀忠が侍女・お静に生ませた幸松(保科正之)を養育した。保科正之は会津松平家初代藩主で、徳川家康の孫 / 江戸幕府3代将軍・徳川家光の異母弟
になる。江戸幕府3代将軍・徳川家光と江戸幕府4代将軍・徳川家綱を輔佐して、幕閣に重きをなした。
|
|
| 平林寺境内に野火止用水(のびどめようすい)平林寺堀 / 境内に沿った西側に野火止用水本流 が流れている。野火止用水は 、東京都立川市の玉川上水(小平監視所)から埼玉県新座市を経て新河岸川(志木市)までの約24kmの用水路。承応2年(1653年)幕府老中で上水道工事を取り仕切っていた川越藩主・松平信綱は、多摩川の水を羽村から四谷までのす玉川上水を開削した。承応4年(1655年)には野火止用水が完成する。開削に前後して川越藩では農民や家臣を多数入植させ、大規模な新田開発を行った。野火止用水の開削によって生活が豊かになったことを感謝して、官職名の伊豆守から伊豆殿堀(いずどのぼり)と呼ぶ様になった。戦後に野火止用水は本来の役割を終える。生活排水が用水に入る様になり、水質汚染が激しくなる。昭和48年(1973年)には、玉川上水からの取水が停止される。埼玉県と新座市は野火止用水を後世に残すため用水路の浚渫(しゅんせつ)などを行い、昭和59年(1984年)高度処理水(下水処理水)を使用して水流が復活した。 |
|
 |
 |
野火止用水本流が流れる水道道路・西堀交差点南西側に、馬頭観音 / 馬頭観音 / 寛政6年(1794年)造立の庚申塔 がある。 |
| 水道道路・西堀交差点付近 |
馬頭観音 / 庚申塔 |
|
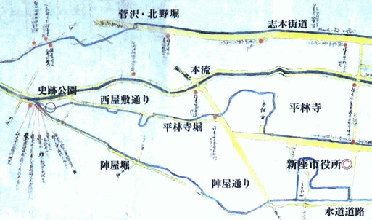 |
 |
| 野火止用水古絵図(野火止用水案内板) |
野火止用水平林寺堀 |
|
 |
 |
 |
| 野火止用水平林寺堀 |
野火止用水平林寺堀 |
野火止用水平林寺堀の鴨 |
|
 |
 |
西堀公園交差点から水道道路を北東へ進むと、右手に史跡公園がある。ここにある西堀分岐から平林寺堀が分岐している。公園内を流れ、平林寺境内の雑木林に続いている。 |
| 野火止用水平林寺堀 |
平林寺境内 |
|
|
|
 |
 |
野火止交差点まで戻り、志木街道を北東へ進む。5分ほどするとJR武蔵野線を潜る。さらに30分ほどすると東武東上線を潜る。15分ほどの本町3丁目交差点を渡る左手角に、道標がある。本町3丁目交差点を渡った右手に正徳5年(1715年)造立の西川地蔵がある。 |
| 道標 |
西川地蔵 |
|
 |
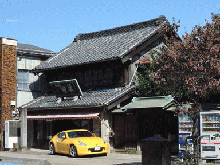 |
 |
| 複合店舗 |
薬舗 |
道標 |
|
|
西川地蔵から5分足らずの右手に前面のみ蔵造り風の複合店舗 / 右手に薬舗 と続く。薬舗前に道標 がある。
|
|
 |
 |
薬舗からすぐの市場坂上交差点の手前右手に、市場跡標柱 / 案内板 がある。市場坂上交差点を渡る手前左手に、慶応2年(1866年)頃と推定されている旧西川家潜り門がある。西川家の中庭にあったもの。西川家は幕末には酒造業
/ 水車業 / 肥料商 を営み、引又(ひきまた)町の組頭を務めていた。
|
| 市場跡標柱 |
旧西川家潜り門 |
|
 |
 |
| 柳瀬川 |
旧村山快哉堂 |
|
|
市場坂上交差点からすぐに柳瀬川に架かる栄橋を渡ると、左手に志木市役所 / 右手に明治10年(1877年)築の旧村山快哉(かいさい)堂がある。木造2階建て土蔵造りの店蔵で,江戸時代から中風根切薬 / 分利膏 / 正齋湯 などの家傅薬を製造・販売していた薬店。本町3丁目から移築された。
|
|
 |
旧村山快哉堂からすぐに新河岸川に架かる“いろは橋”がある。柳瀬川と新河岸川は、すぐ東側で合流している。柳瀬川と新河岸川の流れは往時と異なっているが、この辺りが引又河岸(ひきまたかし)があったところ。江戸への新河岸川(しんかしがわ)舟運が盛んだった。新河岸川に架かる“いろは橋”の北東側に、引又河岸が再現されている。
|
| 新河岸川 |
|
 |