|
| 最新の追加 |
|
|
| 備後国・大可島だいがしま城 |
 |
■城の種別
海城
■築城者
岡部出羽守
■築城年
南北朝時代(1336年〜1392年) |
| 円通寺本堂 |
|
鞆港バス停から東に、すぐに右折して南に進む。Y字路を左に進み石段を登ると、室町時代創建の釈迦堂が始まりの円福寺がある。円通寺本堂前に大可島城趾案内板がある。
[交通]JR山陽本線・福山駅-(バス)-鞆港バス停-(徒歩5分)-円通寺 |
|
 |
往時は島であったが、慶長5年(1600年)頃に埋め立てられて地続きになった。瀬戸内海の良港・鞆の津を支配する要衝で、制海権を巡って戦いが繰り返された。康永元年 / 興国3年(1342年)鞆沖大海戦のとき、鞆の浦が戦場となり街並みは焼失した。桑原重信が守る大可島城は北朝方に攻略された。
天文年間(1532年〜1555年)に大可島城は廃城となったが、遠見番所が置かれていた。円通寺は慶長15年(1610年)頃に現地に移転した。
|
| 円通寺本堂裏からの眺望 |
|
 |
鞆の浦は古くから瀬戸内海の潮待ちの港として知られ、万葉集にも謡われた風光明媚な場所。江戸時代の趣ある建物や数多くの寺社がある。 |
| 鞆港 |
|
 |
鞆港バス停まで戻り、港の護岸沿いに進む。すぐのY字路を右へ進むと、すぐ右手に鞆の津の商家(福山市重文)がある。主屋は江戸時代末期築で、当初は呉服店で後に船具店となった。 |
| 鞆の津の商家 |
|
 |
すぐのY字路は道なりに右に進む。すぐの2本目のT字路を左折して北へ進む。10分ほどの十字路を左折すると、突き当りに文永10年(1273年)創建の安国寺がある。室町時代中期建立の釈迦堂があるが、無常にも「無断拝観禁ず」と標示されている。
|
| 安国寺 |
|
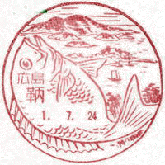 |
十字路まで戻り直進すると、22号線と交差する。左折して北へ進むと、すぐ左手に鞆郵便局がある。風景印は、仙酔島 / 鞆港 / 名産・鯛 の図柄になっている。
鞆郵便局から22号線を南に進むと、安国寺下バス停(福山駅行)がある。 |
| 鞆郵便局風景印 |
|
|
|
| 美作国・津山城(鶴山城) |
 |
■城の種別
平山城
■築城者
山名忠政
■築城年
嘉吉年間(1441年〜1444年)
■主な遺構
石垣 / 堀
■主な再建造物
備中櫓 |
| 石垣 |
|
JR津山線 / 姫新線・津山駅から53号線を北へ進み、大手町交差点を右折する。二本目の道を左折すると、正面に石段が見える。応仁の乱で山名氏が衰退、のちに廃城となる。遺構は、慶長8年(1603年)に入封した森忠政が築城したもの。城址は鶴山(かくざん)公園として桜の名所となっている。城内は有料施設で早朝は入れないため、備中櫓は見られなかった。津山駅からの姫新線や因美線は、時間帯により恐ろしい接続となっている。
[交通]JR津山線 / 姫新線・津山駅-(徒歩/約15分)-鶴山公園 |
|
| 備前国・岡山城(烏城うじょう / 金烏城きんうじょう) |
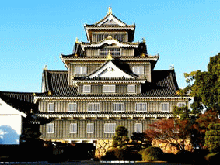 |
■城の種別
平山城
■築城者
上神高直
■築城年
正平年間(1346年 〜1369年)
■主な遺構
月見櫓(重文) / 西の丸西手櫓(重文) / 石垣 / 堀
■主な再建造物
天守 / 不明門 / 廊下門 / 六十一雁木上門 / 塀 |
| 復興天守 |
|
JR山陽本線・岡山駅東口から桃太郎通りを進むと、再建された岡山城復興天守が見えてくる。
正平年間(1346年〜1369年)名和氏の一族・上神高直が築城したのが始まりと云われている。大永年間(1521年〜1528年)には、金光氏が居城していた。元亀元年(1570年)宇喜多直家は金光宗高を謀殺、この地を支配した。宇喜多直家は浦上宗景の被官であったが、備前西部に勢力を拡大していた。天正3年(1575年)浦上宗景を播磨へ放逐、備前
/ 美作 を支配した。宇喜多直家の子・宇喜多秀家は、豊臣政権下で57万4000石となる。天正18年(1590年)〜慶長2年(1597年)大改修が行われ、近世城郭としての体裁を整えた。
慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いで西軍の主力となり改易、宇喜多秀家は八丈島に流刑された。小早川秀秋が備前 / 美作52万石として入封する。慶長7年(1602年)岡山で急死、嗣子がなく断絶する。
慶長8年(1603年)備前28万石は、姫路城主・池田輝政の次男・池田忠継に与えられる。池田輝政の継室は徳川家康の次女・督姫で、池田忠継は徳川家康の孫にあたる。慶長20年(1615年)に死去、元和元年(1615年)池田忠継の弟・池田忠雄が淡路島より31万5千石で入封した。池田忠雄も徳川家康の孫にあたる。寛永9年(1632年)池田忠雄の子・池田光仲は鳥取へ転封となり、代わって鳥取から池田光政が31万5千石で入封した。池田光政は姫路藩2代藩主・池田利隆の長男。母は徳川秀忠の養女で、榊原康政の娘・鶴姫。以後、幕末まで続く。
[交通]JR山陽本線・岡山駅-(徒歩/約30分)-烏城公園 |
|
 |
 |
| 旭川 / 石垣 |
西の丸西手櫓(重文) |
|
 |
 |
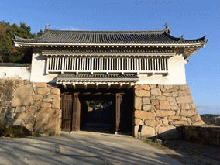 |
| 石垣 / 塀 |
廊下門 |
不明門 |
|
 |
 |
 |
| 六十一雁木上門 |
月見櫓(重文) |
月見櫓(重文) |
|
| 池田綱政により、貞享4年(1687年)から14年を掛けて後楽園が造営される。周囲を土塁と竹垣で囲み、城を守る郭の役割があったと云われている。水戸・偕楽園
/ 金沢・兼六園 とともに、日本三名園に数えられている。明治6年(1873年)廃城になり、御殿 / 櫓 / 門のほとんど が取り壊された。堀は内堀の一部を除いて埋められた。慶長2年(1597年)築の天守は昭和6年(1931年)に旧国宝に指定されるが、昭和20年(1945年)岡山空襲で焼失する。外観は黒漆塗の下見板が特徴で、烏城とも呼ばれていた。昭和41年(1966年)鉄筋コンクリート造りで外観復元される。西之丸西手櫓は、5分ほど西の小学校跡地にある。京橋御門が岡山市南区小串に移築され現存している。城跡は烏城公園として整備されている。 |
|
 |
 |
往時の天守閣の礎石が、保存されている。元の通りの配置になっている。香川県豊島産の凝灰岩(豊島石)の切石で造られた穴蔵があり、非常用の食料を保存していたと云われている。 |
| 天守閣の礎石 |
穴蔵 |
|
| 備前国・下津井城 |
 |
■城の種別
山城
■築城者
宇喜多秀家
■築城年
永禄年間(1592年〜1596年)
■主な遺構
石垣 / 堀 / 移築城門 |
| 本丸跡 |
|
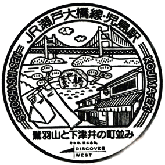 |
 |
| 児島駅スタンプ |
下津井循環線とこはい号 1日乗車券 |
|
| 本四備讃線(瀬戸大橋線)・児島駅で下車する。児島駅のスタンプは、鷲羽山と下津井の町並みの図柄になっている。下津井循環線とこはい号に乗車、下津井城址入口バス停で下車する。 |
|
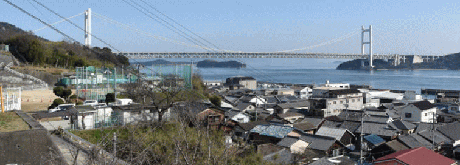 |
 |
| 登城途中からの眺望 |
三の丸下の石垣 |
|
 |
 |
瀬戸大橋を見上げながら東へ進む。すぐに道路標識があり、左折して道なりに坂を登る。分岐を右方向に進むと、すぐ左手に三の丸下の石垣がある。すぐ左手に下津井城跡標柱があり、突き当りから坂を登ると三の丸跡がある。 |
| 下津井城跡標柱 |
三の丸跡 |
|
 |
 |
| 二の丸からの眺望 |
本丸跡 |
|
東屋がある二の丸から、瀬戸内海の島影が見える。本丸には天守があったと云われている。南側に下津井の町並みを見下ろす丘陵の上にあり、北側の丘陵に侍屋敷が配されていた。遺構としては石垣 / 土塁 が残っているのみであるが、倉敷市天城・正福寺に城門と云われる門が移築されている。
[交通] 下津井城址入口バス停-(徒歩25分)-下津井城三の丸 |
|
砦を文禄年間(1592年〜1596年)岡山城主・宇喜多秀家が出城として改修したのが下津井城の始まりと云われている。
慶長5年(1600年)関ヶ原合戦で西軍に属した宇喜多秀家は改易となる。小早川秀秋が岡山に入封、重臣・平岡頼勝が城代となった。慶長7年(1602年)小早川秀秋が急死する。慶長8年(1603年)池田忠継が岡山藩主となり、池田輝政の弟・池田長政が城代となり近世城郭に改修した。
慶長14年(1609年)池田輝政の甥・池田由之が城代となる。慶長18年(1613年)池田忠継の重臣・荒尾成利が城代となる。寛永9年(1632年)池田由成が城代となる。寛永16年(1639年)一国一城令により廃城となる。 |
|
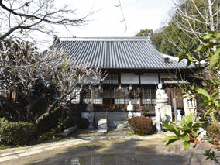 |
 |
| 円福寺 |
下津井港 |
|
| 下津井城から下津井城址入口バス停方向に戻る。バス停がある21号線北側の道を西に進む。港町の風情が残る道を進むと、右手に円福寺がある。すぐに21号線と合流、下津井港に出る。 |
|
 |
 |
| モハ103 / モハ1001 |
ホジ3 |
|
下津井港沿いに進む。すぐの十字路を左折して、下津井港沿いに南に進む。すぐに右折すると、下津井電鐵・下津井駅跡がある。
下津井は天然の良港に恵まれ、奈良時代・平安時代の文献にも記載されている港町である。下津井・丸亀間は、本州と四国を結ぶ航路の主要ルートであった。江戸時代から明治時代にかけては、北前船の寄港地
/ 金比羅参りの渡し場 として賑わった。
明治43年(1910年)国鉄宇野線が開通、宇野・高松間で宇高連絡船の運航が開始される。下津井・丸亀航路の利用者は激減したため、大正3年(1914年)下津井軽便鉄道により茶屋町駅・下津井駅間21kmが軌間762mmで全通する。昭和24年(1949年)電化され、下津井電鉄に改称する。岡山・倉敷へは、乗り換えの必要がなく所要時間も短い自社バスの利用客が増加する様になる。昭和47年(1972年)茶屋町駅・児島駅間14.5kmが廃止される。昭和63年(1988年)本四備讃線(瀬戸大橋線)が開通するが好転することなく、昭和65年(1990年)残る児島駅・下津井駅間6.5kmも廃止された。
旧下津井駅が保存されており、車両も置かれている。 |
|
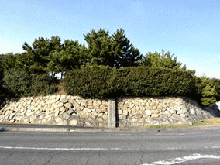 |
 |
21号線まで戻り、東へ進む。10分足らずの突き当りは浄山と呼ばれる丘で、源平合戦時代の下津井古城跡。現在は祇園神社になっている。
|
| 下津井古城跡 |
祇園神社 |
|
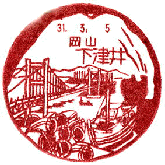 |
突き当りを右折して海岸沿いに道なりに進む。5分余りで下津井郵便局バス停がある。下津井郵便局は、北側の港町の風情が残る道にある。風景印は、瀬戸大橋
/ 漁船 / たこつぼ / 天然記念物・象岩 の図柄になっている。 |
| 下津井郵便局風景印 |
|
| 備中国・高梁城(松山城) |
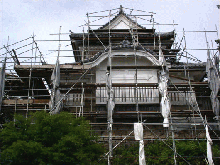 |
■城の種別
山城
■築城者
秋葉重信
■築城年
仁治元年(1240年)
■主な遺構
天守(重文) / 二重櫓(重文) / 三の平櫓東土塀(重文) / 石垣 / 土塁
■主な再建造物
五の平櫓 / 六の平櫓 / 本丸南御門 / 東御門 / 腕木御門 / 路地門 |
| 天守 |
|
|
天守(重文)は天和元年(1681年)に建てられたもの。現存12天守で唯一の山城である。岐阜・岩村城、奈良・高取城とともに日本三大山城に数えられている。
[交通]JR伯備線・備中高梁駅-(徒歩/約60分)-高梁城天守
|
| |
| 備中国・高松城 |
 |
■城の種別
平城
■築城者
石川氏
■築城年
不明
■主な遺構
水攻め堰堤の一部 |
| 高松城址公園 |
|
 |
JR山陽本線・岡山駅より吉備線(きびせん)・総社駅行きに乗車する。桃太郎線という愛称が付けられており、2両編成の先頭車両は、キハ40系ラッピング気動車であった。 |
| キハ40系ラッピング気動車 |
|
 |
備中高松駅より線路沿いに北西に進む。すぐの突き当りを右折して踏切を渡り、北へ進む。すぐの水路に架かる橋の親柱に、“史跡ふなはし”と彫られている。高松城の南手口で、外堀の八反堀があったところである。防御のとき、すぐに遮断できる約64mの舟橋があった。
|
| 舟橋跡 |
|
 |
すぐ左手に高松城址公園がある。永禄3年(1560年)頃に、毛利氏と同盟した三村氏が備中国の支配をほぼ手中にした。築城時期ははっきりしないが、三村氏家臣・石川氏によって築城された。比高2〜3mの微高地に土塁によって築城された平城。東西200m / 南北550m ほどの縄張りは、南北に主郭 / 二の郭 / 三の郭 と設けられていた。周囲は低湿地帯で天然の堀となっていた。城の痕跡はほとんど残っていない。高松城址公園として整備され、資料館がある。
[交通]備中高松駅-(徒歩15分)-高松城址公園 |
| 高松城址公園 / 資料館 |
|
三村元親は毛利氏と対立する様になり、天正3年(1575年)備中兵乱で三村氏とともに石川氏は滅ぼされる。清水宗治が城主となるが、備中国高松城は織田軍と毛利軍対峙の場になった。
天正10年(1582年)羽柴秀吉は高松城攻めに取り掛かる。高松城は周囲が沼地に囲まれた難攻不落とされていたため、持久戦となった。城を堰堤で囲む土木工事が始まり、突貫工事で11日後に堤防が完成する。梅雨時で堰堤内には水が溢れ、低湿地にあった高松城は水没した。本能寺の変で織田信長が討たれると羽柴秀吉は和議を成立させ、城兵の命と引き替えに清水宗治は切腹する。羽柴秀吉は高松城から姫路城まで約100kmを2日間で踏破、さらに約100kmの摂津・山城国境付近の山崎の戦いで明智光秀の軍を撃破した。“中国大返し”と云われ、日本史上屈指の大強行軍として知られている。
高松城は宇喜多直家の領土となり、慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いの後は宇喜多氏の旧臣・花房職秀が城主となる。慶長20年(1615年)の一国一城令で廃城となったと云われている。 |
|
 |
 |
 |
| 清涼閤 |
清水宗治位牌堂 |
星友寺 |
|
| 高松城址公園駐車場の道を挟んだ東側に、清涼閤 / 清水宗治位牌堂 / 寛永元年(1624年)頃創建と云われる星友寺 がある。
|
|
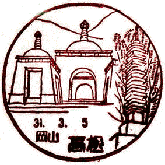 |
踏切まで戻り、直進する。すぐに180号線と交差、右折して北西に進むと、すぐ右手に高松郵便局がある。風景印は、最上稲荷仁王門 / 清水宗治首塚
の図柄になっている。 |
| 高松郵便局風景印 |
|
 |
高松郵便局から180号線を戻り、南東に進む。5分足らずで備中高松交差点がある。左折すると、すぐの突き当りに備中高松駅がある。180号線を南東に進み、5分足らずの交差点を左折して踏切を渡る。道なりに進むとすぐに突き当り、左折して北西に進む。すぐ前方に、高松城水攻め築堤跡がある。堰堤跡は高松城水攻め史跡公園になっている。 |
| 高松城水攻め築堤跡 |
|
| 備中国・高越たかこし城(高越山城) |
 |
■城の種別
山城
■築城者
宇都宮貞綱
■築城年
弘安4年(1281年)
■主な遺構
曲輪 / 土塁 / 堀切 |
| 高越城址石柱 |
|
井原鉄道・早雲の里荏原(えばら)駅から北に進む。すぐの十字路に「4km 高越城址」標識があり、右折して東に進む。5分余りの十字路に「←高越城址 3.4km」標識がある。この標識は大きく迂回して高越城址に至る車道。十字路を直進、すぐに小川を渡る。すぐの十字路を右折すると、すぐ左手に「高越城址」標識があり左折する。ほぼ道なりに進む小路であるが標識がなく、地元の方に道を尋ねる。次の標識のあるところまで、親切に案内していただく。この標識から20分ほど登ると高越城址とのこと。途中から急坂になり、前日の雨で濡れており滑り易かった。
[交通]井原鉄道・早雲の里荏原駅-(徒歩/約45分)-高越城本丸 |
|
 |
 |
| 井原市街地眺望 |
|
 |
| 本丸土壇 |
本丸東屋 |
|
 |
蒙古来襲に備え、弘安4年(1281年)山陽道警護のために執権・北条時宗から命じられた下野国・宇都宮貞綱によって築城されたと云われている。享徳2年(1453年)伊勢行長がこの地に下向、高越城を居城とした。小田原北条氏の祖・伊勢新九郎盛時(のちの北条早雲)は、康正2年(1456年)伊勢盛定の子としてこの地で誕生したと云われている。伊勢氏没落後の天正9年(1581年)には宍戸隆家の持城となり、慶長5年(1600年)毛利氏の転封に伴い廃城となった。宍戸隆家は毛利元就の長女・五龍局を正室にした毛利家の重臣。
標高172.3mの高越山に築かれ、本丸の小高い土壇に北条早雲生誕の地碑 / 高越城址石柱 などがある。 |
| 左:北条早雲生誕の地碑 |
|
 |
往路の急坂が滑り易かったため、帰路は大きく迂回する車道を早雲の里荏原駅まで約4.5kmを歩く。本丸から車道方向に進むと城門があり、車道に出る。右折して道なりに進むが、ここに標識はない。下り坂と思っていたら、アップダウンが2ヶ所あった。 |
| 城門 |
|
| 備後国・福山城(久松城 / 葦陽城) |
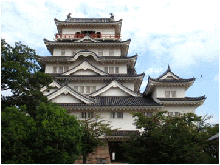 |
■城の種別
平山城
■築城者
水野勝成
■築城年
元和8年(1622年)
■主な遺構
伏見櫓(重文) / 筋鉄御門(重文) / 鐘楼 / 石垣
■主な再建造物
天守 / 月見櫓 / 御湯殿 |
| 復興天守 |
|
|
昭和41年(1966年)天守が復興される。
[交通]JR山陽本線・福山駅-(徒歩/約5分)-福山城
|
|
| 備後国・三原城(浮城 / 玉壺城) |
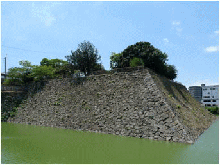 |
■城の種別
平城
■築城者
小早川隆景
■築城年
永禄10年(1567年)
■主な遺構
石垣 / 堀
侍屋敷門が糸崎神社神門に、作事奉行所門が順勝寺山門に移築され現存する。 |
| 本丸天主台 |
|
| JR山陽本線・三原駅北口側から本丸天主台への通路がある。明治27年(1894年)山陽鉄道・三原駅建設の際に、城地は駅用地に使用される。山陽新幹線開業時には、本丸跡を貫いている。天文19年(1550年)竹原・沼田の両小早川家を掌握した小早川隆景(毛利元就三男)は、高山城〜新高山城〜三原城へと本拠を移す。小早川水軍の差配に便利な地で、軍港の機能を備えていた。 |
|
 |