| 最新の追加 | ||
| 伊賀国・名張陣屋(名張城) | ||
 |
■城の種別 陣屋 ■築城者 松倉勝重 ■築城年 天正13年(1585年) ■主な遺構 藤堂家屋敷 / 武家屋敷門 |
|
| 藤堂家屋敷北西側 | ||
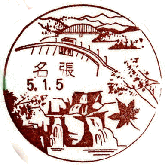 |
近鉄大阪線・名張駅西口から南西に進む。すぐの交差点を右折して57号線を北西に進むと、すぐ右手に名張郵便局がある。風景印は 青蓮寺湖 / 赤目四十八滝 / 荷坦滝 / 紅葉 の図柄になっている。すぐの交差点を左折して坂を登ると、左手に名張小学校 / 右手に藤堂家屋敷 がある。 |
|
| 名張郵便局風景印 | ||
 |
天正13年(1585年)筒井定次の家臣・松倉勝重によって築城されたのが始まり。名張郵便局の57号線を挟んだ向かい側にある名張中学校と、北東側の丘にある名張小学校が城域であった。藤堂家屋敷は宝永7年(1710年)名張大火で焼失、現残する建物は大火後に徐々に再建・増築されたもの。 残念ながら月曜日と木曜日は休館日で、藤堂家屋敷の門は閉ざされていた。 |
|
| 藤堂家屋敷の門 | ||
 |
藤堂家屋敷左側の小路を北西に道なりに進むと、寛文8年(1670年)創建の寿栄(ひさか)神社がある。寿栄神社の名は、藤堂高吉の法号から名付けられている。藤堂家屋敷内にあったが、明治24年(1891年)現在地に移転した。名張城の裏手だったところで、昭和10年(1935年)に移築された藤堂家の武家屋敷門がある。 |
|
| 境内側からの武家屋敷門 | ||
|
慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いの後、藤堂高虎は宇和島城8万石に今治城12万石が加増され20万石となった。慶長13年(1608年)今治城周辺の越智郡2万石
/ 伊賀国内10万石 / 伊勢安濃郡・一志郡内10万石 計22万石となり、津城を本拠とする。 |
||
| 伊勢国・桑名城(扇城 / 旭城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 本多忠勝 ■築城年 慶長6年(1601年) ■主な再建造物 蟠龍櫓 |
|
| 堀 | ||
| JR桑名駅から東へ、1号線を東へ進む。しばらくすると桑名城の堀が見えてくる。桑名城から北へ進むと、“七里の渡跡”がある。旧東海道は愛知県・宮(熱田神宮)から三重県・桑名間は、陸0.8km
/ 海上27.3kmとなっていた。 [交通]JR桑名駅-(徒歩/15分)-桑名城跡 |
||
| 伊勢国・神戸かんべ城(本多城) |
||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 神戸具盛 ■築城年 天文年間(1532年〜1555年) ■主な遺構 石垣 / 堀 大手門が四日市市西日野町の顕正寺に、二の丸太鼓櫓が鐘楼として鈴鹿市東玉垣町・蓮花寺に、本多忠統による書院(坐忘亭)が城下の龍光寺に移築され現存する。 |
|
| 本丸後 | ||
 |
伊勢鉄道・鈴鹿駅から直線距離で1kmほどのところに神戸公園がある。鈴鹿駅より西へジグザグに進むのが最短距離となる。少し遠回りになるが、鈴鹿駅から線路沿いに南へ進む。すぐの鈴鹿駅入口交差点を右折して、旧伊勢街道(553号線)を北西へ進む。5分ほどすると右手の宋林寺前にT字路があり左折する。すぐの突き当りにある神戸高校は二の丸跡で、左折して回り込むと神戸公園がある。本丸の石垣と堀の一部が残っている。 [ |
|
| 堀 | ||
| 神戸城は天文年間(1532年〜1555年)神戸具盛によって築城された。桓武平氏と云われる関氏6代・関盛政が、正平22年(1367年)長男・関盛澄に伊勢国河曲郡神戸郷を与えられ神戸氏を名乗る様になった。7代・神戸具盛は関氏と共に六角氏に臣従していたが、永禄11年(1568年)に織田信長の侵攻を受ける。神戸具盛は信長の三男・三七丸を養子に迎え和睦する。元亀3年(1572年)三七丸が元服して神戸信孝を名乗り、神戸氏当主となる。このとき神戸城はより強固に修築され、5重6階の天守が築かれた。天守は文禄4年(1595年)に解体され、桑名城に三重櫓として移築された。 |
||
| 伊勢国・蒔田城 | ||
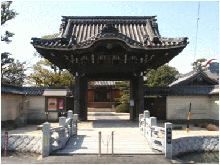 |
■城の種別 平城 ■築城者 蒔田宗勝 ■築城年 文治年間(1185年〜1190年) ■主な遺構 堀 / 土塁 |
|
| 長明寺山門と堀に架かる橋 | ||
|
近鉄名古屋線・富洲原駅から北西へ、JR関西本線方向に進む。66号線(東海道)を左折、南西方向へ進むと右手に長明寺がある。長明寺の境内になっている。 |
||
| 伊勢国・津城(安濃津城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 細野藤敦 ■築城年 永禄年間(1558年 〜1570年) ■主な遺構 藩校正門 / 石垣 / 堀 ■主な再建造物 模擬隅櫓 |
|
| 模擬隅櫓 | ||
| JR/近鉄・津駅から東へ、23号線を右折して南へ進む。三重会館前交差点の南西方向に、お城公園がある。 [交通]JR / 近鉄・津駅-(徒歩30分)-お城公園 または近鉄・津新町駅-(徒歩10分)-お城公園 |
||
| 古くは安濃津(あのつ)と呼ばれた地で、平安時代より伊勢国政治経済の中心地となっていた。鎌倉時代は長野氏が支配、永禄年間(1558年〜1570年)長野氏の一族・細野藤光が安濃津城を築城したのが始まり。 |
||
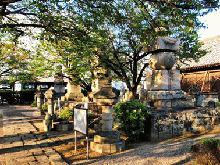 |
 |
23号線を南へ進み、岩田橋交差点を左折する。114号線を左折すると、すぐ右手に藤堂家の墓所である寒松院がある。巨大な五輪塔が立ち並び、壮観である。 |
| 藤堂家の墓所 | 藤堂高虎墓 | |
| [参考]寒松院・藤堂家墓所 / 閑々亭 | ||
 |
上野動物園・東園の象舎近くに動物慰霊碑があり、後方に塀で囲まれた藤堂家墓所が見える。この辺りは藤堂家の下屋敷だったところで、寛永4年(1627年)創建の菩提寺・寒松院があった。 |
|
| 藤堂家墓所 | ||
 |
上野動物園・東園にある閑々亭(かんかんてい)は、藤堂高虎が貴人を持て成した茶室である。彰義隊の戦いで焼失、明治11年(1878年)に再建された。藤堂高虎の持て成しを受けた徳川家光が「武士が風流をたしなむとは世が平和になり武士が閑(ひま)になった証拠」と言ったことから、閑々亭と名付けたと云われている。 |
|
| 閑々亭 | ||
| 伊勢国・松坂城(松阪城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 蒲生氏郷 ■築城年 天正16年(1588年) ■主な遺構 石垣 / 井戸 |
|
| 石垣 | ||
| JR/近鉄・松阪駅より西へ進む。道路を歪斜にしている町割になっており、ジグザグに進まないと方向がずれてしまう。元亀年間(1570年〜1572年)瀬田長政が築いたのが始まりとも云われている。元和5年(1619年)南伊勢は紀州藩領となり、松坂城に城代が置かれた。建物は残っていないが、石垣には圧倒される。 [交通]JR/近鉄・松阪駅-(徒歩/15分)-松阪公園 |
||
| 伊勢国・田丸城(玉丸城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 北畠親房 ■築城年 建武3年/延元元年(1336年) ■主な遺構 富士見門 / 石垣 / 堀 |
|
| 石垣 | ||
|
JR田丸駅から西へ進むと、堀に突き当る。城内に、玉城町役場および玉城中学校がある。現在残る縄張りは、北畠具教の養子になった織田信長の二男・織田信雄が天正3年(1575年)に大改修したもの。元和5年(1619年)南伊勢は紀州藩領となり、松坂城に城代が置かれた。 |
||
| 伊勢国・鳥羽城(鳥羽の浮城 / 錦城 / 二色城) | ||
 |
■城の種別 平山城 / 海城 ■築城者 橘宗忠 ■築城年 永正年間(1504年〜1521年) ■主な遺構 石垣 |
|
|
家老屋敷跡石垣 |
||
|
JR/近鉄・鳥羽駅の南側にある低い丘が、鳥羽城址である。現在残る縄張りは、 文禄3年(1594年)九鬼嘉隆が跡地に築城したもの。慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いで九鬼嘉隆は西軍、嫡子九鬼守隆は東軍に属した。九鬼嘉隆は答志島で自刃する。答志島の岬の頂きに首塚、その麓に胴塚がある。 |
||
| 伊勢国・亀山城(胡蝶城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 関実忠 ■築城年 文永2年(1265年) ■主な遺構 多聞櫓 / 石垣 |
|
| 多聞櫓 | ||
| JR亀山駅から北へ、亀山駅前交差点を過ぎると道は東へ方向を変える。次の信号を左折して北へ進むと亀山城がある。正保年間(1644年〜1648年)に築かれた多聞櫓が現存する。城跡には、移築された江戸時代建立の大久保神官邸宅門や文永2年(1265年)創建と云われる亀山神社がある。 [交通]JR亀山駅-(徒歩/15分)-亀山城 |
||
| 伊賀国・上野城(白鳳城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 筒井定次 ■築城年 天正13年(1585年) ■主な遺構 武具蔵 / 永倉 / 石垣 / 堀 ■主な再建造物 模擬大天守 /模擬小天守 |
|
| 模擬大天守・小天守 | ||
| 伊賀鉄道伊賀線・上野市駅から北へ、25号線を東へ進む。次の交差点を右折して北へ進むと、上野城がある。 [交通]伊賀鉄道伊賀線・上野市駅-(徒歩/10分)-上野公園 |
||
 |
 |
|
| 模擬大天守 | ||
 |
||
| 高石垣 | 高石垣 | |
| 上野城西の丸は、室町時代の伊賀国守護・ |
||
 |
 |
上野公園の南側の上野城内だった場所に、藩校・崇廣堂がある。文政4年(1821年)伊勢国津藩の第10代藩主・藤堂高兌が藩校・有造館の支校として開校。明治5年(1872年)廃校となり、上野義学校を始めとして使用された。昭和59年(1984年)までは上野市立図書館として使用されていた。 |
| 藩校・崇廣 | ||
| 嘉永7年(1854年)伊賀上野地震により、城内の建物の多くが壊れ石垣が所々で破損した。 |
||
 |
 |
|
| 俳聖殿門 | 俳聖殿 | |
| 上野公園には、俳聖殿(重文) |
||
 |
 |
松尾芭蕉は正保元年(1644年)松尾与左衛門と妻・梅の次男として、伊賀国で生まれる。出生前後に松尾家が柘植から赤坂へ引っ越しをしているため、どちらで生まれたか解っていない。俳号は初め実名の宗房(そうぼう) |
| 松尾芭蕉生家(赤坂) | ||
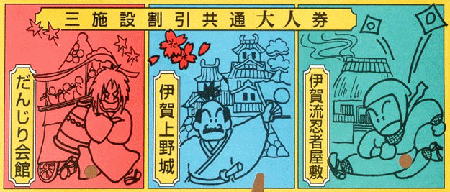 |
 |
|
| だんじり会館 / 伊賀上野白 / 伊賀忍者屋敷 共通入場券 | ||
 |
 |
|
| 伊賀流忍者博物館 |
忍者博物館 入館券 | |
 |
 |
 |
 |
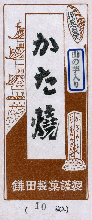 |
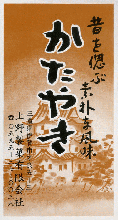 |
| かた焼きは伊賀忍者が携帯した携行食で、日本一硬いせんべいである。 |
||
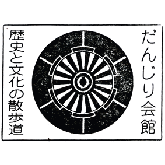 |
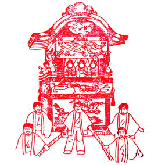 |
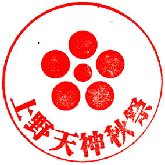 |
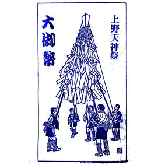 |
 |
秋に行われる上野天神祭の鬼・だんじり行事は、万治3年(1660年)に再興された上野天神祭。 |
 |
 |
城下町西の外れに、伊勢街道 / 奈良街道 などの道が集まっている鍵屋の辻(かぎやのつじ)がある。寛永11年(1634年)渡辺数馬が義兄・荒木又右衛門の助太刀により、弟・源太夫を殺した河合又五郎を打ち取ったところ。曾我兄弟の仇討ち
/ 赤穂浪士の討ち入り とともに日本三大仇討ちに数えられている。鍵屋辻南側の公園に、待ち伏せした萬屋を再現した茶屋がある。 |
| 鍵屋の辻公園 | ||