| 最新の追加 | ||
| 尾張国・大高おおだか城 |
||
 |
■城の種別 平山城 ■築城年 南北朝時代(1337年〜1392年) ■主な遺構 土塁 / 曲輪 |
|
| 本丸跡 | ||
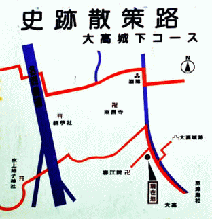 |
最寄り駅はJR東海道線・大高(おおだか)駅である。道が入り組んでおり、大高川を渡る橋が少ないので解りにくい。大高城址入口を地元の方数人に尋ねるが解らず、周辺を徘徊している。諦めて帰路に着く。名古屋市立大高保育園から坂を下ると、左手に案内地図があり辿り着くことができた。この道は最初の突き当りまでは行って戻っていた道である。名古屋市立大高保育園の角に、案内が欲しい。 |
|
| JR東海道線・大高駅前を通る国道23号線を北に進む。すぐの大高駅西交差点を左折して西に進む。この道は常滑街道で、大高城址入口の 大高川は大高城の北東を流れる川で、桶狭間の戦いの前哨戦の舞台となったところである。護岸はコンクリートの壁で味気ない。 |
||
 |
|
|
| 萬乗醸造 | ||
| 築城年代は解っていないが、南北朝時代(1337年〜1392年)と推察される。美濃国 / 尾張国 / 伊勢国の守護を兼務していた土岐氏の一族・池田頼忠が居城していたと云われている。永正年間(1504年〜1521年)には花井備中守
/ 文明年間(1469年〜1487年)には水野為善 が居城、以降は大高水野家の居城となる。天文17年(1548年)織田信秀の支配下にあった大高城を攻略するため、今川義元の家臣・野々山政兼が派遣されるが落ちず野々山政兼は討死する。 永禄2年(1559年)織田信長方の鳴海城主・山口教継が今川義元方に寝返り、大高城は沓掛城とともに攻略される。大高城は今川義元の家臣・朝比奈輝勝が城主となる。織田信長は丸根砦と鷲津砦を築き、大高城を包囲する。永禄3年(1560年)今川義元の配下であった松平元康(徳川家康)が「兵糧入れ」を行い、城の守備に着いた。「兵糧入れ」の時期に関しては、永禄2年(1559年)とも云われている。 永禄3年(1560年)桶狭間の戦いで今川義元が討ち死にすると、松平元康は岡崎城に引き上げた。 |
||
 |
 |
 |
| 土塁 | 二の丸跡 | 曲輪跡 |
|
大高城は比高約20mの丘陵上に立地、南北約32m / 東西約106mの台形状で本丸 / 二の丸 / 曲輪を備えていた。往時は二重の堀が張り巡らせており、堅固な城だったと云われている。 |
||
 |
大高城址から常滑街道を挟んだ南側に、弘治2年(1556年)創建の春江院(しゅんこういん)がある。大高城主・水野大膳が父・水野忠氏の菩提を弔うために創建された。 |
|
| 春江院本堂 | ||
| 尾張国・大野城(宮山城) |
||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 一色範光 ■築城年 観応年間(1350年〜1352年) ■主な遺構 堀 / 土塁 / 曲輪 ■主な再建造物 模擬天守 / 模擬城門 |
|
| 模擬天守 | ||
|
名鉄常滑線・西ノ口駅から線路沿いに北に進む。すぐの突き当たりを右折して踏切を渡り、すぐの突き当たりを左折して北に進む。すぐに2車線道路と交差、右折して北東に進む。 |
||
 |
 |
|
| 本丸からの伊勢湾眺望 | 案内板の縄張り | |
| 尾張国知多郡矢田村金山(現:愛知県常滑市金山)の伊勢湾を望む小高い丘陵(青海山)にある。案内板の縄張りから、かなり規模の城であったことが伺える。 | ||
 |
 |
 |
| 小規模な曲輪 | 立派な階段 | 多目的広場 |
| 城山公園北駐車場奥にある登城口石段 |
||
 |
 |
 |
| 模擬城門 | 城址碑 | 佐治神社 |
| 右手にある散策路を進み階段を登ると、遊具広場になっている大きな曲輪がある。さらに登って行くと、 大野城は、 浅井三姉妹の江(ごう / 後の崇源院)が最初の結婚で佐治一成に嫁いできた城として知られている。婚姻の時期は、織田信長存命時の天正2年(1574年)説などがある。天正12年(1584年)小牧・長久手の戦い後、羽柴秀吉によって離縁させられる。 |
||
|
観応年間(1350年〜1352年)三河国守護・一色範氏は知多半島に勢力を伸ばした。 |
||
| 尾張国・大草城 |
||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 織田長益 ■築城年 天正2年(1574年) ■主な遺構 堀 / 土塁 / 曲輪 ■主な再建造物 模擬櫓 |
|
| 模擬櫓 | ||
| 名鉄常滑線・大野町駅より線路沿いに北に進む。すぐの突き当たりを右折して踏切を渡り、すぐに左折して北に進む。すぐの267号線(大野停車場線)を潜ると、すぐに常滑街道に合流する。すぐにY字路があり、常滑街道は北に進む。Y字路右方向(東)に進み、2本目を左折して坂を登ると模擬櫓が見えてくる。 [交通]名鉄常滑線・大野町駅-(徒歩15分)-大草城模擬櫓 |
||
 |
 |
 |
| 堀 | 本丸土塁 | 二の丸 |
| 天正2年(1574年)この地を領していた佐治信方が長島一向一揆で戦死、織田信長の弟・織田長益が尾張国知多郡大野城を与えられる。織田長益は織田信秀の11男で、織田長益の号“有楽斎”に因んで命名された有楽町(東京都千代田区)が知られている。大野城は水利が悪いため、大草城を築城する。天正10年(1582年)本能寺の変後に尾張国は織田信雄が領することになり、織田長益は甥・織田信雄の家臣となる。天正12年(1584年)小牧・長久手の戦い後、織田長益が摂津国に移封されたため完成することなく廃城となった。 |
||
| 本丸 / 二の丸 / 三の丸 を配し、本丸 / 二の丸 の周囲を堀と土塁で囲っていた。現在は大草公園となっており、本丸に昭和54年(1979年)築の模擬櫓(展望台)がある。 大草城の西側を常滑街道が通る。東海道・鳴海宿の作町三叉路から知多郡大井村(現:知多郡南知多町大井)を結ぶ約62kmの街道。 |
||
| 尾張国・小口城(箭筈城 / 大久地城 / 於久地城) |
||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 織田広近 ■築城年 長禄3年(1459年) ■主な遺構 空堀 / 井戸跡 ■主な再建造物 模擬物見櫓 / 模擬大手門 / 模擬御殿(資料館) |
|
| 模擬物見櫓 / 模擬大手門 | ||
| 名鉄犬山線・柏森駅から線路沿いに北東に進む。5分足らずの左手に、柏森駅から2ヶ目の踏切がある。ここの十字路を右折して、南に道なりに進む。10分ほどの突き当たりを右折すると、すぐ左手に小口城址公園がある。 [交通]名鉄犬山線・柏森駅-(徒歩20分)-小口城址公園 |
||
 |
 |
 |
| 模擬大手門 | 塀 | 模擬御殿(資料館) |
 |
長禄3年(1459年)尾張国守護代・織田郷広の次男・織田広近によって築城された。 文明元年(1469年)織田広近は新たに築城した木ノ下城に移った。文明7年(1475年)弟・寛近(津田武永)に家督を譲り、小口城に戻った。 |
|
| 模擬物見櫓 | ||
 |
 |
小口城址公園の北西300Mほどのところに妙徳寺がある。織田広近は隠居所・萬好軒を築いて閑居した。萬好軒は遺命に基づき、明応元年(1492年)妙徳寺に改称した。 |
| 妙徳寺山門 | 妙徳寺本堂 | |
 |
 |
 |
| 徳林寺山門 | 徳林寺中門 | 徳林寺本堂 |
| 妙徳寺から西に500mほどのところに、正応6年(1293年)創建の徳林寺がある。 |
||
| 尾張国・荒子城 | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 前田利昌 ■築城年 天文13年(1544年) |
|
| 権現公園 | ||
 |
名古屋市営地下鉄東山線・高畑駅から高畑南北37号線の東側歩道を南に進む。 [交通]名古屋市営地下鉄東山線・高畑駅-(徒歩10分)-天満天神宮 |
|
| 犬千代ルート標識 | ||
 |
 |
 |
| 天満天神鳥居 | 天満天神宮社殿 | 前田利家生誕の地幟 |
 |
荒子城は権現公園 / 天満天神宮の辺りにあったが、周辺は宅地となっている。天満天神宮に前田利家生誕の地幟 / 荒子城案内板 / 昭和4年(1929年)造立の前田利家卿誕生之遺址碑
がある。ただし前田利家は前田城で四男として生まれ、7歳のときに荒子城に移ったと云われている。 |
|
| 前田利家卿誕生之遺址碑 | ||
|
荒子城は天文13年(1544年)前田利昌によって築かれたと云われている。 |
||
| 尾張国・古渡ふるわたり城 | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 織田信秀 ■築城年 天文3年(1534年) |
|
| 古渡城址碑 | ||
 |
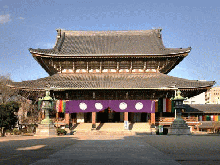 |
美濃路(旧東海道・熱田宿〜旧中山道・垂井宿)の19号線(伏見通)古渡交差点を東へ進むと、すぐ左手に元禄3年(1690年)創建の東本願寺名古屋別院がある。 |
| 山門 | 本堂 | |
|
天文3年(1534年)織田信長の父・織田信秀が東南方に備えるために築城した。天文15年(1546年)織田信長は古渡城で13歳のとき元服した。天文17年(1548年)美濃に侵攻した織田信秀が留守のとき、清洲の守護代・織田信友に攻められるが落城はしなかった。同年に織田信秀は末森城を築いて拠点としたため、古渡城はわずか14年で廃城となった。 |
||
| 尾張国・一宮いちのみや城 | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 関成重 ■築城年 天文年間〜弘治年間(1532年〜1558年) |
|
| 一宮城跡碑 | ||
| JR東海道本線・尾張一宮駅 / 名鉄一宮駅 から457号線を東へ進む。5分足らずの本町交差点手前左手に、一宮城跡碑がある。尾張国一の宮・真清田(ますみだ)神社の神主・関成重が、真清田神社および領地を守るために天文年間(1532年〜1555年)〜弘治年間(1555年から1558年)に築城されたと云われている。伊勢関氏の遠縁と云われている。東西50m / 南北90m の規模で、土塁や堀で囲まれていた。 関成重の嫡男・関共成は森長可の妹を娶り、森氏との関わりが深くなっている。天正12年(1584年)小牧長久手の戦いに羽柴秀吉に従い、森長可とともに戦死する。 |
||
| 尾張国・挙母城ころもじょう(七州城しちしゅうじょう) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 内藤政苗 ■築城年 天明元年(1782年) ■主な遺構 櫓台石垣 ■主な再建造物 隅櫓 |
|
| 復興隅櫓 | ||
|
名鉄・豊田市駅から西へ、愛知環状鉄道・新豊田駅方向に進む。けやき通りを左折して南へ進む。突き当たりを右折すると、右手に隅櫓が見えて来る。三河国・尾張国・美濃国・信濃国・遠江国・伊勢国・近江国の7つの国が見えることから七州城と云われた。トヨタ自動車の発展により、挙母市から豊田市に地名変更される。 |
||
| 尾張国・岩崎城 | ||
 |
■城の種別 |
|
| 模擬天守 | ||
| 名鉄豊田線・日進駅から西へ、57号線をしばらく進む。岩崎交差点を右折、すぐに左折すると突き当りに岩崎城跡公園がある。築城年は不明であるが、尾張国勝幡城主・織田信秀(織田信長の父)の支城であった記録がある。享禄2年(1529年)三河国岡崎城主・松平清康(徳川家康の祖父)が、織田信秀の属将・荒川頼宗の守備する岩崎城を攻め落とした。天文4年(1535年)松平清康が死去すると、本郷城主・丹羽氏清が移り、4代続けて在崎する。天正12年(1584年)小牧・長久手の戦いの緒戦で落城する。慶長5年(1600年)関ヶ原の戦い後、丹羽氏次は三河国伊保に移封となり廃城となる。昭和62年(1987年)築の模擬天守がある。 [交通]名鉄豊田線・日進駅-(徒歩/30分)-岩崎城跡公園 |
||
| 尾張国・旭城(新居城) | ||
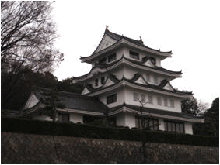 |
■城の種別 平山城 ■築城者 水野良春 ■築城年 康安元年(1361年) ■主な遺構 土塁 ■主な再建造物 模擬天守 |
|
| 模擬天守 | ||
| 名鉄・尾張旭駅東側の通りを北へ進む。新居町交差点を左折して西へ進むと、右手の城山公園に旭城模擬天守が見えて来る。 [交通]名鉄・尾張旭駅-(徒歩/15分)-旭城模擬天守 |
||
| 尾張国・小牧山城 | ||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 織田信長 ■築城年 永禄6年(1563年) ■主な遺構 石垣 / 空堀 / 土塁 / 井戸跡 ■主な再建造物 模擬天守 |
|
| 模擬天守 | ||
| 名鉄・小牧尾駅から西へ進むと、山頂に小牧山城模擬天守が見えて来る。織田信長が美濃攻めのために築城する。永禄10年(1567)稲葉山城を落城させ岐阜城と改めて移り住み、小牧山城は廃城となる。天正12年(1584年)羽柴秀吉と徳川家康・織田信雄連合軍が争った小牧・長久手合戦で、徳川・織田連合軍が本陣を置く。和議が成立して撤退後は使われなくなる。小牧山城模擬天守に、小牧・長久手合戦の陣容などが詳しく解説されている。 [交通]名鉄・小牧尾駅-(徒歩/30分)-小牧山城模擬天守 |
||
| 尾張国・知立城 | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 氷見氏 ■築城年 平安時代 |
|
| 知立城址碑 | ||
| 名鉄・知立駅から北へ、知立駅北交差点の次を左折して旧東海道を北西へ進む。T字路を右折すると、左手に知立城址がある。平安時代〜戦国時代に、知立神社の神主も務めていた永見氏の館があったところ。桶狭間の戦いで落城する。永見貞英の娘・お万の方は徳川家康の側室となり、次男・結城秀康を生んでいる。 [交通]名鉄・知立駅-(徒歩/15分)-知立城址 |
||
| 尾張国・鳴海城(根古屋城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 安原宗範 ■築城年 応永年間(1394年〜1427年) ■主な遺構 空堀 / 土塁 東福院に、鳴海城の廃材で造られたと云われる門が現存する。 |
|
| 鳴海城址碑 | ||
| 名鉄・鳴海駅から西へ、242号線を右折して北へ進む。本町交差点で旧東海道と交差する。円道寺の先を左折すると、城址公園がある。城址公園から天神社が、城郭にあたると云われている。桶狭間の戦いでも落城しなかったが、天正年間末期に廃城になったと云われている。 [交通]名鉄・鳴海駅-(徒歩/10分)-城址公園 |
||
| 尾張国・名古屋城(金鯱城 / 金城 / 柳城 / 亀屋城 / 蓬左城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 今川氏親 ■築城年 大永5年(1525年) ■主な遺構 辰巳隅櫓(重文) / 未申隅櫓(重文) / 御深井丸戌亥隅櫓(重文) / 表二の門(重文) / 二の丸西鉄門二の門(重文) / 旧二の丸東鉄門二の門(重文) ■主な再建造物 大天守 / 小天守 |
|
| 復興天守 | ||
|
名古屋市営地下鉄・市役所駅の北西側が名古屋城跡になる。北へ進むと左手に東門がある。名古屋城二の丸の位置にあったとされる那古屋城で、天文3年(1534年)織田信長が誕生したと云われている。慶長12年(1607年)徳川家康の九男・義直が清洲藩主となる。慶長15年(1610年)より天下普請として名古屋城が築城される。 |
||
| 尾張国・犬山城(三光寺山城 / 白帝城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 織田信康 ■築城年 天文6年(1537年) ■主な遺構 天守(国宝) 矢来門が専修院に、黒門が徳林寺に、松ノ丸門が千秋寺に、内田門と伝わる城門が瑞泉寺に移築され現存する。 ■主な再建造物 隅櫓 / 本丸門 |
|
| 天守 | ||
|
名鉄・犬山遊園駅から東へ、名鉄犬山線に平行する道を南へ進む。内田交差点を右折して木曽川方向に進むと、犬山城がある。郷瀬川を公園橋で渡り、道なりに進む。北へ登る道を進むと三光稲荷神社を経て、犬山城天守に至る。文明元年(1469年)織田広近が築城したとも云われている。 |
||
| 尾張国・清洲城 | ||
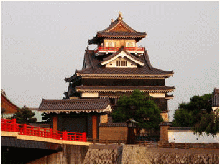 |
■城の種別 平城 ■築城者 斯波義重 ■築城年 室町時代初期 ■主な再建造物 模擬天守 |
|
| 模擬天守 | ||
| JR清洲駅から線路沿いに南へ進むと、清洲公園がある。五条川の対岸に模擬天守が見える。本来の天守は、清洲駅寄りの線路際にあった。織田信長が尾張の統一から天下統一へと、飛躍の拠点となった城。 [交通]JR東海道本線・清洲駅-(徒歩/20分)-清洲城 |
||