|
| 最新の追加 |
|
|
|
遠江国・引間ひくま城(曳馬城 / 引馬城 / 匹馬城)
|
 |
■城の種別
平山城
■築城者
今川貞相
■築城年
永正年間(1504年〜 1520年)
■主な遺構
土塁 / 曲輪
|
| 元城町東照宮 |
|
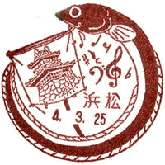 |
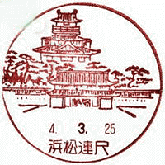 |
 |
| 浜松郵便局風景印 |
連尺郵便局風景印 |
案内マンホール |
|
JR東海道本線・浜松駅から北西方向に進むと、すぐに鍛冶町通りと交差する。JR浜松駅交差点の北西側に浜松郵便局がある。風景印は、鰻の外枠 / 浜松城模擬天守
/ 音符 の図柄になっている。浜松郵便局から鍛冶町通りを西に進む。5分ほどの伝馬町交差点を右折して257号線(大手通り)を北に進む。すぐ左手に連尺郵便局がある。風景印は、浜松城模擬天守
/ 大手門 の図柄になっている。大手門は実在しないが、連尺交差点辺りにあった。連尺郵便局から10分足らずの右手に小高い丘が見えてくる。引間城の主郭があったところに元城町東照宮がある。
[交通]JR東海道本線・浜松駅-(徒歩20分)-元城町東照宮 |
|
永正年間(1504年〜 1520年)今川貞相によって築城されたと云われている。永正11年(1514年)飯尾乗連は今川氏親から曳馬城を与えられた。永禄3年(1560年)桶狭間の戦いで今川義元が討ち死にすると今川氏の衰退が始まる。飯尾乗連の嫡子・飯尾連龍は今川氏真に謀反の疑惑を持たれ、永禄6年(1563年)と永禄7年(1564年)に攻撃されたが城は落ちななかった。永禄8年(1565年)今川氏真からの和議を受諾した飯尾連龍は、駿府に出向いたときに謀殺されたと云われている。曳馬城は飯尾連龍の妻・お田鶴の方を中心に守備していたが、永禄11年(1568年)からの徳川家康の攻撃で落城する。田鶴の方は侍女とともに戦い、討ち死にしたと云われている。
永禄11年(1568年)徳川家康は酒井忠次を派遣して城を接収して支城とした。永禄12年(1569年)掛川城に籠る今川氏真を降伏させ伊豆に追放した徳川家康は、元亀元年(1570年)本拠地を三河国・岡崎から引間城に移した。城域の拡張や改修を行い、浜松城と改称した。引馬の地名は馬を引く負け戦に?がることから、かつて存在した荘園・浜松荘に因んで地名 / 城名 を改めたと云われている。
引間城跡跡には、江戸時代は米蔵などが置かれていた。 |
|
 |
明治19年(1886年)引間城の主郭があったところに、元城町東照宮(浜松東照宮)が創建される。昭和20年(1945年)太平洋戦争で焼失したが、昭和34年(1959年)に再建された。徳川家康ゆかりの地で豊臣秀吉が訪れた城でもあるため、境内に徳川家康像 / 豊臣秀吉像がある。天下人へと導いた場所ということで、出世神社とも呼ばれている。東照宮周囲の道路は空堀跡と云われている。境内の北東隅に土塁が残る。
|
| 元城町東照宮本殿 |
|
 |
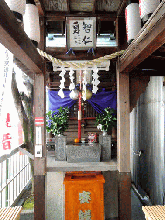 |
元城町東照宮の北側の道を東に進む。二俣街道との交差点を左折して北へ進む。六間道路との交差点を越え、次の交差点を右折して椿観音通りを東に進む。5分足らずの左手にこぢんまりとした椿観音がある。
|
| 椿観音 |
|
|
お田鶴の方は永禄年間(1555年〜1569年)引間城の城主であった飯尾連龍の妻で、椿姫とも呼ばれる。父は鵜殿長持 / 母は今川氏親の娘で、今川義元は伯父
/ 北条氏康の正室・瑞渓院は伯母 / 今川氏真は従兄妹 / 北条氏政は従兄妹 / 徳川家康の正室・築山殿は母同士が義理の姉妹 にあたる。田鶴の方は侍女とともに戦い、討ち死にしたと云われている。お田鶴の方と侍女18人は、この地に手厚く葬られ、たくさんの椿の木を植えて供養された。
|
|
| 遠江国・浜松城(引間城 / 曳馬城 / 引馬城 / 匹馬城) |
 |
■城の種別
平山城
■築城者
今川貞相
■築城年
永正年間(1504年〜 1520年)
■主な遺構
石垣 / 曲輪
■主な再建造物
模擬天守 / 天守門 |
| 大手通りからの模擬天守 |
|
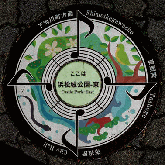 |
引間城の主郭から257号線(大手通り)を挟んだ西側に、浜松城公園がある。元亀元年(1570年)三河国・岡崎城から本拠地を引間城に移した徳川家康は、引間城西側に城域の拡張や改修を行い浜松城と改称した。
[交通]JR東海道本線・浜松駅-(徒歩20分)-浜松城公園 |
| 案内マンホール |
|
 |
城域の拡張や改修は天正10年(1582年)頃に終わったが、天正14年(1586年)徳川家康は浜松城から駿府城に本拠を移した。家康の在城期間は29歳から45歳までの17年間になる。
徳川家康が築城した浜松城は、土造りの城であり石垣はなかったとされる。連尺交差点辺りに大手門があった。 |
| 若き日の徳川家康像 |
|
 |
元亀3年(1573年)武田信玄が浜松城を無視する様に行軍する。徳川家康は浜松城から打って出て三方ヶ原で戦うが、敗北を喫した。徳川家康は討ち死に寸前まで追い詰められ、僅かな供回りのみで浜松城へ逃げ帰ったと云われている。
市役所前交差点から西に進むと、すぐ右手に鎧掛松がある。浜松城へ逃げ帰った徳川家康が鎧を掛けたと云われる松で、三代目になる。
|
| 鎧掛松 |
|
| 天正14年(1586年)徳川家康が駿府城に本拠を移した後は、天正18年(1590年)迄菅沼定政が城代を務めた。天正18年(1590年)徳川家康の関東移封後は、豊臣秀吉の家臣・堀尾吉晴と次男・堀尾忠氏が11年間在城した。安土桃山時代(1568年〜1600年)に天守
/ 天守門 が造られた。関ヶ原の戦いの功績で出雲国富田に移封となった。以後は徳川頼宣の領地だった時期を除いて徳川家譜代大名が城主となり、歴代の城主によって城域の改修が進められた。 |
|
 |
 |
| 模擬天守 |
|
 |
| 富士見櫓跡からの復元天守門 / 模擬天守 |
復元天守門 |
|
|
明治6年(1873年)の廃城令により、浜松城の建物や土地の払い下げが行われた。三の丸 / 二の丸 の宅地化が進行したが、本丸 / 天守曲輪は大きな開発を免れ浜松城公園になっている。
安土桃山時代(1568年〜1600年)に天守 / 天守門 が造られたが、天守は早い時期に失われ再建されなかった。昭和33年(1958年)築の模擬天守は、天守台より小さな三重天守となっている。天守台の後ろ余ることとなった。天守台の規模から五重天守だったとされるが、史料は残っていない。
天守門は天守曲輪の東側に位置している櫓門。天守が早い時期に失われ再建されなかったため、天守門が浜松城の最高所に位置する建造物となった。江戸時代に改修が繰り返されたが、明治6年(1873年)に取り壊された。発掘調査で見つかった礎石
/ 絵図などを基に、平成26年(2014年)復元された。前回、平成21年(2009年)旧東海道を巡ったときには存在していなかった。
|
|
|
|
| 遠江国・諏訪原城(牧野城 / 牧野原城 / 扇城) |
 |
■城の種別
山城
■築城者
馬場信春
■築城年
天正元年(1573年)
■主な遺構
土塁 / 空堀 / 曲輪 / 馬出 / 井戸
■主な再建造物
薬医門 |
| 二の曲輪北側 |
|
|
往路は、JR東海道本線・金谷駅から島田市コミュニティバスを利用する。諏訪原城跡バス停で下車、右方向に諏訪原城跡が見える。島田市コミュニティバスは運行本数が少なく、住民の方の利便性から寄り道が多い。
[交通]JR東海道本線・金谷駅-(島田市コミュニティバス / 15分)-諏訪原城跡バス停
|
|
 |
 |
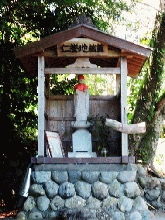 |
| 金谷坂石畳 |
すべらず地蔵堂 |
仁誉地蔵 |
|
 |
 |
 |
| 庚申堂 |
庚申塔 |
鶏頭塚 |
|
 |
帰路は諏訪原城跡から諏訪原城跡バス停のある旧東海道を東に進む。10分ほどすると、左方向に下る金谷坂石畳がある。12年前に旧東海道を歩いたとき、登った懐かしい石畳である。5分ほどの左手に“すべらず地蔵堂”がある。下り坂は、雨が降ると滑って危ないと“すべらず地蔵堂”の存在に納得する。さらに5分ほどすると左手に仁誉地蔵
/ 庚申堂 / 庚申塔 / 鶏頭塚 があり、すぐ左手に石畳茶屋と続く。すぐに473号線と交差、左折して旧東海道と別れる。すぐの金山駅前交差点を過ぎると、すぐ右手にJR東海道本線・金谷駅がある。
[交通]諏訪原城跡-(徒歩30分)-JR東海道本線・金谷駅
|
| 金谷坂石畳 |
|
|
諏訪原城(牧野城)は、遠江国の東端近くの牧之原台地の舌状台地の先端部に立地する。城の南側を旧東海道が通り、東の金谷坂を下ると大井川を渡って駿河国
/ 西の菊川坂を下り青木坂を登ると小夜の中山を経由して掛川 / 南に牧之原台地を下ると菊川下流域の平野部 に出る。大井川西岸の防衛線であり、小山城とともに高天神城の補給を確保する重要な拠点だった。城の三方は台地の断崖となっており、前面の巨大な空堀がこの断崖へと続いている。
|
|
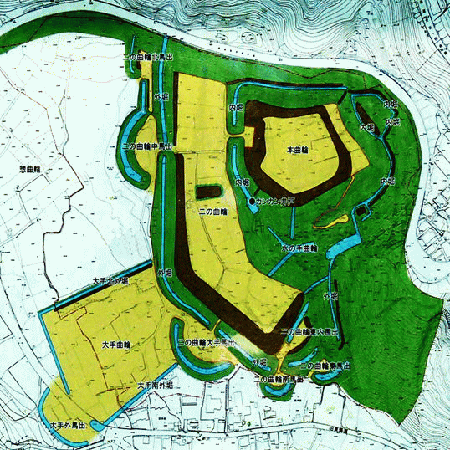 |
|
 |
| 大手南外堀跡 |
|
 |
| 案内看板の地図(抜粋) |
茶畑 |
|
| 諏訪原城跡バス停から右方向(北)に進む。すぐに諏訪原城跡に入ると、案内看板 / 右手に大手南外堀跡 がある。左手に茶畑が拡がる。明治維新後に15代将軍・徳川慶喜が駿府に配されると、随従した旧幕臣たちは荒廃していた牧野城周辺に移住して開墾し主に茶畑とした。 |
|
 |
 |
 |
| 通路 |
諏訪神社 |
諏訪神社社殿側から撮影 |
|
 |
 |
 |
| 深い空堀 |
二の曲輪東内馬出 |
二の曲輪南馬出 |
|
|
通路を北に進むと、すぐ右手に「二の曲輪大手馬出→」の標識があり右方向に進む。深い空堀の端を慎重に進む。分岐があり、右方向に諏訪神社がある。左方向に進み堀を越えると、すぐ左手に二の曲輪東内馬出
/ 右手に二の曲輪南馬出 がある。馬出(うまだし)は、城の出入り口である虎口(こぐち)を守る小さな曲輪のこと。
|
|
 |
 |
 |
| 大手北外堀跡 |
諏訪原城跡石柱 |
二の曲輪 |
|
| 「二の曲輪大手馬出→」標識のところまで戻り、北に進む。すぐ左手に大手北外堀跡 / 諏訪原城跡石柱 と続き、右手に南北に長い二の曲輪が見える。 |
|
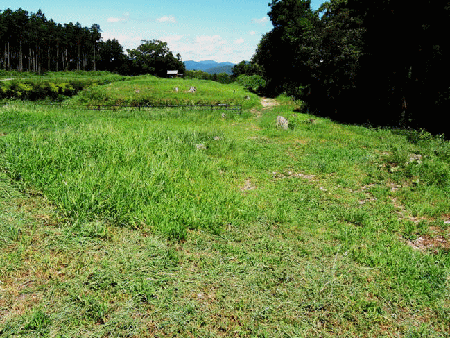 |
 |
| 三日月堀 |
|
 |
| 番小屋跡から復元薬医門方向 |
三日月堀 |
|
| 通路を北に進むと、右手に番小屋跡がある。ここから奥に見える二の丸北馬出の復元薬医門を経て周回できる。 |
|
 |
 |
 |
| 二の曲輪中馬出 |
本曲輪通路 |
本曲輪 |
|
| 番小屋跡から北に進むと、右方向に二の曲輪中馬出がある。空堀を越えると、本曲輪通路を経て本曲輪がある。動物のうめき声が聞こえ、本曲輪の中央まで行くのを躊躇する。 |
|
 |
 |
番小屋跡から北に進む通路に戻り、北に進むと、二の丸北馬出に平成28年(2016年)復元された薬医門がある。ここからは町並みが眺望できる。 |
| 復元薬医門 |
二の丸北馬出からの眺望 |
|
| 武田勝頼は遠江国の獲得を目論み、天正元年(1573年)普請奉行に馬場信春 / 補佐に武田信豊 を命じて諏訪原城を築城する。城内に諏訪大明神を祀ったことから諏訪原城と命名されたと云われている。武田氏時代に構築されたのは本丸と南端にある小型の丸馬出のみと云われている。武田勝頼は遠江国への攻勢を強め、天正2年(1574年)主要拠点であった遠江国・高天神城を攻略する。天正3年(1575年)長篠の戦いで武田軍が織田・徳川連合軍に敗れると、徳川家康は諏訪原城を攻撃する。武田勝頼が援軍を派遣できなかったこともあり開城、諏訪原城は徳川家康によって牧野城と改称したと云われている。城の大規模な改修が行われ、現在見られる遺構はこの時代のものである。徳川家康は牧野城を拠点に駿河国攻撃を続ける。高天神城への補給路を封じたことで戦いを有利に導くことができ、天正9年(1581年)高天神城は落城した。天正10年(1582年)甲州征伐で武田氏が滅亡すると牧野城の存在意義が薄れ、天正18年(1590年)に廃城となった。 |
|
| 遠江国・小山城 |
 |
■城の種別
平山城
■築城者
馬場信春
■築城年
元亀2年(1571年)
■主な遺構
土塁 / 曲輪 / 堀
■主な再建造物
模擬天守 |
| 模擬天守 |
|
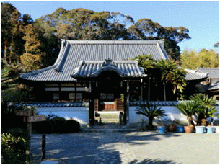 |
JR藤枝駅より静波方面行きバスに乗車、吉田高校前停留所で下車する。停留所が近づくと右手に模擬天守が見えてくる。弘長2年(1262年)創建の能満寺の本堂左手から登る。今川氏によって築かれた砦が始まりで、元亀2年(1571年)武田氏により築城される。諏訪原城とともに大井川西方の防衛ラインを形成、高天神城攻略の拠点となった。天正10年(1582年)徳川家康の攻撃を受け落城、廃城となる。甲州流築城術の特徴である丸馬出しや三日月堀が残る。物見台があったと云われる三の丸跡に、昭和62年(1987年)築の模擬天守がある。
[交通]JR藤枝駅-(バス/30分)-吉田高校前-(徒歩/10分)-小山城天守 |
| 能満寺 |
|
| 遠江国・掛川城(懸川城 / 懸河城 / 雲霧城 / 松尾城) |
 |
■城の種別
平山城
■築城者
朝比奈泰煕
■築城年
文明年間(1469年〜1487年)
■主な遺構
二の丸御殿(重文) / 太鼓櫓 / 移築大手三の門(重文) / 移築蕗の門
■主な再建造物
天守 / 大手門 |
| 復興天守 |
|
|
JR掛川駅から北へ、逆川を渡ると掛川公園がある。応永年間(1394年〜1427年)鶴見氏が砦を築いたのが始まりとも云われている。現在残る城郭は、天正18年(1590年)城主になった山内一豊による。文久元年(1861年)再建された二の丸御殿が現存している。
[交通]JR掛川駅-(徒歩/15分)-掛川城天守
|
|
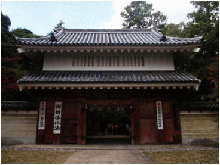 |
 |
大手三の門(重文)が袋井市の油山寺に、蕗の門が掛川市円満寺に移築され現存する。 |
| 油山寺山門(掛川城大手三の門) |
円満寺山門(掛川城蕗の門) |
|
| 遠江国・横須賀よこすか城(松尾城 / 両頭城) |
 |
■城の種別
平山城→平城
■築城者
大須賀康高
■築城年
天正6年(1578年)
■主な遺構
石垣 / 土塁 / 堀跡
不開門が北西にある撰要寺 / 町番所が市役所大須賀支所北側 / 書院が袋井・油山寺 に移築され現存する。 |
| 横須賀城跡碑 |
|
 |
| 玉石垣 |
|
JR東海道本線・袋井駅からバスに乗車、七軒町バス停で下車する。七軒町バス停から東へ進む。すぐの北側に、堀跡の荒れ地が続く。案内板のあるT字路を左折して北へ進むと、すぐ右手に横須賀城跡公園がある。
横須賀城は武田勝頼に奪われていた高天神城攻略の拠点として、徳川家康が大須賀康高に命じて築城された。築城当時は松尾山にある平山城で、二の丸などの平城部分が拡張されて現在の横須賀城になったと云われている。また海が深く入り込み、三方が入江と沼や深田に囲まれた天然の要害の地だった。
天正9年(1581年)高天神城は落城と共に廃城となり、横須賀城が遠州南部の拠点として位置づけられた。戦国時代の城攻めのための陣城が、そのまま近世城郭として続いた城である。
海は宝永4年(1707年)の宝永地震や安政元年(1855年)の安政地震による隆起で遠くなってたが、往時は遠江の陸運と海運を抑える拠点だった。入り江は掛川城の外堀となっている逆川の河口で、掛川城に船で直接行き来することができたと云われている。入り江には、横須賀湊があった。掛川城が東海道の押さえであったのに対し、横須賀城は浜筋道と海上交通の押えであった。
石垣は天竜川の玉石を使用している玉石積みで、三層四階の天守閣があった。大手門が東西にあり、両頭の城と呼ばれていた。 |
|
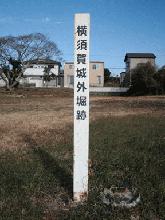 |
 |
 |
| 堀跡 |
本丸玉石垣 |
天守台跡 |
|
大須賀氏は北総を根拠地とした千葉一族で、三河に来て土着したのが三河大須賀氏の始まりである。大須賀康高・大須賀忠政〜渡瀬繁詮〜有馬豊氏〜大須賀忠政・大須賀忠次〜徳川頼宣〜松平(能見)重勝・松平(能見)重忠〜井上正就・.井上正利〜本多利長と、めまぐるしく代わる。天和2年(1682年)譜代大名の西尾忠成が小諸藩から2万5千石で移封となり、8代続き明治維新を迎える。2代藩主・西尾忠尚は、若年寄や老中を務めている。280余年に渡り横須賀藩の中心であった横須賀城は、明治2年(1870年)に廃城となった。
[交通]JR東海道本線・袋井駅-(バス)-七軒町バス停-(徒歩5分)-横須賀城跡公園 |
|
 |
袋井・油山寺に元禄12年(1699年)建立の書院が移築されている。安政6年(1859年)遠州横須賀城主・西尾忠受の寄進。江戸初期の書院として優れた技工と地方色豊かな建築物と云われている。昭和54年(1979年)往時の姿に復元された。 |
| 書院 |
|
| 遠江国・高根城(久頭郷城 / 久頭合城) |
 |
■城の種別
山城
■築城者
奥山氏
■築城年
応永年間(1394年〜1427年)
■主な遺構
土塁 / 堀 / 曲輪
■主な再建造物
井楼櫓 / 大手門 / 塀 |
| 大手門 / 井楼櫓 |
|
 |
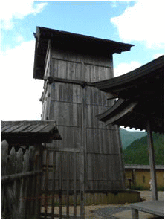 |
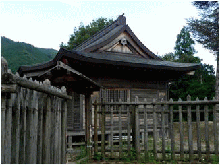 |
| 塀 / 井楼櫓 |
井楼櫓 |
稲荷神社 |
|
JR飯田線・向市場駅より東へ、すぐの突き当りを南へ進む。すぐの十字路に標識があり、右折して坂を下る。JR飯田線鉄橋を潜り、突き当りを左折して橋を渡る。渡り終えた左手に案内板がある。道なりに進むと、左手に登り口がある。河内川が水窪(みさくぼ)川に合流するところに築かれ、本曲輪は三角山(標高420m)山頂にある。遠江国の北端に位置し、室町時代は今川氏の支配下にあった。永禄3年(1560年)桶狭間の戦いで今川義元が討たれると、元亀年間(1570年〜1573年)武田氏の支配下となった。駿遠攻略の最前線として大改修され、そのために奥山氏時代と武田氏時代の遺構が残る。高さ8mの井楼(せいろう)櫓は武田氏時代の遺構で、発掘された柱穴を基に釘を使わない当時の建築技術で復元された。天正4年(1576年)長篠の戦後に武田氏の勢力が一掃された頃に、廃城になったと云われている。本曲輪に稲荷神社がある。
[交通]向市場駅-(徒歩20分)-登り口-(徒歩20分)-本曲輪 |
|
| 遠江国・二俣城 |
 |
■城の種別
山城
■築城者
二俣昌長
■築城年
文亀3年(1503年)
■主な遺構
天守台 / 石垣 / 曲輪 |
| 天守台 |
|
天竜浜名鉄道・二俣本町駅より北へ、152号線との変則五差路を西へ進む。階段を登り、突き当りを右折して道なりに進むと城跡に至る。岡崎三郎信康(徳川家康長男)が織田信長の命により切腹した城で、墓所は北東側の清龍寺にある。
井戸櫓が清龍寺に復元されている。
[交通]天竜浜名鉄道・二俣本町駅-(徒歩/20分)-二俣城天守台 |
|
 |