| 最新の追加 | ||
| 羽後国・久保田城(矢留城 / 葛根城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 佐竹義宣 ■築城年 慶長9年(1604年) ■主な遺構 土塁 / 堀 / 御物頭御番所 ■主な再建造物 本丸表門 / 本丸新兵具隅櫓(御隅櫓) |
|
| 本丸表門 | ||
| 冬景色は2010年12月 / 以外は2022年 9月 |
||
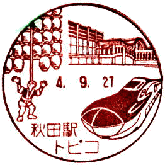 |
 |
 |
| 秋田駅トピコ郵便局風景印 | 蓮で覆われた大手門の堀 | 穴門の堀 |
|
JR秋田駅に隣接して、秋田駅トピコ郵便局がある。風景印は、秋田竿燈まつり / JR秋田駅 / 秋田新幹線こまち の図柄になっている。JR秋田駅西口より26号線西へ進みすぐの久保田町交差点を過ぎると、右手に大手門の堀が見えてくる。すぐの千秋公園入口交差点を右折して穴門の堀を左に見て北に進むと千秋公園に入る。 |
||
 |
安東氏(秋田氏)配下の三浦氏(川尻氏)が矢留ノ城を築城したのが始まりと云われている。 慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いの後、慶長7年(1602年)常陸国54万石から出羽国秋田郡20万石に減転封になる。 佐竹氏は 出羽国湊5万石・秋田実季の居城であった湊城に入城するが、平城で防衛に不向きで54万石規模の家臣団を抱えて手狭であった。慶長9年(1604年)窪田城を本城として湊城を破却した。 |
|
| 久保田城跡石柱 | ||
| 雄物川の支流である旭川の左岸にある神明山に築かれた。僅かにある石垣も土塁を盛られ、ほとんどが土塁であった。天守はなかったが、8基の櫓があった。 窪田城から久保田城の改称時期は寛永10年(1633年)〜正保2年(1645年)頃と云われている。 |
||
 |
 |
 |
| 黒門跡 |
二の丸跡 | 本丸跡への石段 |
 |
 |
明治13年(1880年)の大火で城内の建造物はほぼ焼失、市街再建の過程で堀の多くは埋め立てられた。久保田城本丸 / 二の丸 は千秋公園となっている。平成元年(1989年)本丸新兵具隅櫓(御隅櫓)
/ 平成13年(2001年) 本丸表門 が復元されている。 |
| 帯曲輪門跡 |
御隅櫓 | |
 |
 |
本丸跡に常陸国・佐竹義昌が石清水八幡宮を太田城内に勧請したのが始まりの八幡秋田神社 / 久保田藩(秋田藩)最後(12代)の藩主・佐竹義堯(よしたか)銅像 がある。 |
| 八幡秋田神社 | 佐竹義堯銅像 | |
 |
久保田町交差点から南に進み、中央通りとの交差点の次を左折すると、すぐ左手に |
|
| 秋田駅前郵便局風景印 | ||
| 羽後国・秋田城 | ||
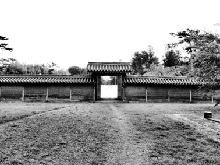 |
■城の種別 古代城柵 ■築城者 大和朝廷 ■築城年 天平5年(733年) ■主な遺構 政庁跡 / 外郭 / トイレ建物跡 ■主な再建造物 政庁東門 / 外郭東門 / 築地塀 |
|
| 政庁東門 / 築地塀 | ||
 |
秋田駅前バスプールから将軍野線 / 寺内経由土崎線 に乗車、秋田城跡歴史資料館前バス停で降車する。 バス停は政庁跡を分断する道路にあり、西側の秋田城跡歴史資料館建物側に停車する。 |
|
| 連絡橋 | ||
|
秋田城の築城は天平5年(733年)に出羽柵が庄内地方から秋田村高清水岡に移転したことに遡り、天平宝字4年(760年)頃に秋田城に改称されたと云われている。 |
||
 |
 |
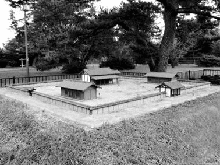 |
| 政庁西門跡 / 連絡橋 | 政庁跡 | 政庁跡模型 |
 |
 |
 |
| 政庁東門 | 場内東西大路 | 外郭東門 |
 |
 |
 |
| 外郭東門築地塀 | 秋田県護国神社神門 | 秋田県護国神社社殿 |
| 秋田城は秋田平野の西部、雄物川河口近くの標高40mほどの丘陵にある。構造は築地塀などで囲われた外郭と、政庁を囲う内郭との構造になっている。外郭の東西南北に城門が配置されていた。政庁の配置は、正殿の南面に広場を設け左右に脇殿が配置されていた。 西側に平成28年(2016年)開館の 平成10年(1998年)に外郭東門および附設の築地塀(延長45m)が復元、政庁東門から外郭東門に至る幅12mの東大路が版築の層を重ねる手法で復元された。 |
||
| 延暦21年(802年)朝廷はアテルイとの軍事的抗争に勝利する。延暦23年(804年)秋田郡が設置され、秋田城が担っていた機能は河辺府へ移されたと云われている。秋田城は出羽北部の軍事
/ 行政 の拠点として存続した。 天長7年(830年)出羽大地震により城廓および官舎のことごとくが損傷する被害を受けた。この時の被害報告から城に附属して四天王寺 / 四王堂 といった宗教施設が存在したことが解っている。 元慶2年(878年)夷俘(いふ)の反乱で秋田城が占拠され、城が焼かれた。軍事的緊張から遠ざかっていた秋田城では警備が手薄になっていたと云われている。出羽権守として派遣された藤原保則は鎮圧にあたり、元慶3年(879年)夷俘の反乱は終結して鎮圧軍は解散した。 天慶2年(939年)の天慶の乱の際にも、秋田城は攻撃を受けている。10世紀後半には秋田城の基本構造と機能が失われたと云われている。 |
||
| 出羽国・亀ヶ崎城(東禅寺城 / 酒田城) |
||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 大宝寺(武藤)氏 ■築城年 文明10年(1478年) ■主な遺構 土塁 三の丸南側にあった搦手門が、円通寺に移築現存している。 |
|
| 酒田東高と八幡神社の間にある土塁 | ||
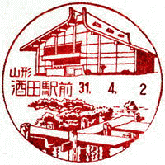 |
JR羽越本線・酒田駅前の交差点から、41号線を南西に進む。すぐの十字路を右折すると、すぐ左手に酒田駅前郵便局がある。風景印は、本間美術館本館
/ 庭園・鶴舞園 の図柄になっている。 |
|
| 酒田駅前郵便局風景印 | ||
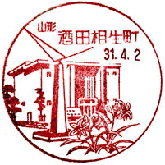 |
十字路まで戻り、41号線を南西に進む。すぐの御成町交差点を左折して南に進む。 |
|
| 酒田相生町郵便局風景印 | ||
 |
一番町交差点から5分ほどの交差点を左折する。すぐの突き当り手前を右折、すぐに道なりに左に折れる。すぐの突き当りを右折して南西に進み、新井田川 |
|
| 八幡神社 | ||
|
尾浦城の大宝寺(武藤)義氏は、支族である砂越城の砂越氏に対抗するために文明10年(1478年)東禅寺城を築城する。城主に任じられた前森蔵人は、東禅寺義長を名乗った。 |
||
|
出羽国・塩越城(八十島城) |
||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 池田茂政 ■築城年 貞治4年 / 正平20年(1365年) ■主な遺構 土塁 |
|
| 塩越城土塁 | ||
 |
 |
JR羽越本線・象潟駅から西に進む。 [交通]JR羽越本線・象潟駅-(徒歩約10分)-塩越城跡 |
| 熊野神社鳥居 | 塩越城案内板 | |
| 貞治4年 / 正平20年(1365年)築城以降、池田氏が代々この地を領する。 |
||
 |
熊野神社は神明の森と呼ばれる小高い丘にあり、松尾芭蕉や菅江真澄らが訪れている。往時は鳥海山と九十九島が一望出来たと云われている。 |
|
| 熊野神社社殿 | ||
 |
 |
 |
| 蚶満寺山門 |
蚶満寺本堂 | 蚶満寺鐘楼 |
| 塩越城跡から熊野神社鳥居方向に東へ進む。すぐの中橋を渡り道なりに進むと、7号線と斜めに交差する。交差点を東方向に進み、JR羽越本線の踏切を越える。すぐのT字路を左折して北に進むと、すぐにJR羽越本線沿いの道となる。すぐ右手に仁寿3年(853年)創建の蚶満寺(かんまんじ)境内が広がる。 [交通]JR羽越本線・象潟駅-(徒歩約15分)-蚶満寺 |
||
 |
||
 |
||
| 蚶満寺境内からの眺望(左:駒留島) | にかほ市象潟町マンホール | |
|
紀元前466年に鳥海山が噴火、山体崩壊により浅い海と多くの小島できた。やがて砂丘によって仕切られて潟湖となり、小島には松が生い茂り風光明媚な象潟の地形ができあがった。古来より歌枕の地として知られ、古今和歌集や新古今和歌集などにも登場する。江戸時代には、東の松島
/ 西の象潟 と称された。松尾芭蕉は西行を偲んで訪れ、松尾芭蕉を偲んで与謝蕪村や小林一茶が訪れている俳人の巡礼地。 |
||
 |
 |
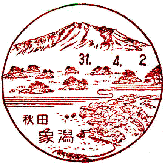 |
| 701系交流電車 | 象潟駅スタンプ | 秋田象潟郵便局風景印 |
| 蚶満寺境内から線路沿いに南に進み、JR羽越本線の踏切を渡る。701系交流電車が通過する。すぐに左折して7号線を南に進む。 象潟駅前交差点から5分ほどの左手に秋田象潟郵便局がある。風景印は、鳥海山 / 九十九島 / 小砂川海岸 の図柄になっている。 | ||
| 出羽国・新庄城(沼田城 / 鵜沼城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 戸沢政盛 ■築城年 寛永2年(1625年) ■主な遺構 石垣 / 土塁 / 堀 |
|
| 堀と本丸表御門石垣 | ||
| JR新庄駅から西へ32号線を進むと、新庄城がある。戊辰戦争では奥羽越列藩同盟を離脱したため、攻撃を受けて城と城下町は大半が焼失する。本丸跡に戸沢神社
/ 護国神社 / 稲荷神社 / 天満神社がある。寛永5年(1628年)創建の天満神社社殿は、藩政時代から現存する寛文8年(1668年)に再建されたもの。 [交通]JR新庄駅-(徒歩/約25分)-新庄城 |
||
| 出羽国・山形城(霞城 / 吉字城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 斯波兼頼 ■築城年 正平11年(1356年) ■主な遺構 大手南門が万松寺に、移築され現存する。八日町宝光院の本堂は、御殿の建物を移築したものと云われている。 ■主な再建造物 東大手門 / 多聞櫓 |
|
| 多聞櫓・最上義光像 | ||
| JR山形駅から西へ、直ぐに右折して北に進むと南門がある。城跡は霞城公園になっている。 [交通]JR山形駅-(徒歩/約10分)-山形城南門 |
||
| 出羽国・鶴ヶ岡つるがおか城(大宝寺城 / 大梵寺城) |
||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 大泉氏 ■築城年 鎌倉時代(1185年頃〜1333年)初期 ■主な遺構 土塁 / 石垣 / 堀 / 藩校 / 庭園 |
|
| 堀 | ||
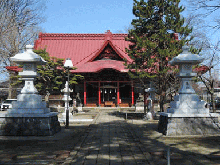 |
 |
 |
| 山王日枝神社 | 田沢稲舟銅像 | 「蝉しぐれ」ゆかりの地案内板 |
| JR羽越本線・鶴岡駅より南へ進む。10分ほどすると、右手に鶴岡で一番古い社と云われる山王日枝神社のある交差点を右折する。5分ほどの内川に架かる橋を渡り、内川沿いの道を進む。鶴岡市出身の小説家・田沢稲舟(たざわ いなぶね)銅像 / 藤沢周平の代表作「蝉しぐれ」ゆかりの地案内板 がある。5分ほどすると47号線と交差、右折して内川に架かる橋を渡り西へ進む。すぐ左手に致道館、すぐの交差点を越えた右手に鶴岡公園がある。 [交通]JR羽越本線・鶴岡駅-(徒歩約30分)-鶴岡公園 |
||
| 築城当時は大宝寺城と呼ばれた鶴ヶ岡城は、鎌倉時代初期に出羽国大泉荘の地頭・大泉氏が築城したと云われている。 |
||
 |
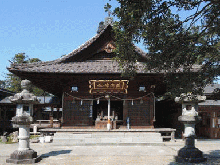 |
 |
| 荘内神社 | 大寶館 | |
 |
本丸跡に、明治10年(1877年)旧藩主を慕う人々 によって創建された荘内神社がある。本丸中門跡に、大正4年(1915年)大正天皇の即位を祝い建てられた大寶館がある。開館当初は物産陳列場、戦後は市立図書館として利用された。現在は、鶴岡出身著名人の資料館となっている。 |
|
| 本丸内北門跡 | ||
 |
鶴岡公園 |
|
| 致道館 |
||
| 出羽国・米沢城(舞鶴城 / 松ヶ岬城) | ||
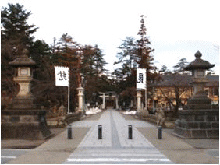 |
■城の種別 |
|
|
松が岬公園 |
||
| JR米沢駅西口から232号線を西へ進むと、左手に松が岬公園がある。本丸跡に上杉神社がある。永禄10年(1567年)伊達正宗が誕生した城として知られている。慶長2年(1597年)120万石で上杉景勝が封じられ、直江兼続が米沢城主になる。関ヶ原の戦い後に30万石に減封され、明治維新まで米沢藩上杉氏の居城となった。 [交通]JR米沢駅-(徒歩/約20分)-松が岬公園 |
||
| 出羽国・上山城(月岡城) | ||
 |
■城の種別 |
|
| 模儀天守 | ||
| JRかみのやま温泉駅西口から北へ、169号線を左折する。13号線(羽州街道)を右折して北へ進むと、左手に月岡公園がある。応永年間(1394年〜1427年)初期に、里見満長が築城したのが始りと云われている。二の丸跡に模擬天守や月岡神社がある。 [交通]かみのやま温泉駅-(徒歩/約10分)-月岡公園 |
||