| 最新の追加 | ||
| 下野国・黒羽くろばね城(九鶴城) |
||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 大関高増 ■築城年 天正4年(1576年) ■主な遺構 土塁 / 堀 / 曲輪 |
|
| 黒羽城 高土塁 | ||
| JR東北本線・西那須野駅からバスに乗車、大雄(だいおう)寺入口バス停で下車する。バスの進行方向に進み、すぐに左折して坂を登る。すぐのT字路に標識があり、右折して道なりに坂を登る。すぐ左手に大雄寺参道がある。 [交通]JR東北本線・西那須野駅-(関東自動車バス40分)-大雄寺入口バス停-(徒歩5分)-大雄寺参道 |
||
| バスの運行本数が極めて少ないため、帰路は大雄寺入口バス停-(大田原市営バス40分)-JR東北本線・那須塩原駅を利用している。 かつては東野(とうや)鉄道が、西那須野駅〜黒羽駅〜那須小川駅の24.4kmを結んでいた。昭和14年(1939年)黒羽駅〜那須小川駅 / 昭和43年(1968年)西那須野駅〜黒羽駅 が廃止された。 |
||
 |
大雄寺は応永11年(1404年) |
|
| 大雄寺山門 | ||
  |
||
| 大雄寺総門 / 廻廊 大雄寺本堂 | ||
 |
大雄寺参道を戻ると、隣接して虚空蔵堂がある。 | |
| 虚空蔵堂 | ||
 |
 |
 |
| 芭蕉句碑 | 浄法寺邸跡 | 大雄寺方向 |
| 虚空蔵尊堂から北に進むと、左手に案内板 / 芭蕉句碑「行く春や鳥啼き魚の目は泪」がある。ここから芭蕉の道に入ると、黒羽城三の丸の南にある浄法寺邸跡に行ける。西方向に、堀を挟んで木々の間から大雄寺の建物が見える。 元禄2年(1689年)4月3日、芭蕉は余瀬の翠桃宅に着く。4月4日に芭蕉と曾良は浄法寺高勝邸に招かれ歓待され、11日まで滞在した。浄法寺高勝は黒羽藩の城代家老で俳人、芭蕉の門下で俳号は桃雪 / 秋鴉。ここで芭蕉は「山も庭もうこき入るや夏座敷」と詠んでいる。 |
||
 |
 |
|
| 黒門跡 | ||
 |
||
| 那珂川 | 三の丸跡 | |
 |
 |
|
| 真先寶壽両社稲荷神社 | ||
 |
||
| 本丸跡 | 本丸堀 | |
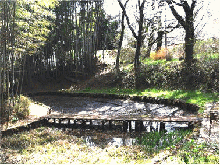 |
黒羽城は那珂川に沿って南北に延びた丘陵に築かれている。南北1.5kmにも及ぶ山城で、本丸の北に二の丸 / 南に三の丸 があった。本丸は黒羽城址公園
/ 北城とも呼ばれる二の丸に黒羽体育館 / 三の丸は芭蕉公園 になっている。本丸は周囲を土塁が巡り、南には深い堀がある。黒羽城を築城したとき、城守稲荷として真先(まさき)稲荷神社を創建する。戦場の先駆けたらんことを祈願した神社で、後に寶壽(ほうじゅ)院の稲荷社を合祀して真先寶壽両社稲荷神社になった。 |
|
| 池 | ||
| 天文11年(1542年)白旗城を居城としていた大関氏13代・大関増次は、大田原資清の奇襲により自刃する。大関増次には嫡子なく、大田原資清は長男・高増を養嗣子として送り込んで家督を継がせた。大関氏は事実上大田原氏に乗っ取られることになった。黒羽城は天正4年(1576年)大関高増が築城した。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐とき、主家の那須資晴は小田原へ参陣しなかったために改易された。大関高増は大田原氏や芦野氏など那須衆と談合して参陣、所領を安堵された。 慶長5年(1600年)関ケ原の戦いのとき、大関晴増は上杉景勝に対する備えとして黒羽城の改修を行った。徳川家康から援兵として、岡部内膳 / 服部市郎右衛門 が付けられた。関ケ原の戦い後に徳川家康から加増されて2万石の大名となった。正保3年(1646年)大関高増の没後、高増の二男・増榮、三男・増公にそれぞれ千石を分知する。以後黒羽藩は一万八千石の大名として明治に至り、廃藩置県により明治4年(1871年)廃城となった。 |
||
| 下野国・児山こやま城 | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 多功朝定(児山朝定) ■築城年 建武年間(1334年?1338年) ■主な遺構 土塁 / 堀 / 曲輪 |
|
| 児山城址 | ||
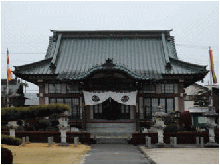 |
JR東北本線・石橋駅西口より西に進む。すぐの石橋交差点を右折して4号線(日光街道)を北に進む。すぐ右手に天応元年(781年)創建の開雲寺がある。東光寺として創建、文亀2年(1502年)に当地に移転する。境内に御殿所が造られ、将軍家の日光東照宮参拝道中の休泊所となっていた。 | |
| 開雲寺 | ||
 |
4号線(日光街道)を北に進むと、すぐ右手に石橋郵便局がある。風景印は、グリムの森の木の外枠 / グリムの館(多目的ホール) の図柄になっている。 | |
| 石橋郵便局風景印 | ||
 |
石橋は平成18年(2006年)に合併して下野市になる前は、栃木県下都賀郡石橋町であった。ドイツ・ディーツヘルツタール(旧シュタインブリュッケン)と姉妹都市協定を締結している。グリム童話の生まれ故郷“シュタインブリュッケン”は日本語で“石橋”となるため、地名が縁となり姉妹都市となった。石橋町マンホールも同じ趣向となっている。 | |
| 石橋町マンホール | ||
|
4号線(日光街道)を北に進み、5分ほどのT字路交差点を左折して西に進む。10分ほどのY字路を右(北西)方向に進む。5分足らずのT字路を左折すると、華蔵寺がある。 |
||
 |
 |
 |
| 華蔵寺山門 | 華蔵寺本堂 | 華蔵寺薬師堂 |
 |
華蔵寺は、弘安6年(1283年)児山朝定が、児山城二の丸に大通寺を創建したのが始まり。児山氏の菩提寺。建武元年(1334年)華蔵寺に改称する。 |
|
| 華蔵寺聖天堂 | ||
| 児山城本丸は華蔵寺の北西側にあり、山門左手から墓地を通って行ける。児山城は姿川東岸の台地上に築かれている。本丸は南北に長い方形で、周囲に土塁と空堀が巡らされている。土塁の四隅は他の部分に比べ高く築かれ、櫓があったと云われている。本丸以外は周囲に断片的に遺構が残るのみであるが、城域はかなりの広さであった。 |
||
 |
 |
 |
| 児山城址入口付近の空堀 | 本丸空堀(通路から右方向) | 本丸空堀(通路から左方向) |
 |
 |
 |
| 本丸 | 本丸土塁 | 本丸から空掘越しに見える曲輪 |
| 建武年間(1334年?1338年)に多功朝定によって築城された。宇都宮頼綱の七男・宇都宮宗朝が多功氏を名乗る。多功宗朝の三男・多功朝定はこの地を分封され、児山城を築城する。後に児山氏を名乗る。元禄元年(1558年)上杉謙信が下野国に侵攻、多功城を攻撃する。多功城主・多功長朝は、児山城主・児山兼朝 / 簗城主・簗朝光などの援軍により撃退した。このとき児山兼朝は討ち死して、児山城は廃城になったと云われている。 | ||
 |
 |
 |
| 下野星宮神社鳥居 | 招福鳥居 | 下野星宮神社社殿 |
 |
児山城の本丸から真北 / 直線距離で500m足らずのところ に下野星宮神社がある。道が入り組んでおり。解りずらい。下野星宮神社は、大同2年(807年)に創建されたと云われている。多功朝定は香取神宮より経津主神を勧請、児山城の守護神とした。 |
|
| 夢福神 | ||
| 下野国・多功たこう城 | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 多功宗朝 ■築城年 宝治2年(1248年) |
|
| 多功城跡 | ||
| JR東北本線・石橋駅東口より東北新幹線高架下沿いに南に進む。5分ほどすると146号線と交差、左折して東に進む。 [交通]JR東北本線・石橋駅東口-(徒歩15分)-日光東往還との交差点 |
||
| 日光東往還は日光街道の脇往還で、水戸街道・小金宿〜我孫子宿間(JR常磐線南柏駅付近)の追分と日光街道・石橋宿〜雀宮宿間(JR宇都宮線・宇都宮貨物ターミナル駅付近)の追分を結んでいた。道程は20里34町(約82km)に及ぶ官道であった。 |
||
| [寄り道]石橋本町郵便局 | ||
 |
146号線を西に進む。東北新幹線高架を潜り、JR東北本線の第一上三川街道踏切を渡る。すぐに4号線(日光街道)と交差、直進するとすぐ左手に石橋本町郵便局がある。風景印は、石橋駅前広場にある時計塔 / グリムの里マスコット の図柄になっている。 | |
| 石橋本町郵便局風景印 | ||
| 地図では交差点の北東側が多功城跡と表記されている。交差点から北東側を徘徊する。多功城跡に含まれる林を撮影しているとき、地元の方に声を掛けられる。曰く「多功城跡の遺跡はなく、地図に表記されているだけ。」とのこと。 | ||
 |
 |
交差点から146号線を東に進み、すぐに右折すると星宮神社がある。 |
| 星宮神社鳥居 | 星宮神社社殿 | |
 |
 |
146号線をさらに東に進むと、右手に見性寺がある。建暦2年(1212年)平貞能が草庵を結んだのが始まり。宝治2年(1248年)多功宗朝が多功城を築城のとき諸堂を建立、宝徳3年(1451年)見性寺と改称、多功城主の菩提寺となる。 |
| 見性寺山門 | 見性寺本堂 | |
|
宇都宮頼綱の七男・宗朝は宝治2年(1248年)多功城を築城、多功氏を名乗る。 |
||
| 下野国・足利氏館 | ||
 |
■城の種別 館 ■築城者 足利義兼 ■築城年 平安時代末期または鎌倉時代初期 ■主な遺構 土塁 / 堀 |
|
| 鑁阿寺太鼓橋 / 山門 / 土塁 / 堀 | ||
| JR両毛線・足利駅から北へ、JR足利駅入口交差点を左折して67号線を西へ進む。通1丁目交差点を右折して293号線を北へ進む。足利学校の北東側にある交差点左折すると、右手に鑁阿(ばんな)寺がある。 [交通]JR両毛線・足利駅-(徒歩10分)-鑁阿寺 |
||
 |
 |
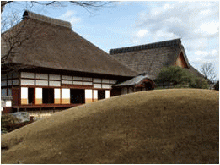 |
| 土塁 / 水堀(293号線側) | 足利学校入徳門 | 足利学校方丈 |
 |
 |
足利学校は、平安時代に創設されたと云われる日本最古の学校。室町時代から戦国時代にかけて、関東における最高学府であった。 |
| 足利学校裏門 | 土塁 / 水堀(鑁阿寺側) | |
 |
 |
 |
| 鑁阿寺土塁 / 水堀 | 鑁阿寺太鼓橋 | 鑁阿寺山門 |
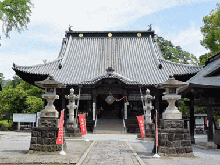 |
 |
 |
| 鑁阿寺本堂(国宝) | 鑁阿寺不動堂 | 鑁阿寺一切経堂(重文) |
 |
 |
 |
| 鑁阿寺多宝塔 | 鑁阿寺鐘楼(重文) | 鑁阿寺御霊屋 |
| 源義家の四男・源義国は上野国八幡荘を相続、また下野国足利荘も領することになる。 足利氏館は、平安時代末期または鎌倉時代初期に足利氏2代・足利義兼によって築かれた。足利義兼は源頼朝の挙兵に応じて平氏追討戦や奥州征伐に従軍、軍功を挙げている。足利尊氏の代に隆盛を迎え、鎌倉幕府を倒し室町幕府を開いた。方形居館の四面を廻る土塁と水堀が残り、鎌倉時代の武士屋敷の面影を伝える遺構になっている。館跡は、鑁阿寺の境内になっている。鑁阿寺は、建久7年(1196年)足利義兼が城内に持仏堂を建立したのが始まり。文暦元年(1234年)足利義氏が堂塔伽藍を建立、足利氏の氏寺となる。 |
||
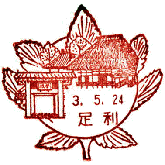 |
鑁阿寺や足利学校の東側を通る293号線を北に進む。足利学校の北東側にある交差点から10分ほどの有楽町交差点を右折すると、5分ほどの左手に足利郵便局がある。 |
|
| 足利郵便局風景印 | ||
| 下野国・足利陣屋 | ||
 |
■城の種別 陣屋 ■築城者 戸田忠言 ■築城年 ■主な遺構 移築陣屋表門(陣屋大門) |
|
| 陣屋大門標柱 | ||
| 東武伊勢崎線・足利市駅より線路沿いに北東に進む。すぐの38号線を右折して、渡良瀬川に架かる中橋を渡る。すぐのJR両毛線の踏切を越える。すぐの通2丁目交差点を左折して67号線を北西に進むと、5分足らずの右手に陣屋大門標柱
/ 陣屋大門案内板 がある。 [交通]東武伊勢崎線・足利市駅-(徒歩20分)-陣屋大門標柱 |
||
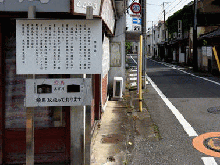 |
 |
 |
| 陣屋跡案内板 | 栄富稲荷神社 | 栄富稲荷神社スタンプ |
| 陣屋大門通りと地図に記載されている小路を北に進む。陣屋井戸があるらしいが、民家の庭とのことで躊躇して諦める。 |
||
|
|
||
| 案内板がある十字路を西に進むと、法玄寺 / 足利織姫神社 に至る。 |
||
 |
 |
 |
| 法玄寺塀 / 水堀 | 法玄寺山門 | 法玄寺本堂 |
|
法玄(ほうげん)寺は、足利義兼の長男・義純が鎌倉時代初期に母(初代執権北条時政の娘・北条時子 北条政子の同母妹)の菩提のために創建したと云われている。 |
||
 |
 |
足利織姫神社は機神山の中腹に鎮座している。階段は229段続き、途中に“境内まで118段 いいわ眺望 関東平野”や“境内まで75段 なごむ心で宮参り”と残りの段数案内がある。 |
| 織姫神社参道 | 残りの段数案内 | |
 |
 |
 |
| 織姫神社社殿 | 足利市内眺望 | 織姫神社絵馬 |
| 宝永2年(1705年)創建の足利織姫神社は、1200年以上の伝統と歴史をもつ足利織物の守り神。織姫神社の背後に続く山道を進むと足利城址に行ける。岩場がある登山道のため、行っていない。 |
||
|
下野国・佐野陣屋(植野城 / 堀田佐野城 |
||
 |
■城の種別 平城(陣屋) ■築城者 堀田正高 ■築城年 貞享元年(1684年) 土塁 大手門が東光寺 / 裏門が(佐野市赤坂町) に移築現存する。 |
|
| 陣屋土塁跡 | ||
|
東武佐野線・田島駅の東西を結ぶ地下道の東側口出口から、線路沿いに南に進む。5分足らずの50号線を潜る手前を左折、50号線の側道〜50号線の歩道〜50号線の側道と20分ほど東に進む。最初の交差点を左折して北へ進む。すぐのY字路を右方向に、すぐのY字路を右方向に進む。すぐ右手の小公園に、城址石碑
/ 佐野城墟(じょうきょ)碑及び城郭図 / 石碑 がある。 |
||
 |
 |
 |
| 城址石柱 | 堀田佐野城址公園門 | 池 |
| 慶長19年(1614年)佐野信吉は改易となり、佐野城は廃城となる。佐野藩は天領となるが、貞享元年(1684年)下野国古河藩主であった老中・堀田正俊の次男・堀田正高が入封する。元禄11年(1698年)堀田正高は近江国・堅田藩に移封、佐野陣屋は廃される。文政9年(1826年)堀田正敦は堅田藩から佐野藩へ移封となる。文政11年(1828年)改めて陣屋が置かれ、明治維新まで続いた。 |
||
|
|
||
 |
 |
 |
| 東光寺山門 | 東光寺仁王門 | 東光寺薬師堂 |
 |
 |
東光寺は延暦年間(782年〜806年)創建で、堀田家の菩提寺であった。中門は、明治9年(1876年)に陣屋大手門(表門)を移築したもの。 |
| 東光寺中門 | 東光寺本堂 | |
 |
東光寺参道入口から道なりに北東に進むと、10分足らずの右手に佐野市駅がある。さらに北に進み、2本目のT字路を左折する。十字路を越えた左手の病院に、移築された陣屋裏門がある。 |
|
| 陣屋裏門 | ||
|
下野国・栃木城 |
||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 皆川広照 ■築城年 天正19年(1591年) 堀 / 土塁 |
|
|
栃木城 |
||
|
JR栃木駅から213号線を北東に進む。すぐの河合町交差点を右折して、31号線を東に進む。 |
||
 |
 |
 |
| 堀 | 栃木城址公園標柱 | 築山 |
|
天正18年(1590年)皆川城が豊臣秀吉の軍勢によって落城、居城を失った皆川広照は天正19年(1591年)栃木城を築城する。 |
||
| 下野国・畠山陣屋 | ||
 |
■城の種別 陣屋 ■築城者 畠山基玄 ■築城年 元禄元年(1688年) 陣屋門 / 代官屋敷 |
|
| 陣屋門 | ||
| JR両毛線 / 東武日光線・栃木駅北口より北へ、11号線を北に進む。途中で例幣使街道と合流する。蔵の街・栃木宿を通り、万町交差点を左折する。すぐに右折してY字路を左に道なりに進むと、すぐ右手に岡田記念館がある。 [交通]JR両毛線 / 東武日光線・栃木駅-(徒歩25分)-岡田記念館 |
||
|
天正年間(1573年〜1592年)岡田嘉右衛門が荒れ地を開墾、江戸幕府より嘉右衛門新田村の名を得る。貞享2年(1685年)旗本・畠山基玄の領地となり、元禄元年(1688年)岡田家の屋敷内に陣屋が置かれた。 |
||
| 下野国・富田城 |
||
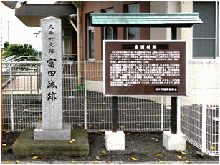 |
■城の種別 平城→陣屋 ■築城者 富田成忠 ■築城年 嘉吉元年(1441年) 土塁 |
|
| 富田城石柱 / 案内板 | ||
| JR両毛線・大平下駅から南西へ進む。すぐに左折して冨田バイパスに平行する道を進む。 [交通]JR両毛線・大平下駅-(約5分)-大平西小学校 |
||
|
|
||
| 下野国・新田義重館跡 | ||
 |
■城の種別 館 ■築城者 新田義重 土塁 |
|
| 総持寺本堂 | ||
 |
東武伊勢崎線・世良田駅の西側を通る69号線を南に進む。15分ほどの世良田交差点を右折して西へ進むと、5分ほどの左手に総持寺がある。新田義重の館跡と云われ、西の早川を背にして堀で囲んでいた。新田氏は、源義国の長男・義重を祖とする。鎌倉攻めに挙兵した9.代・新田義貞が知られている。足利氏は、源義国の次男・義康を祖とする同族である。 | |
| 総持寺山門 | ||
| 新田荘は平安時代末期に新田義重によって開かれ、旧新田郡のほぼ全域と旧太田市の南西部を荘園化した。世良田地区は新田荘の経済的 / 文化的 中心であった。 |
||
 |
 |
 |
| 長楽寺総門 | 長楽寺本堂 | 長楽寺三仏堂 |
 |
 |
|
| 長楽寺太鼓門 |
||
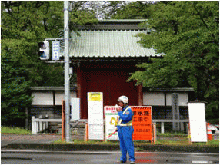 |
||
| 14号線沿いの勅使門 | 蓮池に架かる渡月橋 / 勅使門 | |
| 世良田交差点から南に進むと、すぐ右手に承久3年(1221年) 創建の長楽寺 / 南側に寛永21年(1644年)創建の世良田東照宮 がある。長楽寺境内に、慶安4年(1651年)徳川家光によって再建された三仏堂 / 江戸時代初期建立の太鼓門 / 寛永21年(1644年)世良田東照宮 |
||
 |
 |
|
| 世良田東照宮御黒門 | ||
 |
||
| 世良田東照宮鳥居 | 世良田東照宮拝殿 | |
| 世良田東照宮は、寛永21年(1644年)徳川家光の命により日光東照宮の古社殿を移築して長楽寺境内に創建された。本殿 / 拝殿 / 唐門 は重文。新田義重の四男・義季は、世良田郷を譲られ地頭になる。新田義季は、得川郷を長男・頼有 / 世良田郷を次男・頼氏 に継承させた。頼氏は世良田氏を称した。三河国の戦国大名・松平清康のとき、世良田氏の末裔を称する様になったと云われている。徳川家康は、天正18年(1590年)関東に移封される。世良田氏発祥の地は、徳川氏ゆかりの地とされた。 |
||
| 下野国・鹿沼かぬま城 |
||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 壬生綱房 ■築城年 天文元年(1532年) 土塁 |
|
| 鹿沼城跡 | ||
 |
 |
東武鉄道日光線・新鹿沼駅から東へ、すぐの新鹿沼駅前交差点を左折して壬生道の内町通り(293号線 / 352号線)を北へ進む。15分ほどの市役所前交差点を左折して西へ進む。すぐに市役所に突き当り、左折する。すぐの突き当りを右折すると、鹿沼城跡の御殿山公園がある。 [交通]東武鉄道日光線・新鹿沼駅-(徒歩/20分)-御殿山公園 |
| 鹿沼城案内板 | 登り口 | |
| 黒川の西側の台地上に築かれた平山城で、現在は野球のグラウンド施設となっている。 |
||
| 下野国・壬生みぶ城 |
||
 |
■城の種別 |
|
| 壬生城復元門 | ||
|
東武鉄道宇都宮線・壬生駅より西へ進む。すぐの壬生駅入口交差点を右折して、壬生道(日光西街道)を北へ進む。すぐに、右方向のT字路と左方向のT字路からなる壬生町役場入口交差点がある。左方向のT字路を左折して西へ進む。5分ほどすると右手に壬生城址公園がある。 |
||
 |
文明年間(1469年〜1486年)壬生胤業の子・壬生綱重によって築かれたと云われている。壬生氏は京都の公家・小槻氏の壬生胤業を祖とすると云われているが、宇都宮氏庶流の末裔など諸説がある。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐では、壬生義雄は北条氏に味方して小田原城に立て籠もった。壬生義雄は落城直後で病死、嫡子なく壬生氏は断絶となり所領は没収された。 | |
| 壬生城 堀 / 土塁 | ||
|
徳川家康が関東に入封すると結城秀康が城主となる。以降、慶長7年(1602年)日根野吉明 / 寛永12年(1635年)阿部忠秋 / 寛永16年(1639年)三浦正次 / 元禄5年(1692年)松平(大河内)輝貞 / 元禄8年(1695年)加藤明英
と目まぐるしく入れ替わった。正徳2年(1712年)鳥居忠英が入封、以後8代続いて明治に至る。 天守 / 櫓 はなく、簡素な城であった。本丸に御殿があり、江戸初期には将軍の日光社参の宿舎となった。廃藩後は城の建物は取り壊され、堀や土塁の多くも破壊された。本丸は城址公園として整備され、資料館 / 図書館 などがある。土塁 / 堀 の一部が残り、二の丸門が復元されている。 |
||
 |
掘が遮断された橋に見立てた道を進むと、左手に2基の傍示抗が保存されている。左側は、正面と右側面に「従是南
壬生領」 / 左側面に「下野国 都賀郡 家中村」 と彫られている。右側は、正面と右側面に「従是北 壬生領」と彫られている。 |
|
| 壬生領傍示杭 | ||
 |
 |
 |
| 精忠神社神門 | 精忠神社拝殿 | 畳塚 |
|
奥にある図書館の手前を左に進むと、精忠神社 / 本殿の裏に畳塚 がある。鳥居元忠は徳川家康が今川氏の人質だった頃からの側近の一人で、あらゆる合戦に参戦している。関ヶ原の戦いの前哨戦に当たる伏見城の戦いでは、1800人の兵で宇喜多秀家率いる4万と云われる大軍に攻撃される。13日間持ち堪えて落城、鳥居元忠は戦死する。徳川家康は鳥居元忠の「血染めの畳」を江戸城伏見櫓の階上に置き、登城した大名たちに鳥居元忠の精忠を偲ばせたと云われている。明治維新の江戸城開城のとき、「血染めの畳」は持ち出されて埋められたと云われている。 |
||
 |
 |
精忠神社神門手前の左右に、2基の傍示抗がある。左側は、正面に「従是南」 / 左側面に「下野国都賀」 と彫られている。右側は、正面に「従是北」と彫られている。 |
| 傍示抗 | ||
| 下野国・板橋城 | ||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 遊城坊綱清 ■築城年 永正年間(1504年〜1521年) ■主な遺構 石垣 / 土塁 / 堀 / 郭 |
|
| 城山 | ||
| 壬生道(日光西街道)板橋宿の南東にある城山(443m)に、永正年間(1504年〜1521年)宇都宮一族の遊城坊綱清が築城したと云われている。天文年間(1532年〜1555年)宇都宮氏と敵対していた壬生綱房は、小田原北条氏に支援を求める。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐で、板橋氏は壬生氏とともに滅亡する。関ヶ原の戦い後、松平一生が下野国・板橋藩主となる。 |
||
| 下野国・喜連川城 | ||
 |
■城の種別 平山城のち陣屋 ■築城者 塩谷惟広 ■築城年 鎌倉時代初期 ■主な遺構 空堀 / 土塁 ■主な再建造物 模擬城門 |
|
| 模擬城門 | ||
| 奥州街道の江戸からの入口である連城橋を渡る。宿場通りを進むと左手に「←さくら市役所喜連川支所」標識があり、左折すると模擬城門が見える。 喜連川城は、宇都宮氏の支流・塩谷惟広が鎌倉時代初期に築城した大蔵ヶ崎城に始まる。塩谷惟広は、平安末期から鎌倉初期の武将で、喜連川塩谷氏の祖。 明治3年(1870年)廃藩置県に先立って新政府に奉還、喜連川城は廃城となった。現在はお丸山公園となっており、空堀 / 土塁 が残る。 |
||
 |
模擬城門は陣屋門としては大き過ぎる感がある。お丸山公園登り口にある門の方が陣屋門らしい。 | |
| お丸山公園門 | ||
 |
奥州街道の江戸からの入口である連城橋を渡る。すぐの本町交差点を過ぎると、右手に足利尊氏が創建した龍光寺がある。足利国朝や足利頼氏の父・足利頼純が慶長6年(1601年)に死去したとき葬られ、菩提所となり歴代の廟所がある。 | |
| 龍光寺 | ||
 |
||
| 喜連川城址 / 喜連川スカイタワー | ||
| お丸山公園門山頂に、喜連川スカイタワーがある。東日本大震災による被災により、再開の見通しが立っていないと云う。 | ||
| 下野国・大田原城 |
||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 大田原資清 ■築城年 天文12年(1543年) ■主な遺構 堀 / 土塁 |
|
| 本丸跡 | ||
| 金燈籠交差点から旧奥州街道を北東へ進む。旧奥州街道は次の交差点を左折して、ビジネスホテル手前を右折する。桝形を通り道なりに進むと、太田原神社と龍城公園を繋ぐ461号線横断架橋手前で461号線に合流する。金燈籠交差点から10分ほどになる。すぐ右手に大田原城跡がある。 大俵氏は、武蔵七党の丹党の一族である安保氏の分流とされる。南北朝時代に下野国那須地方の大俵に移住したことから大俵と名乗り、大俵忠清が初代と云われている。那須氏に仕え、大俵胤清の代に大田原氏に変更したといわれている。天正18年(1590年)小田原征伐のとき大田原晴清は豊臣秀吉に従い、那須氏から認められていた領地を安堵される。慶長7年(1602年)12400石となり、大田原藩を立藩した。明治維新まで大田原氏が居城した。戊辰戦争のとき、大田原城は会津攻めの重要拠点とされた。慶応4年(1868年)旧幕府軍による攻撃を受け、三の丸が炎上した。明治6年(1873年)廃城令により廃城となる。現在は龍城公園(城山公園)になっている。 |
||
 |
 |
 |
| 大田原龍城公園石柱 | 龍体山大田原城案内板 | 太田原神社 |
| 旧奥州街道(461号線)を挟んだ反対側に、太田原神社がある。大田原城跡からは461号線横断架橋で行ける。天文12年(1543年) |
||
| 下野国・勝山城(氏家城) | ||
 |
■城の種別 丘城 ■築城者 氏家公頼 ■築城年 建久2年(1191年) ■主な遺構 石垣 / 土塁 / 空堀 ■主な再建造物 木橋 |
|
| 本丸空堀 | ||
|
JR東北本線・氏家駅から西へ進む。4号線と交差、左折して南へ進む。川岸南交差点から125号線を進むと右手に勝山城址がある。旧奥州街道沿いに位置する。 |
||
 |
 |
 |
| 本丸空堀に架かる木橋 | 本丸跡 | 本丸土塁 |
 |
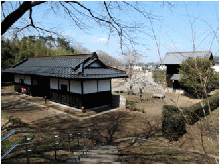 |
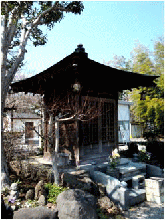 |
| 「勝山城址周辺の鬼怒川」標柱 | 民家広場 | 昌玖寺愛染明王堂 |
|
本丸空堀に架かる木橋が復元されている。本丸跡から西へ進むと、「勝山城址周辺の鬼怒川」標柱がある。旧奥州街道から本丸方向へ進んだ右手の民家広場に、旧森家長屋門と2階建て瓦葺の旧手塚家が移築されている。左手に昌玖寺やさくら市ミュ−ジアムがある。本堂らしき建物は見当たらない。氏家氏の祈願寺とされている。境内の愛染明王堂にある愛染明王は、鎌倉時代末期〜南北朝時代造立のもの。 |
||
| 下野国・徳次郎とくじら城 | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 新田徳次郎昌言 ■築城年 戦国時代 ■主な遺構 曲輪 / 土塁 / 空堀 |
|
| 旧日光街道からの徳次郎城跡 | ||
| 旧日光街道の徳次郎から南へ進む。5分ほどすると、左手に案内板がある。戦国時代に宇都宮氏22代・宇都宮国綱の家臣・新田徳次郎昌言によって築城されたと云われている。慶長2年(1597年)宇都宮国綱の改易に伴ない、廃城となった。田川の西岸に造られた平城で、曲輪 / 土塁 / 空堀 が残る。所有者が一般個人であるため、立ち入ることは出来ない。 | ||
| 下野国・烏山城(臥牛城) | ||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 那須資重 ■築城年 応永25年(1418年) ■主な遺構 石垣・土塁 |
|
| 吹貫門跡の石垣 | ||
|
烏山駅から西へ、駅入口交差点を右折して北へ進む。烏山幼稚園入口交差点を左折、法務局前交差点を右折する。左手に烏山城の案内看板がある。急な七曲り坂を登る。堀切の車橋跡を過ぎると、吹貫門跡に石垣がある。二の丸と本丸間にも堀切がある。本丸は杉の木が生い茂っている。三の丸跡に寿亀山神社がある。 |
||
| 下野国・飛山とびやま城 |
||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 芳賀高俊 ■築城年 永仁年間(1293年〜1298年) 土塁 / 空堀 ■主な再建造物 掘立柱建物 |
|
| 飛山城 |
||
| JR宇都宮駅東口から東へ、すぐの交差点を右折して南へ進む。5分ほどすると1号線と交差、左折して東へ進む。すぐの平松町交差点から水戸袴塚3丁目交差点までは123号線で、宇都宮と水戸を結ぶ主要ルートになっている。街道の雰囲気があるかと往路は歩いたが、期待外れであった。平松町交差点から60分ほどすると、新鬼怒橋西交差点がある。鬼怒川に架かる新鬼怒橋(584.25m)を渡る。北側に見える鬼怒橋は、帰路に利用したバスが通る。新鬼怒橋西交差点から20分ほどの鏡山交差点を左折して北へ進む。15分ほどの交差点に標識があり左折する。ところどころに標識があり迷うことはない。10分ほどすると、飛山城史跡公園がある。 北側と西側は鬼怒川と支流に沿った断崖、東側と南側を二重の土塁と空堀で囲う堅固な造りとなっている。各郭は土塁と空堀で囲まれており、幅15m / 深さ4m の空堀もある。5つの櫓台があった。兵士の詰め所と思われる掘立柱建物 / 貯蔵庫と思われる半地下式の竪穴建物 が確認されている。飛山城跡は飛山城史跡公園 |
||
 |
 |
 |
| 外堀の土塁と空堀 |
桝形土塁 |
土塁と空堀 |
 |
 |
 |
| 北西側の郭 | 掘立柱建物 |
鬼怒川 |
| 永仁年間(1293年〜1298年)宇都宮景綱の家臣・芳賀高俊によって築かれたと云われている。芳賀氏は宇都宮氏の重臣で、養子・姻戚関係により宇都宮氏一族でもある。宇都宮氏は下野国守護だけではなく上野国や越後国の守護にも任じられ、芳賀氏は上野国や越後国の守護代に任じられていた。弘治3年(1557年)宇都宮氏や芳賀氏を支援した佐竹義昭により、壬生綱雄に占領されていた宇都宮城奪回が行われた。このとき飛山城は最前線基地となっている。 |
||
| 下野国・宇都宮城(亀ヶ岡城 / 亀ヶ丘城 / 唐糸城) | ||
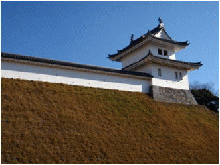 |
■城の種別 平城 ■築城者 藤原宗円 ■築城年 平安時代末期 ■主な遺構 土塁 ■主な再建造物 清明台櫓 / 富士見櫓 / 堀 / 土塀 |
|
| 富士見櫓 | ||
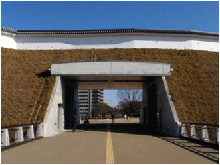 |
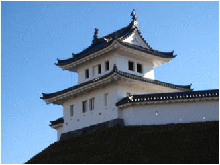 |
JR東北本線・宇都宮駅から大通りを西へ進む。宇都宮二荒山神社のある馬場通り1丁目交差点を左折してバンバ通りを南へ進むと、突き当りに宇都宮城址公園がある。 [交通]JR東北本線・宇都宮駅-(徒歩/約20分)-宇都宮城址公園 |
| 西側の正面入口 | 清明台櫓 | |
| 平安時代末期に藤原宗円(宇都宮氏の祖)が築城したと云われるが、藤原秀郷築城説もある。平安時代末期から改易される慶長2年(1597年)まで、約500年続いた宇都宮氏の居城。戦国時代後期には後北条氏や家臣である壬生氏の攻撃で、占拠されたこともあった。天正18年(1590年)に行われた奥州仕置(おうしゅうしおき)では、豊臣秀吉に謁見するため奥州の大名が宇都宮城に参城した。慶長2年(1597年)宇都宮氏の改易後は、慶長3年(1598年)蒲生秀行 / 慶長6年(1601年)奥平家昌 / 元和5年(1619年)徳川家康の懐刀と言われた本多正純が入封する。徳川将軍の日光東照宮参拝の際に、将軍の宿泊施設として利用された。宇都宮城釣天井事件は、徳川2代将軍・徳川秀忠の暗殺を図ったとされる事件である。釣天井の仕掛けは存在しなかったとされている。本田正純以降は譜代大名がこまめに入れ替わり、戸田氏で幕末を迎える。慶応4年(1868年)戊辰戦争の戦地となり、宇都宮城の建造物は藩校修道館などを残して焼失した。東山道軍の対会津戦争の拠点となり、板垣退助をはじめ東山道軍の幹部等が駐屯した。天守は築かれず、清明台櫓が代わりとなっていた。土塁に清明台櫓と富士見櫓が再建される。 | ||
| 下野国・小山おやま城(祗園ぎおん城) | ||
 |
■城の種別 |
|
|
城山公園入口 |
||
| JR東北本線・小山駅から西へ進む。すぐに旧日光街道(265号線)と交差する。交差点を直進して、西へ道なりに進む。15分ほどすると、思川に架かる観晃橋手前の北側に城山公園がある。 [交通]JR東北本線・小山駅-(徒歩/約15分)-城山公園 |
||
 |
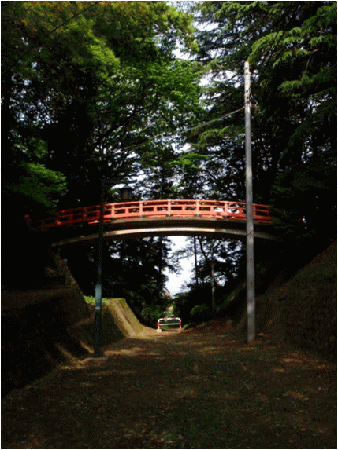 |
 |
| 空堀跡 | 深い堀に架かる祇園橋 | 祇園橋 |
 |
 |
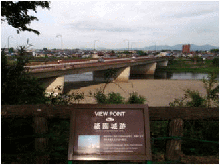 |
| 曲輪を囲む土塁跡 | 銀杏の古木 | 小山城からの思川眺望 |
| 藤原秀郷の後裔を称した武蔵国・太田郷の太田政光が、下野国小山に移り小山氏を名乗った。政光の後妻・寒河尼が頼朝の乳母となり、政光 / 嫡子・朝政
/ 三男・朝光(結城家祖)らは頼朝の挙兵に応じている。鎌倉幕府成立後は重用され、下野国守護を務めた。三男・朝光の母は、寒河尼。小山城は中久喜城や鷲城とともに、小山氏の主要な居城であった。小山郷の総鎮守・須賀神社(祇園社)を城の守り神としてため、祇園城とも呼ばれていた。 天授6年/康暦2年(1380年)〜弘和2年/永徳2年(1383年)下野国守護・小山義政が鎌倉公方・足利氏満に対して起こした反乱で、鎌倉府により追討されて嫡流は断絶する。同族の結城直光の次男・泰朝を養子として迎え再興した。 天正4年(1576年)小山秀綱が北条氏照に降伏して開城、北条氏照が北関東攻略の拠点として改修した。天正18年(1590年)北条氏滅亡後、慶長12年(1602年)本多正純が入封する。元和5年(1619年)宇都宮へ移封となり、小山城は廃城となった。 古河市三国橋の上流で渡良瀬川に合流する思川に沿って、南北に曲輪がある。本丸と二の丸との間には思川へ一直線に伸びる深い堀があり、赤い祇園橋が架けられている。二の丸に、享和3年(1803年)の書物に古木と記されている銀杏がある。 |
||
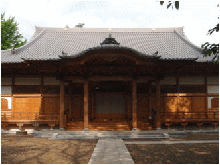 |
城山公園の北側に、久寿2年(1155年)小山政光によって創建された天翁(てんのう)院がある。城山公園の東側を通る4号線を北へ進むと、左手に山門がある。北山(小山市中久喜地内)にあったが、文明4年(1472年)現在地に移転した。小山氏の菩提寺になっている。 | |
| 天翁院 | ||
| 下野国・唐沢山城(栃本城 / 根古屋城 / 牛ヶ城) | ||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 藤原秀郷 ■築城年 延長5年(927年) ■主な遺構 石垣 / 土塁 / 堀 / 大炊の井 |
|
| 本丸石垣 | ||
 |
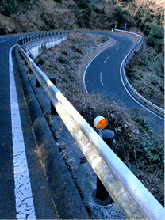 |
 |
| 秋山川 | つづら折りの坂 | つづら折りの坂からの眺望 |
|
東武佐野線・田沼駅から線路沿いに南に進み、すぐの115号線を左折して南東方向に進む。15分ほどの秋山川を渡る。5分ほどすると、115号線はつづら折りの坂になる。30分ほどのところに登山口があり、本丸跡の唐沢山(247m)山頂まで30分ほど掛かる。 |
||
 |
 |
 |
|
城門があった桝形 |
大炊の井 |
四つ目堀に架かる神橋 |
|
四つ目堀に架かる神橋は曳橋だった。四つ目堀に架かる橋はこの神橋しかなく、神橋を曳く事により唐沢山城の東西は独立した状態になった。 |
||
 |
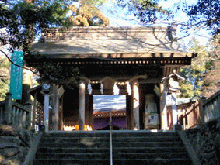 |
 |
| 本丸石垣 | 唐沢山神社神門 | 唐沢山神社拝殿 |
|
||
| 下野国・佐野城(春日岡城・春日城・姥城うばがじょう) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 佐野信吉 ■築城年 慶長7年(1602年) ■主な遺構 曲輪 / 堀切 / 土塁 城門が惣宗寺(佐野厄除大師)山門としてとして移築され現存する。 |
|
| 史跡 佐野城址 石柱 | ||
| JR両毛線 / 東武鉄道佐野線・佐野駅改札口を出て右折してコンコースを北へ進むと、城山公園に行ける。 [交通]JR両毛線/東武鉄道佐野線・佐野駅北口からすぐ城山公園 |
||
 |
 |
 |
| 本丸跡 | 埋め戻された石畳と石垣 | 惣宗寺(佐野厄除大師)山門 |
| 佐野氏は延長5年(927年)藤原秀郷によって築城されたと云われる唐沢山城を居城としていたが、江戸20里四方の山城法度による禁令により廃城となる。惣宗寺(佐野厄除大師)を移転させ、慶長7年(1602年)佐野信吉によって築城される。慶長19年(1614年)佐野信吉は改易となり、廃城となる。本丸虎口の石垣と石畳が発掘されるが、保存のため埋め戻されている。 |
||
| 下野国・川連城 | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 川連仲利 ■築城年 |
|
| 川連天満宮 | ||
| JR両毛線 / 東武日光線・栃木駅北口から北へ進む。すぐの境町交差点を左折して31号線を西に進む。すぐ右手に「蔵の遊歩道」標識がある交差点を左折して、日光例幣使街道を南へ進む。栃木翔南高校入口交差点を右折、川連交差点を越えた左手に天正年間(1573年〜1592年)創建の川連天満宮がある。 [交通]JR両毛線 / 東武日光線・栃木駅-(徒歩/約5分)-蔵の遊歩道標識-(徒歩/約15分)-栃木翔南高校入口交差点-(徒歩/約5分)-川連交差点 |
||
| この辺りは広大な城域の川連城南端となる。 |
||