| 最新の追加 | ||
| 上野国・七日市陣屋 |
||
 |
■城の種別 陣屋 ■築城者 前田利孝 ■築城年 元和2年(1616年) 土塁 / 黒門 / 陣屋御殿の玄関と書院 大手門が民家に移築され現存する。 |
|
| 陣屋御殿の玄関と書院 | ||
| 加賀藩・前田利家の五男・前田利孝は慶長19年(1614年)〜慶長20年(1615年)大坂の陣の功により、元和2年(1616年)上野国甘楽郡内に1万石を領して七日市藩を立藩して陣屋を築いた。以降、七日市藩は明治まで続いた。 七日市陣屋は、上信電鉄線の北側から富岡高校の辺りまであった。254号線が陣屋跡を分断する様に東西に通っている。 [交通]上信電鉄・上州七日市駅-(徒歩5分)-富岡高校 |
||
 |
上州七日市駅から南に進む。すぐ左手に旧七日市藩家老・保阪家の表門だった長屋門がある。 |
|
| 長屋門 | ||
 |
さらに南に進む。すぐの交差点を右折して254号線を南西に進むと、すぐ右手に富岡高校正門がある。 |
|
| 城壁風の白壁 / 黒門 | ||
 |
加賀前田家の江戸屋敷の赤門(現;東大赤門)に対して、黒門と呼んだと云われている。 |
|
| 黒門 | ||
 |
 |
 |
| 陣屋御殿 / 庭園 | 陣屋御殿 | 庭園 |
| 黒門を潜ると、池のある庭園 / 左手に天保14年(1843年)に再建された陣屋御殿の玄関と書院(登録有形文化財)がある。昭和初期に、東向きの建物を北向きに改めている。 |
||
 |
 |
富岡高校の東北に土塁が残り、隅に御殿山櫓台がある。東西に伸びていた土塁 / 櫓台跡 は254号線によって削られてしまっている。 |
| 土塁 | 櫓台跡 | |
| 上野国・名胡桃なぐるみ城 | ||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 沼田氏 ■築城年 明応元年(1492年) 土塁 / 曲輪 |
|
| 名胡桃城址碑 | ||
| 往路は上越線・後閑駅よりタクシーを利用する予定であったが、タクシー乗り場には1台も待機していない。同好の方が2名おり、タクシー会社に電話し続けていた。タクシーが到着したのは1時間余り経った頃で、相乗りさせていただく。所要時間は10分ほどである。 [交通]上越線・後閑駅-(徒歩45分)-名胡桃城 |
||
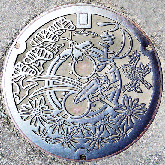 |
 |
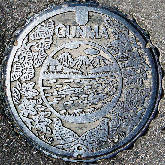 |
| 月夜野町マンホール | 群馬県カラーマンホール | 群馬県マンホール |
| 旧街道を彷彿される道にあるマンホールは、月夜野(つきよの)町と群馬県が混在していた。月夜野町は平成17年(2005年)水上町 / 新治村 と合併、みなかみ町になっている。 | ||
 |
新聞店の角を右折せず直進、5分ほどのところを左折して利根川を渡る。273号線を10分ほど登ると、左手に月夜野郵便局がある。この道は旧三国街道・塚原宿の北側に通じている。風景印は、大峰山
/ 千日堂 / 奈女沢温泉 の図柄になっている。 |
|
| 月夜野郵便局風景印 | ||
 |
 |
|
| 三郭堀切 | ||
 |
||
| 二郭 | 三郭 | |
 |
 |
 |
| 名胡桃城址碑 | 本郭 | ささ郭眺望 |
|
|
||
| 上野国・沼田城(倉内城) | ||
 |
■城の種別 丘城 ■築城者 沼田顕泰 ■築城年 天文元年(1532年) ■主な遺構 石垣・堀 ■主な再建造物 鐘楼
|
|
| 鐘楼 | ||
| 上越線・沼田駅から東へ進む。上り坂を道なりに進み、左手にある階段を登る。突き当たりを左折して北へ進むと、沼田公園がある。北関東の要衝として上杉
/ 武田 / 北条の争奪戦が繰り広げられた。武田氏の滅亡後は真田信幸の支配となる。天和元年(1681年)廃城となり破却されるが、真田信幸によって改修された本丸西櫓台の石垣が発掘される。 [交通]JR上越線・沼田駅-(徒歩/約30分)-沼田公園 |
||
| 上野国・新田金山城(金山城 / 太田金山城) | ||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 岩松家純 ■築城年 文明元年(1469年) 石垣 / 土塁 / 堀 / 曲輪 / 井戸 |
|
| 御台所曲輪 / 日の池 | ||
| 東武伊勢崎線・太田駅の北に位置する新田金山に築かれた城。戦国時代の関東の山城では、珍しく多くの石垣が使用されている。上杉謙信や武田勝頼の攻撃を退けるなど、関東七名城の一つとされる。往路は東武伊勢崎線・太田駅から山上駐車場までタクシーを利用、2020年8月4日訪問時は1860円掛かっている。帰路は本丸跡にある新田神社から御台所曲輪を経て車道を下る。金山城址線から321号線を経由して、東武伊勢崎線・太田駅まで約90分掛かっている。つづら折りの金山城址線を短絡する登山道があるが、同時に降りた方と時間は変わらなかった。 |
||
| 文明元年(1469年)新田一族・岩松家純によって築城される。享禄元年(1528年)岩松守純のとき、家老であった横瀬成繁に奪われる。横瀬成繁は武蔵七党・猪股党の一族で、のちに由良氏を称するようになった。由良国繁と2代続き、天正12年(1584年)小田原北条氏の支配下になる。天正13年(1585年)高山定重と宇津木氏久が新田金山城の守将となる。天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原征伐の際攻撃を受けて落城、廃城となった。 | ||
 |
 |
 |
| 馬橋下通路 | 物見台 | 馬場曲輪 |
 |
 |
 |
| 月の池 | 大手虎口 | 日の池 |
 |
 |
 |
| 二の丸石垣 | 新田神社石段 | 新田神社 |
| 山上駐車場から本丸跡まで、通路 / 案内板 が整備されている。本丸跡に、新田神社 / 御嶽神社 / 梅若稲荷神社 がある。新田神社の石段は登りづらいが、右手にスロープが設けられている。 | ||
| 上野国・伊勢崎城 | ||
 |
■城の種別 平城→陣屋 ■築城者 那波宗俊 ■築城年 室町時代(1500年代中頃) 陣屋門が同聚院総門として移築され現存する。 |
|
| 伊勢崎陣屋跡 | ||
| 両毛線 / 東武伊勢崎線・伊勢崎駅より、75号線を南に進む。10分ほどの信用金庫前交差点を右折して西に進む。5分ほどすると、広瀬川に架かる栄橋の手前右手に、伊勢崎城址に伊勢崎市図書館がある。 [ |
||
| 山内上杉家の家臣・那波宗俊が築城したと云われている。築城当初は赤石城と呼ばれていた。那波宗俊は、後に小田原北条氏に寝返る。永禄3年(1560年)上杉謙信に攻撃され、落城する。所領は横瀬成繁に与えられ、伊勢崎城に改称された。横瀬成繁は武蔵七党・猪股党の一族で、横瀬氏を改めて由良を称するようになった。関ケ原の戦いの功により、慶長6年(1601年)稲垣長茂が伊勢崎藩1万石で入封して城跡に陣屋を構えた。元和2年(1616年)稲垣重綱のとき移封となり、酒井忠世が入封する。元和3年(1617年)本家・前橋藩を継いだため廃藩となり、陣屋も破却された。天和元年(1681年)酒井忠寛によって2万石で再立藩、新たに陣屋を構えた。現在城址には伊勢崎市図書館がある。 |
||
 |
伊勢崎市図書館から北に進み伊勢崎駅に進むと、曲輪町に平治元年(1159年)創建の同聚院がある。総門は、稲垣氏時代の陣屋門を移築したもの。 | |
| 陣屋門 | ||
| 上野国・箕輪(みのわ)城 | ||
 |
■城の種別 平山城城 ■築城者 長野業尚 ■築城年 永正9年(1512年) ■主な遺構 石垣 / 土塁 / 空堀 |
|
| 本丸跡 | ||
| 箕郷(みわ)本町バス停から西へ、西明屋交差点を右折して北へ進む。道なりに進むと、右手に箕輪城大手虎韜門口がある。城の西に榛名白川 / 南には榛名沼があり、天然の堀を形成していた。甲斐の武田氏、越後の上杉氏が侵攻を繰り返す場であった。永禄9年(1566年)武田氏により落城。武田氏の上野経営の拠点と位置づけられる。天正10年(1582年)武田氏は滅亡、北条氏政の弟・氏邦が侵攻する。北条氏と織田氏による攻防が行われるが、本能寺の変後は北条氏の支配となる。天正18年(1590年)小田原征伐後は徳川家康が関東に移封、箕輪城は井伊直政に与えられる。慶長3年(1598年)高崎城に移封、箕輪城は廃城となる。 [交通]JR高崎駅-(群馬バス / 箕輪行き / 30分)- 箕郷本町バス停-(徒歩/約15分)-箕輪城大手虎韜門口-(徒歩/約15分)- 箕輪城本丸跡 |
||
 |
 |
|
| 城址碑 | 三の丸付近の石垣 | |
| 上野国・高崎城(和田城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 和田義信 ■築城年 正長元年(1426年) ■主な遺構 乾櫓・東門・土塁・堀 |
|
| 乾櫓 | ||
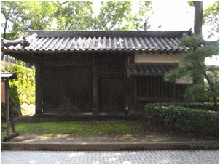 |
高崎駅西口から29号線を西へ、高崎市役所方向に進む。右手にある新町諏訪神社を過ぎ、堀沿いに右折して進む。左手に乾櫓や移築された東門がある。正長元年(1426年)和田義信が和田山城を築城する。天正18年(1590年)小田原合戦のとき落城、和田氏は滅亡する。慶長2年(1597年)井伊直政は和田城跡に築城する。碓井川と烏川の合流点の台地にあり、三の丸外郭の土塁と堀が残る。 [交通]JR・高崎駅-(徒歩/約15分)-高崎城乾櫓 |
|
| 東門 | ||
| 上野国・前橋城(厩橋城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 長野方業 ■築城年 延徳年間(1489年〜1492年) ■主な遺構 石垣・堀 市内総社町に、城門が移築され現存する。 |
|
| 本丸土塁 | ||
| 前橋駅から北へ、109号線を左折して西へ進む。利根橋手前を右折して、利根川沿いに北へ進む。群馬県庁を囲む様に、土塁が残る。利根川の氾濫による浸食により、江戸時代中期には放棄される。文久3年(1863年)松平直克によって再築城を開始される。城址には再築前橋城の案内板がある。 [交通]JR前橋駅-(徒歩/約30分)-群馬県庁 |
||
| 上野国・館林城(尾曳城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 赤井照光 ■築城年 享禄3年(1530年) ■主な遺構 土塁 / 曲輪 ■主な再建造物 土橋門 / 土塀 |
|
| 館林城三の丸 / 土橋門 | ||
 |
館林駅から370号線を東へ進む。市役所前交差点の手前右手に竹生島神社がある。慶長2年(1597年)古くから信仰されていた弁才天を、鶴生田川北岸の大通り付近に建立した。後に城沼続きの池水に囲まれた現在地に移転、浮島弁天と称した。 [交通]東武伊勢崎線・館林駅-(徒歩15分)-館林城土橋門 |
|
| 竹生島神社 | ||
 |
 |
 |
| 土塀 | 土橋門 | 井戸 |
| 城沼を城の東側の外堀とし、沼に突き出す低台地に築城された。城の建物は明治7年(1874年)にほとんど焼失した。昭和58年(1983年)土橋門が復元された。防御用に黒色の鉄板が打ち付けられている。 |
||
| 赤井照光が築城したと云われているが、築城時期 / 築城者 には諸説ある。 |
||