| 陸奥国Ⅱ 宮城県 福島県 最新の追加 | ||
| 陸奥国・湯野陣屋 | ||
 |
■城の種別 陣屋 ■築城者 三河国刈谷藩 ■築城年 寛政4年(1792年) |
|
| 西根神社 | ||
 |
 |
福島交通・飯坂温泉駅北側の交差点を右折して、摺上川に架かる十綱橋を渡る。大正4年(1915年)に竣工した全長51.7mのブレーストリブアーチ橋で、現存する大正期の鋼アーチ橋で最も古いものである。 十綱橋から北方向に、波来湯(はこゆ)が見える。 |
| 十綱橋 | 波来湯 | |
| [寄り道]波来湯 | ||
 |
 |
 |
| 波来湯 | 対岸からの波来湯公園 | 波来湯分湯槽 |
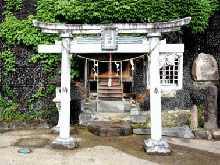 |
平安時代から続く波来湯、湯口の出口温度49.8℃ / 熱い湯44度 / 温い湯42度 |
|
| 波来薬師 | ||
 |
 |
十綱橋を渡ってすぐの交差点を右折して399号線を南に進む。すぐに進路は緩やかに東に変わり、10分ほどの左手に西根神社がある。 |
| 西根神社神門 | 西根神社社殿 | |
|
寛政4年(1792年)~明治維新まで、伊達郡の内11村は三河国刈谷藩の飛び地で湯野陣屋が置かれた。湯野陣屋が支配した領地は1万1700石もあり、刈谷藩領の半分強を占めていた。刈谷藩から遠隔地で財政難もあり、役人は10人程度だった。 |
||
 |
境内に、寛政4年(1792年)湯野陣屋が置かれる前の江戸時代に創建された髙畑天満宮がある。知らず知らずについた嘘を、天神で誠に換えられて罪が許される“うそかえ祭”が行われている。 |
|
| 髙畑天満宮社殿 | ||
| [寄り道]鯖湖湯 / 旧堀切邸 | ||
 |
 |
 |
| 芭蕉と曽良 入浴の地 | 鯖湖碑 | お湯かけ薬師 |
 |
 |
|
| 木造の湯樽塔 | 鯖湖湯 | |
| 福島交通・飯坂温泉駅北側の交差点を左折して、湯沢通りを北西に進む。10分ほどの左手に、「芭蕉と曽良 入浴の地」石柱 / 芭蕉と曽良の案内板 /
鯖湖の碑 / お湯かけ薬師 / 鯖湖湯 と続く。 芭蕉と曽良の案内板には、入浴してから宿を探したことが記されている。見つかった宿は、土間に筵を敷いただけの薄汚い貧乏家だった。灯火はなく、囲炉裏のそばに寝床を取って寝た。夜になって雷雨がひどく、寝ているところに雨が漏れてくる。蚤や蚊にくわれて眠られなかった記載がある。 鯖湖湯は、飯坂温泉発祥の湯とされる。日本最古の木造共同浴場であったが、平成5年(1993年)に改築された。芭蕉が訪れた頃の温泉宿の風呂は、共同浴場だった。 現在でも飯坂温泉には、共同浴場が9ヶ所ある。入浴料金は、波来湯のみ大人300円 / 波来湯以外大人200円 (2023年5月現在)である。正岡子規 / 与謝野晶子 / ヘレン・ケラー も利用している。 |
||
 |
鯖湖湯中心に、中央に鯖湖湯 / 飯坂温泉発祥の地の文字 / 外周に福島果物(リンゴ・モモ・サクランボ・梨)の図柄のマンホールがある。 |
|
| 飯坂町マンホール | ||
 |
 |
 |
| 表門 | 主屋 | 十間蔵 |
 |
鯖湖湯の北方向に、江戸時代の豪農・豪商だった旧堀切邸の下蔵が見える。敷地面積は約1230坪で、明治13年(1880年)の火災以前は現在の約2倍の敷地面積であった。 |
|
| 裏門側の塀 | ||
| 陸奥国・飯坂城(古館 / 湯山城) |
||
 |
■城の種別 丘城(居館) ■築城者 伊達為家 ■築城年 文治5年(1189年) |
|
| 古館公園 | ||
 |
福島交通・飯坂温泉駅北側の交差点をを左折して、湯沢通りを北西に進む。すぐ左手に「城跡古館入口」標識があり、左折して石段を登る。すぐ左手に古館公園(飯坂城跡)が見えてくる。 |
|
| 石段 | ||
| 文治5年(1189年)鎌倉政権と奥州藤原氏との間で行われた奥州合戦後、常陸入道念西は源頼朝から伊達郡の地を賜り伊達氏と改姓した。この常陸入道念西が、伊達氏の祖である伊達朝宗である。 |
||
|
飯坂温泉は古くから温泉地として知られ、平安時代末期には飯坂が「湯の庄」として認知されていた。 |
||
| 陸奥国・大鳥城 | ||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 佐藤基治 ■築城年 保元2年(1157年) |
|
| 大手門跡からの舘山 | ||
 |
古館公園(飯坂城跡)から西に進む。5分余りの右手に飯坂郵便局がある。風景印は、吾妻小富士 / 摺上川に掛かる十綱橋 / 両岸の温泉街 の図柄になっている。 |
|
| 飯坂郵便局風景印 | ||
| [寄り道]飯坂八幡神社 | ||
 |
 |
飯坂郵便局手前の十字路を右折して北に進むと、すぐの突き当りに飯坂八幡神社がある。天喜4年(1056年)後三年の役で奥州に出陣した源義家が必勝祈願のために勧請したと云われている。 |
| 飯坂八幡神社鳥居 | 飯坂八幡神社社殿 | |
|
毎年10月の八幡神社例大祭は“飯坂けんか祭り”と呼ばれ、“日本三大けんか祭り”とされる。6台の太鼓屋台が激しくぶつかり合いながら、神輿の宮入りを阻む。 |
||
 |
飯坂郵便局から西に進む。5分ほどすると、道は大きく北に曲がる。ここに舘ノ山公園の標識があり、左折して南西方向に進む。坂を登ると、大手門跡がある。 [交通]福島交通・飯坂温泉駅-(徒歩20分)-大鳥城大手門跡 |
|
| 大手門跡の案内板 | ||
|
保元2年(1157年)藤原秀衡の家臣・佐藤基治が築城したと云われている。文治5年(1189年)佐藤基治は源頼朝軍を石那坂に迎え撃ったが敗れて捕らわれたが、後に赦されたと云われている。佐藤基治は、源義経に仕えた佐藤継信
/ 佐藤忠信兄弟の父である。娘・浪の戸は、源義経の側室だったと云われている。 |
||
 |
標高230mの舘山に築城された大規模な山城で、現在は舘ノ山公園となっている。大手門跡から、三ノ砦と一ノ砦を経て本丸に続く道がある。大手門跡から鬱蒼とした木立の道を登るが、「熊に注意」の真新しい看板がある。誰とも会わない静寂に怯え、びびって引き返す。 |
|
| 陸奥国・仙台城(青葉城 / 五城楼) |
||
 |
■城の種別 |
|
| 脇櫓(大手門隅櫓) |
||
 |
JR仙台駅より青葉通りを西へ進む。広瀬川を大橋で渡り坂を登ると、左手に脇櫓(大手門隅櫓)が見えて来る。 |
|
| 広瀬川 | ||
| 文治5年(1189年)国分胤通が、千体城を築いたのが始まり。 仙台開府400年に際して始まった仙台城石垣解体復旧工事で、現在の本丸石垣の内側に千代城期の土塁 / 虎口 が発見された。現在は埋め戻されている。 |
||
 |
 |
慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いの後に伊達政宗は千代城跡に新たに築城、仙台城に改称した。慶長7年(1602年)岩出山城から仙台城に移る。 |
| 仙台城跡石柱(三の丸) | 伊達政宗騎馬像 | |
 |
 |
 |
| 脇櫓(大手門隅櫓) |
大手門石垣 | 塀 / 石垣 |
| 築城から奥羽越列藩同盟盟主として戊辰戦争迄、攻防戦がなかった城である。 寅の門が宮城県知事公館の門として移築され現存するが、楼門であった部材を転用したものである。 昭和39年(1964年)脇櫓(大手門隅櫓)が復元された。道路を挟んで大手門石垣があり、間にあった往時の大手門の大きさを偲ばされる。 |
||
 |
 |
三の丸の北面から大手門隅櫓の前に、長沼 / 五色沼 と呼ばれる二つの堀が残る。五色沼は“日本フィギュアスケート発祥の地”とされる。 |
| 長沼 | 五色沼 | |
| 陸奥国・涌谷わくや城(涌谷要害) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 涌谷氏 ■築城年 南北朝時代(1336年~1392年) ■主な遺構 隅櫓(太鼓堂) / 詰之門石垣 ■主な再建造物 模擬天守(資料館) |
|
| 模擬天守 / 隅櫓 | ||
 |
JR石巻線・涌谷駅から155号線を北西に進む。5分足らずの交差点を右折して173号線を南に進むと、すぐ左手に涌谷郵便局がある。風景印は、 [交通]JR石巻線・涌谷駅-(徒歩約15分)-城山公園 |
|
| 涌谷郵便局風景印 | ||
 |
南北朝時代(1336年~1392年)に奥州探題だった大崎氏の城の1つであった。永享3年(1431年)頃、大崎氏の支族である涌谷氏の居城となったと云われている。江合川(北上川水系)東岸の標高約20mにあり、大崎氏と葛西氏の境界付近に位置している。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐に参陣しなかったことから、大崎氏は改易となる。 |
|
| 交差点から城山公園の土塀 | ||
 |
天正18年(1590年)~天正19年(1591年)葛西大崎一揆の後は伊達政宗の所領となる。天正19年(1591年)伊達政宗は亘理城主・亘理重宗を遠田郡に転封、当初は百々城を居城としたが翌年に涌谷城へ移った。亘理氏は19代・伊達定宗のとき伊達姓を許され、涌谷伊達氏と称した。 |
|
| 隅櫓(太鼓堂) / 詰之門石垣 | ||
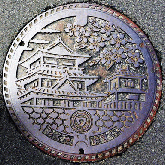 |
涌谷町マンホールは、模擬天守 / 隅櫓 / 桜 |
|
| 涌谷町マンホール | ||
| 陸奥国・岩出山城(岩手沢城 / 岩出山要害) | ||
 |
■城の種別 |
|
| 本丸跡 | ||
 |
JR岩出山駅から164号線を西へ道なりに進むと、城山公園がある。 [交通]JR陸羽東線・岩出山駅-(徒歩15分)-城山公園 |
|
| 城下の町並み | ||
| 応永年間(1394年~1428年)奥州探題であった大崎氏の家臣・氏家直益が築城した。 岩出山城跡は、城山公園 / 有備館 / 宮城県立岩出山高等学校 / 大崎市立岩出山小学校 となっている。 |
||
 |
 |
西の腰曲輪跡に伊達政宗像がある。仙台城跡に置かれていたもの。仙台城跡の銅像は第2次世界大戦における金属類回収令で失われ、コンクリート造りになっていた。昭和37年(1962年)に移設された。 |
| 西の腰曲輪 / 伊達政宗像 | 伊達政宗像 | |
 |
東の腰廓跡と本丸跡の中間にあるSL広場に、C58 114が保存されている。 |
|
 |
 |
|
| 有備館(ゆうびかん)は、元禄4年(1691年)頃に岩出山伊達氏3代・伊達敏親により城内の隠居所・下屋敷の敷地内に開設された仙台藩の学問所(春学館)。元禄4年(1691年)城の北麓にあたる現在地に移転、有備館と改称される。 |
||
 |
 |
有備館の南東側に阿部東庵記念館がある。長崎で蘭学、京都で茶道 / 歌道 / 医学 を学んだ。 |
 |
JR陸羽東線・有備館駅前の伊達政宗騎馬像はJR東北本線・仙台駅構内にあったもので、平成20年(2008年)に移された。 |
|
 |
D51 498牽引の“湯けむり号”。 |
|
| 陸奥国・多賀城(多賀柵 / 多賀国府) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 大野東人 ■築城年 神亀元年(724年) ■主な遺構 多賀城碑(重文) |
|
| 多賀城碑 | ||
 |
 |
 |
| 多賀城政庁跡への階段 | 多賀城政庁跡 | 多賀城南門跡 |
| JR東北本線・国府多賀城の北西方向にあり、駅前から道標に従って進む。神亀元年(724年)に築かれたと云われる多賀城には、陸奥国(現:岩手県 /
宮城県 / 福島県)の国府が置かれていた。出羽按察使(あぜちつか)が配置され、出羽国(現:秋田県 / 山形県)も統轄していた。奈良~平安時代の東北地方における政治 / 軍事 / 文化 の中心地だったが、南北朝時代(1336年~1392年)から荒廃したと云われている。 多賀城南門跡のすぐ傍に、天平宝字6年(762年)造立と云われる壺碑(つぼのいしぶみ)と呼ばれる多賀城碑(重文)がある。壺碑は平安時代の終わり頃からの歌枕で、江戸時代初期に発見された。砂岩を加工して碑面を造り文字を彫刻しており、覆屋(おおいや)で保護されている。 元禄2年(1689年)5月8日、芭蕉は「泪(なみだ)も落つるばかり也」と変わらぬ姿に感動している。 奈良・平城宮跡や福岡・太宰府跡とともに、日本三大史跡に数えられている。 [交通]JR東北本線・国府多賀城駅-(徒歩/約15分)-多賀城碑 |
||
| 陸奥国・白石城(益岡城 / 枡岡城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 苅田経元 ■築城年 寛治5年(1091年) ■主な遺構 厩口門が延命寺に、東口門が当信寺に、どこの門か定かではない城門が名取市・耕龍寺に、移築され現存する。 ■主な再建造物 三階櫓 / 大手門 |
|
| 復興三階櫓 | ||
| JR白石駅から西へ進む。突き当たりを左折して、ジグザグに西へ進むと白石城がある。白石駅にあるパンフレットを手に、白石城下一社七箇寺めぐりをする。東北本線に並行する道を北に進む。延命寺の山門は、白石城厩口門を移築したものである。西側の道を戻ると、専念寺や奥の細道三十三観音霊場札所の妙見寺がある。さらに西側の道には慶長2年(1597年)創建と云われる当信寺がある。山門は白石城東口門を移築したもので、真田幸村の遺児・阿梅や大八の墓がある。碧水園を右折し小川沿いに進むと、慶長13年(1608年)白石城主・片倉家の菩提寺として創建された傑山(けっさん)寺が見えてくる。江戸時代の力士・初代谷風の墓もある。寛永11年(1634年)真田家遺臣が創建した清林寺の紋は、真田六文連銭である。正中2年(1325年)創建と云われる常林寺には、白石城二の丸にあった“時の太鼓”が保管されている。白石城は寛治5年(1091年)苅田経元が居館を築いたのが始まりと云われている。慶長7年(1602年)仙台城の支城として片倉小十郎景綱が城主となる。元和の一国一城令以後も存続が認められ明治維新に至る。平成7年(1995年)天守に相当する三階櫓と大手門が木造で復元される。大同2年(807年)創建と云われる神明社は、奥羽七神明の一つに数えられている。 [交通]白石駅-(徒歩/約10分)-延命寺-(徒歩/約15分)-当信寺--(徒歩/約15分)-傑山寺-(徒歩/約25分)-白石城-(徒歩/約25分)-白石駅 |
||
| 陸奥国・相馬中村城(馬陵城) | ||
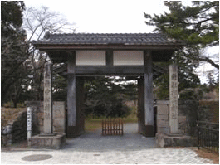 |
■城の種別 平山城 ■築城者 相馬利胤 ■築城年 慶長16年(1611年) ■主な遺構 大手門 / 石垣 / 土塁 / 堀 |
|
| 大手門 | ||
| JR相馬駅から西へ、121号線を左折して南へ進む。大町バス停のある交差点を右折すると、堀に突き当る。左手に進むと大手門がある。延暦年間(782年~806年)坂上田村麻呂が築いたのが始まりとも云われている。
本丸跡に明治13年(1880年)創建の相馬神社、妙見曲輪に寛永20年(1643年)創建の相馬中村神社がある。 [交通]JR相馬駅-(徒歩/約20分)-相馬中村城 |
||
| 陸奥国・福島城(大仏城 / 杉目城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■主な遺構 土塁 / 堀 |
|
| 福島城址碑 | ||
| JR福島駅の3号線を南へ進む。NHKの先にある交差点を左折して東へ進むと、右手に福島県庁がある。県庁が立地している一帯が城址になる。東側の紅葉山公園は、城内にあった庭園の跡である。応永20年(1413年)伊達松持宗が懸田定勝とともに鎌倉公方へ反乱を起こした際に立て籠もった大仏(だいぶつ)城が後の福島城と云われている。 [交通]JR福島駅-(徒歩/約15分)-福島城址 |
||
| 陸奥国・二本松城(霞ヶ城 / 白旗城) | ||
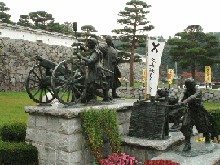 |
■城の種別 山城 ■築城者 畠山満泰 ■築城年 応永20年(1413年) ■主な遺構 茶亭・洗心亭 ■主な再建造物 箕輪門 / 附櫓 |
|
| 千人溜 | ||
| 二本松駅前を北へ進み大通りを右折すると、寛永20年(1643年)城内の八幡宮と熊野宮を合祀、遷宮した二本松神社がある。大通りに戻りすぐに左折すると、石垣が残る大手門跡がある。急坂を越えると二本松小学校が見えてくる。北西方向に霞ヶ城公園がある。二本松城は嘉吉年間(1441年~1444年)、後に二本松氏を名乗る畠山満泰が築城したことに始まる。寛永20年(1643年)織田家・丹羽長秀の孫にあたる光重が白河小峰城より入城、二本松藩の居城として明治に至る。1982年に再建された城壁・平櫓・箕輪門・二重櫓前の千人溜には、戊辰戦争に動員された二本松少年隊の群像がある。菊人形展が三の丸を中心に開催されている様で、箕輪門の先に料金所があった。菊に興味がなく料金を払って混雑した三の丸を見る気はなく、西側を迂回する。樹齢約350年の傘松の左手に丹羽神社、新城館跡には二本松少年隊顕彰碑がある。搦手門から本丸跡へ、大粒の雨が降り始める。1995年に石垣が修復された標高345mの白旗が峰にある本丸跡には何もなく淋しい。木々が色づき始めており、晴れていれば眺望が楽しめると思う。茶亭・洗心亭に寄るのを忘れている。 [交通]二本松駅-(徒歩/約5分)-二本松神社-(徒歩/約15分)-二本松城-(徒歩/約20分)-二本松城本丸 |
||
| 陸奥国・三春城(舞鶴城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 田村義顕 ■築城年 永正元年(1504年) ■主な遺構 石垣 / 土塁 藩校明徳堂の表門が、三春小学校に移築され現存する。 |
|
| 本丸跡 | ||
| JR三春駅から28号線を東へ進む。磐越東線を越えて道なりに南へ進む。道は直角に東へ進路が変わる。三春町役場を過ぎると、左手に三春城への道標がある。大志多山(標高407m)の山頂に本丸がある。三春は桜の名所や伊達政宗の正室愛姫の誕生地として知られている。 [交通]JR三春駅-(徒歩/約45分)-三春城本丸 |
||
| 陸奥国・鶴ヶ城(黒川城 / 若松城 / 会津若松城) |
||
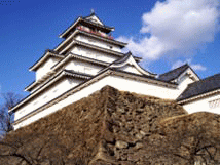 |
■城の種別 平山城 ■築城者 蘆名直盛 ■築城年 至徳元年 / 元中元年(1384年) ■主な遺構 堀 / 土塁 / 石垣 / 御三階(移築) / 大書院表玄関(移築) ■主な再建造物 天守 / 干飯(ほしい)櫓 / 南走長屋 |
|
| 復元天守 | ||
 |
 |
 |
| 若松駅前郵便局風景印 | 会津若松郵便局風景印 | 山鹿素行誕生の地 |
|
JR磐越西線・会津若松駅より東に進む。メイン通りの121号線の手前の旧道(大町通り / 118号線)を南に進む。すぐ左手に若松駅前郵便局がある。風景印は、磐梯山
/ 白虎隊 の図柄になっている。七日町通り(252号線)と交差、左折してすぐの交差点を右折して121号線を南に進む。交差点の北東側に会津若松郵便局がある。風景印は、磐梯山
/ 白虎隊 / 鶴ヶ城 の図柄になっている。15分ほどの交差点を右折すると、すぐ左手に江戸時代の兵学者・山鹿素行誕生の地がある。ここは上杉景勝の執政・直江兼続の住まいでもあったところ。121号線に戻り南に進むと、すぐ左手に堀が見えて来る。 |
||
 |
||
 |
||
| 西出丸 / 堀 | ||
 |
||
| 本丸帯郭 / 堀 | 二の丸石垣 / 廊下橋 |
|
| 至徳元年 / 元中元年(1384年)蘆名氏7代・蘆名直盛が居館を置いたのが始まりと云われている。天正17年(1589年)伊達政宗は蘆名義広を攻め滅ぼして黒川城を奪うが、天正18年(1590年)豊臣秀吉により会津を取り上げられる。 天正18年(1590年)の奥州仕置で、蒲生氏郷が黒川城に入城する。文禄元年(1592年)より近世城郭に改造して城下町を整備した。蒲生氏郷は町の名を黒川から若松へ改称、文禄2年(1593年)天守が竣工して鶴ヶ城に改められた。 |
||
 |
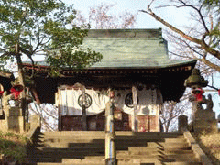 |
 |
| 本丸・二の丸 堀 | 鶴ヶ城稲荷神社 |
鐘撞堂 |
| 鶴ヶ城稲荷神社 |
||
| 鶴ヶ城は城下町の南端に位置、本丸を中心に西出丸 / 北出丸 / 二の丸 / 三の丸 が配置されていた。総石垣造りの城で、盛岡城 / 白河城 とともに東北三名城に数えられている。 明治7年(1874年)建造物はすべて解体された。本丸にあった御三階は、明治3年(1870年)会津若松市七日町の阿弥陀寺に移築され現存する。また本丸大書院の表玄関は、阿弥陀寺御三階の玄関に転用されている。 昭和40年(1965年)に外観復元された天守は、慶長16年(1611年)会津地震により倒壊した天守を組み直したもの。若松城天守閣郷土博物館になっている。 |
||
| [寄り道]飯盛山・さざえ堂 | ||
 |
市街地の東にある飯盛山は、戊辰戦争で白虎隊士19名が悲劇な最後を遂げたところ。白虎隊記念館や白虎隊士の墓がある。自刃の地からは、手前にあがった煙を落城と見誤った若松城が望める。新参道を登った左手に、寛政8年(1796年)建立と云わる円通三匝(えんつうさんそう)堂(重文/有料施設)がある。六角形三層で、らせん状に上ると同じところを通らず下って戻れる。不思議な感じがする。登り降りが別々となるため、参拝者がすれ違うことなく西国観音をお参りができる。さざえ貝の殻に似ていることから、さざえ堂と名付けられる。 | |
| さざえ堂 | ||
| 陸奥国・白河城(小峰城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 結城親朝 ■築城年 暦応3年 / 興国元年(1340年) ■主な遺構 土塁 / 石垣 / 堀 ■主な再建造物 三重櫓 / 多聞櫓 / 前御門 / 桜門 |
|
| 三重櫓 | ||
 |
 |
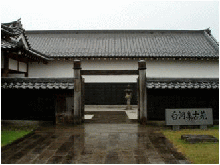 |
| 前御門 | 石垣 / 堀 | 白河集古苑 |
| JR東北本線・白河駅のホームから天守(三重櫓)が見える。南口の改札口から地下道で東北本線を潜り北側に出ると、目の前に城山公園がある。阿武隈川と谷津田川に挟まれた丘陵にある平山城で、下総結城氏の庶流にあたる結城親朝によって暦応3年
/ 興国元年(1340年)に築城されたのが始まり。天正18年 (1590年)豊臣秀吉の奥州仕置により白河結城氏が改易される。寛永4年(1627年)陸奥国棚倉藩より丹羽長重が10万石余で入封、白河城を改修して城下町を整備した。寛永20年(1643年)第2代藩主・丹羽光重のとき、陸奥国二本松藩に転封となった。以降は奥羽地方の外様大名の抑えとして、親藩・譜代大名が頻繁に入れ替わった。文政2年(1823年)武蔵国忍藩より阿部正権が10万石で入封、慶応2年(1866年)棚倉藩へと移封され白河藩領は天領となった。慶応4年(1868年)戊辰戦争で奥羽越列藩同盟軍と政府軍との激戦地となり、白河城は落城する。城下も戦火によって焼失した。平成3年(1991年)天守に相当する三重櫓が木造復元される。三重櫓入口の案内板には、一度に5名づつの人数制限が書かれている。平成6年(1994年)前御門が木造復元される。公園内には、結城家古文書館と阿部家名品館からなる白河集古苑(有料施設)がある。入り口の手前に大手門跡の礎石が移設されている。総石垣造りの城で、盛岡城や会津若松城とともに東北三名城のひとつに数えられている。 *平成23年(2011年)東日本大震災により石垣などが崩壊、三重櫓も含めた本丸は立入禁止となっている。 [交通]JR東北本線・白河駅-(徒歩/約5分)-城山公園 |
||
| 陸奥国・棚倉城(亀ケ城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 丹羽長重 ■築城年 寛永2年(1625年) ■主な遺構 土塁 / 堀 / 南門が、長久寺に移築され山門として現存する。 |
|
| 堀 | ||
| JR水郡線・磐城棚倉駅より南西へ進む。177号線を超え、次の交差点を左折して南西へ進むと左手に亀ヶ城公園がある。元和元年(1622年)常陸国・古渡より棚倉に5万石で入封した丹羽長重は、赤館に入城する。寛永2年(1625年)築城を開始する。慶応2年(1866年)阿部正静が陸奥・白河小峰城から6万石で入封する。慶応4年(1868年)奥羽列藩同盟に参加した棚倉藩は、白河小峰城で破れると帰藩した。板垣退助率いる官軍の攻撃を受け、僅か1日で落城する。堀の内外に約500本の桜や、土塁の内側にはつつじが植えられている。 [交通]JR水郡線・磐城棚倉駅-(徒歩/約10分)-亀ヶ城公園 |
||
| 陸奥国・磐城平城(龍ヶ城 / 竜城 / 飯野城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 鳥居忠政 ■築城年 慶長8年(1603年) ■主な遺構 石垣 / 堀 |
|
| 石垣 | ||
| JR常磐線・いわき駅北側の小高い丘が、磐城平城址である。北口から北東へ進む。すぐに左折して坂を登ると、左手に石垣が見えて来る。慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いの後、慶長7年(1602年)鳥居忠政が10万石で大館城に入る。鳥居忠正は、関ヶ原の戦いの前哨戦である伏見城の戦いで討死した鳥居元忠の嫡男。戦国時代までの飯野平から磐城平に改め、磐城平城を築城する。この城は、伊達氏や相馬氏を抑える役目を担っていた。慶応4年(1868年)戊辰戦争において、安藤氏(5万石)は奥羽越列藩同盟に加わる。明治政府軍攻められ、自ら城に火を放ち逃走する。建物は戊辰戦争と第2次大戦で焼滅する。城跡は民間に払い下げられ宅地化、石垣や土塁の一部が残るだけである。 [交通]JR常磐線・いわき駅-(徒歩/約5分)-磐城平城址 *いわき駅は、平成6年(1994年)に平駅より改称される。 |
||