| 武蔵国Ⅱ 東京都 神奈川県 最新の追加 | ||
| 武蔵国・練馬城(豊島城 / 矢野山城) |
||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 豊島景村 ■築城年 |
|
| 練馬城址 | ||
 |
 |
西武豊島線・豊島園駅から左手方向に進むと、大正15年(1926年)開園 / 令和2年(2020年)閉園 の豊島園跡がある。直進して石神井川を渡ると、南側は鬱蒼とした木立 / 北側は広場 になっている。 |
| 石神井川 | 練馬城址公園 広場 | |
| 練馬城は石神井川の南岸に位置する丘陵を利用して築かれた城である。この鬱蒼とした木立が練馬城の主郭の様であるが、立ち入り禁止区域になっていた。
石神井川の北側を通る道には南岸に渡れる複数の橋が架かっているが、いずれも閉鎖されていた。*2023年11月現在 |
||
| 元弘年間(1331年〜1333年)豊島景村が石神井城の支城として築城したと云われている。 文明8年(1476年)関東管領・山内上杉氏の家宰職相続をめぐり、長尾景春が武蔵鉢形城で挙兵する。文明9年(1477年)山内上杉家の拠点だった武蔵国・五十子城は落城する。 |
||
| 武蔵国・深大寺城 |
||
 |
■城の種別 平城 土塁 / 空堀 / 曲輪 |
|
| 水生植物園 / 右側:深大寺城跡 | ||
| 最寄り駅の京王電鉄・調布駅は、平成24年(2012年)に地下化された。調布駅北口バス乗り場から北に進むと、すぐに調布駅北口交差点を越える。5分ほどすると20号線(甲州街道)に突き当り、左折して北西に進む。10分足らずの下石原交差点を右折して北に進む。15分ほどすると、中央自動車道を潜る。10分足らずの深大寺入口交差点を右折して深大寺通りを東に進む。5分ほどの左手に深大寺参道
/ すぐ右手に神代植物公園の水生植物園 がある。 [交通]京王電鉄・調布駅-(徒歩40分)-神代植物公園の水生植物園 |
||
| [寄り道]神代植物公園前郵便局 |
||
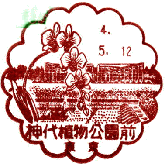 |
深大寺入口交差点を直進して北に進む。5分ほどの左手に神代植物公園前郵便局がある。 |
|
| 神代植物公園前郵便局 |
||
| [寄り道]深大寺 | ||
 |
 |
|
| 深大寺山門 | 深大寺本堂 | |
| 昭和36年(1961年)開園した東京都立神代植物公園は旧深大寺領。 | ||
 |
 |
 |
| 深大寺城跡石柱 | 主郭土塁 | 主郭 |
 |
深大寺城は深大寺の南にある段丘の南端に築かれ、現在は神代植物公園の水生植物園内にある。 |
|
| 二郭 | ||
|
築城年や築城主は解っていない。小田原北条氏が相模国に侵攻したとき、扇谷上杉氏は南武蔵の防衛ラインとしていた。 |
||
| 武蔵国・藤原秀郷館(高安寺砦) | ||
 |
■城の種別 居館→城砦 ■築城者 藤原秀郷 ■築城年 |
|
| 高安寺仁王門 | ||
| JR南武線 / 京王線・分倍河原駅より北に進むと、すぐに229号線(旧甲州街道)に突き当たる。右折して東に進むと、すぐ右手に高安寺がある。 [交通]JR南武線 / 京王線・分倍河原駅-(徒歩5分)-高安寺 |
||
| 多摩川河岸段丘にあり、東 / 西 / 南 に堀を設けた城砦になったと云われている。南側を通るJR南武線は、往時の水堀を埋めたものとされる。 |
||
 |
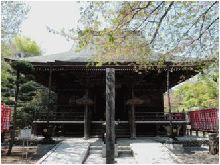 |
戦乱によって荒廃した見性寺は、暦応年間(北朝 / 1338年~1342年)足利尊氏により再興され高安(こうあん)寺と改称された。室町幕府によって武蔵国安国寺として位置付けられ、塔頭10 / 末寺75 の大寺院となった。 |
| 高安寺本堂 | 高安寺観音堂 | |
| 高安寺は鎌倉公方足利氏の影響力を強く受ける事となり、軍事拠点としての色彩を帯びる事となった。 戦国時代に入ってからも、扇谷上杉氏 / 小田原北条氏 が利用するところとなった。 本堂は享和3年(1803年) / 仁王門は明治5年(1872年) / 鐘楼は安政3年(1856年) の建立。観音堂は高安寺西の観音橋付近にあったが、享保年間(1716年~1736年)に移された。 |
||
 |
 |
 |
| 古蹟 弁慶硯の井戸 石柱 | 弁慶硯の井戸 | |
| 本堂の左手にある墓地に入ると案内板がある。突き当りの堂宇の右手に「古蹟 弁慶硯の井戸」石柱 / 坂を下ると弁慶硯の井戸 がある。平家滅亡後に鎌倉入りを許されなかった源義経が立ち寄り、武蔵坊弁慶が大般若経を書き写したと云われている。弁慶硯の井戸は、この井戸の水を汲んで墨を磨ったと云われている。 | ||
| 武蔵国・今井城 | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 今井経家 ■築城年 鎌倉時代後期 ■遺構 空堀 / 石垣 / 曲輪 |
|
| 今井城跡 |
||
| JR八高線・金子駅から北に進む。道なりに左に曲がり、すぐにJR八高線の踏切を渡る。すぐのT字路を右折して霞川を渡り、5分足らずの南峰交差点を左折して63号線(山根通り)を南西に進む。青梅今井病院の案内看板のある十字路を右折して道なりに進むと、左手に今井城跡がある。 [交通]JR八高線・金子駅-(徒歩25分)-今井城跡 |
||
|
武蔵七党・児玉党の出と云われる今井経家と子孫が数代居城した。当初は居館程度の城であったとされる。 |
||
 |
 |
今井城跡から63号線(山根通り)を西に進む。10分足らずの十字路を左折して南に進むと、正応年間(1288年~1293年)創建の今井氏菩提寺・正福寺がある。 |
| 正福寺山門 | 正福寺本堂 | |
| 武蔵国・藤橋城 | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 平山虎吉 ■遺構 土塁 / 空堀 / 曲輪 |
|
| 藤橋城址公園 | ||
| JR八高線・金子駅から北に進む。道なりに左に曲がり、すぐにJR八高線の踏切を渡る。すぐのT字路を右折して霞川を渡り、5分足らずの南峰交差点を左折して63号線(山根通り)を南西に進む。30分余りで岩蔵街道と交差、直進して細い道を進む。5分ほどの十字路を左折して南に進むと、5分ほどの右手に藤橋城址公園がある。 [交通]JR八高線・金子駅-(徒歩50分)-藤橋城址公園 |
||
 |
 |
|
| 土塁 | 北側からの城跡公園 | |
|
南から北の霞川に張り出した台地の北端に築かれている。現在は藤橋城址公園となっており、曲輪の周囲に土塁が巡っている。整備され過ぎてどこが遺構なのか分かりにくいとされる。南側は住宅地と隣接、北側には水田が広がる。 |
||
| 武蔵国・石浜城 |
||
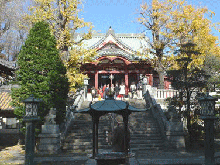 |
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 石浜氏 ■築城年 室町時代中期 |
| 侍乳山聖天 | 東京ガス / 石浜神社 | |
| 石浜城があったところは、侍乳山聖天(まっちやましょうでん)がある待乳山 / 東京ガスや石浜神社がある地 の説がある。江戸時代以降の古利根川(隅田川)の流路変更や都市化の進展によって地形が大きく変わっており、遺構は見つかっていない。 | ||
 |
東京メトロ・浅草駅の吾妻橋出口から日光街道(6号線)を北東へ進む。言問橋西交差点で日光街道と別れ、直進して314号線を進む。右手の隅田公園に、昭和31年(1956年)造立の武島羽衣作詞 / 滝廉太郎作曲「花」歌碑がある。♪春のうららの隅田川 のぼりくだりの船人が櫂のしずくも花と散る ながめをなににたとうべき♪ |
|
| 花歌碑 | ||
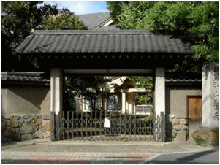 |
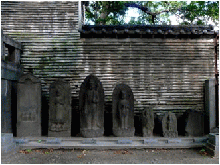 |
 |
| 山門 | 築地塀 / 石仏群 | 地蔵堂 / 歓喜地蔵 |
 |
 |
 |
| 巾着提灯 / 二股大根提灯 | 聖天宮 | 銅造宝篋印塔 |
| 花歌碑からすぐ左手に、推古天皇3年(595年)創建と云われる侍乳山聖天(まっちやましょうでん) がある。待乳山は小高い丘で、低地の浅草では見渡しの良い名所として知られていた。山谷堀を埋めるために丘が削られ、標高10mの東京都最低山になっている。閉ざされた山門左手の階段を登ると、右手の築地塀(ついじべい)前に石仏群がある。築地塀は防火壁の役目をしていた。右折して階段を登ると、左手の地蔵堂の周りに歓喜地蔵が並んでいる。頂上に、銀杏に囲まれた聖天宮がある。ご利益はお金と夫婦和合、巾着と二股大根が描かれた提灯が吊るされている。浅草名所七福神の毘沙門天になっている。聖天宮の裏手に、天明元年(1781年)造立の銅造宝篋印塔(ほうきょういんとう)がある。 | ||
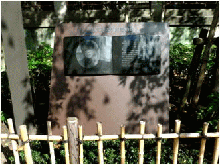 |
西側の待乳山公園に、池波正太郎生誕地碑がある。池波正太郎は、大正12年(1923年)待乳山聖天の南側辺りで生まれている。 |
|
| 池波正太郎生誕地碑 | ||
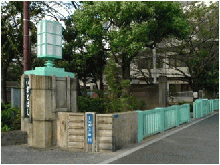 |
 |
 |
| 今戸橋跡 | 蓮窓寺 | 橋場不動 |
|
侍乳山聖天山門から北へ進む。すぐの山谷堀跡に今戸橋跡がある。今戸橋は山谷堀が隅田川に合流する手前に架かっていた橋。 |
||
 |
すぐの白鬚橋西詰交差点の北西側、白鬚橋の袂に「橋場の渡し」案内板がある。文禄3年(1594年)千住大橋が完成して主だった街道筋が変更されるまでは、隅田川を渡る主要ルートであった。大正3年(1914年)白鬚木橋が架けられまで、利用された。 |
|
| 白鬚橋 | ||
 |
 |
 |
| 石浜神社鳥居 | 石浜神社社殿 | 境内社 / 富士塚 |
| 白鬚橋西詰交差点を直進して北へ進むと、すぐ左手に東京ガスのタンク / 神亀元年(724年)創建と云われる石浜神社 / 境内に富士塚 がある。源頼朝が藤原泰衡討伐の折に当社に祈願、大勝したことから社殿を造営したと云われている。浅草七福神の寿老神になっている。 |
||
|
石浜城は秩父氏の支流・武蔵江戸氏の一族である石浜氏が室町時代中期に築城したと云われている。 |
||
| 石浜神社から北に5分ほどの辺りが、古代の渡しがあったところ。宝亀2年(771年)~平安時代中期の古代東海道は、ここから西へ武蔵国国府へ通じていたが痕跡は残っていない。渡しで古利根川(隅田川)を越えると、古代東海道は江戸川まで往時の道が続く。江戸川を越え、下総国~上総国~浦賀水道~横須賀市走水の経路で京に通じていた。 |
||
| 武蔵国・勝沼城(師岡城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 三田氏 ■遺構 空堀 / 土塁 / 曲輪 |
|
| 勝沼城址 | ||
 |
東青梅駅から北に進む。すぐに63号線(旧青梅街道)に突き当り左折、すぐの東青梅駅北口交差点を右折して東に進む。すぐの交差点を左折して、市役所六万通りを北に進む。5分足らずで194号線に突き当ると、嘉元年間(1303年~1305年)創建されたと云われる光明寺
/ 山肌に墓地 / 上段の曲輪に柵 が見える。 [交通]東青梅駅-(徒歩約10分)-光明寺前交差点 |
|
| 光明寺墓地 / 勝沼城址 | ||
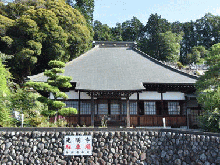 |
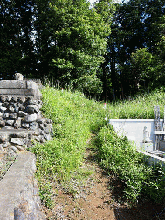 |
 |
| 光明寺本堂 | 光明寺墓地からの土道 | 左方向の道は下り坂 |
 |
 |
勝沼城は加治丘陵端の尾根上にある。光明寺本堂からも右方向に進み、墓地の階段を登る。最後の石段前の踊り場から右方向に進むと、左手に草に覆われた土道がある。土道を進むと、T字路がある。左方向の道は下り坂になっている。右方向に進むと鉄塔がある。鉄塔から右方向に進むと、光明寺前交差点から見えた曲輪に至る。 |
| 鉄塔 | 曲輪 | |
 |
 |
|
| 広い曲輪 | 勝沼城跡案内板 | |
 |
光明寺西側の道を北に進むと、すぐ右手に師岡神社がある。光明寺創建のとき、寺門守護として嘉元年間(1303年~1305年)熊野三社大権現を創建、明治2年(1869年)師岡神社と改称した。 |
|
| 師岡神社 | ||
 |
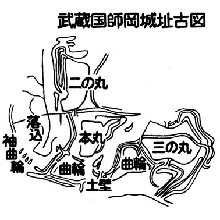 |
師岡神社からさらに北に進むと右手に墓地があり、ここから先は両側がフェンスに囲われた山道になる。194号線から5分足らずの左手に曲輪 / 左手に城山配水場 / 右手に勝沼城跡歴史環境保全地域案内板 がある。勝沼城は本丸を中心に、尾根方面に三の丸 / 丘陵端方面に二の丸 があった。取り囲む様に横堀が全周に設けられていた。 |
| 曲輪 | 武蔵国師岡城址古図(抜粋) | |
 |
勝沼城跡歴史環境保全地域案内板のところから、東方向に進むことができる。部分的に広い場所もあるが、すぐに急な下り坂になる。何処に出られるか心もとなく、引き返す。城山配水場の鉄塔と光明寺側の鉄塔の位置から、広い曲輪に続いている様である。 | |
| 東方向に進む道 | ||
 |
更に北に進むと、すぐ右手のフェンスに切れ目がある。すぐに急な下り坂になる。ここも何処に出られるか心もとなく、引き返す。勝沼城跡歴史環境保全地域案内板の地図では、道が途切れている。 | |
| フェンスの切れ目 | ||
 |
 |
 |
| 分岐(左手に長寿園石標) | 長寿園石標 | 曲輪 |
| 城山配水場の北側に登り坂があり、道なりに進む。すぐに分岐があり、左方向は下り坂で道端に長寿園石標がある。 |
||
 |
直進して坂を下ると、城山配水場 / 勝沼城跡歴史環境保全地域案内板 から続く道と合流する。 |
|
| 曲輪 | ||
文明14年(1482年)以降、山内上杉氏と扇谷上杉氏が対立する様になった。 |
||
 |
光明寺前交差点から194号線を東に進む。すぐの東青梅六丁目交差点の先を左折して北に進むと、勝沼城主・師岡将景の姉・妙光尼が天正2年(1574年)に創建した妙光院がある。 |
|
| 妙光院 | ||
 |
 |
 |
| 勝沼公会堂 | 乗願寺 |
乗願寺 |
| 東青梅駅北口交差点まで戻り、63号線(旧青梅街道)を北西に進む。 |
||
 |
 |
乗願寺から |
| 勝沼神社 | 勝沼神社 | |
| 創建時は現在地より東南約500mの地にあり、神明皇大神宮と称した。安永3年(1774年)現在地に移転、明治元年(1868年)勝沼神社と改称した。 |
||
 |
十字路まで戻り、直進してJR青梅線を越える。すぐに28号線に突き当り左折して北東に進むと、すぐ右手に青梅勝沼郵便局がある。 |
|
| 青梅勝沼郵便局 |
||
 |
青梅勝沼郵便局から28号線を南西に進む。レトロな町並みを10分ほど進むと、左手に昭和レトロ商品博物館がある。すぐ左手に青梅住江町郵便局がある。風景印は、昭和レトロ商品博物館
/ 街灯 / 丸型ポスト の図柄になっている。 |
|
| 青梅住江町郵便局風景印 | ||
|
|
||
| 武蔵国・茅ヶ崎城 |
||
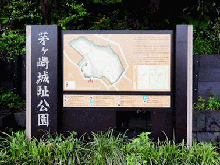 |
■城の種別 丘城 ■築城者 扇谷上杉氏 ■築城年 室町時代 ■遺構 空堀 / 土塁 / 曲輪 |
|
| 茅ヶ崎城址公園入口 | ||
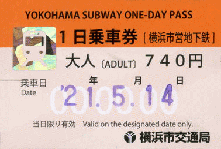 |
茅ヶ崎城と蒔田城を巡るため、横浜市営地下鉄1日乗車券を利用する。紙券は2021年5月31日で販売終了となり、以降はPASMOに書き込む地下鉄IC乗車券のみとなる。 |
|
| 横浜市営地下鉄1日乗車券 | ||
 |
横浜市営地下鉄・センター南駅から東に進む。すぐに歴博通りと交差、直進する。すぐの突き当りに標識があり左折して道なりに進む。すぐの左手に寿福寺観音堂があるT字路を右方向に進むと、すぐ右手に茅ヶ崎城址公園入口がある。寿福寺観音堂は蒔田城と関わりのある寺院と云われている。 |
|
| 寿福寺観音堂 | ||
| 茅ヶ崎城は早渕川南岸の東西に伸びた台地に築城された。東に1kmほどのところを、古くから武蔵国と相模国を結ぶ旧中原街道が通る。古代の東海道は、相模国の三浦半島から海路で上総国に渡っていた。小田原北条氏の時代に整備され、慶長9年(1604年)徳川幕府によって整備された以降に中原街道と呼ばれる様になった。 室町時代に扇谷上杉氏によって築城されたと云われている。文明10年(1478年)小机城の支城として、太田道灌により落城している。大永元年(1521年)頃に小田原北条氏により改修されたと云われている。天正18年(1590年)小田原征伐後に廃城となった。 |
||
 |
 |
 |
| 北郭 | 中郭の土塁 | 中郭 |
| 周辺は宅地になっているが、比較的よく遺構が残っている。立ち入れない小堀切 / 郭 がある。 茅ヶ崎城址公園入口から階段を登ると、「←北郭・中郭 / →西郭」標識があり左に進むと北郭がある。北郭から坂を登ると土塁が廻る中郭がある。 |
||
 |
 |
 |
| 根小屋 | 空堀から東郭へ | 東郭 |
| 中郭から根小屋を経て東郭に進む。往時は主郭との空堀に土橋があった。 | ||
 |
 |
東郭から回り込み西郭、さらに虎口を通り北郭に戻る。 |
| 西郭 | 虎口 | |
| 武蔵国・ |
||
 |
■城の種別 城砦集落 ■築城年 弥生時代(紀元前3世紀頃~3世紀頃)中期 ■主な再建造物 環濠 / 柵 / 竪穴住居 / 墳丘墓など |
|
| 大塚遺跡柵 | ||
|
横浜市営地下鉄・センター南駅から東に進む。すぐに歴博通りと交差、直進する。左折折して北に進む。 |
||
 |
 |
 |
| 大塚遺跡 | 歳勝土遺跡 | |
| 大塚遺跡は高台に造られた弥生時代中期の環濠集落。弥生時代の大規模な環濠集落が完全な形で発掘されたのは極めて稀有とされる。中央部及び西側は開発によって削り取られ消滅した。
約90棟の竪穴住居跡 / 10棟の高床式倉庫跡 が発見され、炭化米 / モモの種子 なども出土した。 |
||
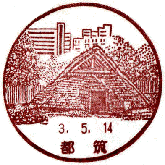 |
横浜市営地下鉄・センター南駅から西に進む。5分足らずの左手に都筑郵便局がある。風景印は、大塚遺跡 / 近代的な街並み の図柄になっている。 |
|
| 都筑郵便局風景印 | ||
| 武蔵国・蒔田まいた城(吉良氏館 / 蒔田御所) |
||
 |
■城の種別 丘城 ■築城者 吉良頼康 ■築城年 室町時代 |
|
| 成美学園遺跡案内板 | ||
 |
 |
横浜市営地下鉄・蒔田駅2番出口から21号線を南西に進む。すぐの休日急患診療所入口交差点手前を左折する。突き当りにある階段をひたすら登る。この階段は右に折れて緩やかな階段になる。登り切ると城址で、青山学院英和小学校の校舎が見える。 [交通]横浜市営地下鉄・蒔田駅-(徒歩10分)-蒔田城跡 |
| 階段 | 青山学院英和小学校 | |
 |
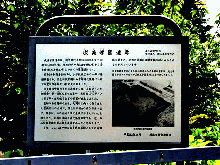 |
敷地沿いに左に進む。左手に“蒔田町原 地区急傾斜地崩壊危険区域 神奈川県”標柱 / 右手の青山学院横浜英和中学高等学校の正門左手に“成美学園遺跡”案内板
と続く。 |
| 地区急傾斜地崩壊危険区域 標柱 | 成美学園遺跡案内板 | |
| 青山学院横浜英和中学高等学校は、明治13年(1880年)山手の居留地に開校したブリテン女学校が始まり。明治19年(1886年)横浜英和女学校となり、大正5年(1916年)現在地に移転する。。昭和14年(1939年)成美学園 / 平成8年(1996年)横浜英和学院 / 平成28年(2016年)青山学院横浜英和中学高等学校 と改称する。発掘調査が行われたときの校名から“成美学園遺跡”になっている。 |
||
|
蒔田城は蒔田駅の南、大岡川に張り出した台地 |
||
 |
 |
正門から坂を下ると、5分足らずの右手に文明11年(1479年)吉良政忠によって創建された勝国寺がある。蒔田城の南麓に位置、吉良氏の菩提寺の一つである。 |
| 勝国寺山門 | 勝国寺本堂 | |
|
[寄り道]横浜中村橋郵便局 / 宝生(ほうしょう)寺 |
||
 |
横浜市営地下鉄・蒔田駅2番出口から21号線を北東に進む。すぐの宮元町3丁目交差点を右折して南東に進む。すぐの変則四差路交差点から東に進む。5分ほどの交差点を越えた左手に横浜中村橋郵便局がある。風景印は 宝生寺本堂(灌頂堂)の図柄になっている。 | |
| 横浜中村橋郵便局風景印 | ||
 |
 |
横浜中村橋郵便局から交差点まで戻り、左折して南に道なりに進む。Y字路交差点を左に進むと、承安年間(1171年~1175年)創建と云われる宝生寺がある。 |
| 宝生寺山門 | 宝生寺本堂 | |
|
江戸時代に近隣五十二寺の末寺を支配する高野山真言宗の本山となる。明治7年(1874年)本山の格が増徳院に移されてしてから次第に衰退した。本堂は延宝8年(1680年)建立の灌頂堂。建立時は茅葺であったが、現在は瓦葺になっている。蒔田城跡の東、直線距離で500m程のところにある。 |
||
| 武蔵国・平山館 | ||
 |
■城の種別 居館 ■築城者 日奉直季 ■築城年 平安時代末期 |
|
| 城壁を模した西園の公園北中央口 |
||
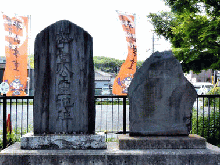 |
京王線・平山城址公園駅前ロータリー南側に、嘉永3年(1851年)造立の平山季重遺跡之碑 / 大正14年(1925年)造立の季重公霊地碑 がある。平山城址公園駅を含めたこの辺り一帯に、平山館があったと云われている。 |
|
| 平山季重遺跡之碑 /季重公霊地碑 | ||
|
天正年間(1573年〜1591年)子孫が平山季重を供養するために、居館跡に大福寺が創建された。明治17年(1884年)廃寺となり、宗印寺に併合された。 |
||
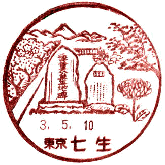 |
京王線・平山城址公園駅から南に進む。すぐの交差点を左折すると、すぐ左手に七生(ななお)郵便局がある。風景印は、中央に平山季重遺跡之碑と季重公霊地碑 / 富士山 / 平山城址公園からの景色 / 市花・菊 の図柄になっている。 |
|
| 七生郵便局風景印 | ||
|
明治22年(1889年)平山村 / 南平村 / 高幡村 / 程久保村 / 三沢村 / 落川村 / 百草村 の七村が合併して七生村が成立する。 |
||
 |
 |
七生郵便局から173号線を東に進むと、すぐ右手に宗印寺の標識がある。右折して坂を登ると、突き当りに寛文3年(1633年)創建の宗印寺がある。大福寺より平山季重墓
/ 日奉地蔵 / 平山薬師 が移されている。 |
| 宗印寺山門 | 宗印寺本堂 | |
 |
 |
宗印寺山門から東に進み、墓地の横を登ると平山城址公園に至る。坂を登り切ったところから、平山城址公園駅方向が眺望できる。 |
| 登り坂 | 平山城址公園駅方向の眺望 | |
 |
 |
平山城は物見台があった程度の規模と云われている。平山城址公園は東園と西園があり、西園の公園北中央口近くに平山季重を祀る季重神社がある。木々が生い茂っているが、 |
| 季重神社鳥居 | 季重神社社殿 | |
 |
 |
 |
| 浅川 | 平山八幡神社 | 平山八幡神社社殿 |
| 平山城址公園駅の南西方向にある浅川に架かる落合橋を渡った北西方向に、平山八幡神社がある。この辺りに居館があったとも云われている。文治年間(1185年~1190年)平山季重が鎌倉の鶴岡八幡宮を勧請して鎮守にしたと云われている。平山八幡神社は丘陵の先端にあり、崖下からは湧水がある恵まれたところだった。また浅川の治水が行われたのは江戸時代に入ってからで、それまでは丘陵地帯に集落があった。 |
||
|
武蔵七党の西党・日奉(ひまつり)直季が平安時代末期に武蔵国多西郡平山に居館を構え平山氏を称した。 |
||
|
戦国時代の平山氏は管領山内上杉氏に属していたと云われている。 |
||
| 武蔵国・小机城(飯田城 / 根古屋城) | ||
 |
■城の種別 丘城 ■築城者 山内上杉氏 ■築城年 永享の乱(1438年~1439年)の頃 ■遺構 空堀 / 土塁 / 曲輪 / 堀切 / 櫓台土塁 |
|
| 伝:二の丸跡 | ||
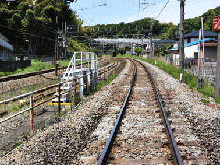 |
JR横浜線・小机駅南口から南に進み、小机駅前交差点を右折して12号線を西に進む。5分ほどの小机辻交差点を右折して北に進む。5分ほどのJR横浜線・城山踏切を渡る。城山踏切から、左手に出城があった丘陵
/ 正面に466号線(第三京浜道路)の橋梁 が見える。 |
|
| 城山踏切から西方向を撮影 | ||
 |
小机城は、鶴見川東岸の丘陵に築城された。 |
|
| 金剛寺 | ||
 |
 |
 |
| 右:466号線(第三京浜道路) | 空堀 | 冠木門 |
 |
階段を登り、さらに土留めされた土道を登る。見上げていた466号線を眼下に見ることになる。 |
|
| 伝:本丸跡 | ||
 |
 |
466号線側の曲輪は本丸 / 東側の曲輪は二の丸とされるが、解っていない。本丸と二の丸の間に深い堀があり、散策路になっている。 |
| 本丸と二の丸の間の空堀 | 伝:二の丸跡 | |
 |
 |
 |
| 櫓台 | 井楼跡 | 櫓跡 |
 |
 |
 |
| 空堀 | 曲輪 | 祠 |
 |
井楼跡から根古谷に抜ける途中の曲輪に祠があり、“大口真神御符”が見える。大口真神とは、日本狼が聖獣として神格化したもので、猪や鹿から作物を守護するとされた。 |
|
| 根古谷広場 | ||
|
小机城は、永享の乱(1438年~1439年)の頃、関東管領・山内上杉氏によって築城されたと云われている。文明年間(1469年~1487年)秩父氏一族・小机氏が築城したとも云われている。 |
||
| 武蔵国・奥沢城 |
||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 吉良頼康 ■築城年 天文年間~永禄年間(1532年~1570年) ■遺構 土塁 |
|
| 九品仏浄真寺 参道入口 | ||
 |
改札口が上下線の間にある東急大井町線・九品仏(くほんぶつ)駅から上り線路を渡り北に進むと、すぐの交差点から九品仏浄真寺の参道となる。 |
|
| 九品仏郵便局 |
||
 |
城域は九品仏駅付近から北方に突き出た舌状台地端まで拡がっていたと云われている。城跡周囲には近年まで堀跡が残り、「奥沢の底なし田圃」と云われた深田が拡がっていた。往時はこの堀と沼地で、守りを固める構えとなっていた。九品仏浄真寺境内に方形に廻る土塁が残る。 |
|
| 奥沢城土塁 | ||
| 世田谷城の出城として、天文年間~永禄年間(1532年~1570年)吉良頼康により築かれ、家臣の大平氏が守った。天正18年(1590年)小田原征伐後に廃城となった。 三河吉良氏は足利義氏の庶長子・長氏に始まり、奥州(武蔵)吉良氏は長氏の弟・義継より始まる。 |
||
 |
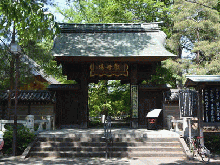 |
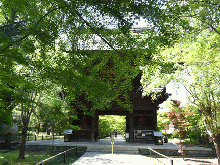 |
| 九品仏浄真寺参道 | 九品仏浄真寺総門 | 九品仏浄真寺山門(仁王門) |
 |
奥沢城跡地に、延宝6年(1678年)九品仏浄真寺が創建される。 |
|
| 九品仏浄真寺本堂 |
||
| 武蔵国・渋谷城(金王丸城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 河崎重家(渋谷重家) ■築城年 平安時代末期 ■遺構 城の石 |
|
| 城の石 | ||
 |
JR山手線・渋谷駅の南側を通る412号線(六本木通り)を東に進む。渋谷2丁目交差点を右折して坂を下ると、金王神社前交差点右手に金王八幡宮の表参道大鳥居がある。渋谷2丁目交差点手前を右折して短絡する道は、堀を兼ねた小川であったと云われている。 |
|
| 金王八幡宮の表参道大鳥居 | ||
| 桓武平氏・秩父武綱の子・基家は、武蔵国橘樹郡(現:川崎市川崎区)を領して河崎氏を称した。 応保年間(1161年~1163年)河崎重家の子・渋谷重国のとき、武蔵国豊嶋郡谷盛(現:東京都渋谷区・港区)から相模国高座郡渋谷荘(現:神奈川県綾瀬市 / 藤沢市 / 大和市)までを領していた。 家督は渋谷重国の次男・渋谷高重が継ぐが、和田義盛の乱に加担したため相模国渋谷荘を没収される。 |
||
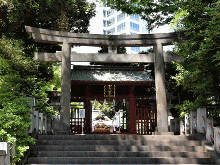 |
 |
 |
| 金王八幡宮鳥居 | 金王八幡宮神門 | 金王八幡宮社殿 |
| 金王八幡宮は寛治6年(1092年)城内に創建したと云われている。社殿は慶長17年(1612年) / 神門は江戸中期 の建立と云われている。 | ||
 |
境内に金王丸御影堂がある。金王丸は渋谷重家の子と云われ、保元元年(1156年)保元の乱や平治元年(1159年)平治の乱に源義朝に従った。平治の乱で源義朝が平清盛に敗れ尾張国で暗殺されると、出家して土佐坊昌俊と名乗ったと云う。 |
|
| 金王丸御影堂 | ||
 |
絵馬の「金王丸と常盤御前」は、 |
|
| 金王八幡宮絵馬 | ||
| 武蔵国・稲付いなつけ城 |
||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 太田道灌 ■築城年 不明 |
|
| 稲付城跡石柱 | ||
 |
JR東北本線・赤羽駅南口から西に、高架線路沿いに南に進む。すぐ左手にコンビニがあり、十字路を右折して西に進む。街路灯に“赤羽西口本通り”の標識がある。460号線(岩槻街道)を越えると、すぐに静勝寺の参道石段がある。 [交通]JR東北本線・赤羽駅-(徒歩10分)-静勝寺 |
|
| 赤羽西口本通り標識 | ||
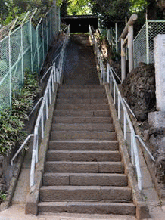 |
 |
 |
| 静勝寺参道石段 | 静勝寺東側山門 | 静勝寺南側山門 |
| 静勝寺の北側からの小路は、石段の東側山門前まで続いている。地元の方数人が東側山門から境内を通り、南側山門から住宅地に通り抜けていた。 |
||
| 三方を崖に囲まれた武蔵野台地に、江戸城と岩槻城を中継する城として築城された。現在の静勝寺や周囲の住宅地が城域とされる。 |
||
 |
 |
静勝寺は永正元年(1504年)に城内に道灌寺を創建したのが始まり。明暦元年(1655年)太田道灌と父・太田資清の法号に因んで静勝寺に改称した。太田氏の菩提寺とされ、正徳5年(1715年)太田道灌の木造を安置する道灌堂が建立される。 |
| 静勝寺本堂 | 道灌堂 | |
| 武蔵国・志村城 | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 志村氏 ■築城年 不明 ■遺構 土塁 / 空堀 |
|
| 志村城跡石柱 | ||
 |
志村三丁目駅から右に進む。すぐの交差点を左折して南に進む。 [交通]都営地下鉄三田線・志村三丁目駅-(徒歩15分)-城山熊野神社 |
|
| 志村城山公園石柱 | ||
 |
 |
北と西は出井川が流れる断崖にあり、攻めるに難い堅城と云われていた。本丸跡に志村小学校 / 二の丸跡に長久3年(1042年)志村将監が紀州から勧請した城山熊野神社 がある。社殿脇に空堀の名残があるらしいが、確認できなかった。 |
| 城山熊野神社鳥居 | 城山熊野神社社殿 | |
|
|
||
| 武蔵国・片倉城 | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 長井時広 ■築城年 室町時代初期 ■遺構 土塁 / 空堀 / 沼 |
|
| 曳橋 | ||
| 京王片倉駅の東側を通る16号線を右折して南に進む。湯殿川を渡ると、すぐに住吉神社参道入口の案内看板があり右折すると、片倉城址公園に至る。 [交通]京王片倉駅-(徒歩5分)-片倉城址公園 |
||
 |
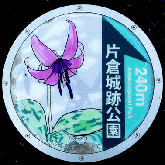 |
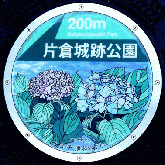 |
 |
帰路は16号線を南に進み、片倉駅入口交差点を左折して東に進む。2本目の十字路を右折すると、片倉城址公園から徒歩5分ほどでJR横浜線・片倉駅に至る。歩道のころどころに片倉城址公園への案内マンホールがある。マンホールは横浜線・片倉駅側から順に並べています。 | |
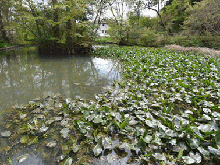 |
 |
 |
| 住吉沼 | 住吉神社 | 二郭 |
 |
 |
 |
| 二郭の藤棚 | 曳橋 | 主郭 |
| 湯殿川と支流の兵衛川に挟まれた小比企丘陵の東端に築城された。周囲は急崖で城の周囲は湿地で、住吉沼の一部が残っている。 |
||
|
鎌倉時代初期の御家人・椚田重兼は武蔵七党の横山党の一族で、武蔵国多摩郡横山荘を領していた。横山時兼は、建暦3年(1213年)和田合戦のとき和田義盛に加担して討死した。 |
||
| 武蔵国・初沢はつざわ城(椚田くぬぎだ城・高乗寺城) | ||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 椚田重兼 ■築城年 鎌倉時代初期 ■遺構 土塁 / 空堀 |
|
| 初沢城跡標柱 | ||
 |
 |
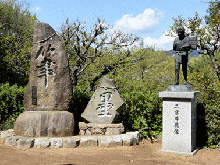 |
| 高尾天神社入口 | 高尾天神社社殿 | 石塔 / 二宮金次郎像 |
| JR中央線 / 京王線・高尾駅南口から南に進む。すぐの突き当りを右折、市立浅川小交差点を左折して南に進む。突き当りを右折して西に進むと、左手に高尾みころも霊堂記念公園
/ 高尾天神社入口 と続く。高尾天神社石柱横に、初沢城址入口標識がある。石段を登ると高尾天神社があり、社殿裏から登る。 [交通]JR中央線 / 京王線・高尾駅南口-(徒歩15分)-高尾天神社入口-(徒歩5分)-高尾天神社社殿 |
||
 |
 |
ところどころに、短絡する急坂がある。高尾天神社から15分ほどの標高294mの初沢山山頂に主郭がある。 |
| 初沢城主郭 | 初沢配水所配水タンク | |
|
|
||
| 武蔵国・関戸せきど城 | ||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 鎌倉幕府 ■築城年 建暦3年(1213年)以降 |
|
| 関戸城天守台跡標柱 | ||
 |
 |
 |
| 多摩市マンホール | さくら公園 | 金毘羅宮 |
| 聖蹟桜ケ丘駅前交差点から“さくら通り”を南に進むと、あらいぐまラスカル / 市花・ヤマザクラ の図柄のマンホールがある。大栗川を渡り、曲がりくねった“いろは坂”を登る。曲がりくねった“いろは坂”を短絡する階段がところどころにある。途中右手に、郭を思わせる“さくら公園”がある。城山の頂上手前の左手に、文政年間(1818年~1830年)創建の金毘羅宮
/ 関戸城天守台跡標柱 と続く。城山の頂上まで住宅地になっている。関戸城天守台跡標柱の東側から北東方向に、鬱蒼とした原生林が広がる霞ケ関保全緑地がある。急傾斜地で土砂災害の危険箇所として立ち入り禁止区域になっている。 [交通]京王線・聖蹟桜ヶ丘駅-(徒歩15分)-関戸城天守台跡標柱 |
||
| 鎌倉時代初期の建暦3年(1213年)の和田合戦後、鎌倉幕府は北関東からの防衛の要衝として関所(霞ノ関)を設置する。霞ノ関背後の山頂に物見台が置かれ、後に関戸城になった。霞ノ関の監視
/ 守備 の役目を持っていたと云われている。 |
||
 |
 |
 |
| 関戸熊野神社鳥居 | 関戸熊野神社社殿 | 霞ノ関南木戸柵跡 |
| 関戸城の東側を高崎と鎌倉を結ぶ旧鎌倉街道(上ノ道)が通っている。霞ノ関は旧鎌倉街道(上ノ道)沿いに設けられ、延徳元年(1498年)創建の関戸熊野神社の参道に霞ノ関南木戸柵跡がある。 | ||
 |
北約230m先の建久3年(1192年)創建の観音寺辺りに 北木戸柵があったと考えられている。 多摩川の南側にあり、川崎街道 / 野猿街道 / 鎌倉街道(上ノ道) が通る交通の要所で往時は宿場町として賑わった。 |
|
| 観音寺本堂 | ||
 |
 |
観音寺北側の鎌倉街道沿いにある地蔵堂の前に、関戸古戦場跡標柱がある。 |
| 地蔵堂 | 関戸古戦場跡標柱 | |
|
|
||
| 武蔵国・八王子城(武州八王寺城) |
||
 |
■城の種別 |
|
| 八王子城跡碑 | ||
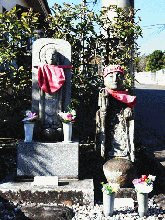 |
 |
 |
| 地蔵 | 閑窓寺 | 稲荷神社 |
| JR高尾駅から北へ進む。すぐに20号線(甲州街道)と交差、46号線(高尾街道)を北へ進む。すぐの南淺川を渡り、15分ほどの城山大橋交差点から左方向に進む。61号線(美山通り) |
||
 |
 |
 |
| 横地堤 | 宗関寺本堂 | 宗関寺梵鐘 |
|
稲荷神社からすぐのT字路北西側に、延喜17年(917年)創建の宗関寺がある。 |
||
 |
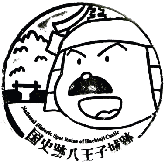 |
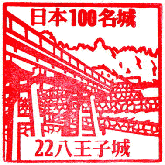 |
| 立て看板 | 八王子城跡ガイダンス施設スタンプ | |
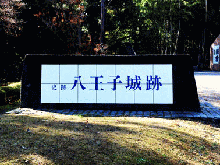 |
ところどころに“イノシシ 危険・注意”立て看板がある。八王子城交差点から15分ほどのところに、八王子城跡ガイダンス施設がある。八王子城跡ガイダンス施設から5分足らずのところに八王子城跡管理棟がある。 [交通]JR中央選・高尾駅-(徒歩50分)-八王子城管理棟 |
|
| 八王子城跡管理棟入口 | ||
 |
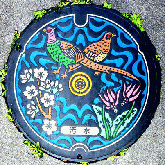 |
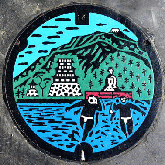 |
| 八王子市マンホール | 小田原市マンホール | |
| 八王子城跡管理棟手前に八王子市マンホール、八王子城跡管理棟から右に進むと小田原市マンホールが埋め込まれている。小田原城・北条氏政 / 八王子城・北条氏照
/ 鉢形城・北条氏邦 の北条3兄弟に因み、マンホールの蓋を交換したもの。 |
||
 |
 |
 |
| 八王子城跡登り口 | 根の階段 | 八王子神社鳥居 |
 |
 |
 |
| 崩落した石段 | 崩落した石段 | 金子曲輪 |
 |
八王子城跡管理棟から右に進むと、すぐの登り口に八王子神社の鳥居がある。登り始めると、すぐに旧道と新道の分岐があり、左折して金子曲輪経由の新道を進む。旧道と新道は柵門跡で合流する。新道の方が比較的楽との情報だったが、土砂 / 石段 の崩落しているところもあり険しい。また小石混じりの坂道は、下るとき滑り往生する。 | |
| 柵門跡 | ||
 |
 |
 |
| 柵門跡~八王子神社の眺望 | 八王子神社社殿 | 八王子神社神楽殿 |
 |
 |
 |
| 松木曲輪 | 八王子城跡碑 | 八王子神社碑 |
|
石段を登ると八王子神社境内で、八王子神社社殿 / 八王子神社神楽殿 / 横地社などの境内社 がある。 |
||
 |
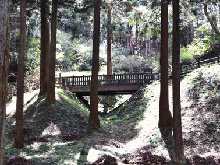 |
 |
| 橋 | 堀切に架かる橋 | 大手門跡付近 |
| 八王子城跡管理棟から左に進む。木立を進み橋を渡り坂を登ると |
||
 |
 |
|
| 大手道 | ||
 |
||
| 曳橋 | 曳橋 / 御主殿(右上) | |
| 大手道を進むと、前方に城山川に架かる曳橋(ひきはし) / 虎口の石垣 / 御主殿跡 が見えてくる。曳橋は橋脚以外の構造は不明で、推定復元となっている。 | ||
 |
 |
 |
| 御主殿虎口 | 御主殿虎口石段 | 櫓門推定地からの曳橋 |
| 曳橋を渡り切ると御主殿虎口で、石垣は土に埋もれていた往時ものである。折れ曲がった石段の途中に、礎石から櫓門があったと推定されている。 |
||
 |
 |
 |
| 冠木門 | 御主殿跡 | 礎石 |
|
|
||
| 永禄12年(1569年)武田信玄は小田原城を攻撃するため碓氷峠を越え、小田原北条方の城を攻撃しながら南下して拝島町に陣を敷いた。 |
||
| 天正15年(1587年)頃に北条氏照は八王子城を築城、滝山城から本拠を移した。小田原城の支城で関東の西に位置する軍事拠点であった。標高445m(比高約240m)の深沢山(現:城山)にあり、延喜16年(916年)八王子権現を祀ったことから八王子城と名付けられた。 |
||
| 武蔵国・滝山城(武州瀧山城 / 横山城 / 竹山城) |
||
 |
■城の種別 丘城 ■築城者 大石定重 ■築城年 大永元年(1521年) ■主な遺構 土塁 / 郭 / 堀 / 井戸 城門が国分寺・観音寺に移築され現存する。 ■主な再建造物 曳橋 |
|
| 滝山城跡碑 | ||
 |
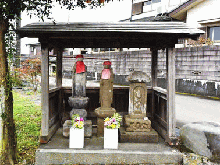 |
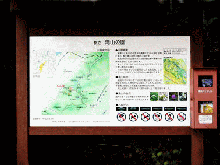 |
| タッチセンサー式 押しボタン | 地蔵 / 地蔵 / 庚申塔 | 滝山公園案内板 |
| 拝島駅南口から7号線(陸橋通り)を北西に進む。すぐに道は西に進路を変える。拝島駅南口から30分ほどの小川交差点を左折、166号線を南に進む。5分足らずで秋川に架かる橋を渡ると、南西方向に長禄2年(1458年)大石顕重によって築城された高月城址がある。秋川に架かる橋から10分ほどの高月浄水場前交差点を越え、すぐに右方向の小路を道なりに進む。高月浄水場前交差点は、タッチセンサー式押しボタン [交通]JR青梅線 / 五日市線 / 八高線 / 西武拝島線・拝島駅南口-(徒歩60分)-滝山城搦手口 |
||
| 大永元年(1521年)山内上杉氏の重臣・大石定重によって築城、高月城から居城を移す。天文15年(1546年)河越の夜戦で北条氏康は上杉憲政 /
上杉朝定 / 足利晴氏 の連合軍に勝利、山内上杉氏は没落する。大石定久は小田原北条氏に臣従、北条氏康の三男・北条氏照を婿養子とした。永禄12年(1569年)武田信玄が滝山城を攻撃、三の丸まで落とされたが持ち堪えた。天正15年(1587年)頃に北条氏照は八王子城を築城、本拠を移した。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐により八王子城とともに落城、廃城になったと云われている。北条氏照は小田原城に籠城、小田原開城後は豊臣秀吉から北条氏政と共に切腹を命じられた。 |
||
 |
 |
|
| 石畳の急坂 | 本丸と中の丸の空堀に架かる曳橋 | |
| 多摩川と秋川が合流する加住丘陵にあり、遺構の保存状態がよく滝山城址公園として整備されている。関東の中世城郭では、八王子城 / 鉢形城 とともに傑作城郭と云われている。「滝山城
城攻めマップ」の縄張図を見ながら散策しないと、何処にいるか解らなくなる。 |
||
 |
 |
 |
| 中の丸 | 曳橋 | 本丸下段 |
| 空堀から中の丸に登り、曳橋を渡ると本丸下段に至る。 | ||
 |
 |
 |
| 霞神社 | 本丸上段 | 金比羅社 |
 |
本丸上段に明治45年(1912年)創建の霞神社 / 奥に天明年間(1781年~1789年)創建の金比羅社 がある。 |
|
| 本丸上段からの眺望 | ||
 |
中の丸の南側に二の丸がある。二の丸から東へ行けば信濃屋敷 / 西へ行けば千畳敷を経て三の丸 / 南には馬出 がある。いたるところに深い堀があある。 | |
| 二の丸南側の空堀 | ||
 |
JR中央線・国立駅から222号線(光町通り)を北に進む。光町交番手前から北西方向、さらに光町2丁目交差点の先から西方向に曲がる道を道なりに進む。突き当りを右折して北に進むと、右手に観音寺がある。国立駅北口から30分弱掛かる。 |
|
| 観音寺山門 | ||
| [参考]北条氏政 / 北条氏照 墓所 | ||
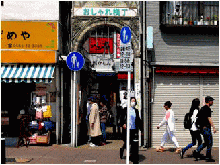 |
 |
|
| おしゃれ横丁入口 | 北条氏政 / 北条氏照 墓所 | |
| JR / 小田急・小田原駅東口から南東に進む。すぐの小田原駅東口交差点を左方向に直進する。すぐ左手におしゃれ横丁入口がある。すぐ道は左に折れ、すぐ右に折れる。 |
||
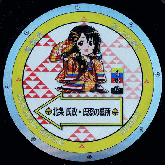 |
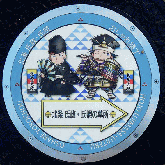 |
 |
| おしゃれ横丁 | 墓所前 | 墓所→小田原城址間 |
| 令和3年(2021年)に再度訪れる。おしゃれ横丁と墓所前のマンホールが案内板になっていた。また |
||
| 武蔵国・江戸城(千代田城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 太田道灌 ■築城年 長禄元年(1457年) ■主な遺構 桜田門(重文) / 田安門(重文) / 清水門(重文) / 石垣 / 堀 ■主な再建造物 大手門渡櫓 / 富士見櫓 / 伏見櫓 / 多聞櫓 / 桜田巽櫓 / 和田倉門 |
|
| 大手門渡櫓 | ||
| 平安時代末期に、江戸氏が居館を構えていたと云われている。長禄元年(1457年)扇谷上杉氏の執事・太田道潅によって築城される。小田原合戦の後,徳川氏の本拠となり修築される。以後,江戸幕府の中枢となる。 [交通]東京駅丸の内中央口-(徒歩5分)-皇居 |
||
| 武蔵国・世田谷城 | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 吉良成高 ■築城年 応永年間(1394年~1426年) ■主な遺構 空堀 / 土塁 |
|
| 空堀 | ||
| 東急世田谷線・上町駅の東側の道を北へ道なりに進む。5分ほどの世田谷城址公園交差点の北側に世田谷城址公園がある。貞治5年(1366年)吉良治家に世田谷郷が与えられる。応永年間(1394年~1426年)に居館を構えたと云われている。豪徳寺付近が主郭で、世田谷城址公園付近まで城域が拡がっていた。城域の三方を取り囲む様に烏山川が流れ天然の堀を成していた。天正18年(1590年)吉良氏朝のとき、小田原征伐後に廃城となった。世田谷ボロ市の始まりは、天正6年(1578年)城下町に開いた楽市とされる。 [交通]東急世田谷線・上町駅-(徒歩5分)-世田谷城址公園 |
||
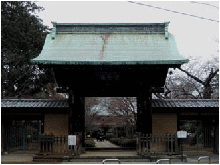 |
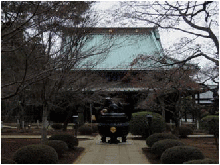 |
 |
| 山門 | 仏殿 | 本堂 |
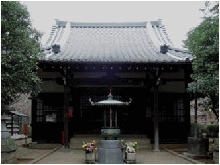 |
 |
 |
| 招猫殿 | 奉納された招福猫児 | 井伊直弼墓 |
| 世田谷城址公園の北側に豪徳寺がある。文明12年(1480年)世田谷城主・吉良政忠が伯母・弘徳院のために、弘徳院と称する庵を結んだのが始まり。寛永10年(1633年)彦根藩2代藩主・井伊直孝が井伊氏の菩提寺として整備した。仏殿は掃雲院が父・井伊直孝の菩提を弔うため、延宝5年(1677年)に建立したもの。井伊直孝が鷹狩りの帰りに豪徳寺の門前にさしかかったとき、住職の飼い猫が手招きするので立ち寄ると雷雨となった。雨に濡れずに済んだ縁で豪徳寺は井伊家の菩提寺となり寺は繁栄、福を招く猫として死後に猫観音として祀られたのが招き猫伝説である。招猫殿の横には、願が成就したお礼として数多くの招福猫児が奉納されている。井伊家墓所の奥まったところに、第15代藩主・井伊直弼(なおすけ)の墓がある。安政5年(1858年)江戸幕府大老に就任、日米修好通商条約の調印 / 安政の大獄で反対派を処罰 した。万延元年(1860年)桜田門外で水戸脱藩浪士17名と薩摩藩士1名に暗殺された。 | ||
 |
吉田松陰は安政の大獄(1859年)に連座、江戸伝馬町で処刑され千住回向院に葬られた。文久3年(1863年)若林に改葬され、明治15年(1882年)墓所に松陰神社が創建された。吉田松陰は江戸時代後期の思想家・教育者・兵学者で、明治維新の事実上の精神的理論者と云われている。死に追いやった井伊直弼の墓と松陰神社は、直線距離で1Kmも離れていない。 | |
| 松陰神社 | ||
| 武蔵国・世田谷代官屋敷 | ||
 |
 |
■城の種別 代官屋敷 ■主な遺構 主屋 / 表門 |
| 表門 | 主屋 | |
| 東急世田谷線・世田谷駅の西側の道を南へ進む。すぐに3号線(世田谷通り)に突き当る。左折してすぐに右折して南へ進む。すぐの世田谷中央病院交差点を右折して、世田谷ボロ市のメイン通りとなる通称ボロ市通りを西へ進む。5分ほどすると、左手に世田谷代官屋敷がある。寛永10年(1633年)彦根藩主・井伊直孝に関東で2万石が加増され、内2306石余が世田谷領であった。代官に起用された大場吉隆は吉良氏の家臣であったが、天正18年(1590年)主家没落後は世田谷に土着していた。
明治4年(1871年)廃藩置県まで代官職を世襲した。世田谷代官屋敷は大場氏の居宅で、役宅として代官の執務を行なっていた。 文化12年(1815年)築の主屋
/ 宝暦3年(1753年)築の表門(長屋門) は重文。敷地内に世田谷区立郷土資料館がある。 [交通]東急世田谷線・世田谷駅-(徒歩10分)-世田谷代官屋敷 |
||
| 武蔵国・品川台場 | ||
 |
■城の種別 海上砲台 ■築城者 徳川幕府 ■築城年 嘉永6年(1853年) ■主な遺構 第三台場 / 第六台場 |
|
| 第三台場 | ||
 |
 |
 |
| 第三台場砲台跡(模擬砲台) | 第三台場内部 | 第六台場 |
| 台場(だいば)は幕末に設置された砲台。幕府や各藩が異国船の打払いのために、各地の海岸や河岸に築かれたものが多かった。戊辰戦争や箱館戦争や西南戦争においては、野戦築城のものも台場と呼ばれるようになった。嘉永6年(1853年)アメリカ海軍東インド艦隊・ペリー司令長官率いる軍艦四隻が浦賀に来航、鎖国政策の幕府に開国を迫った。脅威を感じた幕府は、江戸防備のために洋式の品川台場を築いた。台場は石垣で囲まれた正方形や五角形の洋式砲台で、お台場は幕府に敬意を払って御台場と称したことが由来となっている。品川沖に11基の台場が築かれる計画であったが、嘉永7年(1854年)ペリーの再来航までに第一台場 / 第二台場 / 第三台場が完成している。ペリー艦隊は品川沖まで来たが、この台場のために横浜に上陸することになった。以降、第五台場 / 六台場が完成する。第四台場と第七台場は未完成のまま工事中止となった。第一台場 / 第四台場 / 第五台場は埋立てられ、第二台場 / 第七台場は撤去されている。第三台場はお台場海浜公園と陸続きとなっている。一辺が約150mの正方形で、海面から5~7mの石垣積みの土塁が築かれている。周囲には黒松が植えられている。北側に石組みの船着場跡 / 南側の土塁に砲台跡(模擬砲台)/ 内部の平担な窪地に陣屋の基石 / 土塁の下に弾薬庫跡 がある。レインボーブリッジを間近で見ることができる。第六台場は第三台場の西方約250mにある。第三台場よりも一回り小さく、変形の五角形になっている。交通手段は無く、立ち入りが制限されている。植物や野鳥の宝庫になっていると云う。第三台場から望見するか、レインボーブリッジ遊歩道の南側を歩くと俯瞰することができる。 | ||
| 武蔵国・板橋城 |
||
 |
■城の種別 平城 |
|
| 長命寺本堂 | ||
| 西武有楽町線・新桜台駅より地上に、318号線(環状7号線)を北東に進む。25分ほどの板橋中央陸橋交差点西側に、江戸時代初期創建の長命寺がある。板橋中央陸橋交差点から254号線(川越街道)を北西に進み、すぐに左折して道なりに進む。長命寺墓地に隣接して板橋区立上板橋小学校がある。この一帯が城域になり、小学校内に城址碑がある。校門は全て閉ざされており諦める。長命寺本堂は天明2年(1782年)の建立。 [交通]西武有楽町線・新桜台駅-(徒歩25分)-板橋中央陸橋交差点 |
||
| 平安末期より豊島郡を支配した武蔵豊島氏の一族・板橋氏の居城であるが、築城年代は解っていない。文明10年(1478年)豊島宗家が太田道灌に滅ぼされると、板橋忠康は小田原北条氏に属することになる。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐後、赤塚城とともに廃城になったと云われている。板橋忠康の嫡男・板橋忠政は徳川家に仕え、旗本として明治まで続いた。 板橋忠康は、本貫地にあった応永年間(1394年 ~1427年)創建の乗蓮寺(じょうれんじ)を菩提寺としていた。寛政4年(1792年)板橋忠康の二百回忌が営まれている。昭和48年(1973年)現地(赤塚城二の丸跡)に移転した。乗蓮寺は、昭和52年(1977年)建立の東京大仏があることで知られている。 |
||
| 武蔵國・赤塚城 | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 千葉自胤 ■築城年 康正2年(1456年) ■主な遺構 土塁 / 堀 |
|
| 城址碑 | ||
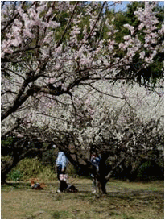 |
東京メトロ・地下赤塚駅 / 東武東上線・下赤塚駅より、赤坂中央通りを北へ進む。446号線(松月院通り)と交差する北東側に松月院がある。ここから大仏通りとなり、右手に不動滝公園
/ すぐ左手に赤塚公園がある。内堀の名残りと云われる池の南側を登ると、本丸跡に城址碑がある。康正2年(1456年)千葉・市川城から移った千葉自胤によって築城されたと云われているが、治承4年(1180年)に挙兵した源頼朝が立ち寄ったとも云われている。赤塚千葉氏は後北条氏の有力な家臣として活躍する。天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原征伐で後北条氏が滅亡すると、千葉氏も所領を没収され赤塚城は廃城になる。本丸跡の梅林はみごとである。 [交通]東京メトロ・地下赤塚駅 / 東武東上線・下赤塚駅-(徒歩15分)-赤塚公園 |
|
| 本丸跡の梅林 | ||
 |
 |
房総に勢力を持っていた千葉自胤が康正2年(1456年)千葉・市川城から赤塚城に移り、当地にあった古寺・宝持寺を菩提寺として松月院と改称したと云われている。幕末の砲術家・高島秋帆が天保12年(1841年)に徳丸ケ原(現高島平付近)にて西洋式の砲術訓練を行った際、本陣がこの松月院に置かれた。明治時代には旧赤塚村役場が境内に置かれた。 |
| 松月院本堂 | 高島秋帆紀功碑 | |
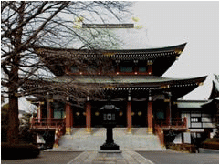 |
 |
 |
| 乗蓮寺本堂 | 東京大仏 | 板橋信濃守忠康墓 |
 |
不動滝公園の手前、赤塚植物園の標識を左折する。すぐ右手の二の丸跡に、応永年間(1394年~1427年)創建の乗蓮(じょうれん)寺がある。応永年間(1394年~1427年)山中村(現板橋区仲町)に創建、江戸時代初期に板橋区仲宿に移転する。郷主・板橋信濃守忠康の菩提寺になる。首都高速道路建設や17号の拡幅により、昭和48年(1973年)に現地に移転する。昭和52年(1977年)関東大震災や東京大空襲など、悲惨な震災や戦災が再び起きないよう願いを込め東京大仏が造立される。板橋信濃守忠康墓は、安政4年(1792年)二百回忌に再建されたもの。板橋氏は平安末期より豊島郡を支配した武蔵豊島氏の一族。板橋信濃守忠康は北条氏康に仕え、子孫は北条氏滅亡後に徳川家康に仕える。旗本として幕末まで続く。境内には天保飢餓供養塔供養塔などがある。 | |
| 天保飢餓供養塔 | ||
 |
かつては板橋にある崖下から、いたるところで湧水が見られた。不動の滝は山岳信仰が盛んとなった江戸時代の中頃に、富士山や大山などに詣でる際に身を清めていたと云われている。薄暗い池の崖上に、不動明王と童子2基がある。 | |
| 不動明王 | ||
| 武蔵国・平塚城(豊島城) |
||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 豊島近義 ■築城年 平安時代 |
|
| 平塚神社鳥居 | ||
| JR京浜東北線・上中里駅前の蝉坂(せみざか)を登ると、すぐ右手に平塚神社の社殿前に出られる階段がある。平塚神社の正面入口は、蝉坂を登り切った本郷通りとの平塚神社前交差点右手にある。入口から鳥居までの参道は駐車場になっている。蝉坂の名は、太田道灌が攻め上った“攻め坂”から転訛したと云われている。 [交通]JR京浜東北線・上中里駅-(徒歩5分)-平塚神社 |
||
 |
平塚神社や西側の滝野川公園は、古代律令国家の武蔵国豊島郡の郡衙(ぐんが)が置かれていたところである。豊島郡は、現在の 千代田区 / 文京区 / 台東区 / 荒川区 / 豊島区 / 北区 / 板橋区 / 練馬区 / 新宿区 の区域になる。武蔵国豊島郡の郡衙跡に、平安時代に秩父氏の一族・豊島近義が築城したと云われている。南側の本郷通りを越えたところまで城域であった。滝野川公園にある女神像は調べてビックリ、非常用の散水塔である。 | |
| 滝野川公園 女神像 | ||
 |
平塚神社は平安時代後期の元永年間(1118年~1120年)城内に創建したと云われている。 |
|
| 平塚神社社殿 | ||
|
治安3年(1023年)秩父常将の次男・秩父武常が武蔵国豊島郡 / 下総国葛飾郡葛西 を領して豊島氏を称したと云われている。 |
||
| 武蔵国・石神井城 | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 豊嶋氏 ■築城年 貞和5年(1349年)以降 ■主な遺構 土塁
|
|
| 城址碑 | ||
| 石神井公園駅南口より右へ進む。石神井公園駅入口交差点を左折して南東へ進む。坂を下ると、右手に石神井池が見えて来る。 [交通]西武池袋線・石神井公園駅-(徒歩10分)-石神井公園 |
||
 |
 |
|
| 三宝寺池・厳島神社 | 水神社 | |
| 石神井池の西側に、井の頭池や善福寺池とともに武蔵野三大湧水地として知られる三宝寺(さんぽうじ)池がある。石神井城は鎌倉時代後期 治安3年(1023年)秩父常将の次男・秩父武常が武蔵国豊島郡 / 下総国葛飾郡葛西 を領して豊島氏を称したと云われている。 文明8年(1476年)関東管領・山内上杉氏の家宰職相続をめぐり、長尾景春が武蔵鉢形城で挙兵する。文明9年(1477年)山内上杉家の拠点だった武蔵国・五十子城は落城する。 石神井城は落城後に廃城となり、僅かに土塁が残る。三宝寺池南西側に厳島神社と水神社 / 南東側に石神井城址碑 がある。 豊島泰経は家宝・黄金の鞍を載せた白馬に跨り、三宝寺池に身を沈める。娘・照姫も後を追い池に身を投じたと云う石神井城伝説がある。 |
||
 |
応永年間(1394年~1428年)豊島氏によって創建された氷川神社の辺りが二の丸で、往時も城内にあったと云われている。 | |
| 氷川神社社殿 | ||
 |
 |
|
| 三宝寺山門 | 三宝寺長屋門 | |
 |
 |
 |
| 三宝寺本堂 | 三宝寺大黒堂 |
三宝寺観音堂 |
 |
 |
 |
| 三宝寺根本大塔 |
三宝寺鐘楼 | 三宝寺平和観音 |
| 氷川神社の東側に、応永元年(1394年)創建の三宝寺がある。往時は石神井城内にあったと云われている。徳川3代将軍・徳川家光の鷹狩の際に休憩場として使われ、山門はこれに因み御成門と呼ばれていた。現在の山門は文政10年(1827年)築のもの。長屋門は勝海舟邸にあったもので、昭和35年(1960年)に移築された。延宝3年(1675年)銘の梵鐘などがある。関東三十六不動11番札所
/ 御府内八十八ヶ所16番札所 / 豊島八十八ヶ所16番札所 / 武蔵野三十三観音3番札所 になっている。 |
||
 |
 |
 |
| 道場寺山門 | 道場寺本堂 | 道場寺三重塔 |
 |
三宝寺の東側に、応安5年(1372年)石神井城主・豊島輝時によって創建された道場寺がある。墓地には、文明9年(1477年)太田道灌に滅ぼされた石神井城城主・豊島泰経と一族の墓と云われる石塔3基がある。永禄5年(1562年)に発給された北条氏康印判状が所蔵されている。本堂は唐招提寺の金堂を模して昭和12年(1937年)に改築された。昭和45年(1970年)~昭和50年(1975年)山門 / 鐘楼 / 三重塔 が建立される。武蔵野三十三観音2番札所になっている。 | |
| 鐘楼 / 梅 | ||