| 最新の追加 | ||
| 伊予国・湯築ゆづき城(湯月城) |
||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 河野通盛 ■築城年 建武3年(1336年)頃 ■主な遺構 郭 / 水堀 / 土塁 ■主な再建造物 武家屋敷 |
|
| 湯築城外堀 | ||
 |
 |
JR予讃線・松山駅前から伊予鉄道市内電車・道後温泉行に乗車、道後公園 |
| 伊予鉄道市内電車 / 背景:道後公園 | 搦手門跡 | |
 |
 |
搦手門から右方向に進むと、湯築城資料館 / 復元された土塀と武家屋敷 |
| 外堀土塁 | 復元された武家屋敷 | |
 |
 |
 |
| 庭園の池 | 内掘 | 断崖 |
| 武家屋敷から庭園跡を通ると、内掘と断崖が現れる。 | ||
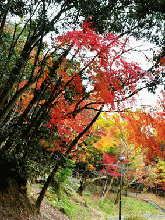 |
 |
 |
| 紅葉 | 杉の壇 | 本壇 |
| 回り込んで“杉の壇”跡から湯築城で一番高いところにある“本壇(ほんだん)”跡に登ると、展望台がある。杉の壇 / 本壇 は江戸時代の呼称で、河野氏時代の呼称は解っていない。 | ||
 |
“本壇”跡から“杉の壇”跡を通り搦手門跡方向に進むと、内濠と内掘土塁がある。 | |
| 内濠と内掘土塁 | ||
| 建武3年(1336年)足利尊氏により室町幕府が事実上成立すると、河野通盛は伊予国守護職に任じられた。この頃に築城され、天文4年(1535年)頃に河野通直(弾正少弼)によって外堀が造られたと云われている。 天正6年(1578年)土佐の長宗我部元親の伊予来襲が始まり、天正8年(1580年)河野通直(伊予守)は軍門に降った。 伊予国は小早川隆景の支配下となるが、天正15年(1587年)九州征伐後に筑前・筑後を領することになる。 |
||
 |
伊予鉄道市内電車・道後公園 |
|
| 道後温泉本館 | ||
| 伊予国・西条陣屋 |
||
 |
■城の種別 陣屋 ■築城者 一柳直重 ■築城年 寛永13年(1636年)頃着手 ■主な遺構 大手門 / 水堀 / 土塁 ■主な再建造物 模擬門 |
|
| 大手門 | ||
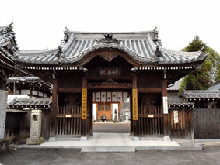 |
 |
 |
| 宝蓮寺山門 | 宝蓮寺霊明殿 / 観音堂 | 南東側からの水堀 |
| JR予讃線・伊予西条駅から駅前本通りを北に進む。10分ほどすると、左手に四国三十三観音第二十四番札所・宝蓮寺がある。すぐの交差点を左折して西に進む。5分ほどすると、西条陣屋の水掘が見えてくる。伊予西条駅から左折する交差点までに案内板が数箇所あり、迷うことはない。西条陣屋跡は西条高校の敷地となっている。東側の水堀に土橋が架かり、大手門が西条高校の校門になっている。 [交通]JR予讃線・伊予西条駅-(徒歩約15分)-西条陣屋 |
||
 |
 |
 |
| 南側にある模擬門 | 大手門北側の土塁 | 北東側からの水堀 |
| 寛永13年(1636年)伊勢神戸藩・一柳直盛が1万8000石の加増を受け、6万8000石で西条藩に転封となる。一柳直盛は領地に入る途中、大阪で没している。遺領は3人の息子に分割され、嗣子・直重が3万石で西条藩主を相続する。この頃から築城に着手したと云われている。次男・直家が2万8000石で伊予川之江藩
/ 三男・直頼が1万石で伊予小松藩 の大名となった。 |
||
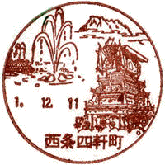 |
水堀の北東角側に西条四軒町便局がある。風景印は、自噴水 / 石鎚山 / 西条まつり山車 の図柄になっている。 |
|
| 西条四軒町便局風景印 | ||
| 讃岐国・高松城(玉藻たまも城) | ||
 |
■城の種別 平城(海城) ■築城者 生駒親正 ■築城年 天正16年(1588年) ■主な遺構 月見櫓(重文) / 渡櫓(重文) / 艮櫓(重文) / 水手御門(重文) / 披雲閣(重文) |
|
| 月見櫓 | ||
 |
JR高松駅の東側、高松琴平電鉄・高松築港駅の北側に玉藻公園(有料施設)西門がある。 [交通]JR高松駅-(徒歩/約10分)-玉藻公園西門 |
|
| 玉藻公園 | ||
|
天正16年(1588年)讃岐国の領主となった生駒親正によって築城された。 |
||
 |
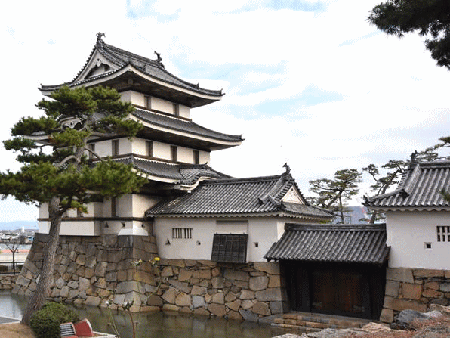 |
|
| 掘 / 石垣 | ||
 |
||
| 報時鐘 | 月見櫓 / 水手御門 / 渡櫓 | |
| 西門から入園せずに、北に進む。すぐの30号線(水城通り)を右折して東に進む。石垣と掘沿いに進むと、右手に 月見櫓(重文) / 水手御門(重文)
/ 渡櫓(重文) が見えてくる。月見櫓の30号線を挟んだ北側に、櫓風の建物に報時鐘がある。往時は外堀の土手に築かれた鐘楼にあり、城下の領民に時を知らせていた。 |
||
 |
 |
すぐの十字路を右折して、フェリー通りを南に進む。すぐにフェリー通りの西側の小路に東の丸石垣がある。建物は県立ミュージアムで、建設に伴う発掘調査で石垣が確認された。この石垣の上に、石を積み足して復元された。道なりに南に進むと、すぐ右手に東門 / 南西方向に艮(うしとら)櫓(重文)がある。 |
| 東の丸石垣 | 艮櫓 | |
 |
 |
 |
| 整備中の石垣 | 本丸石垣と天守台(2019年12月) | 解体修理中の天守台(2008年9月) |
 |
東門から入園すると、桜の馬場に整備中の石垣がある。桜の馬場から北に進むと、左手に内堀に囲まれ本丸石垣と天守台がある。二の丸とは木造の鞘橋で繋がっている。 |
|
| 鞘橋(2008年9月) | ||
 |
 |
右手に大正6年(1917年)に松平家の高松別邸として竣工した披雲閣(重文)がある。往時は藩主が生活する場所 / |
| 披雲閣 | 庭園側からの披雲閣 | |
 |
 |
披雲閣庭園から北に、道なりに西へっ進む。水門を通り過ぎると、西門に至る。西門から南に進むと、すぐ左手に高松琴平電鉄・高松築港駅はある。往時は内堀だったところで、東側は本丸になっている。 |
| 水門 | 高松琴平電鉄・高松築港駅 | |
| 讃岐国・丸亀城(亀山城 / 蓬莱城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 生駒親正 ■築城年 慶長2年(1597年) ■主な遺構 天守(重文) / 大手一の門(重文) / 大手二の門(重文) / 御殿表門 / 番所 / 長屋 |
|
| 天守 | ||
| 丸亀駅から開店前の薄暗い富屋町商店街を南へ進む。商店街には弘法大師を祀っている堂や天平年間(729年〜748年)創建の妙法寺がある。商店街を抜けて、堀沿いに左折すると大手門や天守が見えて来る。丸亀城は室町時代(1336年
〜1573年)初期に、管領・細川頼之の重臣・奈良元安が砦を築いたのが始まりと云われている。丸亀城には万治3年(1660年)に完成した天守(重文)や、大手一の門(重文)・大手二の門(重文)・御殿表門などが現存している。 [交通]丸亀駅-(徒歩/約15分)-丸亀城天守 |
||
| 伊予国・川之江城(仏殿城) | ||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 土井義昌 ■築城年 延元3年(1337年) ■主な再建造物 天守 / 涼櫓 / 櫓門 / 隅櫓 |
|
| 復興天守 | ||
| 川之江駅から西へ進み11号線を越えると、左手に明石寺がある。突き当たりを左折、すぐに右折すると城山に登ることができる。途中に川之江権現があり、本丸跡には昭和59年(1984年)再建の天守や、涼櫓・櫓門・隅櫓・控塀も再建されている。11号線に平行する西側の道を南へ進むと、稲荷神社や奈良時代創建の沸法寺がある。11号線を越えて駅へ戻る途中、右手の路地を入ると寛文4年(1664年)創建と云われる妙蓮寺がある。 [交通]JR川之江駅-(徒歩/約30分)-川之江城天守 |
||
| 伊予国・今治城(吹上城 / 吹揚城) | ||
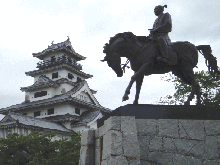 |
■城の種別 平城(海城) ■築城者 藤堂高虎 ■築城年 慶長7年(1602年) ■主な再建造物 模擬天守 / 多聞櫓 / 武具櫓 / 御金櫓 / 山里櫓 / 鉄御門 / 山里門 |
|
| 模擬天守・藤堂高虎像 | ||
| 今治駅から線路沿いに南東へ進み、317号線を左折する。T字路から先は今治銀座商店街が港まで続いている。港の手前を右折すると今治城天守が見えて来る。天守は慶長15年(1610年)に丹波亀山城に移築され、その後は築かれなかったと云われている。昭和55年(1980年)に建てられた模擬天守や、鉄御門・多聞櫓が再建されている。 [交通]今治駅-(徒歩/約40分)-今治城天守 |
||
| 伊予国・松山城(勝山城 / 金亀城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 加藤嘉明 ■築城年 慶長7年(1602年) ■主な遺構 天守 / 三ノ門南櫓 / 二ノ門南櫓 / 一ノ門南櫓 / 乾櫓 / 野原櫓 / 隠門続櫓仕切門 / 三ノ門 / 二ノ門 / 一ノ門 / 紫竹門 / 隠門 / 戸無門 *すべて重文 ■主な再建造物 小天守 / 北隅櫓 / 南隅櫓 / 太鼓櫓 / 天神櫓 / 乾門 / 艮門東続櫓 / 巽櫓十間廊下 / 筒井門 / 太鼓門 |
|
| 松山城本丸 | ||
| JR松山駅から東に伊予鉄道・市内線(路面電車)のJR松山駅前電停がある。道後温泉行に乗車、大街道電停で下車する。北へ進むと、5分ほどのところにロープウェイ乗り場がある。 [交通]JR松山駅-JR松山駅前電停-(伊予鉄道市内線/約10分)-大街道電停-(徒歩/約5分)-松山城ロープウェイ乗り場-(ロープウェイ/約5分)-長者平-(徒歩/約5分)-本丸 |
||
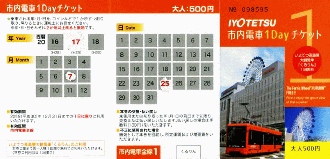 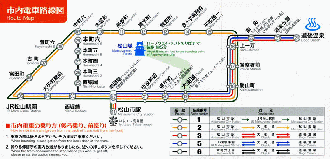 |
||
| 伊予鉄道 市内電車 1日乗車券 | ||
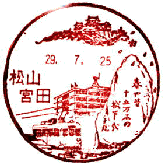 |
JR松山駅から東に伊予鉄道・市内線(路面電車)のJR松山駅前電停がある。線路に沿って進むと、最寄りの大街道電停まで行ける。 |
|
| 松山宮田郵便局風景印 | ||
 |
 |
JR松山駅前電停まで戻り、伊予鉄道・市内線(路面電車)沿いに進む。伊予鉄道・高浜線との平面交差を過ぎると、すぐ左手に松山大手郵便局がある。風景印は、道後温泉本館
/ 松山城 / 温泉マーク内に郵便局名 の図柄になっている。 |
| 伊予鉄道・高浜線との平面交差 | 松山大手郵便局風景印 | |
 |
 |
 |
| 松山城の堀 | 愛媛県庁内郵便局風景印 | 愛媛県庁内郵便局風景印 |
| すぐに松山城の堀に突き当たり、右折して堀沿いに進む。5分ほどすると、堀沿いに左折して北に進む。すぐに右折すると、すぐ左手の愛媛県庁に愛媛県庁内郵便局がある。 |
||
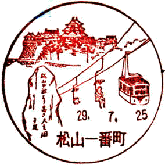 |
 |
すぐに大街道電停前に松山一番町郵便局がある。風景印は、松山城 / 子規句碑 / リフト / ロープウェイ の図柄になっている。 |
|
松山一番町郵便局風景印 |
松山城ロープウェイ 勝山号 / 湯姫号 |
|
|
伊予国・松前城主の加藤嘉明は慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いの戦功により、慶長7年(1602年)伊予松山藩20万石で立藩する。勝山に築城着手、慶長8年(1603年)加藤嘉明はこの地を松山と命名する。 |
||
 |
 |
 |
| 小天守 / 天守 | 太鼓櫓 | 天守曲輪(本壇) |
|
|
||
| 伊予国・大洲城(比志城 / 地蔵ヶ嶽城 / 大津城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者(地蔵ヶ嶽城) 宇都宮豊房 ■築城年 元弘元年(1331年) ■主な遺構 台所櫓(重文) / 高欄櫓(重文) / 苧綿櫓(重文) / 南隅櫓(重文) ■主な再建造物 天守 |
|
| 天守・台所櫓 | ||
| 伊予大洲駅から東へ、56号線を右折して南へ進む。大洲城天守が右手に見える肱川橋を渡って直ぐに右折する。郵便局の手前を右折すると苧綿櫓(重文)がある。市民会館を右折して登ると、平成16年(2004年)木造で再建された天守や台所櫓(重文)・高欄櫓(重文)がある。市民会館を通り過ぎて、左折すると南隅櫓(重文)がある。 [交通]伊予大洲駅-(徒歩/約30分)-大洲城天守 |
||
| 伊予国・宇和島城(鶴島城 / 丸串城 / 板島城) | ||
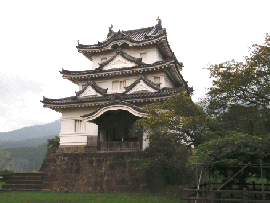 |
■城の種別 平山城 ■築城者 藤堂高虎 ■築城年 慶長元年(1596年) ■主な遺構 天守(重文) / 上り立ち門 |
|
| 天守 | ||
| 宇和島駅前から西へ、56号線を左折する。右手に見える桑折武家長屋門から城山に登る。宇和島城には慶長19年(1614年)に入城した伊達氏により改修された天守(重文)と“上り立ち門”が現存している。南側の“上り立ち門”から56号線を左折すると山家清兵衛屋敷跡に和霊神社がある。56号線は城を回りこむように北西に進路を変える。左手に桑折武家長屋門が見え、しばらくすると56号線は北東に進路を変える。和霊公園を左折すると、石造りでは日本一と云われる大鳥居が見える。須賀川を太鼓橋で渡ると承応2年(1653年)創建の和霊神社がある。川沿いに西へ進むと浄念寺や多賀神社がある。東へ戻り橋を渡り南へ進むと56号線と合流、320号線を左折すると宇和島駅に至る。駅の南東5分程のところに龍光院がある。 [交通]宇和島駅-(徒歩/約25分)-宇和島城天守 |
||
| 土佐国・岡豊おこう城 |
||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 秦(長宗我部)能俊 ■築城年 鎌倉時代(1185年頃〜1333年)初期 ■主な遺構 石垣 / 土塁 / 曲輪 / 空堀 |
|
| 詰(本丸)跡 | ||
| 高知県南国市街の北西部、香長(かちょう)平野の北西端にある。JR土讃本線・土佐大津駅の西側を通る252号線を北上する。国分川を渡ると左手方向に岡豊山(標高97m)があるが、北側を通る384号線側から廻り込まなければならない。高知県立歴史民俗資料館の裏手、南側に位置している。 [交通]JR土讃本線・高知駅-(バス)-歴民館入口 |
||
 |
鎌倉時代(1185年頃〜1333年)初期に、信濃秦氏の一族・秦能俊が土佐へ入国する。長岡郡宗我部郷の地を拠点として、宗我部氏を称する様になった。香美郡にも宗我部氏が居たため、それぞれの郡名から“長宗我部氏”と“香宗我部氏”と称する様になった。正治3年
/ 建仁元年(1201年)の書状に「香宗我部」の記述があり、この時期には既に区別されていた。 岡豊城は秦能俊が土佐へ入国後に築城、南北朝時代に修築して戦国時代には城郭としての規模を整えたと云われている。 応仁の乱(1467年〜1477年)の後に土佐守護の権力が失墜、長宗我部氏 / 本山氏 / 山田氏 / 吉良氏 / 安芸氏 / 大平氏 / 津野氏 の“土佐七雄”と呼ばれた豪族が台頭する。永正5年(1508年)長宗我部兼序のとき、本山氏 / 山田氏 / 吉良氏 などの連合軍により岡豊城は落城する。永正8年(1511年)本山氏 / 山田氏と和睦、岡豊城主に復帰する。永正15年(1518年)頃に長宗我部国親は土佐の有力大名へと成長、一条氏 / 本山氏 / 安芸氏 とともに土佐を四分する様になった。天正2年(1574年)長宗我部国親の子・元親の代に土佐を統一、天正13年(1585年)には四国を統一した。同年に羽柴秀吉の四国征伐に敗れ、土佐一国に減封される。 天正16年(1588年)大高坂山城(現高知城)に本拠を移したが、治水の悪さから再び岡豊城を本拠とした。天正19年(1591年)浦戸城を築城して本拠を移し、岡豊城は廃城となった。 |
|
| 長宗我部氏岡豊城址碑(四の段) | ||
 |
||
| 岡豊城跡碑(詰跡) | ||
 |
 |
 |
| 四の段からの眺望 | 虎口 | 石垣 |
| 土佐国・国分寺 |
||
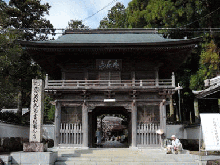 |
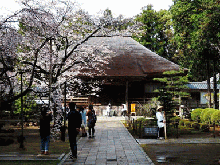 |
 |
| 国分寺山門 | 国分寺本堂 | 国分寺大師堂(札所) |
| この辺りは古代から栄えた地域で、32号線を越えた東側に国分寺や国府跡がある。天平13年(741年)創建の |
||
| 土佐国・国司館跡 | ||
 |
 |
 |
| 国司館跡 | 「土佐のまほろば」国府の碑 | 紀貫之邸跡 |
| 国分寺の東側、徒歩10分余りのところに土佐国・国司館跡がある。土佐日記の著者・紀貫之は、国司として延長8年(930年)から |
||
| 土佐国・国衙跡 | ||
 |
 |
国衙(こくが)は、日本の律令制において国司が地方政治を遂行した役所。国府跡の東側、廻りを水田に囲まれたところにある。 |
| 土佐国衙跡 | ||
| 土佐国・浦戸城 | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 本山茂宗 ■築城年 天文年間(1532年〜1554年) ■主な遺構 石垣 |
|
| 浦戸城趾碑 | ||
| 桂浜の北部丘陵の浦戸山(標高59m)は土佐湾(太平洋)に面している。紀貫之の土佐日記にも浦戸の港として記載されている。古代から水運の拠点となっていたところ。 浦戸山には鎌倉時代〜室町時代初期に城砦が存在していたとされる。天文年間(1532年〜1554年)本山茂宗 慶長4年(1599年)長宗我部元親の死後に家督を継いだ四男・盛親は、関ヶ原の戦いに西軍として参戦して改易となる。大坂の陣に大坂方として参陣するが、敗北となり逃走する。捕えられて京都の六条河原で6人の子女とともに斬首され、嫡流は断絶した。 慶長5年(1600年)山内一豊が代わって土佐藩主となり、慶長6年(1601年)に入城した。この地は手狭であることから、高知城築城に着手する。慶長8年(1603年)に移転、浦戸城は廃城となった。廃城後も高知城築城に資材が使われた。 [交通]JR土讃本線・高知駅-(バス)-歴民館入口 |
||
 |
龍馬記念館前 |
|
| 城八幡 / 大山祇神社 | ||
| 土佐国・高知城(大高坂城 / 河中山城) | ||
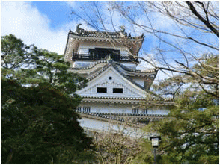 |
■城の種別 平山城 ■築城者 大高坂松王丸 ■築城年 南北朝時代(1336年〜1392年) ■主な遺構 天守(重文) / 追手門(重文) / 本丸御殿(重文) |
|
| 天守 | ||
| 高知駅から32号線を南へ、追手筋を右折すると、突き当たりに高知公園がある。大高坂松王丸が築城した城は、興国2年(1341年)廃城となる。天正15年(1587年)長宗我部元親が跡地に築城、天正19年(1591年)浦戸城に移り廃城となる。現在の城は、山内一豊が慶長6年(1601年)に築城したもの。延享4年(1747年)に天守が再建される。 [交通]JR土讃線・高知駅-(徒歩/約25分)-高知城 |
||
| 阿波国・徳島城(渭山城 / 渭津城) | ||
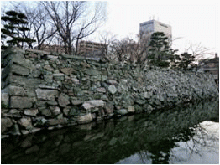 |
■城の種別 平山城 ■築城者 蜂須賀家政 ■築城年 天正13年(1585年) ■主な遺構 石垣 / 堀 / 庭園 ■主な再建造物 鷲の門 |
|
| 石垣 | ||
|
徳島駅の北側に徳島城がある。徳島駅より南東へ進む。左折してJR牟岐線を越えると、右手に石垣と堀がある。文永9年(1272年)河野通純が築城したとも、至徳2年(1385年)細川頼之が築城したとも云われている。天正10年(1582年)長宗我部元親が侵攻、阿波が平定される。現在の城は、天正13年(1585年)四国征伐に功のあった蜂須賀家政が築城したもの。徳島城が廃城となった後も、正門だった鷲の門は残されていた。昭和20年(1945年)徳島大空襲によって焼失するが、平成元年(1989年)復元される。 |
||
| 阿波国・撫養むや城(岡崎城 / 林崎城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 小笠原将監 ■築城年 不明 ■主な遺構 石垣 ■主な再建造物 模擬天守 |
|
| 模擬天守 | ||
|
鳴門駅から28号線を南へ進む。撫養町斉田交差点を左折して東へ進むと、突き当りに妙見神社の鳥居がある。石段を登ると、妙見山頂上に模擬天守がある。古くは小笠原氏の居城と云われている。三好氏配下の四宮氏が城主となるが、天正10年(1582年)長宗我部元親が阿波国へ侵入、配下の真下飛騨守が守備をする。天正13年(1585年)蜂須賀家政が阿波国の領主となる。徳島城の支城として阿波九城を置き、撫養城は益田正忠が城番となる。一国一城令により、寛永15年(1638年)廃城となる。 |
||