| 山城国 最新の追加 | ||
| 山城国・本願寺ノ城(山科本願寺) | ||
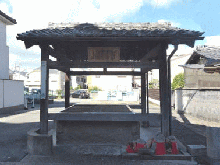 |
■城の種別 平城 ■築城者 蓮如 ■築城年 文明15年(1483年) ■主な遺構 土塁 / 井戸 |
|
| 御指図の井戸 | ||
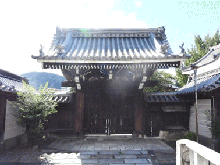 |
 |
 |
| 西本願寺山科別院山門 | 西本願寺山科別院本堂 | 東本願寺山科別院(東御坊)山門 |
 |
京都市営地下鉄東西線・東野駅の西、徒歩5分ほどのところに西本願寺山科別院がある。西本願寺山科別院から北に進むと、すぐに東本願寺山科別院(東御坊)がある。西本願寺山科別院や東本願寺山科別院(東御坊)は、本願寺ノ城(山科本願寺)城域の東端になる。 [交通]京都市営地下鉄東西線・東野駅-(徒歩5分)-西本願寺山科別院 |
|
| 東本願寺山科別院(東御坊)本堂 | ||
| 寛正6年(1465年)現:京都市東山区にあった大谷本願寺が延暦寺宗徒の攻撃をうけ破壊されると、8世・蓮如は文明3年(1471年)に造営された越前吉崎御坊に移った。文明10年(1478年)山科本願寺の造営が開始され、文明15年(1483年)に概ね完成したと云われている。明応8年(1499年)蓮如は85歳で没する。実如 / 証如 と受け継がれ、山科本願寺は本格的に城郭化していった。天文元年(1532年)細川晴元・六角定頼の軍勢によって陥落、証如は明応6年(1497年)に造営された大坂石山本願寺に避難した。 | ||
| 城域は京都市営地下鉄東西線・東野駅の西に位置、南北に1km / 東西に0.8km に及んでいた。北は安祥寺中学校辺り / 南は1号線や東海道新幹線の南側
/ 西は西宗寺の東側 / 東は東本願寺と西本願寺との西側 になる。周囲を幾重にも土塁と堀で囲んでいた。 |
||
 |
||
| 山科中央公園の土塁 | ||
 |
 |
遺構は土塁や堀跡がところどころに点在する。東本願寺山科別院(東御坊)から西に15分ほどのところに、山科中央公園がある。東西75m / 南北60m
/ 高さ7m の内寺内(二の丸)と外寺内(三の丸)との間の土塁跡が残る。高さ7m の土塁に |
| 山科中央公園の土塁 | 山科中央公園の土塁 / 土塁に登る階段 | |
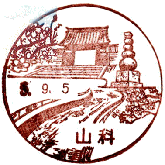 |
山科中央公園から道路を挟んだ西側に山科郵便局がある。風景印は、小野小町ゆかりの随心院 / 随心院の小町文塚 / 琵琶湖疎水 の図柄になっている。 |
|
| 山科郵便局風景印 | ||
 |
 |
東野駅の北東、徒歩10分ほどところに南殿があった。南殿は蓮如の隠居施設と云われていたが、堀 / 土塁 / 柵 / 物見櫓跡 などの防御施設が確認されている。南殿跡に光照寺(東本願寺)がある。 |
| 光照寺山門 | 光照寺本堂 | |
| 東野駅から光照寺に向かう途中、音羽川小学校の少し北側(音羽乙出町)に御指図の井戸(おさしずのいど)がある。蓮如がこの井戸の所まで来て畳を敷かせて座り,杖で指図したところを掘ると清水が湧き出たと云われている。 |
||
 |
 |
 |
| 長福寺山門 | 長福寺本堂 | 櫓風建築物 |
 |
山科中央公園からJR東海道本線・山科駅に向かう途中に、山科別院(東本願寺)長福寺がある。享保17年(1732年)17世・真如が東本願寺境内にあった長福寺を、現在地に移築した。 |
|
| 蓮如銅像台座 | ||
| 山城国・聚楽第(聚楽亭 / 聚楽城) |
||
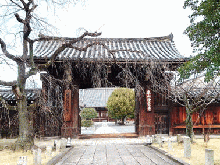 |
■城の種別 平城 ■築城者 豊臣秀吉 ■築城年 天正14年(1586年) ■主な遺構 京都・大徳寺の唐門(撮影禁止) / 京都・妙覚寺の大門 / 萩・常念寺の山門 は、聚楽第から移築されたと云われている。 |
|
| 妙覚寺大門(移築城門) | ||
 |
聚楽第から移築されたと云われている妙覚寺の大門から聚楽第跡まで歩く。地下鉄烏丸線・鞍馬口駅から鞍馬口通を西に進む。5分ほどのところを左折して南に進むが、民家の間を通る狭い小路で解りづらい。地元の方に教えていただき、南西方向にある妙覚寺を目指して進む。 |
|
| 妙覚寺本堂 | ||
| 妙覚寺は永和4年(1378年)四条大宮にあった小野妙覚の邸に創建された。文明15年(1483年)室町幕府将軍・足利義尚の命により、二条衣棚(現・京都市中京区)に移転した。天文5年(1536年)天文法華の乱で伽藍が全焼し堺に避難、天文17年(1548年)二条衣棚の旧地に再建された。 |
||
 |
妙覚寺から西方向に進む。大宮通を左折して南に進むと、左手に名和児童公園がある。ここは、平安時代の一条院跡 / 南北朝時代の名和長年戦死の地 /
安土桃山時代の聚楽第跡 / 江戸時代の大名の藩邸跡 などになる。京都は1200年の歴史があるので、同じ場所でいろいろな出来事が起こっている。 [交通]妙覚寺-(徒歩約30分)-名和児童公園 |
|
| 名和児童公園 |
||
| 平安時代中期、平安京北東に隣接して里内裏の一条院が置かれた。東西2町あり、西側1町が御所 / 東側1町には財政や物資を調達する別納(べつのう)があった。もともとは藤原師輔(もろすけ)から伊尹(これただ)と為光(ためみつ)の兄弟に引き継がれた屋敷があり、時を経て東三条院(藤原詮子)に献上された。長保元年(999年)内裏焼失後は、東三条院の子・一条天皇の里内裏となった。この別納が中宮彰子の直廬(じきろ / 宿泊所)に使用され、彰子に仕えた紫式部もここにいた。宮中の様子を書いた紫式部日記に出てくる内裏とはこの一条院のことで、ある。文化人が集まる華やかな場所だった。 | ||
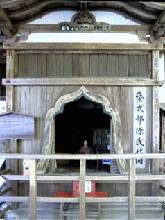 |
紫式部は藤原宣孝に嫁ぐが、長保3年(1001年)結婚後3年程で夫が死去する。その後、石山寺で源氏物語を書き始める。源氏物語の評判を聞いた藤原道長に召し出されて、一条天皇中宮の彰子(藤原道長の長女
/ 後の上東門院)の女房(家庭教師)として仕える。 紫式部は宮仕えをしながら、藤原道長の支援の下で源氏物語を完成させた。寛弘5年(1008年)には完成していたと推測されている。 |
|
| [参考]石山寺 紫式部源氏の間 | ||
 |
元弘元年(1331年)後醍醐天皇は討幕計画が六波羅探題に察知されて隠岐島に流罪となる。名和長年は伯耆(ほうき)国・名和の豪族で、元弘3年(1333年)隠岐島を脱出した後醍醐天皇を船上山(鳥取県東伯郡)に迎え討幕に加わる。 |
|
| 贈従一位名和長年公殉節之所碑 | ||
 |
 |
名和児童公園からすぐに中立売通(なかだちうりどおり / なかだちゅうりどおり)と交差、北西側角に聚楽第址 石柱がある。側面に「此付近 大内裏及聚楽第東濠跡」と彫られている。 |
| 聚楽第址 石柱 | ||
|
中立売通の名称は沿道に、店舗を構えない立ち売りが多かったことに由来しているが、平安京の頃は正親町小路(おおぎまちこうじ)と呼ばれていた。 |
||
|
聚楽第は天正14年(1586年)に着工され、天正15年(1587年)に竣工した。本丸を中心に、西の丸 / 南二の丸 から成り堀を巡らせていた。 |
||
 |
 |
聚楽第東濠跡の聚楽第址 石柱から中立売通を西に進むと、すぐ左手の聚楽第西濠跡に、此付近 聚楽第址 石柱 & 案内板 / 平安宮大蔵省(おおくらしょう)跡 石柱 & 案内板 がある。 |
| 此付近 聚楽第址 石柱 | 平安宮大蔵省跡 石柱 | |
 |
さらに西に進むと、すぐ左手に唐津小笠原藩邸跡 石柱がある。 |
|
| 唐津小笠原藩邸跡 石柱 | ||
 |
 |
 |
| 京都大宮丸太郵便局風景印 | 京都聚楽郵便局風景印 | 朱雀門跡 石柱 |
 |
京都大宮丸太郵便局〜京都聚楽郵便局〜京都西ノ京職司郵便局を経て、JR山陰本線・二条駅に向かう。京都大宮丸太郵便局と京都聚楽郵便局風景印は、二条城東南隅櫓
/ 二の丸庭園 の図柄になっている。京都聚楽郵便局から京都西ノ京職司郵便局に向かう途中、111号(二条停車場円町線)の東側に朱雀門(すざくもん)跡 石柱がある。 |
|
| 京都西ノ京職司郵便局風景印 | ||
| 丹後国・宮津城 |
||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 細川藤孝 ■築城年 天正8年(1580年) ■主な遺構 太鼓門(馬場先御門) / 石垣 ■主な再建造物 大手川城壁 |
|
| 宮津城太鼓門(馬場先御門) | ||
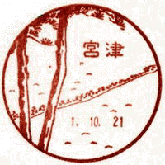 |
 |
|
| 宮津郵便局風景印 | 大手川城壁(大手橋〜中橋) | |
 |
京都丹後鉄道・宮津駅から606号線を北西に進む。 |
|
| 大手川城壁 / 宮津城太鼓門 | ||
|
天正6年(1579年)織田信長の命を受けた明智光秀 / 長岡藤孝(細川藤孝)は、丹後国に侵攻する。南北朝時代から丹後国守護であった足利氏の一門・一色氏は、戦国時代にも丹後の大名として続いていたが侵攻によって滅亡した。 |
||
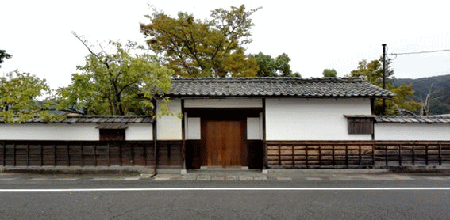 |
 |
|
| 大村家長屋門 | 細川ガラシア像 | |
|
宮津小学校北西角から西に進み、大手川に架かる中橋を渡る。すぐの十字路を右折して北に進むと、すぐ右手の武家屋敷・大村家跡に長屋門 / 隣接する公園に細川ガラシア像
がある。市役所から京口町まで |
||
 |
大手川に架かる大手橋を渡り、本町通りを西に進む。5分ほどの変則十字路と右折して北に進むと、すぐ右手に享保年間創業の茶六本館(重文)がある。 |
|
| 茶六本館 | ||
| 山城国・二条城 | ||
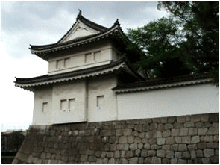 |
■城の種別 平城 ■築城者 徳川家康 ■築城年 慶長8年(1603年) ■主な遺構 二の丸御殿(国宝) / 二の丸御殿障壁画(重文) / 櫓 / 門 / 石垣 / 堀 22棟の建造物が重文指定 |
|
| 隅櫓 | ||
| JR二条駅から、二条駅東交差点を左折する。押小路通りを右折して東へ進むと、左手にある。堀沿いに一周すると、新鮮味がある。将軍の上洛の際の宿泊施設として築城される。15代将軍徳川慶喜が大政奉還を行った舞台としても知られている。平成6年(1994年)古都京都の文化財として、ユネスコ世界文化遺産に登録されている。 [交通]JR山陰本線 ・二条駅-(徒歩/約10分)-二条城堀 |
||
| 山城国・伏見城(桃山城 / 指月城 / 木幡山城) | ||
 |
■城の種別 |
|
| 模擬天守 | ||
| JR奈良線・桃山駅から東へ、最初の交差点を左折して道なりに進む。15分ほどすると、突き当たりに伏見桃山城運動公園がある。伏見城は3度に渡って築城されている。文禄元年(1592年)指月山に築かれた指月山伏見城
/ 地震崩壊後の慶長元年(1596年)に木幡山に再築された木幡山伏見城 / 関ヶ原の戦いで落城後の慶長7年(1602年)焼失跡に再建される。 [交通]JR奈良線・桃山駅-(徒歩/約15分)-大手門 |
||
| 山城国・勝竜寺城(小竜寺城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 畠山義就 ■築城年 室町時代 ■主な遺構 土塁 / 空堀 ■主な再建造物 模擬櫓 / 模擬石垣 |
|
| 模擬櫓 / 模擬石垣 | ||
|
JR東海道本線・長岡京駅より東へ、すぐの交差点を右折して南へ進む。東神足交差点の先、右手に勝竜寺城がある。南北朝時代から江戸時代初期に存在していた城。京都盆地の西南部、小畑川と犬川の合流地点に位置する。西国街道と久我畷が交差する要衝で、京都では山崎城につぐ防衛拠点であった。山城守護・畠山義就が郡代役所として築城したと云われ、郡代の政庁から城郭に発展したと云われている。戦国時代末期には松永久秀や三好三人衆の属城となっていた。永禄11年(1568年)観音寺城の戦いで、織田信長は近江守護である六角義賢・義治父子を降す。続いて三好三人衆の岩成友通が守る勝竜寺城を攻撃、降伏・開城させる。三好三人衆は畿内から掃討され、阿波に押し戻される。慶安2年(1649年)に廃城となる。 |
||
| 山城国・淀城(新淀城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 松平定綱 ■築城年 元和9年(1623年) ■主な遺構 石垣 / 堀 / 天守台 |
|
| 石垣 | ||
| 京阪電鉄・淀駅下りホームから石垣と堀が見える。茶々が居住した古淀城跡の遺構は残っていない。二の丸跡に、応和年間(961年〜964年)創建と云われている与杼神社がある。慶長12年(1607年)建立の拝殿は重文。左隣に明治18年(1885年)創建の稲葉神社がある。 [交通]京阪電鉄・淀駅前 |
||
| 但馬国・豊岡とよおか城(亀城 / 神武山 |
||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 山名祐豊 ■築城年 長享2年(1489年)以前 ■主な遺構 本丸跡 / 萩の丸跡 / 笠の丸跡 |
|
| 豊岡城本丸跡 |
||
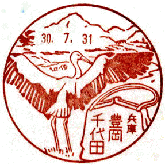 |
JR山陰本線 / 京都丹後鉄道・豊岡駅東口からすぐの豊岡駅前交差点を右折する。すぐのY字路を左方向に道なりに進む。すぐ右手に豊岡千代田郵便局がある。風景印は、円山川からの来日岳
/ 天然記念物・コウノトリ / 特産・かばん の図柄になっている。 |
|
| 豊岡千代田郵便局風景印 | ||
| 但馬国守護大名・山名持豊(宗全)により、長享2年(1489年)以前に築城された木崎城(城崎城)が始まりと云われている。 |
||
 |
慶長3年(1598年)杉原長房が豊後国杵築より入封する。慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いで杉原長房は西軍に与して丹後国田辺城を攻めた。妻が浅野長政の娘だったため、浅野長政の取り成しで旧領を安堵された。承応2年(1653年)3代・杉原重玄が嗣子なく没して改易となり、豊岡は天領となり豊岡城は廃城となった。 豊岡城跡一帯は神武山公園になっている。 |
|
| 笠の丸跡 | ||
| 但馬国・出石いずし城(高城) |
||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 山名持豊 ■築城年 天正2年(1574年) ■主な遺構 辰鼓楼 / 石垣 / 堀 ■再建造物 本丸東隅櫓 / 本丸模擬西隅櫓 / 登城門 / 登城橋 |
|
| 本丸模擬西隅櫓 | ||
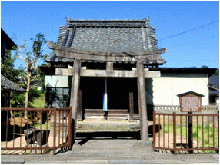 |
出石バス停から2号線を北に進む。すぐの交差点を過ぎると、すぐにT字路がある。直進すると、すぐ左手に水天宮がある。水天宮は小出吉英が菩堤寺として吉祥寺を創建、鎮守として建立したのが始まり。明治の神仏分離令により、明治4年(1871年)頃に現地に移転した。 | |
| 水天宮 | ||
 |
 |
T字路まで戻り、東に進む。すぐ右手に福成寺 / すぐ右手に勝林寺 と続く。福成寺は出石城が築城されたとき、日野辺街道からの敵の侵入を防ぐために現在地に移された。 |
| 福成寺 | 勝林寺 | |
 |
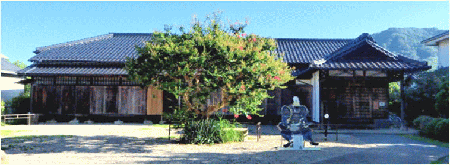 |
|
| 家老屋敷長屋門 | 家老屋敷 | |
| 勝林寺の通りを挟んだ反対側の長屋門を潜ると、 家老屋敷がある。出石城内堀の近くに位置、上級武士の居住があった内町通りに面している。建物の外観は平屋建に見えるが、内部には隠し階段が仕組まれた二階建になっている。 | ||
 |
 |
|
| 有子山城・出石城全景 | 登城橋 / 登城門 | |
| 家老屋敷からすぐのT字路を直進して道なりに南に進むと、登城橋河川公園がある。 [交通]JR山陰本線・京都丹後鉄道豊岡駅-(バス/30分)-出石バス停-(徒歩5分)-出石城 |
||
| 天正2年(1574年)山名祐豊は有子山(ありこやま)城を築城、山麓には下館が置かれた。 |
||
 |
 |
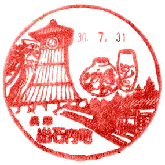 |
| 辰鼓楼 | 出石内郵便局 | 出石内郵便局風景印 |
| 北側の三の丸跡に明治4年(1871年)建立の辰鼓楼がある。城主の登城を知らせる太鼓を叩く楼閣であった。明治14年(1881年)より時計台となった。明治11年(1878年)札幌農学校演武場に建立の時計塔(札幌時計台)は、明治14年(1881年)より時計台となった。どちらが時計台として日本最古になるか、はっきりしないと云う。道路を挟んだ西側に、 |
||
 |
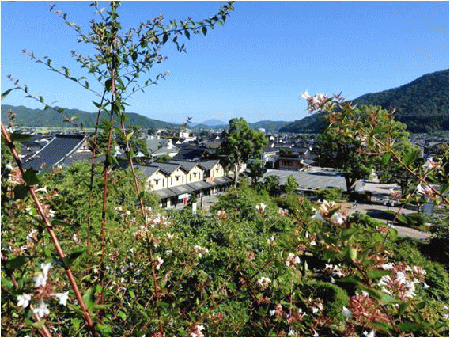 |
|
| 感応殿 | ||
 |
||
| 本丸背後の石垣 | 本丸からの眺望 | |
| 本丸跡に明治に入って旧家臣によって創建された、仙石秀久を祀った |
||
 |
 |
再建された本丸東隅櫓は樹木が生い茂り、見えづらかった。本丸東隅櫓の東側に慶長9年(1604年)創建の有子山稲荷神社への157の石段 / 37の鳥居 がある。城郭内にありながら、身分を問わず参詣が許可されていた。 |
| 本丸東隅櫓 / 塀 | 有子山稲荷神社鳥居 | |
| 本丸背後の石垣の切れ目から登ろうとして足を痛め、有子山稲荷神社 / 有子山城 には行っていない。 | ||
| 丹波国・亀山城(亀岡城 / 亀宝城 / 霞城) | ||
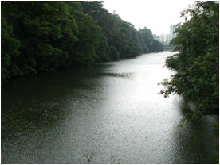 |
■城の種別 平山城 ■築城者 明智光秀 ■築城年 天正6年(1578年) ■主な遺構 石垣 / 堀 新御殿門(長屋門)が、亀岡市立千代川小学校に移築され現存する。 |
|
| 堀 | ||
| JR亀岡駅から南へ、404号線を左折する。さらに右折して25号線を南へ進む。堀が見える先の右手にある。明智光秀によって、丹波統治の拠点として築城される。現在は宗教法人大本の本部が置かれている。 [交通]JR山陰本線 ・亀岡駅-(徒歩/約10分)-亀山城堀 |
||
| 丹波国・園部城 | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 小出吉親 ■築城年 元和5年(1619年) ■主な遺構 本の丸表門(櫓門) / 巽櫓 / 太鼓櫓 / 石垣 |
|
| 巽櫓 | ||
| JR園部駅から東へ、9号線(山陰道)を左折して北西へ進む。園部本町交差点を左折して南へ進むと、右手に園部高校がある。正門は本の丸表門(櫓門)、左手に巽櫓がある。敷地は本丸跡になる。当初は陣屋であったが、明治元年(1868年)に明治天皇の行在所として城構えとなる。 [交通]JR山陰本線 ・園部駅-(徒歩/約20分)-園部高校 |
||
| 丹波国・福知山城(臥龍城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 塩見頼勝 ■築城年 室町時代後期 ■主な遺構 二の丸銅門番所 / 石垣 ■主な再建造物 大天守 / 小天守 / 釣鐘門 |
|
| 二の丸銅門番所 | ||
| JR福知山駅から北へ、24号線(お城通り)を右折して東へ進むと右手にある。天正7年( 1579年)丹波国を平定した明智光秀が、近世城郭へと大修築する。市役所付近にあった銅門番所は、本丸に移築されている。 [交通]JR山陰本線 / 福知山線・福知山駅-(徒歩/約15分)-福知山城 |
||
| 丹波国・篠山ささやま城(桐ヶ城) | ||
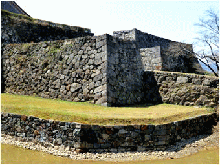 |
■城の種別 平山城 ■築城者 徳川家康 ■築城年 慶長14年(1609年) ■主な遺構 石垣 / 堀 ■主な再建造物 御殿(大書院) |
|
| 石垣 | ||
|
JR福知山線篠・山口駅より東へ、篠山口駅東交差点を左折する。299号線を道なりに進む。丹南弁天交差点から北東に進路が変わる。東吹下交差点を右折して、36号線を東へ進む。枡形を右方向へ、すぐに左方向へ進む。左手に篠山市役所、右手に篠山城がある。慶長14年(1609年)徳川家康は、松平康重を常陸国・笠間城から丹波国・八上城に移封、新城を15ヶ国20の大名による天下普請により築城する。山陰道の要衝である丹波篠山盆地に城を築くことにより、大坂の豊臣氏を始めとする西国大名の抑えとする目的があったと云われている。明治維新後、城郭の遺構は大書院を残してほとんどが取り壊される。大書院は昭和19年(1944年)失火により焼失するが、平成12年(2000年)に復元される。城下町は、国の重要伝統的建造物群保存地区になっている。 |
||
| 丹後国・田辺城(舞鶴城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 細川藤孝 ■築城年 天正7年(1579年) ■主な遺構 石垣 / 堀 / 庭園 ■主な再建造物 大手門 / 二層櫓 / 塀 |
|
| JR / 京都丹後鉄道宮津線・西舞鶴駅から北西に進む。すぐに右折して北に進む。 [交通]JR / 京都丹後鉄道宮津線・西舞鶴駅-(徒歩5分)-舞鶴公園 |
||
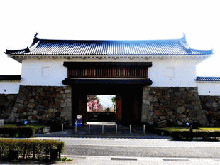 |
 |
 |
| 大手門 | 二層櫓 | 大手門 / 塀 |
| 細川忠興は戦功により豊前国小倉に転封する。京極高知が丹後国12万3千石を与えられ、宮津城を再築して本拠地とする。田辺城の建造物は、破壊されたと云われている。 |
||
 |
大手門の道路を挟んだ西側明倫館跡に、舞鶴市立明倫小学校がある。天明年間(1781年〜1789年)田辺藩第・牧野宣成により明倫齋が創設される。文久年間(1861年〜1864年)に明倫館と改称された。明治5年(1872年)の学制発布に伴い、明倫小学校になる。正門は明倫館当時のものを移築したもの。 |
|
| 明倫館門 | ||
| 舞鶴公園の近くには、北から舞鶴引土郵便局 |
||
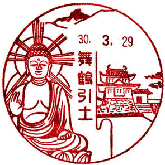 |
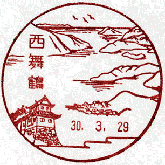 |
舞鶴引土郵便局風景印は、愛宕山 / 阿弥陀如来座象(重文) / 田辺城 の図柄になっている。西舞鶴郵便局風景印は、 |
| 舞鶴引土郵便局風景印 | 西舞鶴郵便局風景印 | |