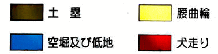| 最新の追加 | ||
| 下総国・相模台城(岩瀬城 | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 北条長時 建長元年(1249年) ■主な遺構 土塁 |
|
| 松戸中央公園 | ||
 |
 |
JR常磐線・松戸駅東口から連絡橋を東に進むと、突き当りにイトーヨーカドーがある。戸定通りに降りて南に進むと、5分ほどの交差点の信号機に「法務局・検察庁・裁判所↑」の標識がある。交差点北東側の台地が松戸中央公園 / 南東側の台地が相模台公園 になる。相模台公園への急な階段がある。 |
| 交差点 / 相模台公園 | 切通し(通称・地獄坂) | |
 |
交差点を左折して、切通し(通称・地獄坂)を道なりに登る。登り切ると、左手に松戸中央公園入口 / 右手に法務局・検察庁・裁判所 がある。 |
|
| 松戸中央公園入口 | ||
| 建長元年(1241年)房総三国守護で6代執権となった北条長時が館を構えたのが始まりと云われている。子・久時 / 久時の子・守時と続き、嘉暦年間(1326年〜1329年)に最後の執権となった15代執権・北条相模守高時が入道して崇鑑と号して居住した。このことから、相模台城と呼ばれるようになった。 永禄7年(1538年)第一次国府台合戦では、相模台城周辺で激戦となった。北条氏綱・氏康父子の軍によって、足利義明は討ち死にして小弓公方は滅亡した。その後相模台城は小金城の支配下となった。 相模台の丘陵には、松戸中央公園 / 相模台公園 / 法務局 / 地方裁判所 / 聖徳大学 / 相模台小学校 などが建ち並ぶ。往時を偲ばせるものはほとんどない。 |
||
 |
 |
 |
| 経世塚 | 相模台戦跡碑 | |
| 松戸中央公園の北側にある聖徳大学構内に、国府台合戦で落命した足利義明父子らを弔った経世塚 / 相模台戦跡碑 がある。 |
||
 |
主郭は法務局・検察庁・裁判所から西に延びる相模台公園にあったと云われている。工事が行われていたため、地獄坂を下りて戸定通りから急階段を登る。 |
|
| 相模台公園 | ||
| 下総国・松戸城(松渡城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■主な遺構 曲輪 / 空堀 / 土塁 |
|
| 戸定が丘歴史公園 | ||
 |
JR常磐線・松戸駅東口から連絡橋で東に進むと、突き当りにイトーヨーカドーがある。戸定通りに降りて南に進むと、5分余りの交差点の信号機に「法務局・検察庁・裁判所↑」の標識がある。交差点北東側の台地が松戸中央公園 / 南東側の台地が相模台公園 になる。相模台公園への急階段がある。戸定通りを南に進み、すぐの交差点を右折して北西に進む。 |
|
| 戸定が丘歴史公園・茅葺門 | ||
| 松戸城は、戸定が丘歴史公園や千葉大学園芸学部の辺りにあったと云われている。戸定が丘歴史公園と千葉大学園芸学部はフェンスで仕切られている。 永禄7年(1538年)第一次国府台合戦では、小田原北条軍が江戸川を渡って松戸城に陣を構えた。 |
||
 |
廃城年は解っていないが、明治17年(1884年)最後の水戸藩主・徳川昭武の別邸・戸定邸(とじょうてい)が現:戸定が丘歴史公園に造営された。 | |
| 戸定邸入口 | ||
| 下総国・飯沼城 | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 海上氏 建久年間(1190年〜1199年)以降 |
|
| 円福寺大師堂 | ||
 |
 |
 |
| 円福寺仁王門 |
円福寺観音堂 | 円福寺五重塔 |
 |
銚子電鉄・観音駅より北に進むと、すぐ右手に弘仁年間(810年〜824年)創建と云われる円福寺がある。隣接して、養老年間(717年〜724年)創建と云われる龍蔵権現が始まりの銚港神社がある。明治の神仏分離によって銚港神社となった。 [交通]銚子電鉄・観音駅-(徒歩5分)-円福寺 |
|
| 銚港神社 | ||
|
飯沼城は円福寺付近に築城され、城址は円福寺の境内になっている。 |
||
| 下総国・銚子陣屋(飯沼陣屋) |
||
 |
■城の種別 陣屋 ■築城者 大河内松平氏 享保2年(1717年) ■主な遺構 井戸 |
|
| 陣屋町公園 | ||
| 銚子電鉄・観音駅より北に進む。5分ほどの馬場町交差点の手前の変則十字路を左折して西に進む。5分足らずの左手に陣屋町公園がある。 [交通]銚子電鉄・観音駅-(徒歩10分)- |
||
 |
 |
 |
| 旧陣屋跡碑 | 井戸 | 熊野神社 |
|
享保2年(1717年)高崎藩の飛び地を管理するため、大河内松平氏によって陣屋が置かれた。享保2年(1717年)当時の石高は5619石だった。郡奉行1名と代官2名が常駐、陣屋は明治まで続いた。 |
||
| 下総国・中島城(海上城 | ||
 |
■城の種別 平山城(台城) ■築城者 海上常衡 建久年間(1190年〜1199年) ■主な遺構 空堀 / 土塁 / 曲輪 |
|
| 中島城遠望 | ||
 |
JR成田線・椎柴駅より北東に進む。すぐに71号線に突き当たり、右折して東に進むと野尻町交差点で356号線に合流する。15分ほどすると左手に商業施設があり、T字路を右折して南西に進む。すぐにJR成田線の一本松踏切を越え、見通しの良い道を進む。堀跡を思わせる切通になっている坂を登ると、左手の電柱に「中島城址
←」標識がある。 [交通]JR成田線・椎柴駅-(徒歩40分)-中島城址 |
|
| 切通になっている坂 | ||
 |
 |
中島城は利根川に面した段丘の東端に築かれている。中島城は銚子地区で最大規模を誇り、東西500m / 南北400m 程に及ぶ。 台地の上に空堀を用いて曲輪を形成していたが、 |
| 中島城址入口の曲輪 | 奥にある曲輪 | |
|
平安時代末期、平常兼の十一男・常衡が下総国海上庄を領して海上(うなかみ)氏を名乗る。海上常衡は隣接する千田庄の下総藤原氏と密接な関係にあったが、千葉氏の初代当主とされる兄の千葉常重は下総藤原氏と対立していた。 |
||
| 下総国・小金城(大谷口城 / 開花城) |
||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 高城胤吉 天文6年(1537年) ■主な遺構 空堀 / 土塁 / 曲輪 |
|
| 大谷口歴史公園石標 | ||
| JR常磐線・北小金駅北口から本土寺参道を北西に進む。すぐに280号線と交差、左折して西に進む。5分ほどすると、右手に松戸大金平郵便局があり、5分ほどの十字路(郵便局から3本目)を左折する。突き当りを右折して西に進むと、すぐ左手に大谷口歴史公園がある。 [交通]JR常磐線・北小金駅-(徒歩15分)-大谷口歴史公園 |
||
| [寄り道]本土寺 | ||
 |
||
 |
||
| 本土寺山門 | ||
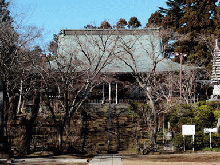 |
||
| 本土寺参道 | 本土寺本堂 | |
| 280号線との交差点を直進、松や杉の並木を道なりに進む。5分ほどの突き当りに、建治3年(1277年)創建の本土寺がある。本土寺は日蓮宗本山のひとつで、紫陽花と菖蒲で有名なところ。 | ||
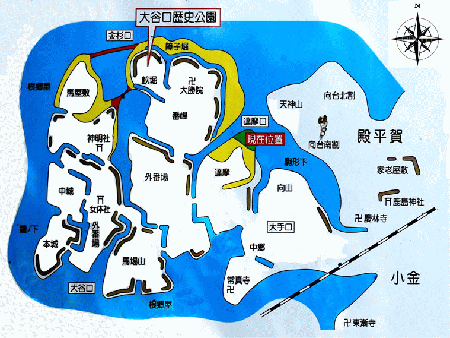 |
古利根川 / 中川 / 荒川 流域の低地帯を一望できる丘陵地帯にある。下総国北西部においては最大規模を誇った。北に金杉口 / 東に大手口 / 丑寅に達磨口 / 西に横須賀口 / 南に大谷口 を設け、横須賀口には家臣を住まわせた。達磨口跡の案内板に小金城復元略絵図があり、城域が解り易い。
|
|
| 小金城復元略絵図 | ||
|
戦国時代に高城氏の小金城下町 / 太日川(現:江戸川)の水運 / 水戸街道の宿場 として発展した。昭和35年(1960年)頃からの宅地開発により、多くの遺構が消失した。 |
||
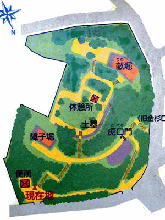 |
 |
 |
| 大谷口歴史公園地図 | 障子堀 | 虎口門跡 |
| 大谷口歴史公園入口に案内板があり、階段を登ると左手に障子堀がある。草木に覆われ、解りづらい。右手方向に下ると虎口門跡があり、金杉口に至る。 | ||
 |
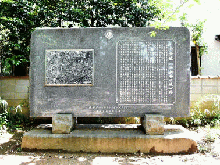 |
 |
| 曲輪 | 小金城跡碑 | 土塁 |
 |
 |
さらに階段を登ると曲輪があり、小金城跡碑 / 土塁 がある。小高いところに休憩所があり、奥の階段を下ると、右手に畝(うね)堀がある。 |
| 曲輪 | 畝堀 | |
 |
大谷口歴史公園入口まで戻り、車道を金杉口方向に進む。南側角に大谷口歴史公園石標がある。 |
|
| 大勝院山門 | ||
 |
 |
大谷口歴史公園入口まで戻り、車道を高地に沿って進む。往路に通ったT字路を直進すると、右手に達磨口跡がある。ここにある案内板に小金城復元略絵図がある。坂を登ると顕彰之碑がある曲輪
/ さらに小高いところに |
| 曲輪 | 小曲輪 | |
| 天文6年(1537年)小弓公方・足利義明に対抗するために高城胤吉によって築城され、根木内城より居城を移した。高城胤吉 / 高城胤辰 / 高城胤則
と3代53年の居城となった。 天文7年(1538年)と永禄6年(1563年)小田原北条氏と安房里見氏の国府台合戦では、小田原北条氏の勝利に貢献する。 永禄年間(1558年〜1570年)古河公方・足利義氏に敵対する関東管領・上杉憲政を擁立して関東へ侵攻した上杉謙信に備えて拡張が行われた。小田原北条氏の城跡で多く見られる畝(うね)堀や障子堀は、このときと云われている。 天正13年(1585年)千葉邦胤が家臣に殺害されると、千葉邦胤の娘婿・千葉直重(北条氏政の7男)が家督を相続する。高城胤則は小田原北条氏家臣として行動する事となった。 徳川家康の関東移封に伴い、徳川家康五男・武田信吉が入城する。信吉は文禄元年(1592年)に下総国佐倉城主として転封となり、小金城は文禄2年(1593年)に廃城となった。 |
||
| 下総国・国府台城(鴻之台城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 太田資忠 文明11年(1479年) ■主な遺構 空堀 / 土塁 |
|
| 江戸川対岸の土手道からの里見公園 | ||
 |
 |
京成電鉄・国府台駅から北に進むと、5分足らずで松戸街道と合流する。すぐ右手に寛治元年(1087年)創建の国府神社がある。松戸街道を隔てた反対側にある斜め左方向の坂を登ると、里見公園分園に至る。松戸街道の坂道を登って行くと、5分ほどの右手に国府台公園がある。国府があったところで、国衙(こくが)は野球場付近にあったと云われている。 |
| 国府神社 | 国府台公園 | |
|
国府台公園からすぐの国府台病院前交差点を左折すると、5分ほどで里見公園に突き当たる。右折して北に進むと、すぐ左手に里見公園に隣接して總寧寺がある。 |
||
| 江戸川〜里見公園分園 |
||
 |
京成電鉄・国府台駅から北に進むと、5分足らずで松戸街道と合流する。すぐに左折して江戸川堤防下の道を北に進む。車止めのあるところの右手に階段があり、登ると坂道になる。辿り着いたところは広大な若草グラウンドで、東側道路際に“里見公園分園B”の標識がある。この道を“里見公園”方面に北に進むと、行き止まりになる。 |
|
| 里見公園分園B | ||
 |
道路を隔てた南東側に“里見公園分園A”がある。“里見公園分園B”とともに国府台城域であるが、詳細は解らない。“里見公園分園A”は隠れた桜の名所になっている。“里見公園分園A”から“里見公園”方面に北に進む道は、両側に学校がある。突き当りを左折すると行き止まりになる。突き当りを右折して東に進むと、松戸街道に突き当たり左折して北に進む。 |
|
| 里見公園分園A | ||
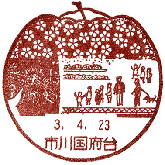 |
国府台病院前交差点を直進して、松戸街道を北に進む。5分ほどの左手に、市川国府台郵便局がある。風景印は、外枠は市川の梨 / 桜 / 民俗文化財・国府台の辻切り
/ 江戸川を望む里見公園 の図柄になっている。辻切りは、集落の出入口にあたる四隅の辻を霊力によって遮断するもの。注連縄(しめなわ)や大蛇を作って、人畜に害を与える悪霊や悪疫が集落に侵入するのを防ぐ。 |
|
| 市川国府台郵便局風景印 | ||
 |
 |
 |
| 藤棚 | 花壇 | 土塁 |
| 太日川(現:江戸川)と坂川の合流地点に隣接する河岸段丘にある細長い城郭だった。現在は、里見公園 / 總寧寺 / 学校 / 住宅地 になっている。南側の国府台城域である“里見公園分園A”や“里見公園分園B”と里見公園の間は、学校や住宅地で遮断されている。 国府台病院前交差点から里見公園に進むと、城跡とは思えないほど整備されている。北側の樹林に入ると城跡らしい雰囲気になり、堀切 / 空堀 / 土塁 が残っているが解りずらい。案内板などはなく、詳細は解らない。北側の樹林には、太平洋戦争中に幾つもの防空壕が掘られたところである。 |
||
 |
總寧寺は永徳3年(1383年)近江守護・佐々木氏頼(六角氏頼)によって近江国坂田郡寺倉村(現:米原市寺倉)に創建したのが始まり。享禄3年(1530年)戦乱によって焼失、遠江国掛川に常安寺として再建した。常安寺は永禄年間(1558年〜1570年)戦乱によって焼失。天正3年(1575年)北条氏政によって関宿宇和田(現:埼玉県幸手市)に再建、総寧寺の旧称になる。元和3年(1617年)徳川秀忠によって関宿内町(現:千葉県野田市)に移転、寛文3年(1663年)徳川家綱によって現在地に移転する。 |
|
| 總寧寺 | ||
| 国府台の地は古代から集落があり、古墳も多く存在した。里見公園内にも前方後円墳の跡があり、文明10年(1478年)太田道灌が仮陣を築いたときに古墳の盛土を取り除いたことで破壊された。発見された緑泥片岩製の箱型石棺は、公園内に保存されている。 また下総国の国府があったところで、房総方面から武蔵国に攻め入るときの要衛であった。争奪戦が繰り返され、国府台城は堅固な城郭に改修された。 文明10年(1478年)扇谷上杉氏の家宰・太田道灌と千葉孝胤との間で下総国境根原の合戦となったとき、仮陣を築いたことに始まる。文明11年(1479年)臼井城の千葉孝胤を攻めたとき、太田道灌の弟・太田資忠が築城した。 |
||
| [寄り道]下総国分寺跡 / 下総国分尼寺跡 | ||
 |
国府台公園から東に徒歩20分ほどのところに、国分尼寺跡公園がある。さらに15分ほどのところに、国分寺がある。 国分寺は、天平13年(741年)聖武天皇が日本の各国に建立を命じた下総国国分寺跡地にある。下総国国分寺を継承すると伝えられているが、戦国時代の国府台合戦や火災により変遷は解らなくなっている。金堂跡に本堂、講堂跡は本堂裏の墓地内に位置している。境内には創建時の礎石が多く残っている。本堂手前左手に、移動された七重塔跡と礎石がある、 |
|
| 国分尼寺跡公園 | ||
 |
 |
 |
| 国分寺東門 | 国分寺南大門 | 国分寺本堂 |
 |
 |
 |
| 国分寺鐘楼 | 国分寺七重塔跡 | 国分寺七重塔礎石 |
| 下総国・結城城(臥牛城) |
||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 結城朝光 寿永2年(1183年) ■主な遺構 空堀 / 土塁 |
|
| 結城城本丸跡 | ||
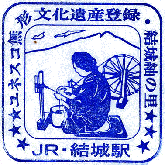 |
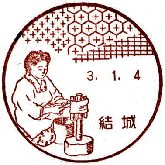 |
結城駅北口から302号線を北東に進む。すぐの交差点を右折すると、すぐ右手に結城郵便局がある。風景印は、結城紬の模様 / 糸紬(いとつむぎ)の婦人 の図柄になっている。 |
| 結城駅スタンプ | 結城郵便局風景印 | |
 |
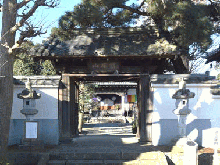 |
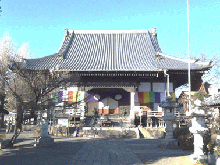 |
| 称名寺山門 | 称名寺中門 | 称名寺本堂 |
| 交差点まで戻る。結城駅から10分足らずの右手に足利銀行結城支店がある。すぐの交差点を左折して西に進むと、すぐ左手に建保4年(1216年)結城朝光によって創建された称名寺の参道がある。寛永3年(1626年) |
||
 |
 |
交差点まで戻り直進する。結城駅からは右折することになる。交差点を右折して東に進む。すぐに道は北に進路を変える。すぐのT字路交差点の北西側に不明の堂
/ 堂手前左手に二十三夜塔 がある。グーグルマップには二十三夜塔のみが記載されている。 |
| 不明の堂 | 二十三夜塔 | |
 |
 |
 |
| 結城小学校(文化の広場側) | 結城小学校 | 結城小学校 |
|
すぐのY字路交差点を右に進む。左手に文化の広場 / 明治5年(1872年)創立の結城高等小学校が始まりの結城小学校 と続く。結城小学校の外壁は、石垣に土塀と城郭を彷彿させる。ご丁寧に古びた門や小さな堀まである。明治40年(1907年)陸軍特別大演習のとき,結城高等小学校に大本営が設置された。 |
||
 |
 |
 |
| 館跡 | 結城聡敏神社 | 三日月橋からの空堀 |
|
結城小学校の先にあるY字路を左に進み、すぐのT字路を右折して東に進む。この道は往時の西館跡を貫いている。すぐ右手に館跡 / 左手に城跡歴史公園
/ 公園の西側に文化13年(1816年)結城藩12代・水野勝愛によって創建された結城聡敏(そうびん)神社 がある。北に田川が流れ、東に深田が入り込む台地北東端に築城された。北東端の実城 / 実城西側の西舘 / 実城南側の中城 / 中城南側の東館
の四つの郭があり、郭間に堀が設けられていた。城跡歴史公園 |
||
|
小山朝光は下野国小山の豪族・小山政光の四男、母親は源頼朝の乳母である八田宗綱の娘・寒河尼である。寿永2年(1183年)志田義広の乱制圧の功により結城郡の地頭職に任命され結城城を築城、小山朝光から結城朝光に改名する。永享10年(1438年)鎌倉公方・足利持氏と関東管領・上杉憲実の対立から永享の乱が発生、足利持氏は敗れて自殺、鎌倉府は滅亡した。 |
||
| 徳川家康の命により、結城城の御殿 / 隅櫓 / 御台所 / 太鼓櫓 / 築地三筋塀 / 下馬札 を埼玉県鴻巣市の勝願寺に移築された。結城城下の結城家8代・結城直光によって建武2年(1335年)頃に創建された華厳寺の鐘も移築された。 勝願寺に移築された |
||
| [参考]鴻巣・勝願寺 | ||
 |
 |
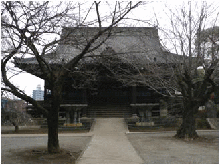 |
| 勝願寺山門 | 勝願寺仁王門 | 勝願寺本堂 |
 |
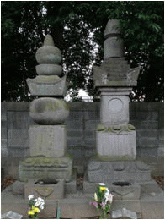 |
 |
| 仙石秀久の墓 | 真田信重の墓 / 信重室の墓 | 真田小松姫の墓 |
 |
鎌倉時代(1185年頃〜1333年)創建の勝願寺は、江戸時代に浄土宗の関東七大寺の一つに数えられていた。敷地は環濠が巡らされていて、城としての構造を有していたと云われる。寺の屋根には徳川家葵の紋瓦がある。江戸増上寺を頂点とする、浄土宗の関東十八檀林の一つ。本堂は明治24年(1891年)、仁王門は大正9年(1920年)に再建されたもの。本堂の左手に、信州小諸藩主・仙石秀久の墓 / 真田信重(信州松代藩主・真田信之の三男)の墓 / 真田信重室の墓 / 真田小松姫(真田信之室)の墓がある。真田信之は真田幸村の兄。真田小松姫は徳川譜代家臣の本多忠勝の長女で、徳川家康の養女として真田信之に嫁ぐ。 | |
| 六地蔵 | ||
| 元禄13年(1700年)水野家宗家筋の水野勝長が能登より入封、明治維新まで続く。元禄16年(1703年)結城城の再興が許され、再築城された。慶応4年(1868年)戊辰戦争の際には佐幕派が城を占拠したため、新政府軍の攻撃を受け、城の建物は多くが焼失した。 |
||
| 下総国・小弓おゆみ城 |
||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 千葉氏 ■築城年 鎌倉時代初期 ■主な遺構 土塁 |
|
| 八剣神社 |
||
 |
京成電鉄千原線・学園前駅で下車する。学園前駅は高架駅であるが、西口から学校にはスロープで行ける構造になっている。高架下の道に辿り着くには、大回りの螺旋道を下らなくてはならない。 |
|
| 大百池 | ||
| 大百池沿いに進むと、5分ほどで池の南端になる。すぐに右折して西へ進む。すぐのY字路を右方に進むと、突き当りの手前右手に八剣神社の鳥居がある。小弓城の南端にあたるところである。八剣神社社殿から北に進むと、主郭だったところはほとんどが畑になっている。 |
||
| 鎌倉時代初期に千葉氏が大百池の西側に位置する標高20〜25mの台地に築城、千葉氏の庶流である原氏の居城となる。永正15年(1518年)真里谷城主・武田信保に奪取される。3代目古河公方・足利高基の弟・足利義明が小弓城に入り、小弓公方を称する。足利義明は里見氏の支援を受け、小田原北条氏方の千葉氏や原氏に対抗した。天文7年(1538年)足利義明 / 嫡男・足利義純 は,下総国・国府台で北条氏綱の軍勢と戦い討死する。天正18年(1590年)小田原征伐が始まる。足利義明の次男・足利頼純は、里見氏の支援を受けて小弓城を奪還する。足利頼純の嫡男・足利国朝は、最後の古河公方・足利義氏の娘・氏姫と結婚して喜連川氏として存続することになる。 |
||
| 下総国・生実おゆみ城 |
||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 千葉氏 ■築城年 鎌倉時代初期 ■主な遺構 土塁 |
|
| 生実神社 | ||
 |
八剣神社社殿から左方向に、ほとんどが畑になっている小弓城の主郭だった城地を北に進む。5分足らずのY字路を左に進む。すぐのY字路を右に進むと、すぐ左手に千葉県埋蔵文化財調査センターがある。すぐのY字路を左に進むと、すぐにバス停のある通りに突き当たる。左折して西に進むと、すぐ右手に千葉生実郵便局がある。 |
|
| 千葉生実郵便局風景印 | ||
 |
千葉生実郵便局東側の道を道なりに北に進む。5分ほどの突き当りを右折して、すぐに左折して北に進む。ここに生実神社石柱がある。すぐに66号線と交差、北西側に生実神社がある。 |
|
| 案内板 / 生実神社鳥居 | ||
| この辺りは鎌倉時代初期に築城されたと云われる生実城跡で、城内に天文年間(1532年〜1555年)創建と云われる御霊神社(現:生実神社)があった。境内には石仏石塔が多い。 北生実の生実城を本城、南生実の小弓城を支城とする説もある。天文7年(1538年)小弓城を奪還した原氏は、生実城に居城したと云われている。 天正18年(1590年)徳川家康の関東移封後は、西郷家員が支配した。元和9年(1623年)酒井重澄が2万5000石で生実藩を立藩するが、寛永10年(1633年)改易され廃藩となった。寛永4年(1627年)上総国・下総国・相模国にそれぞれ1万石を与えられた森川重俊は、生実藩を立藩して陣屋を置いた。生実神社西側に隣接して、江戸時代の森川藩の生実陣屋が置かれていた。以後明治4年(1871年)の廃藩置県まで続いた。 |
||
 |
 |
生実神社から66号線を東に進む。すぐの北生実上宿交差点を越えた左手に地蔵の祠 / 北小弓城大手口跡石柱 がある。ここでは生実城ではなく、北小弓城になっている。 |
| 地蔵の祠 | 北小弓城大手口跡 | |
| [寄り道]千葉緑郵便局 | ||
 |
北小弓城大手口跡石柱から66号線を東に進む。10分ほどすると、京成電鉄千原線を跨ぎ南東方向に進む。この道は途中に公園やトイレもあり、歩道が高台になったりと楽しい。20分ほどのおゆみ野中央5交差点手前を左折すると、すぐ左手に千葉緑郵便局がある。 |
|
| 千葉緑郵便局 | ||
| 京成電鉄千原線は、千葉中央駅・ちはら台駅10.9km |
||
| 下総国・関宿(せきやど)城 | ||
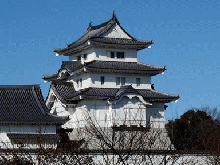 |
■城の種別 平城 ■築城者 簗田成助 ■築城年 康正3年(1457年) ■主な遺構 埋門と大手門と云われる門が市内に移築され現存する。茨城県・逆井城に城門と云われる薬医門がある。 ■主な再建造物 模擬御三階 |
|
| 模擬櫓 | ||
|
利根川と江戸川の分流点にあり、埼玉県と茨城県境にくさびを打ち込んだ様な地形になっている。千葉県最北端に位置する。往時は水運の最重要拠点だったところであるが、鉄道の駅からは離れて訪問には不便なところになっている。 |
||
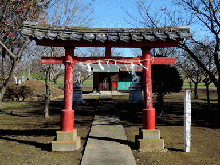 |
関宿城博物館手前の道が大きく左に曲がるところの右手に、鬼門除け稲荷神社がある。関宿城の鬼門の方角にあたるところで、寛文9年(1669年)城内に創建された。千葉県立関宿城博物館に、平成7年(1995年)築の御三階櫓を模した模擬櫓がある。江戸時代に御三階櫓があったところは、河川改修により解らなくなっている。 |
|
| 鬼門除け稲荷神社 | ||
|
康正3年(1457年)古河公方家臣・簗田成助が築城したと云われている。 |
||
 |
 |
 |
| 実相寺 | 実相寺客殿 | 関宿郵便局風景印 |
|
新町バス停から南へ進む。5分ほどの野田市関宿台町交差点を左折して南東に進むと、5分ほどの左手に応永16年(1409年)創建の実相寺がある。 |
||
 |
利根川東岸の茨城県・逆井城に、関宿城の城門と云われる薬医門がある。 | |
 |
都立庭園・清澄庭園は、関宿藩の江戸下屋敷だったところ。明治13年(1880年)深川親睦園として開園する。全国から名石が集まった庭園で、石の大きさや数が半端ではない。ほぼ池に沿って1周する単純なコースであるが、池の端々に飛び石を置いて渡れる様にしている。石の配置が素晴しい。 | |
| 清澄庭園 | ||
 |
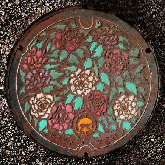 |
 |
| 関宿汚水マンホール | 関宿汚水マンホール | 関宿汚水マンホール |
|
平成15年(2003年)関宿町は、野田市に編入される。関宿城博物館デザインのマンホールやボタン絵柄のマンホールには、 |
||
| 下総国・根木内ねぎうち城 | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 高城胤忠 ■築城年 寛正3年(1462年) ■主な遺構 土塁 / 空堀 |
|
| 本郭 | ||
 |
JR常磐線・北小金駅南口から南へ、すぐの交差点を左折して東へ進む。10分足らずで 根木内交差点で6号線と交差する。すぐ左手に根木内城址口がある。 寛正3年(1462年)高城胤忠によって築城されたと云われている。天文6年(1537年)小金城を築城して移るまで、高城氏の拠点であった。天文18年(1590年)に廃城となっている。根木内歴史公園として整備されており、空堀や土塁が残る。6号線で分断された北西側は、宅地化で遺構は残っていない。 [交通]JR常磐線・北小金駅-(徒歩/約10分)-根木内城址口 |
|
| 根木内城址口 | ||
| 下総国・古河城(古河御陣) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 下河辺行平 ■築城年 平安時代末期の1180年頃 ■主な遺構 堀 / 土塁 二の丸御殿乾門が市内の福法寺に、文庫蔵と乾蔵が市内の商店に移築され現存する。 |
|
| 本丸後 | ||
| JR東北本線・古河駅から西へ、5分ほどの旧日光街道(261号線)を左折する。すぐの本町2丁目交差点を右折して西へ進む。10分ほどの渡良瀬川の堤防に登り、南へ進む。15分ほどの三国橋と新三国橋の中間辺りに、古河城本丸跡標柱がある。平安時代末期の1180年頃、源頼朝に従った下河辺行平が古河立崎に城館を築いた。北条氏が鎌倉幕府の実権を握ると、北条氏の支配下に置かれたと云われている。室町時代(1336年〜1573年)前期の南北朝時代(1336年〜1392年)は、北朝・足利氏の拠点の一つであった。室町時代後期の享徳4年(1455年)今川範忠に鎌倉を占拠されると、第5代鎌倉公方・足利成氏は下総古河に本拠を移した。以降約130年間、古河公方の本拠となる。当初は古河鴻巣の古河公方館を居館としたが、古河立崎の古河城を整備した後に移動した。後北条氏による関東支配が進むと、古河公方も次第に体制に組み込まれる。永禄10年(1567年)〜天正年間(1573年〜1592年)佐竹氏や結城氏に対抗するため、北条氏照によって城の整備・拡充が進められた。天正18年(1590年)豊臣秀吉が後北条氏を滅ぼした後は、徳川家康に従って小笠原秀政が古河城の修復・拡張を行った。江戸時代には譜代大名が入れ替わりで城主を務めた。日光街道の古河宿
/ 渡良瀬川による河川水運 で賑わい、徳川将軍による日光社参時の宿ともなっていた。明治6年(1873年)廃城令によって、建造物はすべて破却された。明治末から開始された渡良瀬川の改修工事により、残された城跡もほとんどが消滅した。 [交通]JR東北本線・古河駅-(徒歩/約30分)-古河城本丸跡標柱 |
||
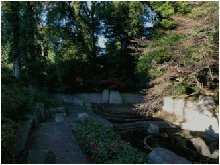 |
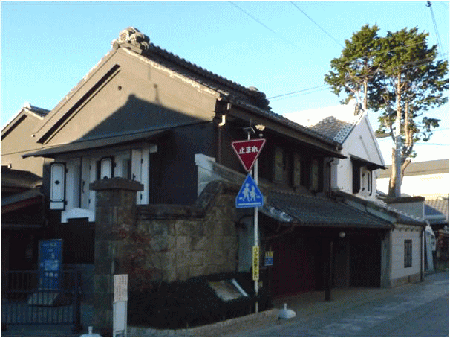 |
 |
| 諏訪曲輪・土塁 / 堀 | 店蔵(文庫蔵) / 袖蔵(乾蔵) | 福法寺山門 |
| 本町2丁目交差点から旧日光街道(261号線)を南へ進む。すぐの交差点を右折して、肴町通りを西へ進む。すぐ左手にある坂長本店の店蔵は旧古河城文庫蔵 / 袖蔵は旧古河城乾蔵。坂長本店と蛭子神社の間にある道を左折して南へ進むと、すぐ右手に福法寺がある。福法寺山門は、二の丸御殿乾門が移築されたもの。南へ進み、すぐの突き当りを右折する。すぐに突き当りに歴史博物館がある。古河城諏訪曲輪だったところで、土塁 / 堀 が残る。 | ||
 |
本町2丁目交差点から西へ、渡良瀬川方向へ進む。15分ほどすると、左手に頼政(よりまさ)神社石標があり左折する。すぐの右手に、延宝5年(1677年)創建の頼政神社がある。治承4年(1180年)以仁王(もちひとおう)の挙兵で敗死した源頼政の首を従者が持ち帰り、立崎に葬ったと云われている。頼政神社は、古河城南端の立崎曲輪(頼政曲輪)にあったが、渡良瀬川の河川改修工事のため大正元年(1912年)に古河城北端の観音寺曲輪土塁にあたる現在地に移転した。 | |
| 頼政神社 | ||
| 下総国・一色氏館 | ||
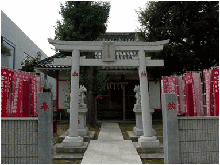 |
■城の種別 居館 ■築城者 一色直朝 ■築城年 天文年間(1532年〜1555年) |
|
| 一色稲荷神社 | ||
| 東武鉄道・幸手駅から東へ、すぐ右手に一色稲荷神社がある。陣屋稲荷神社とも称されている。東武鉄道・幸手駅付近には、古河公方・足利氏の家臣である一色氏が館を構えていた。江戸時代に一色義直は5160石の旗本となり、陣屋が構えられた。城山や陣屋の地名が残る。一色稲荷神社は、館跡と推定されるところから巽(南東)方向に一色氏の守り神として創建されたと云われている。 | ||
| 下総国・佐倉城(鹿島城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 鹿島幹胤 ■築城年 天文年間(1532年〜1555年) ■主な遺構 土塁 |
|
| 出丸跡 | ||
|
JR佐倉駅北口から北へ進む。296号線を越える。突き当たりを右折してすぐに左折、薬師坂を登る。突き当たりを左折して道なりに進む。296号線と合流する手前を左折、道なりに進む。突き当たりを左折すると、佐倉城公園に至る。慶長15年(1610年)土井利勝によって築城が再開、佐倉城が完成する。武家屋敷が残っている。 |
||
| 下総国・本佐倉もとさくら城(将門山城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 千葉輔胤 ■築城年 文明年間(1469年〜1486年) ■主な遺構 土塁 / 堀 |
|
| 土塁 | ||
| 京成電鉄・京成酒々井駅から南東へ、すぐの小路を右折して道なりに進む。線路沿いに進むと、道なりに京成電鉄の踏切を渡る。左折して線路沿いに南西へ進む。10分ほどのT字路を左折して京成電鉄のガードを潜ると、前方に本佐倉城が見える。突き当りを右折すると、すぐ左手に案内板と「マムシ注意!」の大きな看板がある。夏草が生い茂っている道で、躊躇して内部には行っていない。道を直進、突き当り右折する。すぐに京成電鉄線路に突き当り。ガードを潜らずに右折して線路沿いに進む。道なりに進むと、右手に大佐倉駅がある。京成電鉄・酒々井駅に“本佐倉城跡アクセスガイド”パンフが置かれている。将門山に築かれ、千葉宗家後期9代の本拠地となった城。天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原征伐後、千葉重胤は改易となる。徳川氏に接収、破却されて城下に陣屋が置かれた。慶長11年(1606年)に移封された小笠原吉次が本佐倉城に佐倉藩の藩庁を置いたと云われている。慶長15年(1610年)に土井利勝が移封される。元和元年(1615年)藩庁が佐倉城へ移転、一国一城制により廃城となる。 [交通]京成電鉄・京成酒々井駅-(徒歩20分)-本佐倉城-(徒歩10分)-京成電鉄・大佐倉駅 |
||
| 下総国・臼井うすい城 | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 臼井常康 ■築城年 永久2年(1114年) ■主な遺構 土塁 / 堀 |
|
| 本丸 | ||
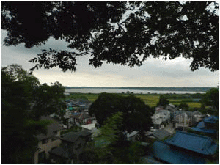 |
 |
 |
| 本丸からの印旛沼眺望 | 空堀(本丸と郭の間) | 土塁(北側) |
| 京成電鉄・京成臼井駅より北西へ、すぐの交差点を右折する。突き当りを左折して、296号線を北西へ進む。中宿交差点の次の交差点を左折する。すぐに右折して道なりに進むと、臼井城址公園がある。途中に標識などはなく、解りづらい。永久2年(1114年)平常兼(たいらのつねかね)五男・臼井常康が、居館を築いたのが始まりと云われている。平常兼は平安時代の武士で、下総国千葉郷に因んで千葉大介と称した千葉氏の初代。文明10年(1478年)境根原合戦で千葉自胤に敗北した千葉孝胤は、臼井持胤の守る臼井城に籠城した。7ヶ月に及ぶ籠城戦で臼井城は落城する。足利義明が小弓公方を称したときには、臼井城主・臼井景胤は小弓公方側に属し千葉孝胤の嫡男・勝胤とは立場を異にした。天文7年(1538年)第一次国府台合戦で足利義明が討ち死にすると、千葉氏に属した。永禄4年(1561年)臼井久胤の時、上総大多喜城主・正木信茂に攻められ臼井城は落城する。臼井久胤は結城城・結城晴朝を頼って脱出、臼井氏は滅亡する。永禄9年(1566年)上杉謙信と里見義弘に攻められた千葉胤富が、臼井城に籠城する。天正2年(1574年)里見勢に生実城を追われた原胤栄は、臼井城を本拠とする。天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原征伐後、酒井家次が入封する。文禄2年(1593年)に城内より出火、灰燼に帰す。慶長9年(1604年)酒井家次は上野国・高崎藩に移封、臼井藩は廃藩となり臼井城は廃城となる。 [交通]京成電鉄・京成臼井駅-(徒歩20分)-臼井城址公園 |
||
 |
 |
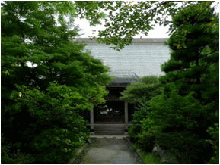 |
| 古峯神社 | 道祖神社 | 円応寺本堂 |
| 臼井城址公園内の南側に、古峯神社と道祖神社が並んでいる。臼井城址公園の北側に、歴応元年 / 延元3年(1338年)臼井興胤により創建された円応寺がある。臼井氏の菩提寺。文禄2年(1593年)臼井城とともに消失、後に再建される。 | ||
| 下総国・亥鼻城(千葉城) | ||
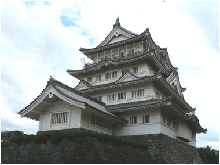 |
■城の種別 |
|
| 模擬天守 | ||
| JR外房線・本千葉駅から線路沿いに北西へ進み、20号線を右折する。県立図書館入口交差点の手前を右折、道なりに進み階段を登ると亥鼻(いのはな)公園がある。 [交通]JR外房線・本千葉駅-(徒歩/約15分)-亥鼻公園 |
||
| 天治元年(1124年)千葉常重は叔父・相馬常晴より下総国相馬郡の郡司を譲られ、大治元年(1126年)に死去した父・平常兼より下総国千葉郡を継承して両郡を支配した。 千葉氏の実質的な初代当主とされる千葉常重は、大治元年(1126年)亥鼻城を築城して大椎城から拠点を移した。 文明年間(1469年〜1487年)本佐倉城を本拠地にして、亥鼻城は廃城となる。 |
||
| 北は都川、西は断崖に面した地に築かれた平山城である。 |
||
| 下総国・古河公方(こがくぼう)館(古河御所) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 足利成氏 ■築城年 享徳4年(1455年) ■主な遺構 堀 / 土塁 |
|
| 御所沼 | ||
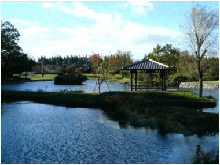 |
 |
 |
| 星糊釣殿 | 史跡 古河公方館趾 | 史跡 古河公方館址 |
|
JR東北本線・古河駅西口より西へ、すぐの261号線(旧日光街道)を左折して南へ進む。鴻巣交差点を越えると、左手に古河総合公園入口がある。古河公方館跡地の大半は古河総合公園にある。右折して道なりに進むと、星糊釣殿が見えてくる。古河公方館は、古河御所とも呼ばれる中世の城館。享徳4年(1455年)享徳の乱の際に、初代古河公方・足利成氏により築かれたと云われている。長禄元年(1457年)足利成氏は古河城へ本拠を移す。天正18年(1590年)最後の古河公方・足利義氏の娘である氏姫(氏女)の居館となった。天正19年(1591年)豊臣秀吉は氏姫に対して、小弓公方・足利頼純の子・国朝との縁組を指示した。天文7年(1538年)国府台合戦で小弓公方が滅びると、安房国・里見氏に庇護されていた。この婚姻の結果、鎌倉公方以来の関東公方家は統一され、下野国喜連川(きつれがわ)の喜連川氏として江戸時代へ継承される。寛永7年(1630年)氏姫の孫にあたる喜連川尊信が下野国喜連川に移った後、十念寺の寺域となる。御所沼に突き出た半島状の台地に築かれた。先端にあたる西側から、1曲輪(根城)
/ 2曲輪(中城) / 外郭(宿) から成り立っていた。1曲輪は本丸に相当、現在は公方様の森と呼ばれる一角。2曲輪には、昭和5年(1930年)まで十念寺があった。現在は民家園(旧中山家住宅
/ 旧飛田家住宅 )がある。外郭には、城下集落である「宿」が形成されていた。旧中山家住宅は、延宝2年(1674年)頃の建築物。旧飛田家住宅(重文)は県内の曲り家農家で最も古いもので、18世紀前半の建築物。御所沼は第二次世界大戦後に干拓・埋立されて消滅したが、平成8年(1996年)に復現された。古河公方の時代と比較すると、大幅に縮小されている。 |
||