| 信濃国 / 甲斐国 | ||
| 甲斐国・市川陣屋 |
||
 |
■城の種別 陣屋 ■築城者 徳川幕府 ■築城年 明和2年(1765年) ■主な遺構 移築門 |
|
| 奥:中央公園 / 手前:市川陣屋 |
||
 |
JR身延線・市川大門駅に着くと、平成7年(1995年)に改築された中国風のデザイン |
|
| ホームからの駅舎 | ||
 |
市川大門駅から徒歩約15分のところに大門碑林公園があり、そこにある建物をモチーフにしているとのこと。大門碑林公園には中国歴代の15基もの名碑を復元、展示している。市川大門の町は古くから手漉き和紙が特産品であることから、書道の手本となる中国の古文書や石碑を復元して公開している。 |
|
| 正面からの駅舎 | ||
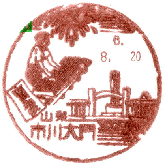 |
市川大門駅から北に進み、すぐの変則十字路を右折する。すぐの市川大門交番西交差点を右折して東に進む。10分足らずの左手に市川大門郵便局がある。風景印は、神明の花火 / 市川和紙 / 甲斐源氏旧趾 の図柄になっている。 |
|
| 市川大門郵便局風景印 | ||
 |
市川大門郵便局から東に進む。すぐの交差点を左折して北に進む。 [交通]JR身延線・市川大門駅-(徒歩15分)-市川陣屋跡-(徒歩5分)-市川本町駅 |
|
| 移築門 | ||
| 明和2年(1765年)に築かれ、巨摩郡と八代郡の天領を管轄して明治まで続いた。 | ||
| 信濃国・飯田城(長姫城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 坂西宗満 ■築城年 室町時代 ■主な遺構 桜丸御門(赤門) / 土塁 / 空堀 桜丸西門 / 薬医門 / 馬場調練場門(脇坂門)が移築され現存する。 |
|
| 飯田城二の丸跡 | ||
 |
JR飯田線・飯田駅前から21号線(中央通り)が南東方向に延びている。21号線(中央通り)に平行する道が数多くあるが、南東に進むにつれ各道は高度差を生じる。21号線(中央通り)から4本目の道を南西に進む。すぐ左手に福島家住宅がある。城下町殿町にある飯田藩士の住居で、江戸後期築と云われている。 | |
| 福島家住宅 | ||
 |
すぐの十字路の左手(北側)に、寛永年間(1624年〜1644年)造立の道標がある。飯田最古の道標で、案内板によると「南は三州街道 / 北は甲州街道 / 西は大平街道を越えて木曽に通ずる」と彫られているとのこと。補強されており、本来の高さは解らない。 |
|
| 飯田最古の道標 | ||
| 十字路を左折。さらにすぐの十字路を右折する。この道は21号線(中央通り)から3本目の道で、突き当たりにある本丸跡までの道はこの付近では最高地点を通る。 |
||
 |
 |
追手町小学校交差点を過ぎた左手の飯田城桜丸跡に、長野県飯田合同庁舎 / 宝暦年間(1751年〜1764年)築の飯田城・桜丸御門(赤門) がある。桜丸は藩主の居館のあったところ。 |
| 飯田城桜丸御門(赤門) | 桜が満開の飯田城二の丸跡 | |
 |
 |
 |
| 長姫神社鳥居 | 長姫神社社殿 | |
|
|
||
 |
馬場調練場門(脇坂門)に向かう北側の道からの飯田城址。中央の木立が本丸跡 / 左側に見える建物は温泉施設。谷底を151号線(中央通り)が通る。 | |
|
城は天竜川支流の松川と野底川に挟まれた河岸段丘に築かれた。城郭の東側に本丸、断崖に面して西側に向かって二の丸 / 桜丸 / 出丸 と曲輪を配していた。 |
||
|
鎌倉時代の飯田郷の地頭は阿曽沼氏で、鎌倉幕府が滅亡後の観応元年(1350年)阿曽沼氏から同族の小山氏に譲与された。 |
||
 |
 |
|
| 馬場調練場門(脇坂門) | 旧飯田測候所 | |
| 追手町小学校交差点の西側にある銀座3・4丁目交差点を右折して銀座通りを北東に下る。151号線(中央通り)の中央交差点を越え、すぐのT字路を右折して南東に進む。 旧飯田測候所は大正11年(1922年)年竣工、79年間に渡って飯田市の気候観測が行われていた建物。 [交通]銀座3・4丁目交差点-(徒歩15分)-馬場調練場門(脇坂門) |
||
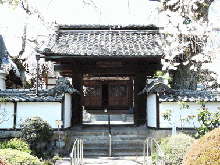 |
JR飯田線・飯田駅より辰野駅方面に2駅、上郷駅より東に進む。すぐに進路が南東に変わる。さらに東に進路が変わるところにある十字路を右折して南に進む。すぐの突き当りを右折、すぐに左折して南に進む。長い坂を下り、変則五差路を南東に進む。すぐ右手に元和3年(1617年)創建の経蔵寺がある。経蔵寺の山門は、桃山時代築の薬医門を移築したもの。 [交通]伊那上郷駅[出口]から徒歩約15分 |
|
| 経蔵寺山門(飯田城薬医門) | ||
 |
経蔵寺からさらに坂を下ると、すぐに御殿山交差点に突き当り右折する。すぐに153号線に合流、高屋交差点を過ぎた左手に雲彩寺がある。雲彩寺の山門は、江戸時代築の飯田城桜丸西門を移築したもの。 |
|
| 雲彩寺山門(飯田城桜丸西門) | ||
 |
||
| 飯田城二の丸八間門(櫓門) | ||
| JR飯田線・飯田駅より豊橋駅方面に4駅目、伊那八幡駅より北に進む。すぐの突き当りを左折、すぐに右折して北西に進む。飯田線の島田井踏切を越えた右手に黒塀の民家があり、手前の小路を下る。個人宅の南東側に移築された文禄年間(1592年〜1596年)築の飯田城二の丸八間門(櫓門)がある。門の前には趣向を凝らした小さな水路が設けられている。 [交通]JR飯田線・伊那八幡駅-(徒歩10分)-飯田城二の丸八間門がある個人宅 |
||
 |
JR飯田線・伊那八幡駅より西に進む。すぐの伊那八幡駅交差点手前右手に松尾郵便局がある。風景印は、中央アルプス / りんご並木 / 天竜舟下り
の図柄になっている。 |
|
| 松尾郵便局風景印 | ||
| 甲斐国・勝沼氏館 | ||
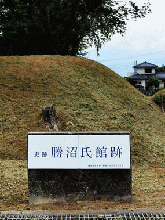 |
■城の種別 館 ■築城者 勝沼信友 ■築城年 永正17年(1520年)頃 ■主な遺構 土塁 / 空堀 / 曲輪 |
|
| 勝沼氏館跡(東郭北側) | ||
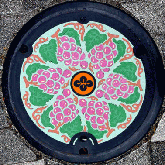 |
 |
 |
| 葡萄のカラーマンホール | 葡萄畑 | 上行寺 |
 |
 |
 |
| 勝沼氏館跡(東郭方向) | 勝沼宿 脇本陣跡 | 勝沼氏館跡入口 |
|
JR中央本線・勝沼ぶどう郷駅から38号線を南に道なりに進む。歩道に葡萄のカラーマンホールがある。旧勝沼町のデザインで、中央に甲州市の市章がある。葡萄畑やワイナリーがあるなだらかな坂道を下る。帰路はなだらかな登り坂になる。20分ほどすると、旧甲州街道に突き当たる。この辺りは江戸時代に勝沼宿があったところで、右折するとすぐ右手に上行寺
/ 左手に勝沼氏館駐車場 と続く。奥に説明板があり、草地の勝沼氏館跡を突っ切っても主郭方向に行ける。旧甲州街道を北西に進むと、すぐ右手に脇本陣跡がある。すぐの上町交差点を左折すると、すぐ左手に勝沼氏館跡入口がある。 |
||
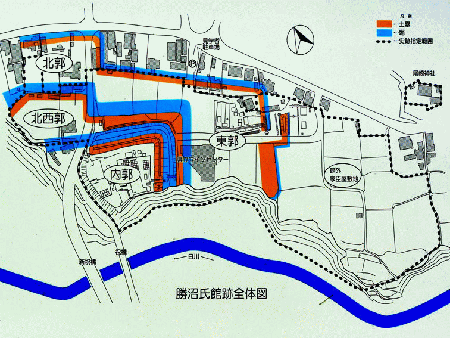 |
勝沼氏館跡は昭和48年(1973年)県立ワインセンターを建設する際に発見され、玉翠苑の敷地も勝沼氏館跡となる。土塁 / 空堀 が復元され、公園となっている。 案内地図の東側部分、北郭 / 北西郭 / 内郭 / 東郭の北側 を巡ることができる。近接する黒川金山から金鉱石が搬出され、精錬 / 加工 が行われていた可能性が指摘されている。 |
|
| 案内地図 | ||
 |
 |
 |
| 北郭・北西郭間の空堀 | 北西郭・内郭間の空堀 | 模擬北門の残骸 |
 |
 |
 |
| 内郭(西側 / 日川 方向) | 内郭 番屋跡 | 内郭 工房跡 |
 |
 |
 |
| 内郭 会所跡 | 内郭 主屋跡 | 内郭 土塁 |
 |
 |
 |
| 東模擬門 | 櫓台跡 | 内郭 築地塀跡 |
 |
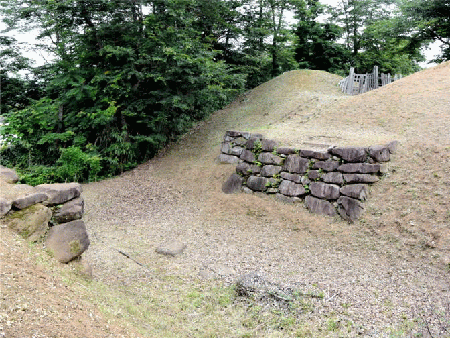 |
|
| 東郭北側の空堀 | ||
 |
||
| 東郭北側 | 空堀 / 木橋跡 / 東模擬門 | |
| 甲斐国・武田信虎の弟・武田信友が、永正17年(1520年)頃に勝沼の地を知行して勝沼信友と名乗った。 |
||
| [寄り道]祝橋(いわいばし) | ||
 |
 |
 |
| 左:勝沼氏館跡入口 | 祝橋 / 右方向は新祝橋 | 祝橋 / 背後は勝沼氏館跡 |
 |
勝沼氏館跡入口から、南に進む。すぐに分岐があり、直進すると日川に架かる新祝橋 / 勝沼氏館跡に沿って左方向に進むと祝橋 がある。 |
|
| 新祝橋からの祝橋 | ||
| 信濃国・龍岡城(龍岡五稜郭 / 桔梗城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 松平(大給)乗謨 ■築城年 元治元年(1864年) ■主な遺構 御台所櫓 / 石垣 / 土塁 / 堀 大広間が佐久市鳴瀬落合の時宗寺の本堂、東通用口が佐久市野沢の成田山薬師寺の門、薬医門と塀が市内の個人宅に移築され現存する。 |
|
| 石垣 / 堀 | ||
|
JR小海線・臼田駅から線路沿いに北へ進む。右折して踏切を渡り、93号線を道なりに進む。龍岡橋南交差点を直進して、次の十字路を右折すると五稜郭公園がある。 |
||
| 信濃国と三河国に領地を持つ三河奥殿藩は、幕末の動乱期に拠点を田野口に移すことを決める。元治元年(1864年)築城を開始するが、完成前に明治維新を迎える。江戸時代末期に築城された、蝦夷国・五稜郭と同じ星形稜堡式の城郭。石垣が低く水堀も狭いため、実戦には耐えられないと云われている。 | ||
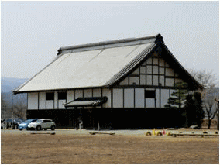 |
 |
廃城後の御台所櫓は、農機具倉庫として使用される。小学校設立の際に校舎として活用され、築城当時と反対方向に移築された。城跡には、佐久市立田口小学校と招魂社がある。 |
| 御台所櫓 | 招魂社 | |
| 信濃国・松代城(海津城 / 貝津城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 武田信玄 ■築城年 永禄2年(1559年) ■主な遺構 石垣 / 堀 ■主な再建造物 太鼓門 |
|
| 松代城本丸 | ||
| 長野電鉄屋代線・松代駅から南へ、突き当たりを右折する。美術館の角を右折して線路を越えると、海津城址公園がある。平成24年(2012年)屋代線は廃止され、松代駅は廃駅となる。 [交通]長野電鉄屋代線・松代駅-(徒歩10分)-海津城址公園 |
||
 |
 |
 |
| 本丸内掘 | 太鼓門前橋(復元) | 太鼓門 |
 |
 |
 |
| 不明門前橋 | 北不明(あかず)門 | 戌亥隅石垣 |
|
天文年間(1532年〜1555年)甲斐国・武田信玄が信濃国に侵攻する。北信豪族を庇護した越後国・長尾景虎(上杉謙信)との間に、川中島地域を巡る戦いが起きる。 |
||
| 信濃国・荒砥あらと城(新砥城) | ||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 山田二郎 ■築城年 大永4年(1524年) ■主な遺構 土塁 / 空堀 ■主な再建造物 櫓 / 兵舎 |
|
| 櫓 / 兵舎 | ||
|
しなの鉄道・戸倉駅から西へ、戸倉市山田中学校前交差点を左折して南へ進む。総合体育館前交差点を右折して西へ、千曲川に架かる万葉橋を渡る。城山入口交差点を直進して坂道を登ると、千曲市城山史跡公園(標高895m)がある。 |
||
 |
 |
 |
| 柵 / 兵舎 / 櫓 | 櫓 | 兵舎 |
| 平安時代からの豪族・山田二郎が築城したと云われている。村上氏の本城・葛尾城の支城としての役割を果たしていた。天文22年(1553年)武田信玄により葛尾城が落城、武田信玄に従った屋代政国が屋代城から移る。天正10年(1582年)武田氏滅亡後、屋代秀正は上杉氏に従った。天正11年(1583年)屋代秀正は徳川氏に通じたため、上杉景勝に攻められる。天正12年(1584年)荒砥城は落城、廃城となる。屋代秀正は徳川家康を頼って敗走、旗本となり存続する。 |
||
 |
 |
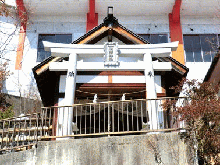 |
| 善光寺大本願別院 観音寺 | 戸倉上山田温泉街眺望 | 澳津神社 |
| 城山史跡公園入口に、善光寺大本願別院 観音寺 / 隣に澳津神社 がある。善光寺 / 善光寺大本願 / 善光寺大本願別院 観音寺 を参拝することを“三世参り”と呼ばれている。境内からは、戸倉上山田温泉街が眺望できる。澳津神社の御神体は男性と女性のシンボルで、子宝に恵まれると云われている。 |
||
| 信濃国・上田城(尼ヶ淵城 / 真田城) | ||
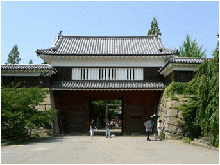 |
■城の種別 平城 ■築城者 真田昌幸 ■築城年 天正11年(1583年) ■主な遺構 北櫓 / 南櫓 / 西櫓 / 石垣 / 土塁 / 堀 ■主な再建造物 東虎口櫓門 / 塀 |
|
| 東虎口櫓門 | ||
| しなの鉄道・上田駅から141号線を北東へ進む。松尾町交差点を左折して北西へ進むと、突き当りの藩主居館跡に上田高校がある。堀沿いに北西へ、突き当りを左折する。すぐに右折、さらに市役所前交差点を左折して北西へ進む。突き当りに上田城がある。 [交通]しなの鉄道 ・上田駅-(徒歩/約15分)-上田城跡公園 |
||
| 土豪・小泉氏の古い城館が存在したと云われている。真田昌幸は甲斐武田氏の武将。天正10年(1582年)武田氏滅亡後は、織田信長に属し滝川一益の与力となる。本能寺の変後、有力勢力の狭間で揺れ動くことになる。上田・小県地方制圧の拠点として、上田城が築城される。天正13年(1585年)と慶長5年(1600年)の上田合戦で、真田昌幸が徳川軍の攻撃を撃退した城として知られている。天正13年(1585年)徳川軍およそ7000の兵を真田昌幸がおよそ1200の兵で迎え撃ち、守り抜いた。慶長5年(1600年)中山道から西へ進む徳川秀忠軍およそ38000の兵を、真田昌幸と真田信繁(幸村)がおよそ2000の兵で迎え撃ち守り抜いた。徳川秀忠軍は、関ヶ原の戦いに間に合わなかった。西軍に就いていた真田昌幸と真田信繁(幸村)は、慶長6年(1601年)紀伊国九度山に配流になる。上田城は徳川軍に徹底的に破却され堀も埋められた。東軍に就いていた嫡男・真田信之が上田領を引き継ぎ、三の丸跡地に居館(陣屋)を構える。元和8年(1622年)真田信之は信濃国・松代に転封となり、仙石忠政が入封する。寛永3年(1626年)から再建が始められたが、寛永5年(1628年)仙石忠政の死により城普請は中断される。仙石氏三代の後、宝永3年(1706年)松平(藤井)忠周が入封する。松平氏が明治維新まで城主を務めるが、本格的な再建は行われなかった。真田昌幸時代の上田城について正確な構造は、解っていない。 |
||
 |
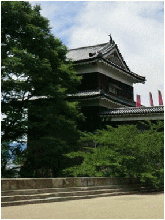 |
 |
| 北櫓 | 南櫓 | 西櫓 |
 |
明治4年(1871年)廃城後、明治7年(1874年)から上田城の土地 / 建物は民間へ払い下げられる。城址には、石垣と寛永3年(1626年)〜寛永5年(1628年)に建てられた西櫓が残るのみであった。北櫓と南櫓は上田市常磐城(新地)にあった遊郭に払い下げられ、連結されて使用されていた。昭和24年(1949年)に復元される。東虎口櫓門は平成6年(1004年)に再建される。東虎口櫓門の正面右手の石垣に、真田昌幸が築城のときに柱石として据えたと云われる真田石がある。真田信之は信濃国・松代に転封のとき、持ち運ぼうとしたびくとも動かなかったと云われている高さ約2.5m / 幅約3mもある大石。 | |
| 真田石 | ||
 |
 |
 |
| 真田神社 | 真田赤備え兜オブジェ | 酒樽茶室・百余亭 |
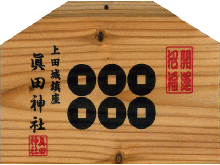 |
本丸跡には、明治12年創建の松平(しょうへい)神社として建立された歴代城主を祀った神社がある。現在では、真田神社と呼ばれている。拝殿手前左手に真田赤備え兜オブジェがある。真田信繁(幸村)は、大阪夏の陣で武具を赤で統一した部隊を率いた。真田信繁(幸村)が被った兜が真田赤備え兜。その手前左手に、酒樽茶室がある。 | |
| 真田神社絵馬 | ||
 |
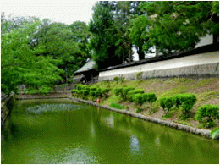 |
上田城は政務用の建物が、三の丸に置かれている。これは、真田信之が上田領を上田領を引き継いだとき上田城は破却されており、三の丸跡地に居館(陣屋)をを構えたことによる。寛政2年(1790年)再建の上田城主屋敷門(現上田高校正門)と堀と土塀が残る。 |
| 上田城主屋敷門 | 堀 / 土塀 | |
 |
二の丸の堀だったところには、昭和2年(1927年)上田温泉電軌・北東線の線路が敷設された。二の丸橋のすぐ下には、公会堂下駅(後に公園前駅と改称)があった。昭和47年(1972年)に廃止となり、昭和56年(1981年)にケヤキ並木遊歩道が完成した。 | |
| ケヤキ並木遊歩道 | ||
| 信濃国・鍋蓋城 | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 大井光忠 ■築城年 長享元年(1487年) |
|
| 鍋蓋城址 | ||
| JR小海線 / しなの鉄道・小諸駅から北東へ進む。相生町交差点を左折して141号線を北西へ進む。本町交差点を左折すると、右手の城郭を思わせる白塀に“大井伊賀守居城鍋蓋城址”の案内板がある。 [交通]JR小海線 / しなの鉄道・小諸駅-(徒歩10分)-鍋蓋城址 |
||
| 小諸は平安時代末期から滋野氏一族・小室氏が支配していた。南北朝時代に南朝方として戦い、衰退する。替わって北朝方の大井光忠が小諸を支配、長享元年(1487年)鍋蓋城 / 乙女坂城 を築城する。天文23年(1554年)甲斐国・武田信玄が侵攻、鍋蓋城 / 乙女坂城 は落城する。 | ||
| 信濃国・小諸城(酔月城 / 穴城 / 白鶴城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 武田信玄 ■築城年 天文23年(1554年) ■主な遺構 大手門(重文)・三之門(重文)・石垣 ■主な遺構 大手門(重文) / 三之門(重文) / 石垣 / 空掘 足柄門が光岳寺山門 / 黒門が正眼院山門 として移築現存する。 |
|
| 大手門 | ||
| JR小海線 / しなの鉄道・小諸駅から北へ道なりに進むと、右手に大手門がある。小諸駅北側の地下道で線路を潜ると、小諸公園に三之門 / 三之門を潜ると小諸城址懐古館(有料施設)
がある。城郭は城下町よりも低地に縄張りされているため、穴城とも呼ばれていた。 [交通]JR小海線 / しなの鉄道・小諸駅-(徒歩5分)-大手門 |
||
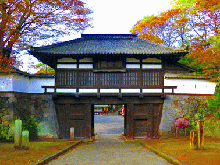 |
 |
 |
| 三之門 | 本丸への石段 | 本丸石垣 |
| 大手門は慶長17年(1612年)に建てられたもの。三之門は |
||
| 天文23年(1554年)鍋蓋城を鍋蓋曲輪 / 乙女坂城を二の丸 として取り込み、武田信玄によって築城される。天正10年(1582年)織田・徳川連合軍の甲斐侵攻のとき、城代・下曾根浄喜は逃れてきた武田信玄の甥・武田信豊を打ち取る。武田氏滅亡後、上野国
/ 信濃国佐久郡と小県郡 は滝川一益が支配して城代が置かれた。天正10年(1582年)本能寺の変後、佐久郡国衆・依田信蕃が小諸城主となる。天正18年(1590年)小田原征伐後、仙石秀久が5万石で入城する。現在みられる縄張りが完成する。三重天守も建てられたが、寛永3年(1626年)落雷によって焼失する。元和8年(1622年)仙石忠政は上田藩へ移封、徳川秀忠の3男・徳川忠長(甲府藩主20万石)の所領となり城代が置かれた。寛永元年(1624年)徳川忠長は駿府藩50万石に移封、
松平憲良が美濃大垣藩より5万石で入封する。正保4年(1647年)嗣子が無く死去して改易、小諸藩は廃藩となり天領となる。慶安元年(1648年)青山宗俊が3万石で入封する。寛文2年(1662年)青山宗俊は2万石を加増されて大坂城代に転出、酒井忠能が上野伊勢崎藩より3万石で入封する。延宝6年(1678年)百姓に対して苛酷な政治を行なったため、領民による一揆が発生した。延宝7年(1679年)酒井忠能は駿河国田中藩へ移封、西尾忠成が2万5000石で入封する。天和2年(1682年)西尾忠成は遠江横須賀藩へ移封、松平(石川)乗政が常陸小張藩より2万石で入封する。元禄15年(1702年)松平乗紀のとき美濃岩村藩へ移封、牧野康重が越後国与板藩より1万5000石で入封して明治まで続く。 |
||
 |
 |
本丸跡に元禄15年(1702年)創建の赤坂稲荷神社が始まりの懐古園稲荷神社 / |
| 懐古園稲荷神社 | 鹿嶋神社 | |
 |
懐古園の有料駐車場前に、蒸気機関車C56 144が静態保存されている。丙線用のC12に炭水車を追加した機関車。昭和13年(1938年)製造され、北海道の深川に配属された。昭和17年(1942年)に小海線・中込期間区に転じ、昭和48年(1973年)に廃車なるまで活躍した。 |
|
| 蒸気機関車C56 144 | ||
 |
小諸城の西側に、北国(ほっこく)街道・小諸宿がある。北国街道は江戸幕府によって整備された脇街道で、北国脇往還 / 善光寺街道 とも呼ばれる。 |
|
| 分去れ(左:旧中山道 / 右:北国街道) | ||
 |
 |
 |
| 古商家 | 古商家 | 小諸本陣 |
 |
||
| 本陣主屋 | ||
| 信濃国・犬甘(いぬかい)城(放光寺城) | ||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 犬甘氏 ■築城年 正平年間(1346年〜1370年) ■主な遺構 堀 / 土塁 |
|
| 二の曲輪 | ||
 |
JR松本駅東口より北へ進む。20分ほどすると城山入口交差点があり左折して西へ進む。5分ほどすると右手に正麟寺があり、Y字路を北西へ進む。10分ほど坂を登ると、城山(じょうやま)公園がある。 正麟寺は、室町時代中期に創建された少林寺が始まり。天正11年(1583年)小笠原長時の菩提寺となり、正麟寺に改められる。 [交通]JR松本駅-(徒歩35分)-城山公園 |
|
| 正麟寺 | ||
| 松本は、犬甘氏 / 平瀬氏 / 桐原氏 などの犬甘一族によって支配されていた。建武元年(1334年)小笠原貞宗が信濃守護に任じられると、麾下に属する様になる。 |
||
| 信濃国・松本城(深志城 / 烏城) | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 小笠原貞朝 ■築城年 永正元年(1504年) ■主な遺構 天守(国宝) / 乾小天守(国宝) / 渡櫓(国宝) / 辰巳附櫓(国宝) / 月見櫓(国宝) / 二の丸土蔵 / 石垣 / 土塁 / 堀 ■主な再建造物 黒門 / 太鼓門 |
|
| 松本城天守 | ||
|
JR大糸線・北松本駅北側の通りを東に進むと、左手に松本城天守が見えてくる。 |
||
|
|
 |
|
| 埋橋 / 乾小天守 / 天守 | ||
 |
||
| 左から辰巳附櫓 / 手前に月見櫓 / 天守 / 乾小天守 | 太鼓門 | |
| 永正元年(1504年)信濃国守護・小笠原氏が林城を築城、支城として深志城が築城した。平安時代末期に松本行光が築城したとも云われている。 天文年間(1532年〜1555年)甲斐国・武田信玄による信濃侵攻が始まる。天文19年(1550年)林城 / 深志城 などが落城、信濃国守護・小笠原長時は追放された。 国宝になっている天守は、天正19年(1591年) / 文禄3年(1594年) / 慶長2年(1597年) / 慶長5年〜6年(1600年〜1601年) / 慶長20年(1615年) 説がある。 |
||
 |
松本城の堀と道路を挟んだ北側向に、寛永13年(1636年)創建の暘谷(ようこく)大神社が始まりの松本神社がある。 |
|
| 松本神社 | ||
| 信濃国・諏訪高島城(諏訪の浮城 / 島崎城) | ||
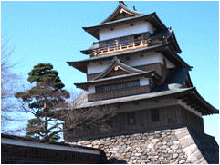 |
■城の種別 水城 ■築城者 日根野高吉 ■築城年 文禄元年(1592年) ■主な遺構 三の丸家屋敷裏門 温泉寺や浄光寺に、城門が移築され現存する。 ■主な再建造物 天守 / 隅櫓 / 櫓門 |
|
| 復興天守 | ||
| 上諏訪駅の東を通る20号線を南へ、諏訪町1・2丁目交差点手前を右折して南西へ進む。JR中央本線を越え、県道衣の渡橋や中門橋を渡ると高島公園に至る。 [交通]JR上諏訪駅-(徒歩/約20分)-高島城天守 |
||
 |
 |
 |
| 隅櫓 | 櫓門 | 三の丸家屋敷裏門 |
 |
 |
 |
| 諏訪護国神社 |
温泉寺山門 | 温泉寺本堂 |
| 文禄元年(1592年)日根野高吉によって築城される。関ケ原の合戦の翌年に日野根氏は下野国壬生藩に転封となり、替わって諏訪頼水が入封する。以降明治まで諏訪氏の居城として続く。往時は諏訪湖に突き出た水城で、諏訪の浮城と呼ばれた。江戸時代初期の諏訪湖干拓により、湖は遠くなった。昭和45年(1970年)天守が復興される。移築されていた三の丸家屋敷裏門が本丸に復元される。温泉寺に城門や文政10年(1827年)建立の能舞台が移築されており、山門と本堂となっている。高島公園内に諏訪護国神社 |
||
| 信濃国・桑原くわばら城(高鳥屋たかとや城 / 水晶すいしょう城 |
||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 諏訪氏 ■主な遺構 土塁 / 空堀 |
|
| 桑原城跡 | ||
| JR中央本線・茅野駅西口から192号線を北へ進む。上原交差点で20号線に合流する。上原頼岳寺交差点の次にある十字路を右折して道なりに進む。四賀桑原交差点を右折すると、正面に桑原城跡の看板が見える。 [交通]茅野駅-(徒歩45分)-四賀桑原交差点 |
||
| 上原交差点から四賀桑原交差点間は、旧甲州街道となる。 |
||
| 信濃国・高遠城(兜山城 / 甲山城) | ||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 不詳 ■築城年 不詳 ■主な遺構 大手門 / 石垣 / 土塁 / 空堀 / 藩校進徳館 本丸門が伊那市内の個人宅に / 本丸冠木門が伊那市内の個人宅に / 搦手門が岡谷市の久保寺に 移築され現存。 ■主な再建造物 太鼓櫓 |
|
| 太鼓櫓 | ||
| JR飯田線・伊那市駅より北西へ、すぐの伊那市駅前交差点を右折して146号線を北東へ進む。坂下入舟交差点を右折して飯田線の踏切を渡る。361号線(伊那街道)を道なりに東へ進む。しばらくすると、左手に高遠駅バス停がある。さらに361号線を東へ進み、突き当りの秋葉街道を右折する。すぐに左折、さらに左折して高遠警察署前を通る。道なりに進むと、右手に高遠城址公園入口がある。 [交通]伊那市駅-(徒歩110分)-高遠駅バス停-(徒歩30分)-高遠城址公園入口 |
||
| 築城主や築城年は不詳であるが、治承3年(1179年)または元暦年間(1184年〜1185年)に笠原平吾頼直によって築城されたと云われている。木曽家親築城説もある。高遠城主・高遠頼継は諏訪氏一門であるが、甲斐国守護・武田氏と同盟関係にある諏訪頼重とは反目していた。天文10年(1541年)武田晴信(信玄)に内応、諏訪攻略を援護している。諏訪頼重が滅ぼされると、諏訪の領有を巡り武田と高遠頼継は対立する。天文14年(1545年)に武田信玄によって攻略される。天文16年(1547)高遠城の大改修を行い、現在見られる城郭の原形が築かれる。永禄5年(1562年)武田晴信の庶子で諏訪氏の娘を母とする四郎勝頼(武田勝頼)が諏訪氏を継承、高遠城主となる。元亀元年(1570年)武田信玄の嫡子・義信が廃嫡されると、勝頼は後継者となる。武田信玄により本拠の躑躅ヶ崎館に呼び戻され、高遠城主は信玄実弟の武田信廉となった。天正3年(1575年)長篠の戦いに敗退する。天正9年(1581年)新府城を築城して領国の維持を図とともに、武田勝頼の弟・仁科盛信を高遠城主とする。天正10年(1582年)織田信忠は5万の大軍で、高遠城を攻撃する。3千の守備隊は玉砕、仁科盛信は自決して城は落城した。9日後、武田勝頼は天目山へ逃避する途中で落命する。武田氏滅亡後、毛利長秀が城主となる。3ヵ月後に本能寺の変が起こり、武田家旧臣・木曾義昌が攻め込み占領した。天正壬午の乱の結果、徳川家康の支配となる。江戸時代になると高遠藩の藩庁となり、京極氏・保科氏・鳥居氏と城主が交代した。元禄4年(1691年)内藤清枚が入封、明治維新まで続く。明治5年(1872年)に廃城となる。 | ||
 |
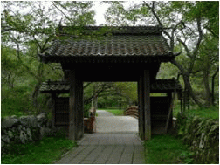 |
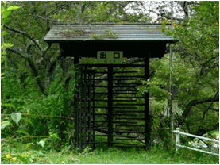 |
| 大手門 | 問屋門 | 有料な時期の門 |
| 高遠城址公園入口手前の左手に、大手門と云われる門がある。伊那市富県北福地の所有者より寄贈を受け移築され、昭和29年(1954年)〜昭和59年(1984年)県立高遠高校正門として使用されていた。大手門のあった場所とは異なる。桜雲橋を渡ると、本丸入口に問屋門がある。問屋役所にあった門で、昭和23年(1948年)に町内の旧家から移築したもの。桜の時期は城内が有料となるため、いたるところに現代の城門が設置されている。 | ||
 |
 |
 |
| 桜雲橋 | 本丸跡 | 新城・藤原神社 |
| 高遠城は桜の名所としても知られ、本丸にも桜の木が多い。復元された太鼓櫓と新城・藤原神社がある。 | ||
 |
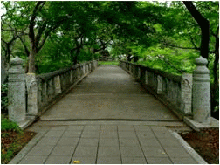 |
 |
| 藩校進徳館 | 白兎橋 | 高遠閣公園管理事務所 |
| 三の丸に万延元年(1860年)最後の藩主・内藤頼直によって創設された藩校進徳館がある。明治4年(1871年)に廃校となった。高遠城唯一の残存建造物である。本丸跡と法憧院郭の堀に白兎橋が架かる。北ゲートに高遠閣公園管理事務所がある。 | ||
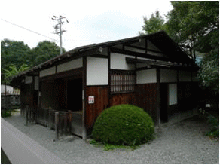 |
本丸跡から白兎橋を渡る。法憧院郭の南門から標識に従い5分ほどの歴史博物館に、絵島(えしま)囲み屋敷がある。絵島は、徳川幕府の大奥で月光院(7代将軍・徳川家継の生母)に仕えていた女中で、出世して大年寄りにまでなった。絵島は山村座に度々出掛け、役者・生島新五郎と馴染みを重ねるようになった。正徳4年(1714年)月光院の代わりに、増上寺に徳川家宣の墓参をする。帰路に山村座で芝居見物、大奥門限に遅れる。公務を疎かにしたということで裁きを受け、高遠に遠流となる。33歳の時で、61歳で亡くなりなるまでの28年間幽閉された。絵島を口実に大奥の粛清を断行したと云われている。 | |
| 絵島囲み屋敷 | ||
| 信濃国・妻籠城 | ||
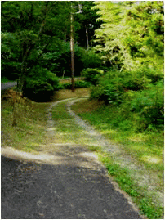 |
■城の種別 山城 ■築城者 木曾氏 ■築城年 室町時代中期 ■主な遺構 土塁 |
|
| 総堀 | ||
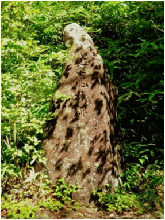 |
旧中山道・妻籠宿「JR南木曽駅3.2km これより妻籠宿の町並み」道標から、旧中山道を北へ進む。10分ほどすると、妻籠城跡碑と妻籠城跡案内看板がある。すぐに妻籠城総堀になる。元禄16年(1703年)道の付け替え工事が行われ、妻籠城総堀を通る様になった。標高521mにある山城で、戦国時代には木曾義昌が城主であった。元和2年(1616年)の一国一城令により、廃城になった。 |
|
|
妻籠城跡碑 |
||
| 信濃国・馬篭城 | ||
 |
■城の種別 山城 ■築城年 室町時代 |
|
| 馬篭城跡 | ||
| 馬篭宿南の入口十字路から南へ進む。急な坂道を下り道なりに10分ほど進と、丸山坂の右手に馬籠城跡案内板がある。この辺りは城山とも言われ、室町時代から馬篭城があった。元和元年(1615年)尾州徳川家の領地になり、いつしか廃城になった。 [交通]馬篭宿-(徒歩/約10分)-馬籠城跡案内板 |
||
| 甲斐国・川田館かわだやかた | ||
 |
■城の種別 居館 ■築城者 武田信昌 ■築城年 寛正5年(1464年) 水堀 |
|
| 川田館跡案内板辺りからのぶどう畑 | ||
| JR中央本線・石和温泉駅南口より西へ進む。すぐにJR中央本線を陸橋で越える手前を左方向に進み、すぐに右折して川を越える。道なりに進むとJR中央本線の踏切を渡るが、手前を左折して南へ小路を進む。すぐの突き当りを左へ進む。周囲はぶどう畑になっている。5分ほどの突き当りを右折して西に進むと、右手のぶどう畑に川田館跡案内板
/ 二宮神社参道 / 寿徳院 と続く。 [交通]JR中央本線・石和温泉駅-(徒歩15分)-川田館跡案内板 |
||
| 甲府市川田町あった甲斐守護の武田氏居館跡。 |
||
 |
 |
 |
| 二宮神社鳥居 | 二宮神社社殿 | 二宮神社境内東側 |
 |
二宮神社の創建は、 |
|
| 寿徳院 | ||
| 甲斐国・新府城(韮崎城) |
||
 |
■城の種別 平山城 ■築城者 武田勝頼 ■築城年 天正9年(1581年) ■主な遺構 土塁 / 堀 |
|
| 新府城本丸跡 | ||
 |
JR中央本線・新府駅から南西へ道なりに進む。すぐのT字路を左折して南へ道なりに進む。藤武神社の鳥居を潜り西へ進むと、新府城跡がある。 [交通]JR中央本線・新府駅-(徒歩20分)-新府城本丸跡 |
|
| 藤武神社鳥居 / 前方に新府城跡 | ||
 |
 |
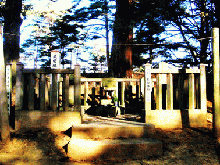 |
| 甲州街道からの七里岩台地 | 藤武神社 | 武田勝頼公霊社 |
| 甲府盆地西部の七里岩台地にあり、西側を釜無川 / 東側を塩川 が流れる天然の堀となっていた。 織田信長は甲斐国駿河諏訪郡に河尻秀隆を配置、岩窪館(現:甲府市岩窪町)を本拠とした。 本丸跡に、新府築城のとき創建された稲荷社が始まりの藤武神社 / 貞享元年(1684)頃創建の武田勝頼公霊社 がある。武田勝頼公霊社の社殿は無く、石祠がある。 |
||
| [参考]景徳院 | ||
 |
 |
|
| 景徳院総門 | ||
 |
||
| 景徳院本堂 | 景徳院山門(本堂側からの撮影) | |
| 甲斐国は徳川家康が領することになり、武田遺臣は徳川家康に臣従することになる。武田勝頼と家臣の殉死者菩提を弔うため、天正10年(1582年)徳川家康により田野寺が創建された。 |
||
| 甲斐国・躑躅ヶ崎館 | ||
 |
■城の種別 平城 ■築城者 武田信虎 ■築城年 永正16年(1519年) ■主な遺構 石垣 / 土塁 / 堀 |
|
| 躑躅ヶ崎館跡 | ||
 |
 |
 |
| 土塁 | 堀 | 武田神社 |
| 甲府駅より31号線を北へ進むと、突き当たりに大正8年(1919年)創建の武田神社がある。永正16年(1519年)武田信虎によって築城された躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)跡で、背後にある要害山城を詰城としていた。武田信虎・晴信(信玄)・勝頼の3代60年余りに渡り、府中として機能した。武田氏滅亡後、徳川家康によって館域は拡張されて天守も築かれた。天正11年(1583年)甲府城が築城されると、廃城となった。 [交通]JR中央本線・甲府駅-(徒歩約30分)-武田神社 |
||
| 甲斐国・甲府城(舞鶴城 / 一条小山城) | ||
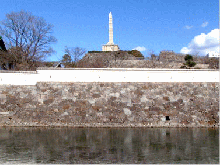 |
■城の種別 平山城 ■築城者 徳川家康 ■築城年 天正11年(1583年) ■主な遺構 石垣 / 堀 ■主な再建造物 稲荷櫓 / 鍛冶曲輪門 / 稲荷曲輪門 |
|
| 掘 / 石垣 / 恩賜林謝恩碑 |
||
| 甲府駅の南東に舞鶴公園がある。 [交通]JR中央本線・甲府駅-(徒歩10分)-甲府城 |
||
 |
 |
 |
| 坂下門跡石垣 | 中の門跡石垣 | 天守台 |
 |
 |
 |
| 恩賜林謝恩碑 | 稲荷櫓 | 本丸 / 天守台 |
 |
 |
 |
| 内松陰門 | 稲荷曲輪門 | 鍛冶曲輪門 |
|
|
||
| 甲斐国・石和陣屋 |
||
 |
■城の種別 陣屋 ■築城者 徳川綱重 ■築城年 寛文元年(1661年) ■主な遺構 陣屋門 |
|
| 陣屋門 | ||
| 石和陣屋は石和南小学校の辺りに置かれていた。石和陣屋は寛文元年(1661年)甲府藩主・徳川綱重(徳川家光の三男)によって設けられ、徳川綱重は江戸城桜田邸に居住したため代官所として使用された。宝永2年(1705年)柳沢吉保が入封、享保9年(1724年)柳沢吉里は大和郡山へ移封となる。再び幕府天領の代官所となった。旧石和陣屋門は寛文元年(1661年)代官所設立のとき建立され、明治7年(1874年)に払い下げられ移築された。 |
||
 |
||
| 陣屋門 | ||
 |
 |
旧石和陣屋門を潜ると、慶長6年(1601年)築の八田家書院がある。八田家御朱印屋敷に付属する別棟書院で、茅葺き入母屋造りになっている。八田氏は武田家臣で、蔵前衆の要職を務めていた。天正10年(1582年)武田滅亡後、甲斐を領した徳川氏に臣従する。
|
| 八田家書院 | 願念寺 | |
旧甲州街道は“食堂かどや”がある五差路を左折して南へ進み、すぐに411号線に突き当り右折する。 |
||
| 甲斐国・岩殿山城(岩殿城) | ||
 |
■城の種別 山城 ■築城者 小山田信茂 ■築城年 大永7年(1527年) ■主な遺構 郭 / 空堀 |
|
| 岩殿山 | ||
| JR中央本線で新宿方面から大月駅に近づくと、右手に標高634mの岩殿山が見える。大月駅前から東へ進み、岩殿登山口が掲げられたアーケードを左折する。踏切を渡り右折すると139号と合流、北へ道なりに進むと左手に岩殿山城登山口がある。 [交通]JR中央本線・大月駅-(徒歩15分)-登山口-(徒歩5分)-ふれあいの館-(徒歩40分)-岩殿山頂上 |
||
 |
 |
 |
| ふれあいの館 | 南面の絶壁 | 揚木戸跡 |
 |
 |
 |
| 乃木希典詩碑 / 岩殿山城址碑 | 岩殿山城址碑 | 南物見台からの眺望 |
| 5分程で中世の城をイメージしたと云う「ふれあいの館」に到着する。頂上への道は階段も多く、整備されているが勾配はきつい。自然の岩を利用した揚木戸跡を過ぎると、南物見台に陸軍大将・乃木希典が明治12年(1879年)に登頂した際の詩碑がある。南物見台からの展望は素晴らしいが、富士山は雲が厚く隠れている。帯郭跡から三の丸 / 二の丸 / 本丸 方面へ進む。烽火(のろし)台には鉄塔かあり、工事中で機材が占領していた。空湟跡から岩殿へ下る短絡路は落ち葉が深くて滑り易く、途中から引き返し帯郭跡まで戻る。帯郭跡から岩殿までは比較的整備されているが、落ち葉が堆積している。朝から誰も通っていない様で、蜘蛛の巣を払い除けながらの下山となる。車道を下ると往路の登山口に至る。標高634mの岩殿山には大同元年(806年)創建と云われる円通寺があり、修験道の場となっていた。大月は武蔵国へ至る街道が交差する地に位置する。小山田氏は初め武田氏に対抗していたが、永正6年(1509年)武田氏の傘下に入った。岩殿山城は、大永7年(1527年)小山田信茂により築城された。相模の北条氏 / 駿河の今川氏 / 武蔵の上杉氏 との国境警備の役割を担っていた。東西に長い岩山をそのまま城にしている。南面は西から東までほとんどが絶壁で、北面も急傾斜になっている。戦国時代には、東国の城郭の中でも屈指の堅固さを持っていた。天正10年(1582年)織田軍が甲斐に侵攻したときに、小山田信茂は織田方へ寝返る。岩殿山城へ落ち延びてくる武田勝頼は、進退に窮し天目山で自害した。武田家を滅亡させる事に深く関わった小山田信茂は、この戦いの後に織田信長により処刑されている。江戸時代にも岩殿山城は要塞として存続している。 | ||
