| 棨墱崙嘥丂惵怷導丂娾庤導丂嵟怴偺捛壛 | ||
| 棨墱崙丒崅娰偨偐偩偪 |
||
 |
仭忛偺庬暿 嶳忛 仭抸忛幰 摗尨惔峵 仭庡側堚峔 杧 / 搚椲 / 妔 |
|
| 媊宱摪偺偁傞崅戜偺妔 | ||
 |
俰俼搶杒杮慄丒暯愹墂傛傝惣偵恑傓丅偡偖偺廫帤楬傪塃愜偟偰丄侾侾侽崋慄乮拞懜帥捠傝乯傪 |
|
| 柍検岝堾愓 | ||
 |
 |
 |
| 昗幆 | 奒抜 | 妔 |
| 柍検岝堾愓偐傜侾侽暘傎偳偡傞偲塃庤偵昗幆偑偁傝丄塃愜偟偰嶁傪搊傞丅師偄偱奒抜傪搊傞偲丄嵍庤偵妔 / 拞墰偵奒抜 / 塃庤偵帠柋強偑偁傞丅 乵岎捠乶俰俼搶杒杮慄丒暯愹墂-乮搆曕俀侽暘乯-崅娰媊宱摪帠柋強 |
||
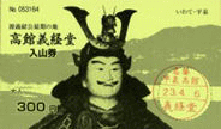 |
崅娰媊宱摪傊偺擖嶳寯乮戝恖俁侽侽墌乯偑昁梫偱偁傞丅 |
|
| 崅娰媊宱摪擖嶳寯 | ||
 |
 |
|
| 撍偒摉傝偐傜偺挱朷 | 妔 | |
 |
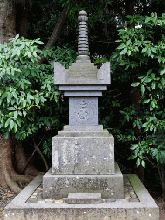 |
 |
| 媊宱摪 | 曮飧報搩 | 媊宱摪偺偁傞崅戜偐傜偺挱朷 |
| 奒抜傪搊傝撍偒摉傝傪嵍偵恑傓偲妔偑偁傝丄奒抜傪搊傞偲媊宱摪乮偓偗偄偳偆乯 / 曮飧報搩乮傎偆偒傚偆偄傫偲偆乯 偑偁傞丅媊宱摪偼揤榓俁擭乮侾俇俉俁擭乯愬戜斔係戙斔庡丒埳払峧懞偑峛檋巔偺媊宱偺栘憸傪廂傔偰寶棫偟偨丅曮飧報搩偼丄摗尨廏峵 / 尮媊宱 / 晲憼朧曎宑 偺嫙梴偺偨傔偵徍榓俇侾擭乮侾俋俉俇擭乯偵憿棫偝傟偨丅媊宱摪廃埻偼栘乆偵埻傑傟丄奒抜墇偟偵杒忋愳 / 傪懇堫嶳乮偨偽偟偹傗傑乯 偑挱傔傜傟傞丅 | ||
 |
 |
撍偒摉傝傪塃偵恑傓偲丄崅娰乮堖壨娰乯偑偁偭偨妔偵攎徳嬪旇偑偁傞丅 |
| 崅娰乮堖壨娰乯偑偁偭偨妔 | 攎徳嬪旇 | |
| 惣峴乮侾侾侾俉擭乣侾侾俋侽擭乯偼丄俀侽戙屻敿偺崰偲暥帯俀擭乮侾侾俉俇擭乯偵暯愹傪朘傟偰偄傞丅俀搙栚偼丄搶戝帥嵞寶偺偨傔偺嵒嬥姪惪偵墱廈摗尨巵俁戙丒摗尨廏峵傪朘偹偨偲偒丅 尦榎俀擭乮侾俇俉俋擭乯攎徳偼墱偺傎偦摴偱暯愹傪朘傟丄乽壞憪傗 暫乮偮傢傕偺乯偳傕偑 柌偺愓乿偲塺傫偩偺偼偙偺応強偲偝傟傞丅 |
||
|
姲帯尦擭乮侾侽俉俈擭乯墱榋孲傪椞偡傞惃椡幰偲側偭偨摗尨惔峵偼丄壝曐擭娫乮侾侽俋係擭乣侾侽俋俇擭乯崰偐傜斨堜孲暯愹傪嫃娰偲偟偨丅壝彸俁擭乮侾侾侽俉擭乯偵拞懜帥憿塩傪奐巒丄墱廈摗尨巵係戙侾侽侽擭偺塰壺偺婎慴傪抸偄偨丅崅娰偼摗尨惔峵偺帪戙偐傜梫奞偲偝傟偰偄偨偲塢傢傟偰偄傞丅 |
||
| 乵婑傝摴乶拞懜帥娙堈梄曋嬊 | ||
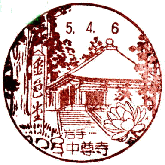 |
 |
 |
| 拞懜帥娙堈梄曋嬊晽宨報 | 悽奅堚嶻暯愹億僗僩 | 悽奅堚嶻暯愹億僗僩懁柺 |
| 侾侾侽崋慄乮拞懜帥捠傝乯偵栠傝杒惣偵恑傓丅偡偖偵俰俼搶杒杮慄偺摜愗傪搉傞偲丄俁侽侽崋慄偲岎嵎偡傞嵍庤偵拞懜帥娙堈梄曋嬊偑偁傞丅晽宨報偼丄拞懜帥嬥怓摪偺恾暱偵側偭偰偄傞丅 |
||
| 棨墱崙丒嬨屗忛乮暉壀忛 / 媨栰忛乯 | ||
 |
仭忛偺庬暿 暯嶳忛 仭抸忛幰 嬨屗岝惌 仭抸忛擭 柧墳擭娫乮侾係俋俀擭乣侾俆侽侾擭乯 仭庡側堚峔 搚椲 / 愇奯 / 杧 / 嬋椫 / 堜屗 |
|
| 杮娵嬻杧 | ||
 |
偄傢偰嬧壨揝摴丒擇屗墂搶岥偐傜侾侾係崋慄傪搶偵恑傓丅偡偖偵侾侾係崋慄偼撿搶偵嬋偑傝丄俀俈係崋慄偵撍偒摉偨傞丅岎嵎揰傪嵍愜偟偰丄攏暎愳偵壦偐傞愳尨嫶傪搉傞丅摴側傝偵杒曽岦傊恑傓偲丄塃庤偵撣崄乮偲傫偙偆乯堫壸恄幮偑偁傞丅愇抜傪搊傞偲丄嬨屗忛徏僲娵惣偺崢嬋椫愓偵撣崄堫壸恄幮偺幮揳偑偁傞丅彸榓擭娫乮俉俁係擭乣俉係俉擭乯偵憂寶偝傟偨偲塢傢傟丄揤榓俀擭乮侾俇俉俀擭乯偵尰嵼抧偵堏揮偟偨丅 [岎捠] 偄傢偰嬧壨揝摴丒擇屗墂-乮俁侽暘乯-撣崄堫壸恄幮 |
|
| 撣崄堫壸恄幮 | ||
 |
 |
嫬撪塃庤偵嬨屗惌幚恄幮 / 戝嶌恄幮 偑偁傞丅嬨屗惌幚恄幮偺憂寶帪偼嬨屗忛擇僲娵愓偵偁偭偨偑丄幮揳偺榁媭壔偵傛傝暯惉侾俁擭乮俀侽侽侾擭乯偵堏抸怴抸偝傟偨丅 |
| 嬨屗惌幚恄幮 | 戝嶌恄幮 | |
| 戝嶌恄幮偼惙壀丒敧敠媨嫬撪偵偁偭偨偑丄攑斔抲導偺嵺偵攑幮偲側偭偨丅戝惓俈擭乮侾俉侾俋擭乯壓搇暷廏擵恑乮憡攏戝嶌乯枛遽偺暉壀挰戭抧撪偵嵞嫽丄徍榓俇擭乮侾俋俁侾擭乯撣崄堫壸恄幮偵堏偝傟偨丅 暥惌係擭乮侾俉俀侾擭乯撿晹斔巑丒壓搇暷廏擵恑傪庱杁幰偲偡傞悢恖偑丄嶲嬑岎戙傪廔偊偰峕屗偐傜婣崙偺搑偵偮偄偰偄偨捗寉斔庡丒捗寉擩恊偺埫嶦枹悑帠審偑婲偒傞乮憡攏戝嶌帠審乯丅 捗寉斔庡丒捗寉巵偼丄惙壀斔庡偲側偭偨嶰屗撿晹巵偲摨偠撿晹巵偺堦懓偩偭偨丅 |
||
 |
撣崄堫壸恄幮幮揳塃庤偺愇抜傪搊傞偲丄嬨屗忛徏偺娵愓偑偁傞丅 | |
| 嬨屗忛徏偺娵愓 | ||
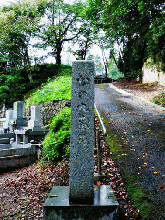 |
 |
 |
| 徏僲娵愇拰 | 岺帠偺埬撪娕斅 | 巎愓 嬨屗忛愓 愇拰 |
| 徏僲娵愓傪杒搶傊恑傒嶁摴傪壓傞偲乽徏僲娵乿愇拰偑偁傝丄塃愜偟偰幵摴傪撿搶偵恑傓丅岺帠偺埬撪娕斅偑偁傝丄嬨屗忛偼椷榓係擭俆寧俁侾擔乣侾侾寧侾俈擔傑偱惍旛岺帠拞偱偁偭偨丅嶁摴傪搊傞偲嵍庤偺崅戜偵乽巎愓 嬨屗忛愓乿愇拰偑尒偊傞丅 | ||
 |
 |
乽巎愓 嬨屗忛愓乿愇拰偐傜偡偖嵍庤偵嬨屗忛擇偺娵戝庤偑偁傞丅棫偪擖傝嬛巭偺昞帵偼側偐偭偨偨傔丄揝斅偑傂偐傟偨摴傪恑傓丅偡偖塃庤偵峀偄擇偺娵愓偑偁傞丅 |
| 揝斅偑傂偐傟偨摴 | 擇偺娵愓 | |
 |
 |
擇偺娵偼偲偙傠偳偙傠偵棫偪擖傝嬛巭偺昗幆偑偁傝丄杧偵壦偐傞嫶傕捠峴巭傔偵側偭偰偄偨丅 |
| 杮娵嬻杧 | 杮娵嬻杧 | |
 |
 |
杮娵屨岥愓偐傜杮娵偵擖傝嶣塭偟偰偄傞偲丄岺帠娭學幰偺曽偐傜擇偺娵戝庤偐傜棫偪擖傝嬛巭偵側偭偰偄傞偲尵傢傟傞丅帪偼侽俉丗係俆丄岺帠偑巒傑傞慜偱擖傝崬傔偨偑丄杮娵愇奯傑偱偼峴偔偙偲偑偱偒側偐偭偨丅 |
| 杮娵屨岥愓 | 杮娵愓 | |
| 杒懁傪敀捁愳 / 搶懁傪擫熀愳 / 惣懁傪攏暎愳 偲嶰曽傪壨愳偵埻傑傟偨揤慠偺梫奞偱丄忛撪偼嬻杧偵傛偭偰丄杮娵 / 擇偺娵 / 嶰偺娵 / 庒嫹娰乮傢偐偝偩偰乯 / 奜娰乮偲偩偰乯 / 徏偺娵 側偳偺嬋椫孮傪宍惉偟偰偄偨丅搶杒抧曽偱偼桳悢偺婯柾偱偁傝丄杮娵偵搶杒嵟屆偺愇奯偑偁傞丅嶰偺娵愓偼戝晹暘偑巗奨抧偲側偭偰偄傞丅 |
||
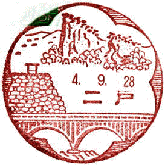 |
岺帠拞偺偨傔墲楬傪栠傞偟偐側偔丄徏僲娵愓偲偺娫偺摴傪杒惣偵恑傓丅偡偖偵俀俈係崋慄偵撍偒摉偨傝丄嵍庤偵擇屗梄曋嬊偑偁傞丅晽宨報偼丄攏愬嫭偺婏娾 / 嬨屗忛愇奯 / 攏暎愳偵壦偐傞峳悾嫶 偺恾暱偵側偭偰偄傞丅 |
|
| 擇屗梄曋嬊晽宨報 | ||
|
柧墳擭娫乮侾係俋俀擭乣侾俆侽侾擭乯嬨屗岝惌偵傛偭偰抸忛偝傟偨偲塢傢傟偰偄傞丅嬨屗巵偼撿晹巵偺慶丒尮岝峴乮撿晹岝峴乯偺榋抝丒撿晹峴楢偑棨墱崙嬨屗孲埳曐撪乮娾庤導嬨屗懞乯傪椞偟偰嬨屗巵傪徧偟偨丅 |
||
| 棨墱崙丒壴姫忛乮捁扟儢嶈忛乯 |
||
 |
仭忛偺庬暿 暯嶳忛 仭抸忛幰 埨攞棅帪 仭抸忛擭 慜嬨擭偺栶乮侾侽俆侾擭乣侾侽俇俀擭乯崰 仭庡側堚峔 墌忛帥栧 / 帪忇摪 仭庡側嵞寶憿暔 惣屼栧 |
|
| 惣屼栧乮瀍宍 / 楨栧乯 | ||
|
俰俼搶杒杮慄丒壴姫墂搶岥傛傝搶偵丄偡偖偺俀俋俈崋慄傪塃愜偟偰撿搶偵恑傓丅偡偖偺倄帤楬傪嵍曽岦偵恑傓偲丄俀俋俈崋慄偼搶偵恑楬傪曄偊傞丅俆暘懌傜偢偺偲偙傠偵偁傞嫶偺庤慜偺岎嵎揰傪塃愜偡傞偲丄偡偖嵍庤偵捁扟儢嶈岞墍偑偁傞丅 |
||
 |
 |
 |
| 撪杧偵壦偐傞塤堜嫶 | 杮娵擖岥 | 惣屼栧 |
 |
壴姫忛偼杒忋愳惣娸偺抜媢偵抸偐傟丄杮娵偼捁扟儢嶈岞墍偵側偭偰偄傞丅寢峔峀偄忛堟偱丄擇偺娵偼壴姫彫妛峑 / 壴姫梒抰墍 / 晲摽揳 堦懷偱偁傞丅擇偺娵偺撿懁偑嶰偺娵偱丄搶偼屼拰恄幮乮捁扟儢嶈恄幮乯偺曈傝偐傜惣偼壴姫巗栶強偺曈傝偲側傞丅壴姫巗栶強偺曈傝偵戝庤栧偑偁偭偨丅 | |
| 杮娵 | ||
 |
 |
 |
| 捁扟儢嶈恄幮 | 墌忛帥栧 | 壴姫忛帪忇 |
| 壴姫忛嶰偺娵偵捁扟儢嶈恄幮 / 嫬撪偵堏抸偝傟偨墌忛帥栧 偑偁傞丅墌忛帥栧偼榓夑巵偺嫃忛偱偁偭偨旘惃忛偺捛庤栧傪宑挿侾俋擭乮侾俇侾係擭乯偵堏抸偟偨傕偺丅壴姫忛嶰偺娵潕庤偺墌忛帥嶁偵堏抸偝傟偨偨傔丄墌忛帥栧偲柦柤偝傟偨丅柧帯係擭乮侾俉俈侾擭乯壴姫忛庢傝夡偟偺偲偒丄屄恖偵暐偄壓偘傜傟帺揁偺栧偲偟偨丅徍榓俈擭乮侾俋俁俀擭乯偙偺栧傪峸擖丄屼拰恄幮乮捁扟儢嶈恄幮乯捁扟儢嶈恄幮嫬撪偵堏抸偟偨丅 |
||
| 慜嬨擭偺栶乮侾侽俆侾擭乣侾侽俇俀擭乯偺崰丄埨攞棅帪偺忛嶒偑偁偭偨偲偙傠偲塢傢傟偰偄傞丅暥帯俆擭乮侾侾俉俋擭乯偺墱廈崌愴偵傛偭偰棨墱崙旴娧孲傪梌偊傜傟偨旴娧乮傂偊偸偒乯巵偼丄嫕榎擭娫乮侾俆俀俉擭乣侾俆俁俀擭乯偵杮忛傪捁扟儢嶈偵堏偟偨丅揤惓侾俉擭乮侾俆俋侽擭乯朙恇廏媑偺墱廈巇抲偵傛偭偰丄彫揷尨偵嶲恮偟側偐偭偨榓夑媊拤
/ 旴娧峀拤 偼丄強椞杤廂偺張暘偲側偭偨丅 旴娧孲偼撿晹椞偲側傝丄撿晹怣捈偺戙姱丒杒廏垽偑忛戙偲偟偰擖傞丅捁扟儢嶈忛偺夵廋偑峴傢傟丄壴姫忛偲夵徧偝傟偨丅 |
||
| 棨墱崙丒堦娭忛乮掁嶳娰 / 崅嶈忛乯 | ||
 |
仭忛偺庬暿 嶳忛 仭抸忛幰 嶁忋揷懞杻楥 仭抸忛擭 暯埨帪戙弶婜 仭庡側堚峔 杧 / 嬋椫 / 堏抸戝庤栧 仭庡側嵞寶憿暔 斔庡偺堜屗 / 惔埩儢抮 |
|
| 愮忯晘 | ||
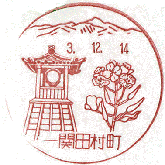 |
俰俼搶杒杮慄丒堦僲娭墂惣岥傛傝俁係俀崋慄傪惣偵恑傓丅俆暘傎偳偺塃庤偵堦娭揷懞梄曋嬊偑偁傞丅晽宨報偼丄恵愳妜 / 帪偺懢屰 / 巗壴丒嵷偺壴 偺恾暱偵側偭偰偄傞丅 | |
| 堦娭揷懞梄曋嬊晽宨報 | ||
 |
 |
偡偖偵塃愜偟偰杒偵恑傓偲丄偡偖塃庤偵媽徖揷壠晲壠廧戭偑偁傞丅峕屗帪戙屻婜偵寶偰傜傟偨堦娭斔壠榁怑傪嬑傔偨徖揷壠偺媽戭丅 |
| 媽徖揷壠晲壠廧戭 | ||
 |
俁係俀崋慄傑偱栠傝惣偵恑傓丅偡偖偺斨堜愳庤慜傪嵍愜偟偰撿偵恑傓偲丄偡偖嵍庤偵怱帤儢抮 / 揷懞壠嫃娰愓偺挀幵応 / 摴傪嫴傫偱掁嶳岞墍 偑偁傞丅 乵岎捠乶俰俼搶杒杮慄丒堦僲娭墂-乮搆曕侾俆暘乯-掁嶳岞墍 |
|
| 怱帤儢抮 | ||
 |
 |
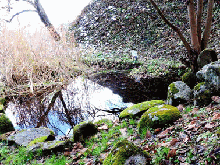 |
| 斔庡偺堜屗 / 惔埩儢抮偺嬋椫傪朷傓 | 斔庡偺堜屗 | 惔埩儢抮 |
| 堦娭忛偼斨堜愳偵柺偟偨掁嶳偵抸偐傟偰偍傝丄掁嶳岞墍偲側偭偰偄傞丅掁嶳岞墍擖岥偐傜嶁傪搊傝嫶傪搉傞丅揷懞嶁傪摴側傝偵搊傞偲丄嵍庤偵暅尦偝傟偨乬斔庡偺堜屗乭傗乬惔埩儢抮乭偑偁傞丅 | ||
 |
 |
 |
| 庡妔傪朷傓 | 揷懞恄幮 | 偺傠偟戜愓 |
| 惔埩儢抮偐傜嵍曽岦偵恑傒嶁傪搊傞偲丄嶳捀偵庡妔偲偝傟傞愮忯晘偵揷懞恄幮 / 偺傠偟戜愓 偑偁傞丅 | ||
 |
愮忯晘塃曽岦偵恑傓偲丄偍偝傫堫壸恄幮偑尒偊傞丅奒抜傪壓傝摴側傝偵恑傓偲丄擔杮掚墍偐傜旛峳惔埩栰憪墍傪宱偰乬斔庡偺堜屗乭偵帄傞丅 |
|
| 偍偝傫堫壸恄幮 | ||
|
暯埨帪戙弶婜偵壼埼摙敯偱墦惇偟偨嶁忋揷懞杻楥偑恮傪峔偊丄崅嶈忛偲柦柤偟偨偲塢傢傟偰偄傞丅揤婌擭娫乮侾侽俆俁擭乣侾侽俆俉擭乯権廁偺挿偱偁傞埨攞掑擟偺掜丒斨堜壠擟偑嵲偲偟偰巊梡偟偨丅慜嬨擭偺栶乮侾侽俆侾擭乣侾侽俇俀擭乯偱埨攞巵偼柵朣偡傞丅暥帯5擭乮侾侾俉俋擭乯尮棅挬偵傛傞墱廈崌愴偱墱廈丒摗尨巵偑柵朣偡傞偲丄岟愌偑偁偭偨妺惣惔廳偑墱廈憤曭峴偵擟偤傜傟偰妺惣巵偺強椞偲側偭偨丅妺惣巵偼晲憼丒暯捤忛偺朙搱巵偺堦懓偱丄愇姫忛傪杮嫆偲偟偨丅堦娭忛偵偼壠恇偺嫽揷巵
/ 崅嶈巵 / 彫栰帥摴徠 偑嫃忛偲偟偨丅 |
||
| 堏抸忛栧 | ||
 |
暯愹丒栄墇帥嶳栧偼丄戝惓侾侽擭乮侾俋俀侾擭乯堦娭忛偺戝庤栧傪堏抸偟偨傕偺丅 | |
| 栄墇帥嶳栧 | ||
 |
 |
俰俼搶杒杮慄丒暯愹墂傛傝惣偵恑傓偲丄撍偒摉傝偵壝徦俁擭乮俉俆侽擭乯拞懜帥偲摨擭偵憂寶偝傟偨栄墇帥偑偁傞丅壩嵭傗暫壩 偵傛傝峳攑丄姲暥擭娫乮侾俇俇侾擭?侾俇俈俀擭乯偵偼悈揷偵側偭偰偄偨丅暯惉尦擭乮侾俋俉俋擭乯暯埨帪戙偺杮摪偑嵞寶偝傟偨丅 |
| 栄墇帥杮摪 | 栄墇帥忩搚掚墍 | |
| 棨墱崙丒敧屗忛 | ||
 |
仭忛偺庬暿 暯嶳忛 仭抸忛幰 拞娰怣彆 仭抸忛擭 幒挰帪戙弶婜 仭庡側堚峔 妏屼揳昞栧 / 敧屗忛搶栧 / 搚椲 |
|
| 敧屗忛杮娵愓 | ||
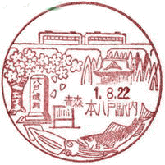 |
俰俼敧屗慄丒杮敧屗墂撿岥傪弌傞偲丄塃庤偵惵怷杮敧屗墂撪梄曋嬊偑偁傞丅晽宨報偼丄俰俼敧屗慄 / 嶰敧忛岞墍乮嶗丒敧屗忛毈丒嶰敧忛恄幮乯 / 敧屗嫏峘偵悈梘偘偝傟傞僀僇偲僒僶
偺恾暱偵側偭偰偄傞丅 乵岎捠乶俰俼敧屗慄丒杮敧屗墂-乮搆曕/栺俆暘乯-嶰敧忛岞墍 |
|
| 惵怷杮敧屗墂撪梄曋嬊晽宨報 | ||
 |
 |
 |
| 敧屗忛愓 愇拰 | 敧屗忛愓偺旇 | 嶰敧忛恄幮 |
| 崻忛撿晹巵俀戙丒撿晹惌挿偺俁抝丒拞娰乮側偐偩偰乯怣彆偑幒挰帪戙弶婜偵抸忛偟偨偺偑巒傑傝偲塢傢傟偰偄傞丅姲塱係擭乮侾俇俀俈擭乯崻忛撿晹巵俀俀戙丒撿晹捈媊偑墦栰丒墶揷忛偵堏晻偲側傞偲丄拞娰巵傕廬偆丅敧屗偼捗寉椞偲愙偡傞梫徴偱偁偭偨偙偲偐傜丄敧屗偼撿晹斔偺捈妽抧偲偟偰戙姱偑巟攝偟偨丅 姲暥係擭乮侾俇俇係擭乯惙壀斔俁戙斔庡丒撿晹廳捈偑巏巕傪掕傔偢偵昦杤偡傞丅枊晎偺嵸掕偵傛傝堚椞侾侽枩愇傪撿晹廳捈偺俀恖偺掜丄幍屗廳怣偵杮斔俉枩愇 / 拞棦悢攏偺敧屗斔俀枩愇偵暘妱偟偨丅 尦榎尦擭乮侾俇俉俉擭乯俀戙斔庡丒撿晹捈惌偼丄俆戙彨孯摽愳峧媑偺懁梡恖偵側傝晥戙戝柤暲偺懸嬾傪庴偗偰偄偨丅 |
||
 |
 |
敧屗巗栶強偺俀俁崋慄傪嫴傫偩斀懳懁偵丄撿晹夛娰偑偁傞丅妏屼揳昞栧偼屆嶗栧偲傕屇偽傟丄撿晹夛娰偺昞栧偲側偭偰偄傞丅敧屗忛搶栧偼埨惌俉擭乮侾俉俆俋擭乯戜晽偱搢傟丄敧屗斔偺壠榁偵暐偄壓偘傜傟偨丅敧屗崻忛愓偵堏抸偝傟丄尰嵼偼崻忛巎愓偺峀応擖岥偲側偭偰偄傞丅 |
| 敧屗忛妏屼揳昞栧 | 媽敧屗忛搶栧 | |
| 棨墱崙丒敧屗崻忛 | ||
 |
仭忛偺庬暿 暯嶳忛 仭抸忛幰 撿晹巘峴 仭抸忛擭 仭庡側堚峔 搚椲 / 嬻杧 / 堜屗 仭庡側嵞寶憿暔 庡揳 / 拞攏壆 / 岺朳 / 抌栬岺朳 / 斅憅 / 擺壆 |
|
| 敧屗崻忛杮娵愓 | ||
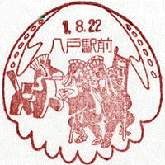 |
俰俼搶杒怴姴慄 / 敧屗慄 / 惵偄怷揝摴丒敧屗墂偐傜偡偖偺敧屗墂慜岎嵎揰偺撿惣懁偵丄敧屗墂慜梄曋嬊偑偁傞丅晽宨報偼丄僀僇偺奜榞 / 嫿搚娺嬶丒敧敠攏
/ 弶弔偺恄帠丒偊傫傇傝 偺恾暱偵側偭偰偄傞丅 |
|
| 敧屗墂慜梄曋嬊晽宨報 | ||
 |
敧屗墂慜岎嵎揰偐傜撿搶偵恑傓丅偡偖偺岎嵎揰傪嵍愜偟偰俀侽崋慄傪搶偵恑傓丅侾侽暘傎偳偺嵍庤偵敧屗惣梄曋嬊偑偁傞丅晽宨報偼丄嫿搚娺嬶丒敧敠攏 / 媏 偺恾暱偵側偭偰偄傞丅 | |
| 敧屗惣梄曋嬊晽宨報 | ||
乵岎捠乶俰俼搶杒怴姴慄 / 敧屗慄 / 惵偄怷揝摴丒敧屗墂-乮搆曕/栺係俆暘乯-崻忛巎愓偺峀応擖岥 |
||
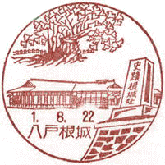 |
侾侽係崋慄傪捈恑偡傞偲丄偡偖塃庤偵敧屗崻忛梄曋嬊偑偁傞丅晽宨報偼丄嬧埱 / 敧屗崻忛 偺恾暱偵側偭偰偄傞丅 | |
| 敧屗崻忛梄曋嬊晽宨報 | ||
 |
 |
 |
| 媽敧屗忛搶栧 | 嬻杧愓 | 惣懁偐傜尒偨杮娵愓 |
撿晹巘峴偺巕懛偼丄崻忛撿晹巵 / 敧屗撿晹巵 / 敧屗巵 傪徧偟偨丅撿晹巵偺側偐偱傕斾妑揑戝偒側惃椡傪桳偟偰偍傝丄摉弶偼撿晹廆壠偵埵抲晅偗傜傟偰偄偨偲塢傢傟偰偄傞丅 揤惓侾俉擭乮侾俆俋侽擭乯嶰屗撿晹巵丒撿晹怣捈偼彫揷尨惇敯傊嶲恮丄朙恇廏媑偐傜強椞傪埨揼偝傟傞丅 敧屗巗崻忛巎愓偺峀応擖岥偵偁傞搶栧偼丄媽敧屗忛搶栧傪堏抸偟偨傕偺丅 |
||
| 棨墱崙丒嶰屗忛乮棷儢嶈忛乯 | ||
 |
仭忛偺庬暿 嶳忛 仭抸忛幰 撿晹惏惌 仭抸忛擭 仭庡側堚峔 昞栧乮棿愳帥嶳栧乯 / 潕庤栧乮朄愹帥嶳栧乯 / 戙姱強栧乮娤暉帥嶳栧乯 / 愇奯 / 嬋椫 仭庡側嵞寶憿暔 柾媅揤庣乮嶰屗忛壏屘娰乯 / 峧屼栧 |
|
| 嶰屗忛柾媅揤庣 | ||
 |
惵偄怷揝摴丒嶰屗墂偐傜惣傊恑傓偲丄俀俉俆崋慄偵撍偒摉偨傞丅岎嵎揰傪塃愜偟偰杒偵恑傓偲丄偡偖嵍庤偵嶰屗墂慜梄曋嬊偑偁傞丅晽宨報偼丄柤媣堜妜 /
撿晹嵳傝 / 壊扥 偺恾暱偵側偭偰偄傞丅 |
|
| 嶰屗墂慜梄曋嬊晽宨報 | ||
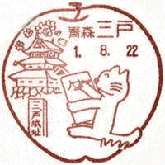 |
岎嵎揰傑偱栠傝丄俀俉俆崋慄傪撿偵恑傓丅侾侽暘懌傜偢偺尦栘暯岎嵎揰傪捈恑偡傞丅 |
|
| 嶰屗梄曋嬊晽宨報 | ||
 |
惵偄怷揝摴丒嶰屗墂偼惵怷導嶰屗孲撿晹挰 / 嶰屗忛愓偼惵怷導嶰屗孲嶰屗挰偺巗奨抧拞怱晹 偵埵抲偟偰偄傞丅嶰屗挰偺儅儞儂乕儖偼丄嶰屗挰偺儅僗僐僢僩丒偸偐傋偊
/ 嶰屗忛柾媅揤庣 偺恾暱偵側偭偰偄傞丅嶰屗忛偼攏暎愳偲孎尨愳偺怹怘偵傛偭偰宍惉偝傟偨壨娸抜媢偵偁傞嶳忛偱偁傞丅椉壨愳傪揤慠偺悈杧偲偟丄廃埻傛傝屒棫偟偨戜抧偵側偭偰偄傞丅 |
|
| 嶰屗挰儅儞儂乕儖 | ||
 |
 |
 |
| 嶰屗忛愓 愇拰 | 愇奯 | 峟晹恄幮 |
|
墱廈撿晹巵偼峛斻尮巵偺巕懛偱丄暥帯俆擭乮侾侾俉俋擭乯墱廈摗尨巵摙敯偺愴岟偵傛偭偰棨墱崙峟晹屲孲傪椞偡傞偙偲偵側傞丅墱廈撿晹巵弶戙丒撿晹岝峴偼寶媣俀擭乮侾侾俋侾擭乯偵擖崙偡傞丅嶰屗忛偼丄揤暥俉擭乮侾俆俁俋擭乯撿晹惏惌傛偭偰抸忛偝傟偨偲塢傢傟偰偄傞丅 |
||
| 棨墱崙丒峅慜忛乮戦壀忛 / 崅壀忛乯 | ||
 |
仭忛偺庬暿 暯忛 仭抸忛幰 捗寉怣杚 仭抸忛擭 宑挿侾俇擭乮侾俇侾侾擭乯 仭庡側堚峔 揤庣乮廳暥乯丒扖枻楨乮廳暥乯丒塏撔楨乮廳暥乯丒枹怽楨乮廳暥乯丒捛庤栧乮廳暥乯丒搶栧乮廳暥乯丒撿撪栧乮廳暥乯丒搶撪栧乮廳暥乯丒杒栧乮廳暥乯 |
|
| 揤庣 | ||
| 峅慜僶僗僙儞僞乕偐傜杒惣偵恑傒丄俈崋慄傪嵍愜偡傞丅廧媑擖岥岎嵎揰傪塃愜偡傞偲丄嵍庤偵姲墑俁擭乮侾俈俆侽擭乯憂寶偺岇崚恄幮偲徏旜恄幮偑偁傞丅峅撿揹揝偺摜傒愗傝傪墇偊捈偖偵嵍愜偡傞偲丄塃庤偵揤暥尦擭乮侾俆俁俀擭乯憂寶偺嵟彑堾偑尒偊偰偔傞丅姲暥俈擭乮侾俇俇俈擭乯寶棫偺屲廳搩乮廳暥乯偑偁傞丅椬偵偁傞峅慜敧嶁恄幮懁偐傜惣傊恑傓偲怴帥挰偵擖傞丅嵍懁偵戃媨帥丄塃懁偵愒偄捁嫃偑暲傇怴帥挰堫壸恄幮偑偁傞丅宑埨俁擭乮侾俇俆侽擭乯偵帥堾奨偵側偭偨偲偙傠偱丄埬撪斅傪尒傞偲俀俁傕偺帥偑暲傫偱偄傞丅怴帥挰妏岎嵎揰傪杒傊恑傒丄摗怷撿岥岎嵎揰傪嵍愜偡傞丅捈偖偵塃愜偡傞偲墱偵峅慜揤枮媨偺捁嫃偑尒偊傞丅俀杮栚偺摴傪嵍愜偡傞偲慣椦奨偱慣帥俁俁傕偺帥偑暲傫偱偄傞丅慣帥偑椦偺傛偆偵暲傫偱偄傞偙偲偐傜慣椦奨偲屇偽傟傞條偵側偭偨丅墱偵崟栧偑尒偊傞丅塃庤偵巕堢抧憼懜偑偁傝丄椬偺愒栧偐傜塃傊擖傞丅摴側傝偵恑傓偲撍偒摉偨傝偵廆摽帥偑偁傝丄彮偟栠傝塃愜偟偰彫摴傪恑傓丅捠傝偵弌傞偲嵍庤偵崟栧偑尒偊傞丅 | ||
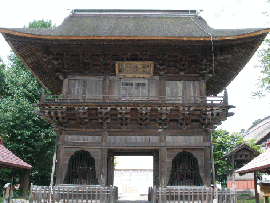 |
撍偒摉偨傝偵丄嫕榎尦擭乮侾俆俀俉擭乯憂寶偺挿彑帥偑偁傞丅嶰栧丒屼塭摪丒夵廋拞偺杮摪丒屔棤丒捗寉壠楈壆丒摵忇偑廳暥偲側偭偰偄傞丅 | |
| 挿彑帥嶰栧 | ||
| 崟栧曽岦傊恑傓偲丄崟栧偺庤慜塃庤偵揤曐侾侽擭乮侾俉俁俋擭乯寶棫偺偝偞偊摪偑偁傞丅愒栧偐傜搶傊恑傒丄T帤楬傪嵍愜偡傞偲峅慜揤枮媨偑偁傞丅嫬撪偐傜搶傊恑傒捠傝傪嵍愜偡傞丅偝傜偵T帤楬傪嵍愜丄偟偽傜偔偡傞偲宑挿尦擭乮侾俆俋俇擭乯憂寶偺惥婅帥傊偺摴昗偑偁傞丅塃愜偟偰杒傊恑偲丄峕屗帪戙拞婜寶棫偺掃婽栧偲傕屇偽傟偰偄傞嶳栧乮廳暥乯偑尒偊偰偔傞丅嶳栧慜傪搶傊恑傓偲丄峅慜忛偵帄傞丅暥壔俈擭乮侾俉侾侽擭乯嵞寶偝傟偨揤庣偼丄侾俀売強巆偝傟偰偄傞尰懚揤庣偺堦偮偱偁傞丅巗柉懱堢娰岥偐傜惣崍増偄偺嶗暲栘傪杒傊丄弔梲嫶傪搉傞丅撿傊曽岦傪曄偊丄撿撪栧乮廳暥乯偐傜揤庣乮廳暥乯偑尒偊傞壓忔嫶偵恑傓丅搶撪栧乮廳暥乯偐傜搶栧乮廳暥乯傊丄傆偨偨傃搶撪栧曽岦偵栠傝杒傊恑傓丅塏撔楨乮廳暥乯偐傜杒栧乮廳暥乯傊丄杒栧庤慜偺嵍懁偵偼岇崙恄幮偑偁傞丅杒栧偐傜弌傞偲丄岦偐偄懁偵斔惌帪戙偺崑彜丒愇応壠乮廳暥乯偑偁傞丅崍増偄偵撿傊恑傓丅偝傜偵搶栧偺慜傪嵍愜搶傊恑傓丅梄曋嬊偺偁傞彫摴傪恑傓偲尦榓俁擭乮侾俇侾俈擭乯憂寶偺幙慺側峅慜搶徠媨偑偁傞丅峅慜搶徠媨慜偺摴傪惣傊恑傓偲栻墹堾偑偁傞丅搶栧傑偱栠傝崍増偄偵撿傊丄偝傜偵惣傊恑傓偲捛庤栧乮廳暥乯偑偁傞丅捠傝傪栠傝捈恑偡傞偲丄塃庤偵惵怷嬧峴帒椏娰乮廳暥乯偑尒偊偰偔傞丅T帤楬傪嵍愜偟偰俀杮栚偺摴傪塃愜偡傞偲丄峅慜僶僗僙儞僞乕慜偐傜峅慜墂偵帄傞丅 乵岎捠乶峅慜僶僗僙儞僞乕-乮搆曕/栺俁侽暘乯-嵟彑堾-乮搆曕/栺俆暘乯-怴帥挰-乮搆曕/栺侾俆暘乯-慣椦奨愒栧-乮搆曕/栺俁侽暘乯-惥婅帥-乮搆曕/栺俁侽暘乯-壓忔嫶-乮搆曕/栺俆俆暘乯-搶徠媨-乮搆曕/栺俀侽暘乯-捛庤栧-乮搆曕/栺係侽暘乯-峅慜墂 |
||
| 棨墱崙丒埨攞娰愓 | ||
 |
仭忛偺庬暿 嶒 仭抸忛幰 埨攞巵 仭庡側堚峔 嬻杧 |
|
| 埨攞娰愓 昗拰 | ||
 |
 |
偄傢偰嬧壨揝摴丒惵嶳墂偐傜搶偵恑傓丅偡偖偺俿帤楬岎嵎揰傪塃愜偟偰撿偵恑傓丅俆暘懌傜偢偺嵍庤偵丄埨攞娰愓偑偁傞丅嬻杧偐傜搶懁傪棳傟傞杒忋愳曽岦偵恑傓偲丄悀愳敧敠媨偑偁傞丅 乵岎捠乶偄傢偰嬧壨揝摴丒惵嶳墂-乮搆曕/栺侾侽暘乯-埨攞娰愓 |
| 嬻杧 | 悀愳敧敠媨 | |
| 悀愳嶒乮偔傝傗偑傢偺偝偔乯愓偱丄墱榋孲乮尰丗墱廈巗偐傜惙壀巗偺抧堟乯傪嫆揰偲偟偰偄偨埨攞巵偺娰偑偁偭偨偲偙傠偲塢傢傟偰偄傞丅 埨攞巵偺弌栚偼夝偭偰偄側偄丅搶埼偺廢挿偲偝傟傞埨攞拤棅埲慜偺妋偐側宯恾偼晄柧偲偝傟傞丅埨攞拤棅埲崀丄埨攞拤椙仺埨攞棅帪仺埨攞掑擟 偲懕偔丅埨攞棅帪偺偲偒偑嵟惙婜偱丄峟晹乮尰丗惵怷導搶晹乯偐傜榡棟丒埳嬶乮尰丗媨忛導撿晹乯偵惃椡傪峀傔偰偄偨丅 慜嬨擭偺栶乮侾侽俆侾擭乣侾侽俇俀擭乯偺揤婌俆擭乮侾侽俆俈擭乯偵埨攞棅帪偼丄尮棅媊偵摙偨傟傞丅峃暯俆擭乮侾侽俇俀擭乯埨攞棅帪偺師抝丒埨攞掑擟偼丄尮棅媊偵摙偨傟傞丅埨攞棅帪嶰抝丒埨攞廆擟偼埳梊崙 / 巐抝丒埨攞惓擟偼旍屻崙 偵攝棳偝傟偨丅埲屻丄惔尨巵偑悀愳傪椞偡傞丅 暥帯俆擭乮侾侾俉俋擭乯姍憅枊晎偺屼壠恖丒岺摗峴岝偼娾庤孲偺抧摢偲側傝丄岺摗巵偺娰丒悀愳娰偑偁偭偨偲偙傠偲偝傟傞丅 |
||
| 棨墱崙丒惙壀忛乮晄棃曽忛乯 | ||
 |
仭忛偺庬暿 暯嶳忛 仭抸忛幰 撿晹怣捈 仭抸忛擭 宑挿俀擭乮侾俋俆俉擭乯 仭庡側堚峔 搚憼丒愇奯丒杧 曬壎慣帥傗惔悈帥偵丄堏抸偝傟偨偲塢傢傟傞忛栧偑偁傞丅 |
|
| 杮娵愇奯 | ||
|
俰俼惙壀墂偐傜搶傊丄奐塣嫶傪搉傞丅屲嵎楬偺奐塣嫶搶岎嵎揰傪撿搶傊恑傓偲丄撍偒摉偨傝偵偁傞丅惙壀斔撿晹巵偺嫃忛丅 |
||
| 棨墱崙丒崟戲怟嶒愓 | ||
 |
仭忛偺庬暿 忛嵲廤棊 仭抸忛幰 埨攞惓擟 仭抸忛擭 暯埨帪戙乮俈俋係擭乣侾侾俋俀擭崰乯屻婜 |
|
| 崟戲怟嶒愓偲埬撪斅 | ||
| 俰俼杒忋墂偐傜搶傊侾侽俈崋慄傪杒傊恑傓偲丄塃庤偵埨攞娰岞墍乮愳娸堚愓乯偑偁傞丅棨墱偺崑懓埨攞巵偵傛偭偰丄杒忋愳増偄偵憿塩偝傟偨嶒偺堦偮丅愴崙帪戙偺忛偲堎側傝丄廤棊傪嶒楍偱墌宍埻傫偱偄偨丅慜嬨擭偺栶偑廔傢傞峃暯俆擭乮侾侽俇俀擭乯偵丄崟戲怟嶒傕棊偪傞丅 乵岎捠乶杒忋墂-乮搆曕/栺俆暘乯-埨攞娰岞墍 |
||