| 東海道53次 No.44 草津追分-(約12.5km)-膳所駅 |
| 2010年 7月 3日(土)09:30 雨 |
|
| 中山道69次 No.43 草津追分-(約15km)-大津駅 |
| 2013年 4月17日(水)08:15 晴のち曇り |
|
| 草津駅東口より南西に進む。すぐの交差点を左折、旧中山道を南西へ進む。すぐの十字路は、明治19年(1886年)旧草津川隧道(トンネル)開通後に東海道と中山道の分岐点になったところ。交差点から5分ほどの草津川隧道を通ると、草津追分。 |
|
 |
 |
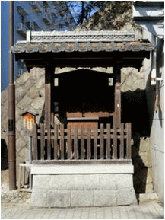 |
| 草津川隧道 |
道標を兼ねた常夜燈 |
高札場 |
|
 |
 |
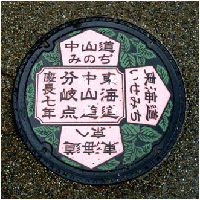 |
| 延命地蔵 |
マンホール |
|
 |
 |
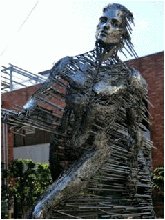 |
| 草津町道路元標 |
書状集箱 |
オブジェ |
|
| 草津追分は東海道と中山道が分岐・合流するところ。北東側に草津川隧道(トンネル) / 東側の高台に文化13年(1816年)造立の道標を兼ねた常夜燈があり、「左 中仙道 美のじ」「右 東海道 いせみち」と彫られている。西側に高札場と延命地蔵
/ 合流する路面にカラフルなマンホール がある。南側の草津公民館前に、草津町道路元標 / 明治4年(1871年)当時に復元された書状集箱(現役の郵便ポスト)
/ 「近江路や秋のくさつはなのみして 花咲くのべぞ何處ともなき」尭孝法師句碑 / 旅人が行き交う時間を表現したオブジェがある。 |
|
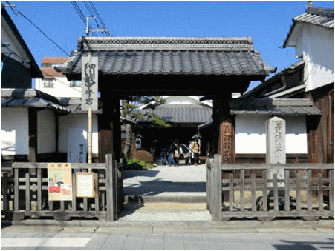 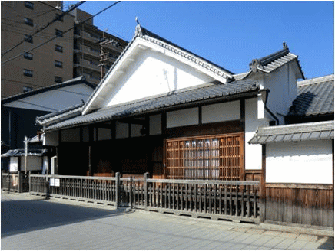 |
| 草津宿本陣 |
|
 |
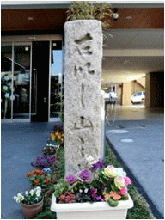 |
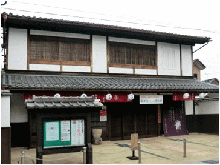 |
| 脇本陣跡 |
不明の道標 |
草津宿街道交流館 |
|
 |
 |
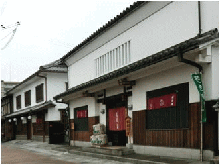 |
| 常善寺 |
正定寺 |
太田酒造 |
|
|
草津追分から南西へ進むと、すぐ右手に草津宿本陣(国指定史跡)がある。宿帳には、吉良上野介 / 浅野内匠頭 / 皇女和宮 / シーボルト / 近藤勇
などが記載されている。左手の脇本陣跡に草津市観光物産館 / 左手に不明の道標 / 右手に草津宿街道交流館(有料施設) / 右手に天平7年(735年)創建と云われる常善寺
/ 左手に寛永15年(1634年)創建の正定寺 / 左手の太田酒造に“草津宿と政所”案内板 と続く。太田酒造は、江戸築城で知られる太田道灌の末裔が営む酒造。この辺りには人馬継立業務や宿の管理を行う問屋場や貫目改所があり、草津の政所と言われてきた。草津追分から太田酒造まで5分ほどの距離である。
|
|
 |
 |
 |
| 伯母川に架かる参道の橋 |
伯母川に架かる立木橋 |
立木神社鳥居 |
|
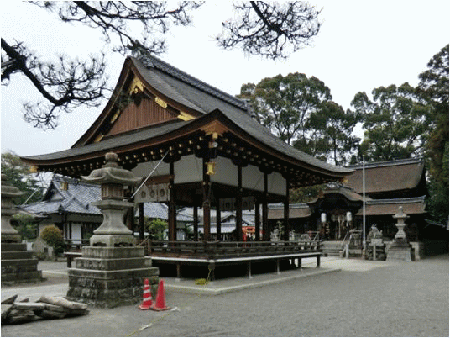 |
太田酒造からすぐに立木神社前交差点があり、右手に伯母(おば)川に架かる立木神社参道の橋が見える。伯母川に架かる立木橋を渡ると、すぐ右手に神護景雲元年(767年)創建と云われる立木神社がある。旧草津村(草津宿)と旧矢倉村の氏神で、かつては境内に神宮寺があった。明治元年(1868年)神仏分離により、神宮寺は草津市草津一丁目に移転される。 |
| 立木神社 |
|
 |
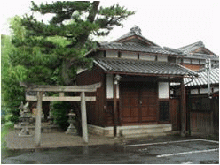 |
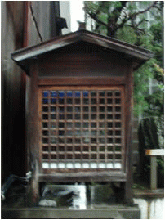 |
| 光伝寺 |
武甕槌神社 |
地蔵の祠 |
|
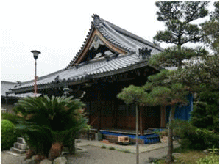 |
 |
 |
| 養蓮寺 |
地蔵の祠 |
矢橋追分道標 |
|
|
立木神社からすぐに、新草津川に架かる矢倉橋を渡る。すぐ左手に承平年間(931年〜938年)創建の光伝寺がある。鎌倉時代作の阿弥陀如来坐像は重文。すぐ右手に武甕槌神社
/ 右手に地蔵の祠 / 左手に天平2年(730年)創建の養蓮寺 / 右手に地蔵の祠 / 右手に寛政10年(1798年)造立矢橋追分道標「右 や者せ道
古連より廿五丁 大津へ船わ多し」 と続く。矢橋の渡し場に通じる矢橋道と東海道の分岐点で、草津の名物・姥が餅(うばがもち)屋があったところ。姥が餅の起源については諸説があるが、江戸時代に街道が整備された頃には存在していたと云われている。よく知られているのが「近江源氏・佐々木義賢が織田信長に滅ぼされる。3才になる遺児を託された乳母が養育のため、餅を作って街道を行き交う人々に売り歩いた」由来。明治時代になると交通手段は徒歩から汽船や鉄道へと変化、店も対応するために移転している。
|
|
 |
 |
 |
| 愛宕神社 |
道祖神の祠 |
地蔵の祠 |
|
 |
 |
矢橋追分道標からすぐのT字路を右折すると、すぐ左手に愛宕神社がある。街道に戻り南西へ進むと、すぐ左手に道祖神の祠 / 右手に地蔵の祠 / 左手に稲荷神社
と続く。朱色の鳥居が続く参道を進んだ奥に社殿がある。 |
| 稲荷神社 |
|
 |
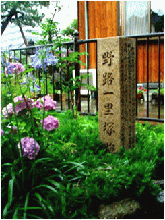 |
 |
| 上北池公園 |
野路一里塚跡 |
案内地図 |
|
| 稲荷神社からすぐに1号線と斜めに交差する。矢倉南交差点で1号線を横断する。細い道を進むと、一里塚跡の看板が見える。左折すると右手の上北池公園に野路一里塚跡石標がある。野路一里塚は、ここから北西30mと道を挟んだ北東20mの2ヶ所にあった。右手の野路交差点で“かがやき通り”を横断して迂回する。この区間は、旧東海道のときに引き続き、旧中山道でも迷っている。野路交差点にある案内地図を見ていると、地元の方に声を掛けられる。電線だけが旧東海道に沿っているとのこと。確かに電線は直線で結ばれている。旧東海道のときは、“かがやき通り”沿いの店で昼食を摂っている。 |
|
 |
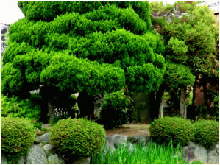 |
 |
| 教善寺 |
清宗塚 |
地蔵の祠 |
|
 |
 |
 |
| 浄泉寺 |
新宮神社鳥居 |
願林寺 |
|
 |
案内地図から“かがやき通り”を東へ、すぐに右折して南へ進む。すぐ左手に教善寺 / 右手の塀の上に清宗塚案内板 と続く。門から清宗塚(胴塚)が見える。平家は壇ノ浦合戦で敗れ、建礼門院 / 平宗盛 / 平清宗 / 平時忠は捕えられる。平宗盛・平清宗親子は源義経に連れられて鎌倉へ下ったが、頼朝に追い返される。首を京へ持ち帰るため、平宗盛は野洲篠原 / 平清宗はここ野路で斬首された。清宗塚からすぐの左手に地蔵の祠 / 左手に浄泉寺 / 左手に新宮神社鳥居 / 右手に願林寺 / 右手に石仏群 と続く。 |
| 石仏群 |
|
 |
 |
| 地蔵の祠 |
|
 |
| 野路の玉川 |
地蔵の祠 |
|
 |
 |
| 弁天池 |
|
| 右手に石仏群からすぐの43号線を越えて十禅寺川を渡ると、右手に昭和51年(1976年)に復元された“野路の玉川”がある。野路は平安時代から鎌倉時代にかけて宿駅だったところ。十禅寺川の伏流水の清水が流れる名勝地で、萩が全面に植えられていたことから“野路萩の玉川”とも呼ばれていた。宿駅が野路から草津に移るととともに、江戸末期には泉も枯れて忘れ去られてしまった。“野路の玉川”からすぐの右手に地蔵の祠が2基続く。5分ほどの右手の弁天池に弁財天神社がある。 |
|
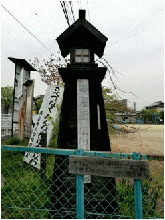 |
 |
 |
| 常夜燈 |
浄安寺 |
常夜燈 |
|
 |
 |
 |
| 地蔵の祠 |
月輪大池道標 |
地蔵の祠 |
|
 |
弁天池沿いに進み、5分ほどすると左手に「東海道狼川」木製常夜燈がある。フェンスに「東海道 草津本陣3.7km 瀬田唐橋4.9km」標識が架かっている。すぐの交差点を直進すると、すぐ右手に浄安寺
/ 右手に「東海道草津宿 これより大津市」木製常夜燈と続く。5分ほどすると、右手に地蔵の祠がある。さらに5分ほどすると 左手に「名勝 月輪大池
南約1籵」道標 / 左手に地蔵の祠、奥に文久3年(1863年)創建の月輪寺がある。 |
| 月輪寺 |
|
 |
 |
 |
| 東海道立場跡 |
地蔵の祠 |
一里塚跡 |
|
| 月輪寺からすぐの交差点を渡った左手に、東海道立場跡 / 背後に昔の名所図会にも紹介された月輪池がある。5分ほどすると左手に地蔵の祠がある。さらに5分ほどすると一里山1丁目交差点の東側に一里塚跡がある。旧東海道は交差点えお直進するが、右折して北西へ進むと、5分ほどの突き当りにJR東海道本線・瀬田駅がある。 |
|
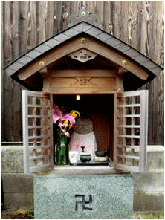 |
一里山1丁目交差点を直進、5分ほどすると左手に地蔵の祠がある。 |
| 地蔵の祠 |
|
 |
 |
 |
| 旧東海道標識 |
祠 |
題目塔(南無妙法蓮華経) / 堂 |
|
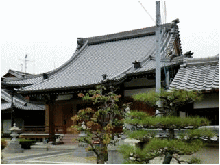 |
地蔵の祠から5分ほどすると十字路の電柱に「←↓旧東海道」標識や案内地図がある。左折すると、すぐ左手に祠 / 右手に題目塔「南無妙法蓮華経」のある堂
と続く。5分ほどすると、電柱に「旧東海道→」標識があり右折する。すぐ右手に浄光寺がある。 |
| 浄光寺 |
|
 |
 |
 |
| 地蔵の祠 |
檜山神社鳥居 |
妙見大菩薩堂 |
|
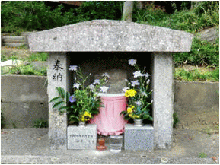 |
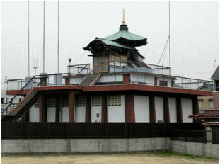 |
浄光寺から5分ほどすると、突当り手前に地図があり左折する。すぐ右手の“たぬき”の横に地蔵の祠 / 左手に建部大社末社・檜山神社鳥居 / 右手に妙見大菩薩堂
/ 左手に地蔵の祠 / 右手に正法寺と続く。 |
| 地蔵の祠 |
正法寺 |
|
 |
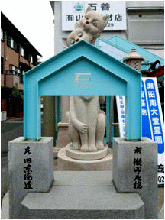 |
 |
| 艶っぽい猫のオブジェ |
「左 旧京街道 右 瀬田唐橋」道標 |
建部大社鳥居 |
|
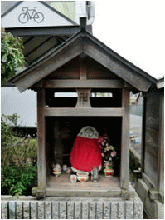 |
 |
 |
| 地蔵の祠 |
地蔵の祠 |
地蔵の祠 |
|
 |
 |
正法寺から直進するとすぐに神領交差点で、16号線と合流する。神領交差点手前左手の艶っぽい猫のオブジェ前に、「左 旧京街道 右 瀬田唐橋」道標があり左折する。すぐに16号線に突き当り、右折する。左手に景行天皇46年(116年)創建と云われる建部大社鳥居が見える。16号線を西へ進む。すぐの神領交差点を直進過ぎると、左手に地蔵の祠が3基 / 右手に「瀬田の唐橋 建部の社」道標 と続く。 |
| 「瀬田の唐橋 建部の社」道標 |
古民家 |
|
 |
 |
 |
| 妙真寺 |
西光寺 |
常夜燈 |
|
 |
 |
 |
| 常夜燈 / 大江匡房句碑 |
雲住寺石標 /龍王宮道標 / 祠 |
不動寺道標 |
|
 |
 |
| 瀬田唐橋擬宝珠 |
|
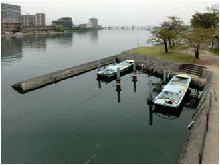 |
| 瀬田唐橋 |
琵琶湖遠望 |
|
| 「瀬田の唐橋 建部の社」道標からすぐの瀬田唐橋手前に唐橋東詰交差点がある。唐橋東詰交差点の北東側に、妙真寺 / 慶長7年(1602年)創建の西光寺
がある。唐橋東詰交差点の北西側橋の袂に常夜燈がある。唐橋東詰交差点の南東側に、寛政12年(1800年)造立の「上田 太神山不動寺 是より二里半」道標がある。唐橋東詰交差点の南西側橋の袂に常夜燈と大江匡房句碑、左手に雲住寺石標
/文化14年(1817年)造立の「跋難陀龍王宮 是より 俵藤太秀郷社 川ばた半丁」道標 / 祠 と並んでいる。雲住寺と龍王宮は南方向にある。瀬田川に架かる瀬田唐橋を渡ると、右手に琵琶湖が見える。瀬田唐橋は琵琶湖から流れ出る瀬田川に架かる橋。奈良時代からの橋で、瀬田川に架かる唯一の橋として交通の要衝であった。源平合戦や応仁の乱などの戦乱のたびに焼け落ち、その都度架け替えられている。鎌倉時代に架け替えられたとき唐様になったため、唐橋と呼ばれる様になったと云われている。俵藤太百足退治伝説がある。蛇に化けて唐橋で寝ていた龍神を跨いだ俵藤太に、三上山に住む仇敵百足退治を依頼した。俵藤太は百足の目を射抜き見事仕留めたと云う話。 |
|
 |
瀬田唐橋は中州で一旦途切れ、再度短い唐橋を渡る。渡り終えたところの唐橋西詰交差点の南東側に社がある。案内板があるが、判読できない。 |
| 社 |
|
|
|
| [寄り道]石山寺 |
|
 |
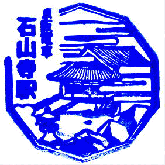 |
 |
| 石山寺駅ロータリー |
京阪電鉄・石山寺駅スタンプ |
朗澄大徳ゆかりの庭園 |
|
| 唐橋西詰交差点を左折して422号線を南へ進む。15分ほどすると、右手に 京阪電鉄・石山寺駅がある。10分ほどすると、右手に朗澄大徳ゆかりの庭園がある。朗澄大徳ゆかりの庭園は、朗澄律師(ろうちょうりっし)が死後に鬼の形になって現れたところと云われている。 |
|
 |
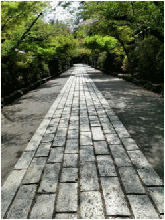 |
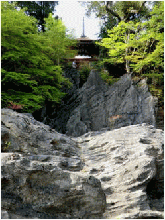 |
| 東大門 |
参道 |
珪灰石 |
|
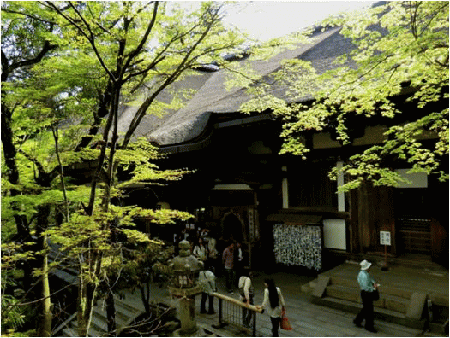 |
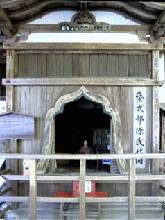 |
| 紫式部源氏の間 |
|
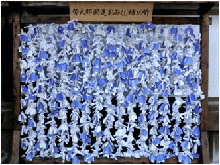 |
| 本堂 |
紫式部開運おみくじ結び所 |
|
 |
|
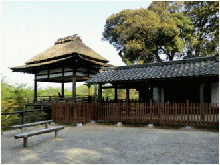 |
| 月見亭 / 芭蕉庵 |
|
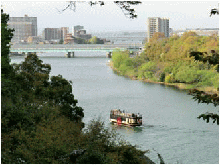 |
| 多宝塔 |
瀬田川眺望 |
|
|
朗澄大徳ゆかりの庭園からすぐの右手に、天平19年(747年)創建の石光山・石山寺がある。琵琶湖の南端近くに位置、琵琶湖から唯一流れ出る瀬田川の右岸にある。永長元年(1096年)再建された本堂(国宝)は珪灰石(国の天然記念物)という巨大な岩盤の上にあり、これが寺名の由来にもなっている。石山寺は兵火に遭わなかったため、東大門(重文)や源頼朝の寄進と云われている建久5年(1194年)建立の多宝塔(国宝)なども残っている。月見亭
/ 芭蕉庵からは、瀬田川が眺望できる。西国三十三所観音第13番札所 / 江州三十三観音1番札所 / 近江三十三観音3番札所 となっている。蜻蛉日記
/ 更級日記 / 枕草子 などにも登場する。本堂内の紫式部源氏の間は、紫式部が源氏物語を執筆したところと云われている。
|
|
|
|
 |
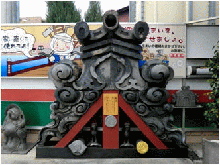 |
| 楼閣に使用されていた瓦 |
福応寺本堂の鬼瓦 |
|
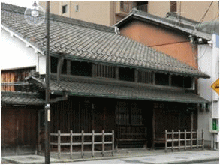 |
 |
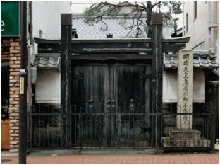 |
| 古民家 |
長徳寺 |
旅籠松屋跡 |
|
 |
唐橋西詰交差点を直進して西へ進むと、すぐ右手に瓦店がある。店先に、百年前に建立された野口家の楼閣に使用されていた瓦の一部 / 愛知県愛西市・福応寺本堂の鬼瓦
などが並んでいる。すぐの京阪石山坂本線踏切を渡ると、すぐの鳥居川交差点の南西側に長徳元年(995年)創建の長徳寺がある。鳥居川交差点を右折して北へ進む。すぐ左手の旅籠松屋があったところに明治天皇鳥居川御小休所石柱がある。5分ほどすると1号線ガード下を潜り、すぐに京阪石山坂本線踏切渡る.。すぐ右手に地蔵の祠
/ すぐに松原町西交差点がある。 |
| 地蔵の祠 |
|
 |
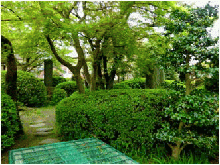 |
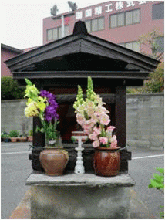 |
| 今井兼平之墓 / 兼平庵 |
地蔵の祠 |
|
 |
松原町西交差点を左折する。旧東海道は少し先で左折するが、JR東海道本線で分断している。右手のJR石山駅コンコースを通り、JR東海道本線を越える。北口から左へ、復活した旧東海道を西へ進む。道なりに5分ほど進むと、左手に今井兼平の墓案内板
/ 左手に今井兼平之墓と兼平庵 / 左手に地蔵の祠 と続く。5分ほどの突き当り手前に“大津の散策路”案内があり、左折するとすぐ右手に社がある。 |
| 社 |
|
 |
 |
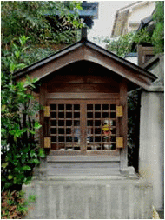 |
| 社 |
浄光寺 |
地蔵の祠 |
|
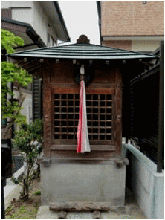 |
 |
 |
| 地蔵の祠 |
地蔵の祠 |
若宮八幡神社表門 |
|
 |
社からすぐに京阪電鉄・石山坂本線の踏切を渡る。すぐの十字路を右折して、狭い道を進む。すぐ右手に社 / 左手に浄光寺 / 左手に地蔵の祠 / 左手に地蔵の祠
/ 右手に地蔵の祠 と続き、道なりに右へ進む。右手に杉浦重剛誕生の地道標があり、旧東海道はすぐに左折して北へ進む。直進して東へ進むと、すぐ左手に若宮八幡神社がある。若宮八幡神社表門は、明治3年(1870年)に廃城になった膳所城本丸の犬走り門を移築したもの。 |
| 若宮八幡神社 |
|
|
|
| [寄り道]松原町西交差点から琵琶湖側を通る道 |
|
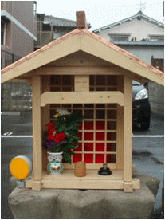 |
 |
 |
| 地蔵の祠 |
地蔵の祠 |
地蔵の祠 |
|
 |
 |
松原町西交差点を直進して南へ進み、JR東海道本線を潜る。 松原町西交差点から5分ほどすると、右手に地蔵の祠 / 突当りで左にカーブする右手に膳所城勢多口総門跡 / 右手に地蔵の祠 と続く。すぐの京阪電鉄・石山坂本線の踏切を渡ると、左手に地蔵の祠 / 右手に白鳳4年(675年)創建の若宮八幡神社がある。 |
| 若宮八幡神社表門 |
若宮八幡神社 |
|
|
|
 |
 |
 |
| 妙福寺 |
京阪電車・瓦ヶ浜駅 |
専光寺 |
|
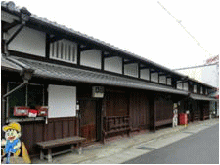 |
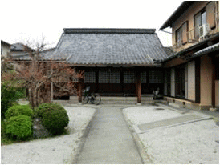 |
 |
| 古民家 |
光源寺 |
篠津神社表門 |
|
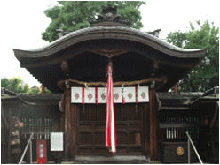 |
南へ進むとすぐ左手に妙福寺がある。すぐの京阪電鉄・石山坂本線の踏切を渡ると、すぐ左手に専光寺 / 左手に光源寺 / 左手に篠津神社 と続く。篠津神社表門は、明治3年(1870年)に移築された膳所城北大手門。 |
| 篠津神社 |
|
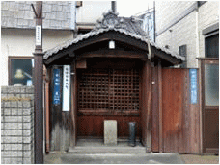 |
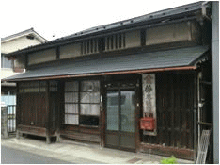 |
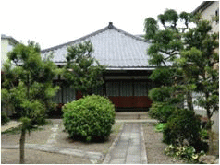 |
| 地蔵の祠 |
古民家 |
景沢寺 |
|
 |
篠津神社からすぐの突き当たりを、道なりに左へ進む。京阪電鉄・石山坂本線の踏切手前にある交差点を右折して北へ進むと、すぐ右手に地蔵の祠 / 右手に景沢寺
/ 左手に大養寺 と続く。 |
| 大養寺 |
|
 |
 |
大養寺からすぐの交差点を左折して西へ進むと、桝形の角に膳所神社がある。膳所神社表門は、明治3年(1870年)に移築された膳所城本丸大手門(重文)。 |
| 膳所神社表門 |
膳所神社 |
|
 |
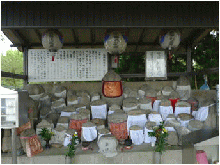 |
交差点から東へ進むと、慶長6年(1601年)築城の膳所城址がある。明治3年(1870年)膳所城は廃城、本丸 / 二の丸 / 三の丸から姿を現した60基の石鹿地蔵は、比叡山にあった石地蔵。元亀2年(1571年)織田信長による比叡山を焼き打ち後、比叡山にあった石地蔵を坂本城の礎石にする。天正14年(1586年)大津城築城に転用する。膳所城築城に再度転用する。 |
| 膳所城址碑 |
石鹿地蔵 |
|
 |
 |
 |
| 古民家 |
緑心寺 |
町並み |
|
 |
 |
 |
| 和田神社表門 |
和田神社 |
地蔵の祠 |
|
 |
 |
 |
| 古民家 |
町並み |
響忍寺 |
|
| 旧東海道は交差点を直進して北へ進む。すぐ左手に慶長7年(1602年)創建の縁心寺 / 左手に本殿が重文の和田神社 と続く。緑心寺は膳所藩主・本多家の菩提寺。和田神社表門は、膳所藩校遵義堂(じゅんきどう)門。和田神社からすぐのT字路右手の電柱に標識があり、左折する。すぐ左手に地蔵の祠 / 突き当たりに響忍寺 と続く。 |
|
| 響忍寺から道なりに右へ進む。すぐのT字路の電柱に旧東海道標識があり、左折する。すぐの小川に架かる橋を渡ると、突き当りに“大津の散策路”案内板がある。 |
|
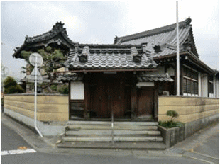 |
道を間違い、南へ小川沿いの道を進む。5分ほどすると、右手に浄業寺がある。旧東海道のときは、間違えていないところ。 |
| 浄業寺 |
|
 |
 |
 |
| 石坐神社 |
桃源禅寺 |
ふなずしを販売している商店 |
|
 |
 |
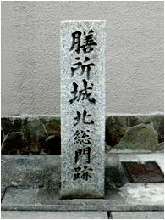 |
| 法傳寺 |
古民家 |
膳所城北総門跡 |
|
| “大津の散策路”案内板から南西へ道なりに進むと、すぐ左手に天智天皇の頃創建と云われる石坐神社がある。御霊殿山の大岩上に祠があったことが、石坐の由来となっている。社殿は文永3年(1266年)に建立されたもの。すぐ右手に桃源禅寺
/ 左手にふなずしを販売している商店 / 左手に法傳寺 / 右手に膳所城北総門跡 と続く。 |
|
 |
次を左折すると突き当りに地蔵群がある。通りかかった地元の方が教えくれる。 |
| 地蔵群 |
|
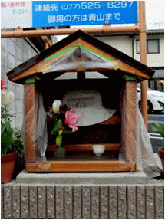 |
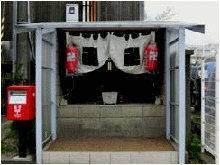 |
 |
| 地蔵の祠 |
地蔵の祠 |
福正寺 |
|
 |
 |
旧東海道に戻り西へ進む。すぐ左手に地蔵の祠 / 左手に地蔵の祠 / 左手に福正寺 / 左手に光林寺と続く。すぐの十字路を越えると、すぐ左手に義仲寺(ぎちゅうじ)がある。旧東海道のときは、到着が17:00過ぎとなり門は閉ざされていた。 |
| 光林寺 |
義仲寺 |
|
| 十字路まで戻り、右折して南へ進む。5分ほどすると。京阪電鉄・膳所駅 / JR東海道本線・膳所駅に至る。 |
|
 |