| 東海道53次ぶらり旅 No.40 関駅-(約18km)-土山支所バス停 |
|
| 2010年 5月15日(土)09:15 晴 |
|
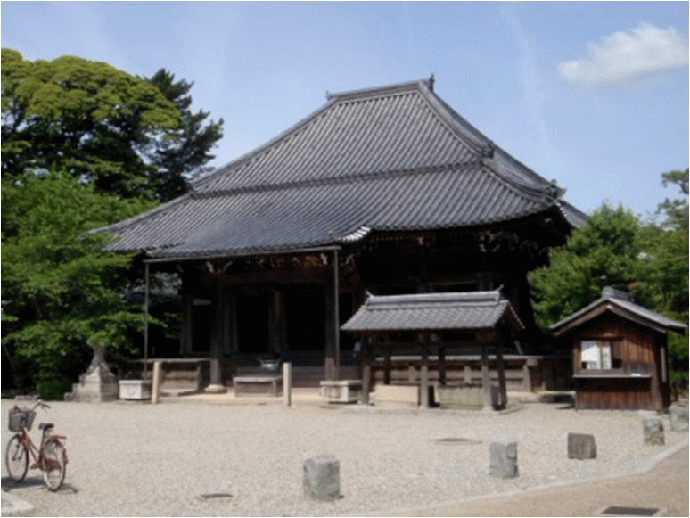 |
| 地蔵院 |
|
 |
 |
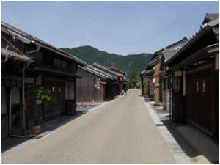 |
| 誓正寺 |
長徳寺 |
町並み |
|
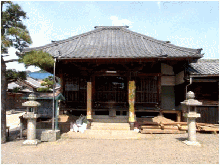 |
 |
 |
| 観音院 |
関神社御旅所 |
西の追分 |
|
| 関駅から北へ、坂を5分ほど進むと東海道と交差する。左折して前回訪れた地蔵院まで、古い町並みを西へ進む。天平13年(741年)創建と云われる地蔵院の木造地蔵は、日本最古の地蔵である。元禄12年(1699年)に建立された本堂
/ 愛染堂 / 鐘楼は、重文に指定されている。5分ほどすると右手に誓正寺、右手に万治2年(1659年)創建の長徳寺と続く。さらに5分ほどすると右手に、弘仁11年(820年)創建と云われる観音院がある。本堂は文政年間(1818年〜1829年)に建立されたものである。すぐ右手に観音山公園への道標、鎌倉時代創建の関神社御旅所と続く。関神社の祭事のとき、関神社と御旅所を神輿が往復する。すぐに西の追分になる。左へ進むと大和道で、加太〜柘植〜伊賀上野〜奈良へ通じる。伊賀上野では、三大敵討ちで知られる鍵の辻を通る。 |
|
 |
 |
 |
| 市之瀬社常夜燈 |
西願寺常夜燈 |
西願寺 |
|
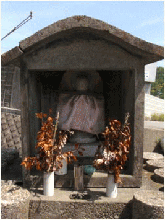 |
 |
 |
| 地蔵 |
超泉寺 |
鈴鹿峠自然の家 |
|
|
西の追分から15分ほどすると、右手の駐車場に転び石がある。何度片づけても、街道に転がりでたと云われている。鈴鹿川に架かる市瀬橋の手前を右折する。東海道はその先を左折して橋を渡っていたが今はなく、直進して道なりに進む。橋を渡り分断された東海道と合流すると、右手に大正9年(1920年)造立の市之瀬社常夜燈がある。すぐ左手に大正7年(1918年)造立の西願寺常夜燈
と天正3年(1575年)創建の西願寺、橋のたもとに地蔵の祠がある。15分ほどすると、筆捨山案内板がある。あまりに素晴らしい景観に、絵師が筆を捨てて眺めたと云われている。5分ほどすると右手に国道改良記念碑、10分ほどすると左手に観音と木像が並んでいる。さらに5分ほどすると右手に超泉寺がある。すぐ右手にある沓掛公民館のベンチで昼食を摂る。10分ほどすると“まなびの小径”があり、左手の鈴鹿馬子唄会館に立ち寄る。東海道53次の宿場が書かれた木柱の並ぶ坂を登ると、右手に鈴鹿峠自然の家がある。坂下尋常高等小学校の校舎として昭和13年(1938年)に建てられた。10分ほどすると河原谷川を河原谷橋で渡り、坂下宿に入る。
|
|
東海道53次 48番 坂下宿宿
所在地:三重県亀山市
天保14年(1843年)資料
人口:564人 家数:153 本陣:3 脇本陣:1 旅籠:48 問屋場:1 |
|
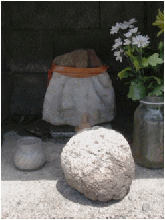 |
 |
 |
| 地蔵の祠 |
松屋本陣跡 |
大竹屋本陣跡 |
|
 |
 |
 |
| 茶畑 |
梅屋本陣跡 |
法安寺 |
|
| 河原谷橋を渡ると、右手に地蔵の祠がある。すぐ左手の伊勢坂下バス停前が松屋本陣跡で、バスの車庫や坂下集会所がある。すぐ左手に大竹本陣跡 / 左手に梅屋本陣跡 / 右手に永正2年(1505年)創建の法安寺と続く。 |
|
 |
 |
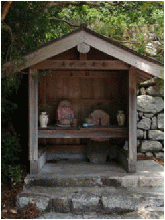 |
| 小竹屋脇本陣跡 |
金蔵院跡 |
身代地蔵 |
|
 |
 |
 |
| 土蔵 |
櫛屋の地蔵 |
岩屋十一面観世音菩薩石柱 |
|
|
中乃橋を渡ると、右手に小竹屋本陣跡がある。すぐ右手に見える石垣が、仁寿年間(851年〜853年)に創建され明治になって廃寺となった金蔵院跡である。さらに右手に身代地蔵の祠
/ 右手に櫛屋の地蔵 / 右手に岩屋十一面観世音菩薩石柱と続く。階段を登った奥に、万治年間(1658年〜1660年)創建の観音寺観音堂がある。
|
|
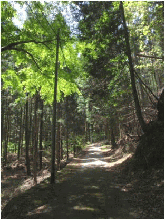 |
 |
| 山道 |
|
 |
| 地蔵堂 |
片山神社 |
|
| 極楽橋から10分ほどすると、緩い山道に入る。すぐ左手の階段下に、地蔵堂がある。さらに5分ほどすると、突き当たりに延喜式内社の片山神社がある。石垣が見事な階段を登ったところにあった社殿は、平成14年(2002年)に焼失している。 |
|
 |
 |
 |
| 県境石柱 |
鈴鹿峠 |
万人講常夜燈 |
|
| 急な山道と長い階段を登り、1号線を潜る。階段を登りきると公園があり、案内板左手の道を進む。坂道が終わると、鏡岩への道標がある。ここまで片山神社から20分ほどになる。視界が開ける左手に、県境の石柱がある。“界 左
三重県 伊勢の国 右 滋賀県 近江の国”と彫られている。茶畑を見ながら5分ほど進むと、右手に鈴鹿峠のシンボルとも言える江戸時代中期に造立の万人講常夜燈がある。 |
|
 |
 |
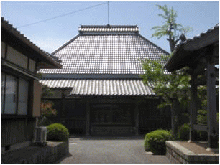 |
| 石塔と石仏 |
熊野神社の鳥居 |
十楽寺 |
|
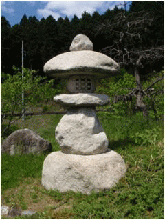 |
 |
 |
| 常夜燈 |
山中公園 |
地蔵堂 |
|
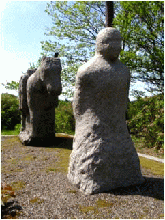 |
 |
 |
| 鈴鹿馬子歌の像 |
鈴鹿馬子歌の碑 |
常夜燈 |
|
|
万人講常夜燈から15分ほどすると、左手に石塔と石仏がある。すぐ右手に熊野神社の鳥居があり、遠くに参道に並ぶ灯籠が見える。10分ほどすると左手に文明18年(1486年)創建の十楽寺
/ 右手に常夜燈 がある。10分ほどすると右手に山中公園 / 右手に地蔵堂 と続く。10分ほどすると第2名神高速道路の高架下を潜り、右手に山中一里塚公園がある。鈴鹿馬子歌の像
/ 鈴鹿馬子歌の碑 / 常夜燈などがある。これから先の東海道は途切れ、1号線を進む。途中に膨らむ様に短い東海道がある。
|
|
東海道53次 49番 土山宿
所在地:滋賀県甲賀市
天保14年(1843年)資料
人口:1505人 家数:351 本陣:2 脇本陣:0 旅籠:44 問屋場:1 |
|
 |
 |
 |
| 石仏 |
榎島神社 |
蟹坂古戦場跡 |
|
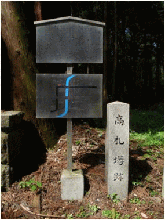 |
 |
 |
| 高札場跡 |
田村神社 |
茶畑 |
|
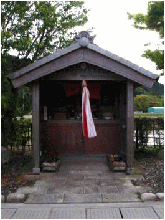 |
 |
 |
| 生里野地蔵堂 |
一里山地蔵 |
土山一里塚跡 |
|
 |
 |
 |
| 来見橋 |
白川神社 |
町並み |
|
|
山中一里塚公園から20分ほどすると案内板があり、1号線から右方向へ進む。すぐ右手に石仏2基と榎島神社がある。榎島神社は白川神社の末社で、白川神社御旅所石柱がある。工場の間を通ると、右手に蟹坂古戦場跡がある。天文11年(1542年)北畠軍が甲賀に侵攻するが、山中城主・山中秀国によって敗走させられる。再び侵攻するが、佐々木六角氏の援軍により阻止される。安永4年(1775年)架橋の田村永代橋を復元した海道橋を渡る。田村神社鳥居の手前右手に、高札場跡がある。右折して鳥居を潜り参道を進むと、弘仁3年(812年)創建の田村神社の仮殿がある。鳥居まで戻り、参道を南西へ進む。一之鳥居を潜り1号線を渡ると、右手に道の駅・あいの土山がある。抹茶ソフトクリームで一休みする。5分ほどすると左手に生里野地蔵堂があり、古い町並みが始まる。旧跡を表記した石柱がやたらに多い。右手に一里山地蔵、右手に土山一里塚跡と続く。
来見橋を渡ると、左手に白川神社鳥居がある。来見橋の瓦屋根が乗った白塀には、街道風景が埋め込まれている。バス3台120名余の大群と出くわす。とても散策の雰囲気でなくなる。右手にある土山宿本陣を過ぎ、交差する539号線を右折して北へ進む。土山支所前交差点の東側にある土山支所バス停から、宿泊する水口へ移動する。
|
|
 |