| 東海道53次 No.36 桑名駅-(約17.5km)-JR四日市駅 |
|
| 2010年 3月27日(土)09:00 晴 |
|
 |
 |
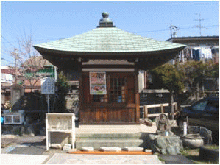 |
| 海蔵寺 |
海蔵寺薩摩義士墓所 |
地蔵堂 |
|
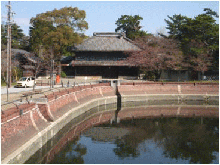 |
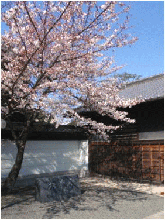 |
 |
| 六華苑・番蔵棟 |
六華苑・長屋門 |
住吉神社 |
|
| 桑名駅より18号線を東へ進むと、左手に宝暦治水工事犠牲者の薩摩義士墓所で知られる海蔵寺がある。宝暦3年(1753年)幕府は薩摩藩に、木曽川 /
揖斐川 / 長良川の河川改修工事を命じる。宝暦5年(1755年)工事は完成するが、多数の犠牲者と40万両の巨費を費やした。犠牲者は、岐阜と三重の14ヶ寺に埋葬される。海蔵寺には、責任を取って切腹した治水総奉行・家老平田靱負
他21人の墓石がある。海蔵寺から北へ進み、地蔵堂や蔵前祭車庫を通り六華苑へ進む。運河沿いに進むと、六華苑の番蔵棟が見える。右方向から回り込むと、正面の長屋門に着く。六華苑は、二代目諸戸清六の邸宅として大正2年(1913年)に完成した施設である。時間の都合でなかは見ていない。揖斐川沿いに七里渡し跡へ進むと、右手に住吉神社がある。 |
|
東海道53次 42番 桑名宿
所在地:三重県桑名市
天保14年(1843年)資料
人口:8848人 家数:2544 本陣:2 脇本陣:4 旅籠:120 問屋場:1 |
|
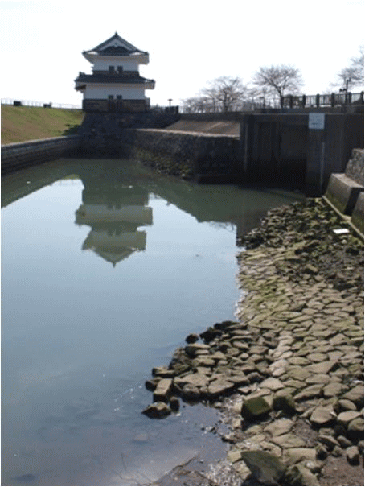 |
|
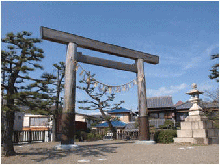 |
| 伊勢神宮一之鳥居 |
|
 |
| 七里渡し跡 |
本多忠勝像 |
|
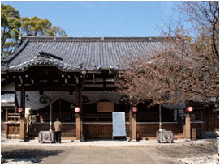 |
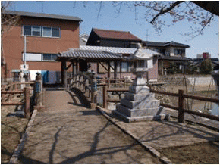 |
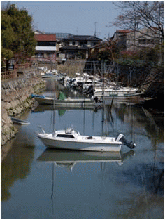 |
| 桑名宗社 |
歴史を語る公園 |
堀川の城壁 |
|
|
七里渡し跡には、復元された蟠龍櫓(水門統合管理所)や伊勢神宮一之鳥居がある。桑名城の堀に平行する東海道を南へ進む。江戸町の十字路を左折すると、三の丸跡左手に慶長6年(1601年)桑名城を築城した本多忠勝像がある。東海道に戻り南へ進むと、右手に桑名宗社(春日神社)がある。桑名神社(三崎大明神)と中臣神社(春日大明神)の両社から成り、拝殿には2ヶ所お参りするところがある。東海道に戻り南へ進むと、すぐ左手に歴史を語る公園がある。川口門より南大手橋にいたる堀川東岸の城壁約500mは、桑名城築城当時の面影を残している。
|
|
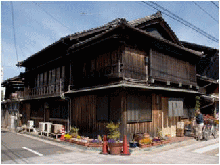 |
 |
 |
| 古民家 |
吉津屋見附跡 |
貝増本店 |
|
|
東海道を南へ進み、突き当たりを右折する。京町交差点を越え、すぐに左折する。504号線を越えると鍛冶町で、右手の吉津屋見附跡に案内板がある。右折してすぐに左折すると、右手に大正元年(1912年)創業の貝増本店がある。さらに左折すると、上記の画像“ほねつぎ”の看板が見える通りを左方向に進むことになる。案内があるので、注意して歩けば迷うことはない。さらに3本目を右折して、613号線西側の東海道を南西へ進む。
|
|
 |
 |
 |
| 教宗寺 |
泡洲崎八幡社 |
光徳寺 |
|
 |
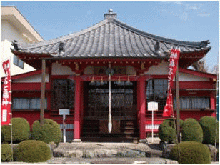 |
 |
| 十念寺 |
七福神殿 |
壽量寺 |
|
|
右折してしばらくすると、右手に明応2年(1493年)創建の教宗寺がある。すぐ右手に泡洲崎八幡社、隣に円光大師遺跡の石柱が立つ光徳寺がある。
光徳寺は、桑名西国三十三観音8番・9番札所
/ 桑名二十四地蔵7番になっている。さらに右手に十念寺、壽量寺と続く。十念寺
境内には七福神殿があり、毎年11月23日に七福神まつりが開かれている。
|
|
 |
 |
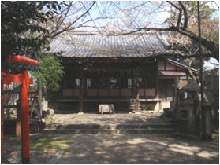 |
| 長円寺 |
報恩寺 |
天武天皇社 |
|
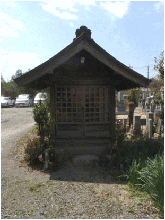 |
 |
横断歩道がない401号線を渡る。右手に長円寺 / 右手に報恩寺 と続く。613号線と合流、すぐに日進小学校前交差点を右折して西へ進む。右手に天武天皇社
/ 左手に室町時代初期創建の本願寺 と続く。本願寺は戦争で焼失、地蔵堂と墓地しかない。向かい側に、製鉄や鍛冶の神である天目一箇命を祀る一目連神社がある。 |
| 本願寺地蔵堂 |
一目連神社 |
|
 |
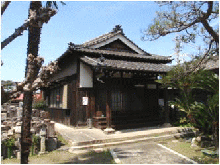 |
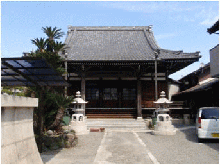 |
| 明円寺 |
教覚寺 |
善西寺 |
|
 |
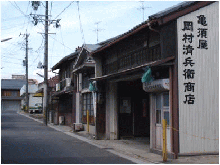 |
 |
| 立阪神社石柱・鳥居 |
商店 |
矢田立場 |
|
|
5分ほどすると、右手に明円寺 / 教覚寺 / 善西寺 / 立阪神社石柱・鳥居 と続く。立阪神社は、右折して北へ進み401号線を越えた突き当たりにある。初代桑名藩主・本多忠勝が創建したと云われる 突き当たり手前右手に矢田立場があり、左折する。矢田立場には、案内板
/ 道標 / 復元された火の見櫓などがある。ここを右折して北へ進むと、桑名駅が近い。
|
|
 |
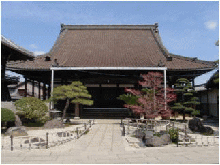 |
 |
| 神戸岡神社 |
了順寺 |
城南神社 |
|
 |
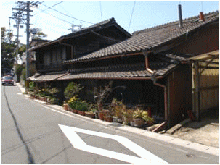 |
 |
| 晴雲寺 |
古民家 |
休憩所 |
|
 |
 |
 |
| 伊勢神宮常夜燈 |
町屋橋跡案内板 |
町屋川 |
|
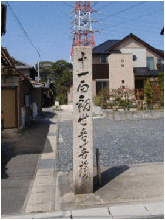 |
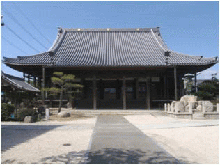 |
 |
| 十一面観世音菩薩石塔 |
真光寺 |
縄生一里塚跡 |
|
|
矢田立場から5分ほどすると、右手に神戸岡神社がある。さらに5分ほどすると、左手に元和7年(1621)創建の了順寺がある。山門は桑名城の城門を移築したと云われている。すぐ右手に城南神社、大永2年(1523年)創建と云われる晴雲寺と続く。258号線高架下の交差点を、地下道で渡る。左手の民家の庭先に藤棚があり、ベンチが置かれた休憩所になっている。5分ほどすると、右手に文化元年(1818年)造立の伊勢神宮常夜燈がある。すぐ先の安永第一公園に、町屋橋跡案内板がある。南側の1号線で町屋川を町屋橋で渡る。町屋橋南詰交差点を右折、すぐに左折して東海道を進む。すぐ右手に十一面観世音菩薩石塔、大同2年(807年)創建の真光寺と続く。十一面観世音菩薩石塔を折すると、天平12年(740年)創建と云われる金光寺がある。桑名西国三十三観音25番札所
/ 桑名二十四地蔵11番になっている。5分ほどすると、左手に縄生一里塚跡がある。
|
|
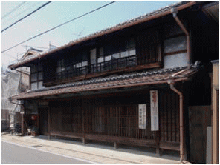 |
 |
 |
| 古民家 |
小向神社石柱 |
浄泉坊 |
|
 |
 |
 |
| 西光寺 |
古民家 |
多賀大社常夜燈 |
|
|
近鉄名古屋線の踏切を越えて10分ほどすると、右手に小向神社石柱がある。小向神社は、右折してJR関西本線を越えたところにある。すぐ右手に浄泉坊
、5分ほどすると右手に西光寺がある。20分ほどすると朝明川の対岸右手に、弘化3年(1846年)造立の多賀大社常夜燈が見える。あさけ橋を渡る。
|
|
|
|
| [参考]多賀大社 |
|
 |
 |
| 鳥居 |
|
 |
| そり橋 / 神門 |
社殿 |
|
 |
多賀大社は和銅5年(712年)編纂の古事記に記載がある古社で、式内社。伊勢神宮 / 熊野大社とともに参詣で賑わった。江戸時代は「お伊勢参らば
お多賀に参れ お伊勢お多賀の子でござる」「お伊勢へ七度 熊野へ三度 お多賀さまへは月参り」「お伊勢参らばお多賀へ参れ」と云われた。祭神の「伊邪那岐命」と「伊邪那美命」が伊勢神宮の天照大神の親であることから「お伊勢お多賀の子」と云われた。お守りとして杓子(しゃもじ)を授ける「お多賀杓子(おたがじゃくし)」は、「お玉杓子」や「オタマジャクシ」の名の由来とされている。そり橋は豊臣秀吉が寄進したもの。 |
| 絵馬 |
|
|
|
 |
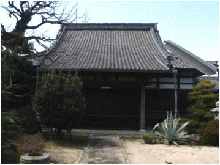 |
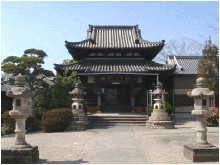 |
| 神明社石柱 |
蓮證寺 |
宝性寺 |
|
 |
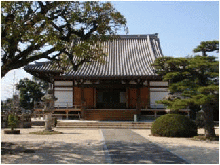 |
 |
| 神明社 |
長明寺 |
鏡ヶ池跡碑 |
|
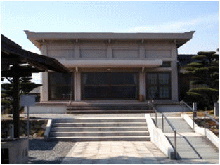 |
 |
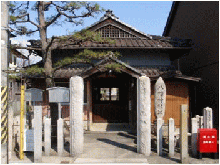 |
| 三光寺 |
富田一里塚跡 |
八幡神社 |
|
|
伊勢湾岸道路高架下にある柿交差点で、1号線と交差する。朝明橋を渡るとすぐ右手に神明社石柱、蓮證寺と続く。10分ほどすると右手に宝性寺、境内に神明社がある。左隣には、濠と築塀に囲まれた長明寺がある。蒔田宗勝が築城した蒔田城跡である。築城年代は不明であるが、文治年間(1185〜1190)伊勢平氏残党の反乱のときに、蒔田宗勝が居城していたと云われる。交差する26号線沿いのコンビニで昼食を摂る。食事スペースがあるのが有難い。左手にある鏡ヶ池跡碑を過ぎると、JR関西本線の踏切と三岐鉄道貨物線高架橋が見えて来る。すぐ右手に三光寺がある。東海道は南西方向に進路を変える。三岐鉄道と近鉄名古屋線の高架を潜る。右手に富田一里塚跡、5分ほどすると弘安2年(1279年)創建の八幡神社がある。十字路を越えて、道標のあるところを右折する。近鉄・富田駅より続く中央通りを左折する。しばらくすると十字路があり、右折して南西へ進む。
|
|
 |
 |
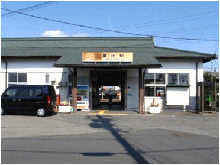 |
| 古民家 |
JR富田駅への町並み |
JR富田駅 |
|
 |
 |
 |
| 海抜1.7m |
古民家 |
長興寺16 |
|
| [迷い道] |
|
| 十字路を越えてから、道標を見落として直進する。八幡神社から5分ほどすると、左手奥の突き当たりにJR富田駅が見える。地図と異なるので道を伺うと、東海道に間違いないと言われる。JR富田駅は、JR東海・関西本線と三岐鉄道貨物線の共同駅である。以前は三岐鉄道の旅客列車も運行されていたが、近鉄富田駅発着に変更されている。三岐鉄道の使用されなくなった島式ホーム(3・4番線)、多数の貨物側線が広がる。古い町並みが残る誤った道を進むと、ところどころに海抜表示がある。突き当たりを右折すると、右手に養老6年(722年)創建の長興寺がある。道なりに進むと、前方にJR関西本線の踏切が見えて来る。再度道を伺うと、親切に中央通りの道標のあるところまで案内していただいた。 |
|
 |
 |
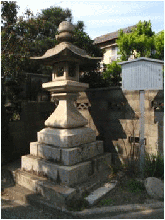 |
| 南町集会所 |
善教寺 |
常夜燈 |
|
 |
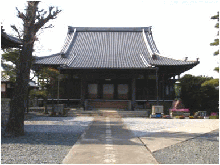 |
 |
| 薬師寺 |
常照寺 |
力石&水道碑 |
|
 |
 |
 |
| 證円寺 |
茂福神社石柱 |
常夜燈 |
|
 |
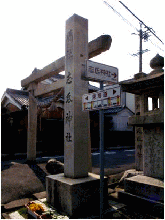 |
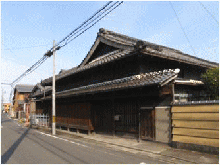 |
| 八幡地蔵堂 |
志氏神社石柱・鳥居 |
古民家 |
|
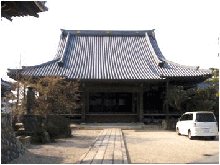 |
 |
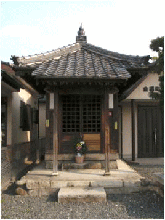 |
| 光明寺 |
町並み |
地蔵堂 |
|
 |
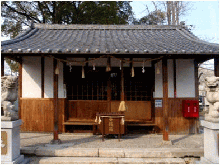 |
 |
| 分岐 |
多度神社 |
一里塚跡 |
|
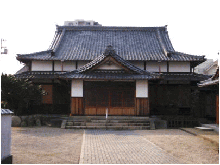 |
 |
 |
| 法泉寺 |
三滝橋のタイル |
|
|
中央通りを右折して南西に進むと、すぐ右手に鳥居がある南町集会所がある。十畳ほどの広さで、奥に太鼓や提灯が見える。十四川の手前左手に善教寺がある。重厚な本堂で、阿弥陀如来像は重文になっている。十四川を渡ると右手に天保10年(1839年)造立の常夜燈、当地唯一の尼寺であった薬師寺と続く。薬師寺境内の堂には、大小の石仏が納められている。すぐ右手に天文7年(1538年)創建の常照寺、力石&用水道碑と続く。突き当たりを左折、すぐに右折すると右手に證円寺がある。證円寺を回り込む様な道になっている。すぐ右手に、応永28年(1421年)創建の茂福神社石柱がある。64号線の高架を潜ると、右手に明治35年(1902年)造立の八田常夜燈がある。5分ほどすると右手に八幡地蔵堂がある。さらに10分ほどすると、右手に垂仁天皇の代創建の志氏神社石柱 / 鳥居 / 灯篭 / 道標がある。すぐ右手に光明寺と続く。変形十字路からカーブが続き、1号線に合流する。左手にある地蔵堂を過ぎると、5分ほどで1号線と分岐して左へ進む。左手に、多度大社を勧請した明治18年(1885年)創建の多度神社がある。土手の左手に一里塚跡があり、海蔵川に突き当たる。右折して1号線の海蔵橋を渡り、すぐに左折して1号線に平行する東海道を進む。右手にある法泉寺を過ぎると、10分ほどで三滝川をタイルが埋め込まれている三滝橋で渡る。
|
|
東海道53次 43番 四日市宿
所在地:三重県四日市市
天保14年(1843年)資料
人口:7114人 家数:1811 本陣:2 脇本陣:1 旅籠:98 問屋場:1 |
|
 |
 |
 |
| 笹井屋本店 |
江戸の辻道標 |
|
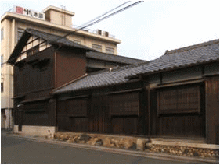 |
 |
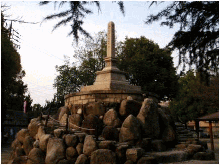 |
| 民家 |
諏訪神社 |
諏訪公園 |
|
|
三滝川を越えると四日市宿で、すぐ左手に“なが餅”で知られる天文19年(1550年)創業の笹井屋本店がある。164号線を越えると変則十字路の右手に、江戸の辻道標がある。東海道はここで途切れ、迂回して西側の1号線を横断する。アーケードのある商店街に入ると、すぐ右手に建仁2年(1202年)創建の諏訪神社、奥に諏訪公園がある。商店街を抜けると中央通りに出る。右折して西へ進むと近鉄・四日市駅、左折して東へ進むとJR・四日市駅に至る。
|
|
 |