| 東海道53次 No.20 丸子橋入口バス停-(約14km)-藤枝駅 |
|
| 2009年 8月 8日(土)10:00 雨のち晴 |
|
2017年 4月 5日(水) 晴
|
|
| JR東海道本線・静岡駅から中部国道線の藤枝駅行きバスに乗車、丸子橋入口バス停で下車する。 |
|
 |
 |
 |
| いざり地蔵 |
丸子宿道標 |
丸子橋 |
|
 |
 |
丸子橋入口バス停のからすぐに左折して小路を進むと、右手に駿河一国百地蔵13番の“いざり地蔵”がある。丸子川に架かる丸子橋手前左手に丸子宿道標
/ 右手に細川幽斎歌碑 がある。丸子橋を渡ると、すぐ右手に高札場跡がある。丸子戸斗の谷・津島神社から発見された高札のレプリカが掲げられている。すぐ左手に社がある。 |
| 高札場跡 |
社 |
|
 |
高札場跡から20分ほどすると、二軒屋交差点で1号線に合流する手前右手に観音堂がある。 |
| 観音堂 |
|
 |
 |
 |
| 長源寺山門 |
長源寺本堂 |
丸子紅茶発祥の地碑 |
|
 |
二軒屋交差点から5分足らずの左手に旧東海道の標識があり、左へ進む。さらに5分ほどすると、寛保元年(1741年)創建の長源寺がある。少し手前の道端から境内まで、羅漢が並んでいる。境内を進むと、右手にある山門は品川の東海寺から移築されたもの。境内に、水子観音
/ 子育観音 / 丸子弁財天 / 耳地蔵 がある。境内を直進すると、右手に丸子紅茶発祥の地碑 / 起樹天満宮 がある。 |
| 起樹天満宮 |
|
 |
長源寺から5分足らずで1号線に合流する。15分ほどすると道の駅があり、すぐの歩道橋で1号線を越え、宇津ノ谷(うつのや)に入る。 |
| 宇津ノ谷入口 |
|
 |
 |
 |
| Y字路(2017年) |
道標 |
宇津ノ谷集落 |
|
 |
歩道橋から10分ほどするとY字路があり、左へ進むと宇津ノ谷集落に入る。すぐに標識があり右折して道なりに進むと、天正6年(1578年)創建の慶龍寺がある。宇津ノ谷峠にあった延命地蔵が移転され、駿河一国百地蔵15番になっている。
|
| 慶龍寺 |
|
|
 |
 |
| 御羽織屋・石川家 |
|
 |
| 宇津ノ谷集落(2017年) |
宇津ノ谷集落(2017年) |
|
 |
 |
雨が一段と強くなる。旧東海道に戻り南西へ進むと、すぐ右手に豊臣秀吉が小田原城攻めの際に立ち寄ったと云われる御羽織屋・石川家がある。すぐに直進すると階段のT字路があり、右折してさらに鋭角に左折する。この辺りから宇津ノ谷集落が一望できる。すぐ右手に宇津ノ谷峠越え標識 / 道標 / 案内板 がある。 |
| 宇津ノ谷峠越え標識(2017年) |
道標(2017年) |
|
|
|
| 2009年に2人で訪れたときは、宇津ノ谷峠越え標識 / 道標 / 案内板 を見逃して道なりに進んでいる。雨と雨具の蒸し暑さから逃れられる明治のトンネルは、涼しげで快適であった。トンネルを出てから気付くが、そのまま進んでいる。坂下地蔵堂西側を通る道に出て、旧東海道と合流する。 |
|
 |
 |
 |
| 広場の桜(2017年) |
常夜燈(2017年) |
石仏石塔群(2017年) |
|
| 明治のトンネル手前の広場右手に、常夜燈 / 石仏石塔群 がある。
|
|
 |
| 明治のトンネル(2017年) |
|
| 明治のトンネルは明治9年(1876年)地元有志の結社によって造られ、開通から50年は道銭徴収を許された日本で最初の有料トンネル。開通により、険しい峠道の通行は大変便利になった。開通当時は、くの字に曲がった出口の見えないトンネルだった。明治29年(1896年)トンネル内を照らしていたカンテラが原因の葛西が発生、トンネルの一部が崩落する。明治37年(1904年)に修復されたときに、直線なトンネルになった。現役のトンネルとしては初めて国の登録有形文化財になっている。 |
|
|
|
| 峠道〜坂下地蔵堂の画像は、2017年に訪れたときの撮影。 |
|
 |
 |
| 峠道入口付近 |
|
 |
| 馬頭観音 |
見晴らしが良い広場 |
|
|
宇津ノ谷峠越え標識 / 道標 / 案内板 があるところから、峠道を進む。すぐ左手に馬頭観音がある。左が大正5年(1916年) / 右が嘉永5年(1852年)
に造立されたもの。すぐ左手にある見晴らしが良い広場は、岡部宿側から無事に峠を越えてほっと息をついたところ。宇津ノ谷名物の十団子も売られていたところ。
|
|
 |
すぐ右手に享保15年(1730年)造立の俳人・山口雁山の墓がある。雁山が旅の途中で亡くなったと勘違いをした友人によって造立された。雁山は明和4年(1767年)82歳迄生存している。この辺りは明治43年(1910年)の集中豪雨により山崩れが発生、地形が大きく変わったところ。往時は山側上方を通っており、この先にある階段は便宣的に設けられたもの。すぐ左手に、これらが記載された案内板がある。
|
| 山口雁山の墓 |
|
 |
 |
すぐ右手に石垣があり、上の平らになっているところに地蔵堂があった。江戸時代中頃、傾斜地に地蔵堂建立するために積まれた。地蔵と常夜燈は、明治42年(1909年)宇津ノ谷集落の慶龍寺に移された。
|
| 石垣 |
地蔵堂跡 |
|
 |
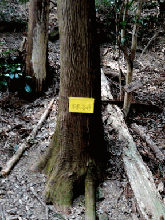 |
 |
| 宇津ノ谷峠から丸子宿側 |
宇津ノ谷峠 |
宇津ノ谷峠から岡部宿側 |
|
|
地蔵堂跡の脇を通ると、すぐに小さな手書きの木札があるだけの宇津ノ谷峠に着く。峠道に入ってから15分ほどのところである。
|
|
 |
 |
 |
| 旧東海道登り口標柱 |
明治のトンネルからの合流点 |
題目塔 |
|
|
宇津ノ谷峠から5分ほどの急坂を下ると、国道1号宇津ノ谷隧道の換気口への管理道と合流する。この急坂部は、管理道の開通により往時とは異なっている。岡部宿方面からは間違え易いところで、旧東海道登り口標柱
/ 案内看板 がある。すぐに明治のトンネルから分岐した道と合流する。画像は岡部宿側からで、左が明治のトンネル方向 / 右が丸子宿方向 になる。すぐ左手に天保6年(1835年)造立の題目塔「南無妙法連華経」がある。
|
|
 |
 |
| 峠道 |
|
 |
| 旧東海道 / 蔦の細道 合流点 |
坂下地蔵堂 |
|
|
題目塔から5分足らずで、蔦の細道から続く道と合流する。蔦の細道は、平安時代から室町時代後期まで使用された宇津ノ谷峠越えの官道。豊臣秀吉が小田原城攻めのとき新しい道を開き、蔦の細道は人の往来がなくなった。すぐ右手に坂下地蔵堂がある。左手に見える道は、明治のトンネルに続く道で、2009年に訪れたときは、ここに出ている。坂下地蔵堂の周りは、道標 / 標識 /
案内板 が多い。
|
|
 |
坂下地蔵堂からすぐの左手に、岡部宿側に向いた「つたの細道 西口」石標がある。
|
| つたの細道石標(2017年) |
|
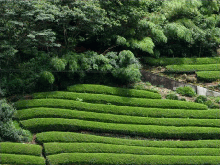 |
 |
 |
| 茶畑 |
古民家 |
東海道岡部宿案内板 |
|
| すぐに1号線に合流、側道を進む。10分ほどの交差点から歩道橋で1号線を越え、北西方向へ進む。10分ほどすると、左手に東海道岡部宿案内板がある。
|
|
 |
 |
東海道岡部宿案内板からすぐの右手に、十石坂観音堂がある。廃寺となった最林寺の観音堂が残されたもので、徳川氏によって十石の寺田が与えられたことに由来すると云う。境内の石仏石塔群に、河野?園(そんえん)碑文がある。 |
| 十石坂観音堂 |
石仏石塔群 |
|
 |
 |
十石坂観音堂から5分足らずの右手に、社 / 常夜燈 がある。 |
| 社 |
常夜燈 |
|
 |
常夜燈からすぐに、旧東海道は岡部橋の手前を右に進む。2009年に誤って直進したところで、すぐ左手の上り坂に立光山不動標柱がある。 |
| 立光山不動標柱 |
|
 |
 |
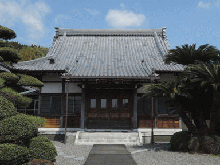 |
| 三星寺(2017年) |
古民家(2017年) |
専称寺(2017年) |
|
|
岡部橋を渡る手前に標識があり、旧東海道は右方向へ進む。すぐの変則十字路を右折すると、すぐの突き当りに三星寺がある。旧東海道は変則十字路を左折して南へ進み、すぐに岡部川を越える。すぐに208号線に合流する手前を右折すると、すぐ右手に文禄4年(1595年)創建の専称寺がある。
|
|
 |
 |
| 岡部宿本陣址(2017年) |
|
 |
| 大旅籠・柏屋(2017年) |
常夜燈 |
|
|
208号線に合流すると、すぐ左手に大旅籠・柏屋 / 左手に岡部宿本陣址 / 左手の公園に常夜燈 と続く。大旅籠・柏屋の建物は、天保7年(1836年)に建てられたもの。国の登録有形文化財で、歴史資料館となっている。
|
|
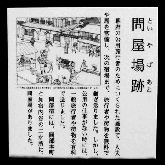 |
 |
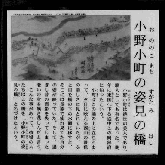 |
| 問屋場跡案内板 |
初亀酒造(2017年) |
小野小町の姿見の橋案内板 |
|
 |
常夜燈からすぐの左手に問屋場跡案内板がある。すぐ 右手にある初亀酒造の先を、旧東海道は左方向に進む。すぐの水路に架かる石橋は、小野小町の姿見の橋と呼ばれている。すぐ左手の小道を進むと、佐護神社がある。石段の頂上に社務所、途中の左手に社殿がある。
|
| 佐護神社 |
|
 |
 |
 |
| 弘法大師堂(2017年) |
正応院 |
岡部宿(2017年) |
|
 |
 |
旧東海道に戻り南へ進む。すぐ右手の弘法大師堂のところに高札場跡案内板がある。 すぐ左手に正応院 / すぐ左手に祠 / すぐのT字路右手に常夜燈 と続く。
|
| 祠 |
常夜燈(2017年) |
|
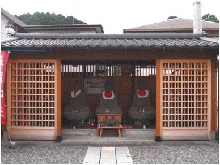 |
 |
旧東海道は右折して、すぐの岡部支所前交差点を左折して208号線を南へ進む。五智如来像公園にある冷房の利いた建物で食事を摂る。岡部町が合併して藤枝市になっていることを知る。五智如来像公園から旧東海道を南へ進むと、東海道岡部宿杉並木が続く。 |
| 五智如来 |
東海道岡部宿杉並木 |
|
 |
 |
 |
| 常夜燈 |
岩村藩傍示杭 |
慈眼院 |
|
 |
 |
常夜燈を過ぎ、1号線藤枝バイパスを潜る。1号線から右へ進むと、すぐ右手に岩村藩傍示杭がある。美濃岩村藩の飛地があったところ。左手に慶長4年(1599年)創建の慈眼院があり、右手の常夜燈には神札が置かれている。構内に案内地図がある。構内橋の手前に町内会館があり、毎年8月16日に行われる“夏祭り川原供養祭”で灯される“あげんだい”が展示されている。 |
| 常夜燈 |
あげんだい |
|
 |
 |
 |
| 橋場町地蔵と川除地蔵 |
川除地蔵 |
|
 |
 |
 |
| 橋向地蔵と川除地蔵 |
松並木 |
岩村藩傍示杭 |
|
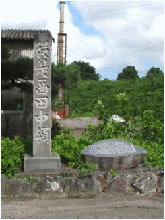 |
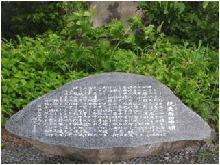 |
 |
| 従是西田中領の碑 |
一里塚跡の標柱 |
|
| 朝比奈川に架かる構内橋手前右手に、橋場町地蔵と川除地蔵の祠がある。構内橋を渡ると左手に川除地蔵の祠、右手に橋向地蔵と川除地蔵の祠がある。5分ほどすると、松並木が続く。分離帯に岩村藩傍示杭がある。五差路の仮宿交差点の横断歩道橋を渡り、斜め方向へ進む。左手に従是西田中領の碑がある。10分ほどすると、注意しないと見落す一里塚跡がある。旧東海道は、1号線に寄り添い南へ方向を変える。 |
|
 |
 |
 |
| 地蔵 |
葉梨川 |
地蔵 |
|
 |
 |
 |
| 常夜燈と鬼島の建場 |
青山八幡神社の鳥居 |
秋葉神社 |
|
 |
 |
 |
| 須賀神社 |
楠 |
全居寺 |
|
| 葉梨川沿いにある祠のベンチで休憩する。濁って増水している葉梨川を渡りすぐに右折すると、右手の土手に地蔵がある。5分ほどするとで常夜燈と鬼島の建場の説明板 / 右手に八幡山の麓にある青山八幡神社の鳥居と続く。右手に樹齢500年の須賀神社の楠が見えてくる。鳥居が小さく見える。手前右手に秋葉神社 / 奥に全居寺がある。 |
|
 |
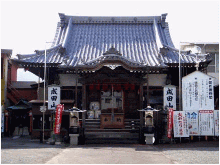 |
東海道まわり道と書かれた道標を右折すると、右手に観音堂がある。208号線を横切り、1号線に面するガソリンスタンドの裏側を通る。1号線と斜めに交差するが、棒の分離帯があり渡ることはできない。北側にある水守交差点を横断歩道で渡る。旧東海道を進むと、すぐ右手に成田山新護寺がある。 |
| 観音堂 |
成田山新護寺 |
|
|
|
| [寄り道]田中城 |
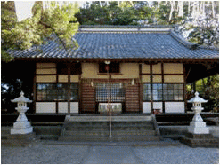 |
 |
 |
| 田中神社 |
田中城二之堀 |
田中城本丸跡標柱 |
|
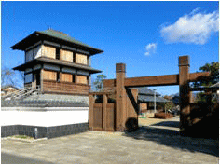 |
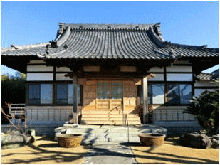 |
 |
| 田中城下屋敷 |
旭傳院 |
旭傳院山門 |
|
| 成田山新護寺から5分ほどすると交差点があり、左折する。5分ほどすると1号線と大手交差点で交差する。横断して左折すると、すぐ右手に元亀年間(1570年〜1573年)創建の田中神社がある。田中城本丸に鎮座、明治23年(1890年)移転する。大手交差点まで戻り東へ、すぐにY字路を右へ南東に進む。すぐ右手に田中城二之堀
/ 右手に西益津小学校校門前に田中城本丸跡標柱と続く。円形輪郭式縄張の城で、三重に堀が巡らされていた。二の丸と三の丸に丸馬出しが計6箇所設けられており、武田流城郭の特徴を示している。武田氏による駿河侵攻以降、三河の徳川氏に対抗する駿河西部の城砦網の要になった城。徳川家康の死因とも云われている鯛の天ぷらを食した場所がこの田中城である。本丸・二の丸跡に西益津小学校
/ 三の丸跡に西益津中学校があり、周囲も宅地化されいる。二の丸・三の丸の堀の一部 / 三の丸平島口付近に土塁 / 虎口の石垣が残る。田中城本丸跡標柱から5分ほどすると六間橋がある。手前を左折すると、右手に田中城下屋敷が見えてくる。田中城下屋敷に、本丸櫓や米倉などが移築されている。本丸櫓は明治4年(1871年)旗本に払い下げられ、移築して住居として利用されてきた。昭和60年(1985年)寄贈され、田中城下屋敷に移築される。六間橋を渡り南東へ5分ほど進むと左手に旭傳院の看板があり、左折して5分ほどすると右手に旭傳院がある。田中城不浄門が移築され現存するが、城内屋敷の門とも云われている。 |
|
|
|
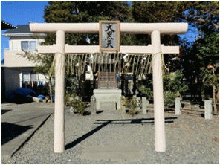 |
 |
 |
| 大黒天 |
養命寺 |
養命寺延命地蔵堂 |
|
 |
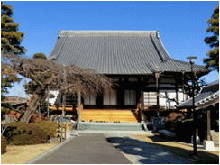 |
 |
| 了善寺 |
蓮生寺 |
常夜燈 |
|
| 旧東海道の交差点まで戻り、左折して南西へ進む。すぐ右手に大黒天 / 左手に養命寺がある。養命寺山門前に延命地蔵堂がある。右手に文明18年(1486年)創建の了善寺
/ 右手に建久7年(1196年)創建の蓮生寺と続く。蓮生寺から北西方向に進むと、蓮華寺池がある。旧東海道に戻り南西へ進むと、すぐ右手に常夜燈がある。 |
|
 |
 |
 |
| 藤枝の夏祭り |
大慶寺 |
久遠の松 |
| |
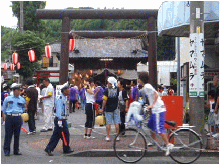 |
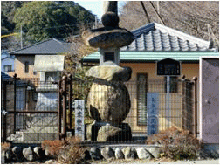 |
 |
| 神明神社 |
秋葉神社 / 常夜燈 / 一里塚跡 |
駅前神社 |
|
| 藤枝名店街は夏祭りで賑わっている。左手に樹齢700年の久遠の松がある大慶寺 / 右手に夏祭りで大賑わいの神明神社がある。10分ほどすると、右手に秋葉神社
/ 常夜燈 / 一里塚跡が並んでいる。15分ほどすると、1号線と交差する五差路の青木交差点がある。旧東海道は直進して南へ進む。南西へ進み藤枝駅北交差点を右折すると、左手に駅前神社がある。藤枝駅北交差点に戻り、右折して南へ進むと藤枝駅に至る。 |
|
 |