| 東海道53次 No.15 元箱根-(約22km)-三島駅 |
|
| 2009年 4月19日(日) 09:45 晴 |
|
 |
 |
 |
| 大鳥居 |
身替わり地蔵 |
箱根神社の鳥居と富士山 |
|
 |
 |
 |
| 葭原久保一里塚跡 |
杉並木 |
箱根関所 |
|
|
箱根湯本駅前の箱根湯本バス停から、箱根登山バス・箱根町行きに乗車する。元箱根バス停で下車する。芦ノ湖を右手に見ながら東海道を進むと、正面に大鳥居が見える。左手に身替わり地蔵や石塔があり、対岸には箱根神社の鳥居と富士山が見える。葭原久保(よしわらくぼ)一里塚跡から杉並木を進む。再び車道と合流すると、右手方向に復元された箱根関所がある。
|
|
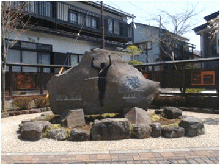 |
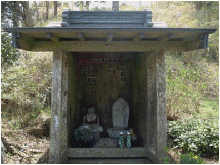 |
 |
| 箱根駅伝広場 |
山の神 |
駒形神社 |
|
 |
 |
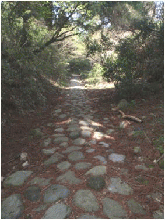 |
| 毘沙門堂 |
芦川の石仏群 |
向坂 |
|
 |
 |
 |
| 赤石坂 |
風越坂 |
挟石坂 |
|
| 左手にある箱根駅伝広場を通り、さらに進むと左手に山の神がある。道標があり右手の道を進むと左手に駒形神社、境内には箱根七福神の毘沙門堂がある。向坂の入口右手には、芦川の石仏群がある。杉並木の石畳を進むと、1号線の下を潜り赤石坂に入る。釜石坂〜風越坂と続き、階段状の挟石坂を登ると1号線に合流する。 |
|
 |
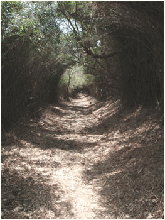 |
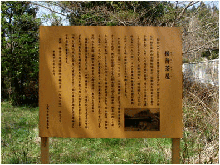 |
| 新箱根八里記念碑 |
甲石坂 |
接待茶屋跡 |
|
 |
 |
箱根峠に到着、県境を越えると、右手に道の駅がある。駐車場側の歩道を進むと、右手に新箱根八里記念碑(峠の地蔵)がある。1号線の右手からの甲石坂を進み1号線を横断すると、接待茶屋跡
/ 東海道案内板 がある。右手に、以前は甲石坂にあった“かぶと石”がある。 |
| 接待茶屋跡前の東海道案内板 |
かぶと石 |
|
 |
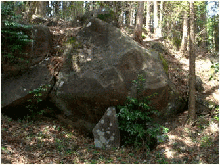 |
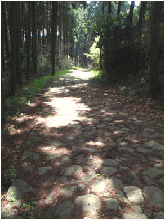 |
| 石原坂 |
念仏石 |
大枯木坂 |
|
 |
石原坂を進むと、右手に念仏石がある。民家の庭先を通り、突き当りを左折する。大枯木坂〜小枯木坂と進む。 |
| 小枯木坂 |
|
 |
 |
 |
| 駒形諏訪神社鳥居 |
駒形諏訪神社 |
山中城土塁 |
|
| 1号線を渡ると、右手に山中城の守り神だった駒形諏訪神社がある。境内から右へ進むと、山中城土塁がある。社殿前を左へ進むと、山中城址の案内看板がある。山中城は、永禄年間(1558年
〜1570年)小田原北条氏3代・北条氏康により築城される。本拠地である小田原の西の防衛を担う最重要拠点で、湯坂城 / 鷹ノ巣城 / 宮城野城
/ 韮山城 / 進士城 / 塔之峰城 / 浜居場城 / 新庄城 / 足柄城 とともに箱根十城と呼ばれる。城は旧東海道を取り込む様に築城されている。天正18年(1590年)小田原征伐で、豊臣秀次率いる7万の軍勢が山中城を攻撃する。山中城の守備は、城主・松田康長 / 松田康長の弟・松田康郷 / 武蔵笹下城主・間宮康俊 / 上野箕輪城主・多米長定 の4000人だったと云われている。抗戦するも戦力差は甚だしく、僅か半日で落城する。松田康長 / 松田康郷 / 間宮康俊 / 多米長定 を始め城兵の多くが討死した。豊臣秀次軍も一柳直末が討死するなど、多くの戦死者を出した。小田原北条氏滅亡より廃城となる。 |
|
 |
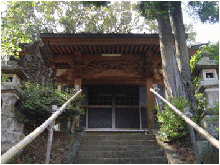 |
 |
| 宋閑寺 |
芝切地蔵 |
箱根八里記念碑 |
|
| 山中の町並みを三島方向に進むと、右手に宋閑寺がある。山中城三の丸跡だったところで、元和6年(1620年)間宮康俊の娘・お久の方によって創建された。お久の方は天正18年(1590年)小田原征伐後に徳川家康の側室となり、娘・松姫を産んだ。 山中城主・松田康長 / 松田康郷 / 副将・間宮康俊 /上野箕輪城主・多米長定 / 豊臣秀次軍・一柳直末 の墓がある。さらに進むと、右手の階段上に芝切地蔵がある。石畳に入ると、右手に箱根八里記念碑 / 石仏 がある。 |
|
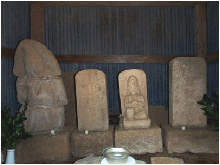 |
 |
 |
| 馬頭観音 |
笹原一里塚 |
道祖神 |
|
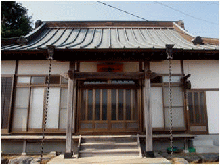 |
1号線を渡る手前の左手に芭蕉の句碑がある。左方向にある横断歩道から横断する。上長坂を進むと笹原新田に馬頭観音などがある。笹原一里塚は片方だけが残っている。民家の庭先を通ると、1号線を渡る手前の右手にベンチがある。一休みして、途中で購入した寒さらし餅を食する。道祖神や一柳院があり、「急勾配で背に負った米も人の汗や温気で蒸されて、強飯のようになる」と云われた“こわめし坂”に入る。 |
| 一柳院 |
|
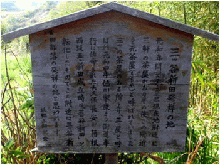 |
 |
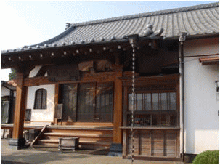 |
| 三ツ谷新田発祥の地 |
松雲寺 |
法善寺 |
|
 |
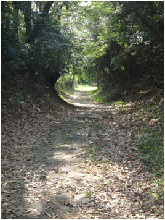 |
 |
| 六地蔵 |
臼転坂 |
馬頭観音 |
|
| “三ツ谷新田発祥の地”案内板を過ぎると、右手に明暦2年(1656年)創建の松雲寺がある。法善寺や生垣に囲まれた六地蔵を過ぎ、臼転坂に入ると馬頭観音がある。 |
|
 |
 |
 |
| 堂 |
石仏群 |
宋福寺 |
|
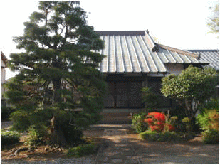 |
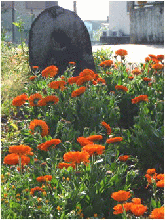 |
 |
| 宋福寺 |
石仏 |
松並木 |
|
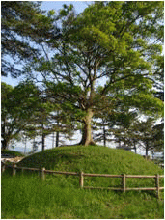 |
 |
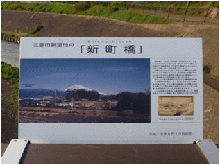 |
| 錦田一里塚 |
愛宕橋たもとの社 |
東海道53次三島狂歌入り佐野喜版 |
|
| 堂の左手に石仏群が並び、直ぐに山門にこいのぼりがなびいている宋福寺がある。花に埋もれている石仏を過ぎると、東海道は通行止めとなっている。案内の看板に従い、1号線沿いに迂回することになる。松並木に入る手前の横断歩道を右折して、松並木が続く1号線沿いに進む。歩道部分は石畳風に整備されているが、歩きづらい。錦田一里塚が1号線の両側にある。愛宕坂を進むと愛宕橋のたもとに社がある。東海道本線の踏切を渡り、“東海道53次三島狂歌入り佐野喜版”の案内板がある新町橋を渡る。 |
|
 |
 |
 |
| 守綱八幡神社 |
妙行寺 |
三島大社 |
|
|
右手に寛永年間(1624年〜1643年)創建の守綱八幡神社、左手奥に妙行寺がある。妙行寺の山門は楽寿園の表門を移築したものである。しばらくすると右手に三島大社がある。三島大社の先を右折、川沿いの歩道を進む。白瀧公園までは三島に関係した文学作品の文章を刻んだ碑が立てられている。楽寿園前を通り、三島駅に至る。
|
|
 |