| 奥の細道 敦賀→関ケ原 | ||
| ■元禄2年(1689年)8月17日 芭蕉は敦賀宿を出立、8月21日頃に大垣宿に到着した。 | ||
|
琵琶湖水運を利用しない陸路の場合、敦賀宿-(北国街道)-木之本宿-(北国脇往還)-小谷宿-(北国脇往還)-関ケ原宿-(中山道)-垂井宿-(美濃路)-大垣宿
の経路と思われる。この経路は、江戸時代の参勤交代で越前の諸大名が利用する ことが多かった。 |
||
 |
敦賀宿から塩津宿は約19km / 北陸本線・敦賀駅から近江塩津駅は14.5km の距離である。近江塩津駅前を通る道は北国街道(8号線)で、塩津交差点を経て5kmほどのところに塩津の湊があった。 近江塩津駅は湖西線が分岐する駅であるが、塩津宿は古くから琵琶湖海運や街道が交わる賑やかなところであった。 |
|
| 近江塩津駅 | ||
 |
←近江塩津駅スタンプ 近江塩津駅 海運・あぢかまの宿。近江塩津駅舎の図柄。 近江塩津駅スタンプ→ 丸子船の図柄。 |
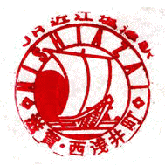 |
| 琵琶湖は北奥で三つの入り江があり、塩津 / 大浦 / 海津の湊が造られていた。各湊から敦賀に通じる道が開かれていた。 長徳2年(996年)秋、紫式部は越前の国司になった父・藤原為時に伴って京を出立した。大津から船で琵琶湖を北上、塩津港で船を下りた。途中、琵琶湖西岸にある高島三尾の浜辺の沖で「三尾の海に綱引く民のてまもなく 立居につけて都恋しも」と詠んでいる。 |
||
| 往時は琵琶湖海運が盛んで、芭蕉は塩津湊から竹生島(ちくぶしま)に立ち寄っているかも知れない。 | ||
 |
 |
|
| 竹生島 / 前方:竹生島港 | ||
 |
||
| 竹生島全景 | 竹生島港 | |
 |
JR湖西線・今津駅から5分ほどのところに今津港がある。今津港(観光船乗り場)では加藤登紀子の♪琵琶湖就航の歌♪が流れ、気分が高揚する。 |
|
| 琵琶湖汽船乗船券 | ||
 |
||
| 竹生島入島券 | ||
  |
||
| 宝厳寺 都久夫須麻神社 | ||
 |
竹生島は琵琶湖北部にある島で、沖島に次いで面積が広い。 |
|
| 竹生島弁才天 | ||
| 往時賑わった塩津港から木之本宿までは約11kmである。途中に琵琶湖と余呉湖に挟まれたところがあり、ここが賤ヶ岳古戦場である。 | ||
 |
JR北陸本線・木ノ本駅東口からバスに乗車、大音(おおと)バス停で降車する。バスはいろいろ経由するため、3kmほどの距離の割には時間が掛かる。また手前に賤ヶ岳入口バス停があり、紛らわしい。大音バス停から北国街道(8号線)を西に進み、すぐのトンネル入口手前を右折して北に進む。すぐに514号線を越え、左方向にある坂を登る。駐車場から、さらに賤ヶ岳リフト乗り場まで登る。帰路の大音バス停→木ノ本駅は、15:28発の後は18:29発になる。リフト乗り場から木ノ本駅まで35分ほど歩くが、1/3程は歩道のない道でトラックの通行量も多い。 [交通]JR北陸本線・木ノ本駅-(バス)-大音バス停-(徒歩約10分)-賤ヶ岳リフト乗り場 / JR北陸本線・木ノ本駅-(徒歩約35分)-賤ヶ岳リフト乗り場 |
|
| 山頂の賤ヶ岳戦趾碑 | ||
  |
||
| 琵琶湖 / 余呉湖 | ||
 |
賤ヶ岳は標高421mの山で、琵琶湖と余呉湖を分ける風光明媚な位置にある。山頂からは、余呉湖 / 琵琶湖 / 竹生島 / 伊吹山 が望まれる。賤ケ岳の古称は伊香山(いかぐやま)で、「伊香山
野辺に咲きたる 萩見れば 君が家なる 尾花し思ほゆ」と万葉集に読まれている。昭和25年(1950年)に指定された琵琶湖八景のひとつに数えられている。 |
|
| 万葉歌碑 | ||
 |
賤ヶ岳の戦いは、天正11年(1583年)近江国伊香郡(現:滋賀県長浜市)賤ヶ岳周辺での合戦。柴田勝家に勝利した羽柴秀吉は天下人への道が開かれた。両軍とも多くの砦を造って陣地を固めた。 |
|
 |
賤ヶ岳から北東に延びた尾根の先にある大岩山(標高270m)は、賤ヶ岳の戦いの火蓋が切られたところである。羽柴秀吉軍の多くが近江から離れた隙に、大岩山砦の守将・中川清秀は佐久間盛政に攻撃され戦死する。 |
|
| 七本槍古戦場賤ヶ岳 |
||
| 賤ヶ岳古戦場から北国街道を進むと、3kmほどで木之本宿に着く。ここから北国脇往還を進むと、7kmほどで小谷おだに宿に着く。小谷宿は北国脇往還の重要な宿場で、戦国時代には小谷おだに城の城下町であった。 |
||
| 河毛駅コミュニティハウスのスタンプ | ||
 |
← 浅井長政 / お市の方 の図柄になっている。 → 電車に乗って 北びわこ巡りの文字 / 琵琶湖のハクチョウ の図柄になっている。 |
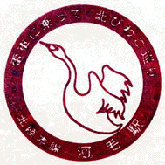 |
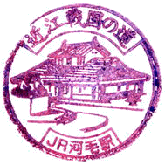 |
JR北陸本線・河毛駅より256号線を東へ進む。365号線の郡上交差点を右折する。郡上南交差点を左折して北へ進むと、小谷城戦国歴史史料館手前右手に登山道がある。
[交通]JR北陸本線・河毛駅-(徒歩30分)-登山道(追手道)入口-(徒歩30分)-本丸 JR北陸本線・河毛駅のスタンプは,近江戦国の道の文字 / 河毛駅舎 の図柄になっている。 |
|
 |
 |
 |
| 小谷城戦国歴史資料館 | 小谷山登山道(追手道) |
磯野屋敷跡 |
 |
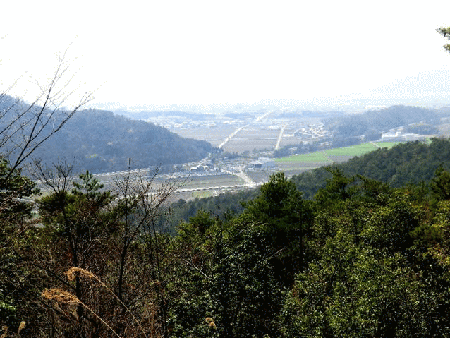 |
|
| 追手道 | ||
 |
||
| 間柄峠 | ぼうしょう峠からの眺望 |
|
| 小谷山登山道(追手道)を進むと磯野屋敷跡 |
||
 |
 |
金吾丸は大永5年(1525年)浅井氏と六角氏の調停のため、朝倉宗滴(教景)が小谷城の一角に布陣したとされる。金吾とは、朝倉宗滴の官名・衛門府の唐名。
番所には登城道に面して石垣が築かれていたと云われている。 |
| 金吾丸跡 | 番所跡 | |
 |
 |
 |
| 御茶屋跡 | 馬洗い池跡 | 首据石 |
| 馬洗池は馬を洗う池とするより、桜馬場下の石垣に取り付くことを防ぐための水堀と云われている。黒金門跡手前に首据石がある。天文2年(1533年)浅井亮政のとき、敵方へ寝返った家臣の首を晒した石と云われている。 | ||
 |
 |
 |
| 黒金門跡 |
桜馬場跡 | 浅井氏 / 家臣 の供養塔 |
 |
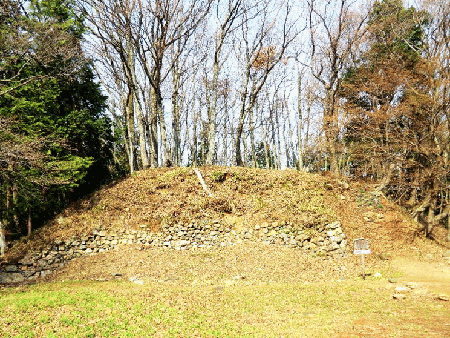 |
|
| 本丸跡 | ||
 |
||
| 本丸の北側にある堀切 |
本丸石垣 | |
| 浅井亮政 / 久政 / 長政 の三代に渡り、湖北を治めた浅井氏の居城。大永3年(1523年)または大永4年(1524年)築城と云われ、堅固な山城として知られている。本丸には石垣が残り、二層の天守があったと云われている。元亀元年(1570年)姉川の戦いで織田・徳川軍に敗れ、天正元年(1573年)清水谷から攻め登った織田軍によって落城した。浅井氏滅亡後に木下籐吉郎に湖北三郡を与えられる。天正3年(1575年)今浜の地に長浜城が築城され、廃城となる。浅井長政とお市の方との悲劇の舞台として知られている。 | ||
| 小谷宿から北国脇往還を進むと、約28kmで関ケ原宿に着く。 | ||
 |
 |
 |
| 松平忠吉・井伊直政陣跡 | 旧山王権現社唐門 | 旧山王権現社社殿 |
 |
||
 |
||
| 祠 | ||
 |
||
| 東首塚 | 首洗いの古井戸 | |
| 関ケ原宿が近づくと、右手に松平忠吉・井伊直政陣跡 / 奥に東首塚がある。松平忠吉は徳川家康の四男で、井伊直政の娘婿。 東首塚は関ヶ原戦い直後に、この地の領主・竹中重門が築いたもの。竹中重門は、軍師として知られる竹中半兵衛重治の息子。徳川家康によって実検された将士の首がここに葬られている。昭和17年(1942年)名古屋・山王権現社唐門や社殿が移築され、東西両軍の戦没者供養堂になっている。 |
||
 |
松平忠吉・井伊直政陣跡から北国脇往還を南に進むと、すぐに東海道本線を関ヶ原古戦橋で越える。関ヶ原古戦橋から関ヶ原駅構内を見ると、3番線 / 4番線ホームが異常に長いことに気付く。 | |
| 関ヶ原古戦橋からの関ヶ原駅構内 | ||
 |
 |
関ヶ原古戦橋で越えると、天正16年(1588年)創建と云われる八幡神社の裏手に突き当たる。右折して廻り込んで南に進むと、中山道(21号線)に突き当たる。 |
| 八幡神社鳥居 | 八幡神社社殿 | |
 |
 |
中山道(21号線)を左折して東に進むと、すぐ左手に門が残る相川脇本陣跡と江戸時代前期の高僧・至道無難禅師生誕地石標がある。 |
| 相川脇本陣跡 | 至道無難禅師生誕地石標 | |
| 中山道69次 58番 関ヶ原(せきがはら)宿 岐阜県不破郡関ケ原町 天保14年(1843年)中山道宿村大概帳 人口:1389人 家数:269 本陣:1 脇本陣:1 旅籠:33 |
||
| 伊勢神宮に通じる伊勢街道 / 越前に通じる北国脇往還 が分岐する交通の要衝として賑わった。天武天皇元年(672年)壬申の乱の戦場となり、その後天武天皇の命で不破の関が置かれた。慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いの地。宝暦10年(1760年)の大火で宿が焼失、復興にあたり道幅を倍に拡張した。道の中央に水路を設け、両側に梅 / 桃 / 柿などを植えて防火対策を講じた。当時の宿場の名残りは殆ど残っていない。 | ||
| [寄り道]関ヶ原ウォーランド | ||
 |
中山道(21号線)を右折して東に進む。関ヶ原西町交差点から365号線を北東へ進む。15分ほどの21号線関ヶ原バイパスと立体交差するところを左折して南へ進むと、すぐに関ヶ原ウォーランドがある。実物大の武将像 / 旗指物 / 陣幕などをを配し、関ケ原合戦を史実に基づいて再現している。 | |