| 2025年 5月25日 追加部分 | ||
 |
 |
157号線(北国街道)まで戻り南に進む。すぐの香林坊交差点の北東側に、香林坊地蔵がある。加賀 |
| 香林坊石柱 | 香林坊地蔵 | |
 |
香林坊交差点から10分足らずの 犀川に架かる犀川大橋を渡ると、西側に にし茶屋街 / 東側に寺院群 がある。主計町(かずえまち)茶屋街 / ひがし茶屋街 に比べると、伝統的建造物が少なく規模も小さい。寺院群は金沢三寺院群のなかで最も規模が大きく、約70もの寺社が集まっている。 金沢駅からは少し遠いが、江戸時代の中心地・片町や香林坊(こうりんぼう)からは近い。 |
|
| にし茶屋街 | ||
 |
 |
157号線(北国街道)の野町1丁目交差点を左折して野町1丁目線1号を東に進む。 |
| 願念寺山門 | 願念寺本堂 | |
| 芭蕉は、蕉門・小杉一笑が元禄元年(1688年)に36歳で早世したことを知る。 |
||
 |
 |
 |
| 町並み | 妙立寺本堂 | 本堂裏からの物見台 |
| 野町1丁目線1号まで戻り東に進む。すぐに右折すると、電柱に忍者寺の案内看板があり、すぐ右手に妙立寺がある。天正13年(1585年)前田利家が前田家の祈願所として金沢城付近に創建、寛永20年(1643年)加賀藩3代藩主・前田利常が現在地に移築した。 本堂屋根の先端に物見台があり、加賀平野を遠望できた。金沢城とは明かりによる連絡も可能であった。 |
||
| 奥の細道 金沢→大聖寺 | ||
| ■元禄2年(1689年)7月15日 高岡→倶梨伽羅峠→金沢 9泊 |
||
| 芭蕉が訪れたときの金沢は、加賀100万国の加賀前田家5代・前田綱紀が藩主であった。支藩に、富山藩10万石 / 大聖寺藩7万石 などがあった。 蕉門・小杉一笑が元禄元年(1688年)に36歳での早世したことを知る。 |
||
| 金沢は第二次世界大戦の戦災を受けることなく、城下町の遺構が色濃く残る。 |
||
 |
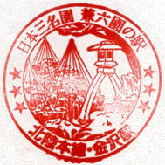 |
 |
| 日本三名園 兼六園の駅。金沢城 / 兼六園 の図柄。 | 日本三名園 兼六園の駅。 | 日本三名園 兼六園の駅。北陸新幹線バージョン。 |
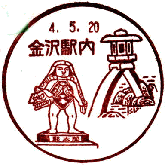 |
 |
JR金沢駅あんと内に金沢駅内郵便局がある。風景印は、金沢港口にある郵太郎ポスト / 兼六園の徽軫(ことじ)燈籠 の図柄になっている。郵太郎ポストは、昭和29年(1954年)国鉄・金沢駅舎の落成記念に設置された。金沢の伝統工芸である加賀人形をモチーフに製作した陶器製の人形が郵便ポストの上に乗っている。 |
| 金沢駅内郵便局風景印 | 郵太郎ポスト | |
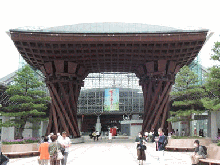 |
 |
|
| 後:もてなしドーム / 前:鼓門 | 鼓門夜景 | |
| JR金沢駅東口(兼六園口)を出ると、もてなしドーム / 鼓門(つづみもん)がある。金沢城門ではなく、金沢伝統芸能の能楽で使われる鼓をイメージしたもの。 |
||
 |
JR金沢駅東口(兼六園口)から金沢駅通りを南東に進む。すぐ左手に金沢駅前郵便局がある。風景印は、金沢駅もてなしドーム / 鼓門(つづみもん) の図柄になっている。 | |
| 金沢駅前郵便局風景印 | ||
 |
 |
 |
| 尾山神社神門(社殿側から) | 尾山神社神門(春) | 尾山神社社殿 |
| 金沢駅通りを南東に進む。近江町市場に近い武蔵交差点を右折して157号線を南西に進む。157号線は往時の北国街道である。5分ほどの左手に明治6年(1873年)創建の尾山神社がある。金沢城跡の西側に |
||
 |
 |
尾山神社スタンプは、昭和60年(1985年)頃のもの。 |
 |
 |
尾山神社から西に進むと、10分足らずのところに足軽屋敷2棟を移築した足軽資料館がある。足軽資料館を抜けて水路沿いに進むと、長町武家屋敷跡 |
| 足軽資料館 | 長町武家屋敷跡 | |
 |
 |
157号線(北国街道)まで戻り南に進む。すぐの香林坊交差点の北東側に、香林坊地蔵がある。加賀 |
| 香林坊石柱 | 香林坊地蔵 | |
 |
香林坊交差点から10分足らずの 犀川に架かる犀川大橋を渡ると、西側に にし茶屋街 / 東側に寺院群 がある。主計町(かずえまち)茶屋街 / ひがし茶屋街 に比べると、伝統的建造物が少なく規模も小さい。寺院群は金沢三寺院群のなかで最も規模が大きく、約70もの寺社が集まっている。 金沢駅からは少し遠いが、江戸時代の中心地・片町や香林坊(こうりんぼう)からは近い。 |
|
| にし茶屋街 | ||
 |
 |
157号線(北国街道)の野町1丁目交差点を左折して野町1丁目線1号を東に進む。 |
| 願念寺山門 | 願念寺本堂 | |
| 芭蕉は、蕉門・小杉一笑が元禄元年(1688年)に36歳で早世したことを知る。 |
||
 |
 |
 |
| 町並み | 妙立寺本堂 | 本堂裏からの物見台 |
|
|
||
 |
武蔵交差点から百万石通りを東に進む。武蔵交差点の南東側に近江町市場がある。5分ほどの尾張町交差点を左折、すぐの突き当りを8右折して百万石通りに平行する道を進む。すぐ左手に、久保市乙剣宮(くぼいちおとつるぎぐう)がある。明治元年(1868年)神仏分離令 境内の裏手から、主計町へと抜ける「暗がり坂」に通じている。花街に遊びに行く旦那衆が通った坂であると云う。 |
|
| 久保市乙剣宮 | ||
 |
 |
 |
| 主計町茶屋街 | 主計町茶屋街 | 浅野川沿いの主計町茶屋街 |
 |
尾張町交差点から東に進み、橋場交差点を左折する。すぐの浅野川に架かる浅野川大橋を渡らずに左折する。浅野川沿いに進むと、狭い通りが花街を彷彿する主計町(かずえまち)茶屋街がある。 | |
| 浅野川に架かる中の橋 | ||
 |
浅野川に架かる浅野大橋を渡ると、359号線に古い建物の町並みが続く。 | |
| 359号線に古い建物の町並み | ||
 |
 |
 |
| ひがし茶屋街 |
ひがし茶屋街 |
ひがし茶屋街 |
| 359号線の東側に、最も規模が大きく重要伝統的建造物群保存地区にも指定されているひがし茶屋街 |
||
 |
橋場交差点まで戻り、百万石通りを南に進む。すぐに西側を平行する小路に、加賀藩中級武士の武家屋敷・寺島蔵人邸がある。金沢市内には武家屋敷 |
|
| 寺島蔵人邸 | ||
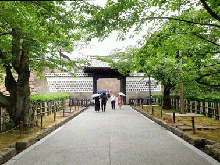 |
橋場交差点から10分ほどの兼六園下交差点を右折して土産店が建ち並ぶ紺屋坂を登ると、右手から金沢城に入れる。 遺構として、石川門(重文) / 三十間長屋(重文) / 鶴丸倉庫(重文) / 石垣 / 堀 / 土塀 がある。 |
|
| 金沢城石川門 | ||
 |
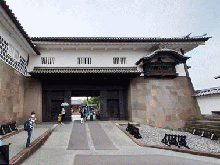 |
 |
| 石川門 櫓(春) | 石川門 | 櫓門塀(鉄砲狭間) |
 |
 |
|
| 二の丸跡 | 菱櫓 | |
| 天文15年(1546年)に造営された尾山御坊(金沢御堂)は、加賀国の統治を行う加賀一向一揆の拠点となっていた。金沢平野のほぼ中央を流れる犀川と浅野川とに挟まれた小立野台地の先端に築かれ、 天正8年(1580年)大阪石山本願寺が織田信長に降伏すると、大聖寺城主・佐久間盛政は尾山御坊を陥落させた。 金沢の地名が広く知られていたため、慶長7年(1602年)頃から金沢城の名称が定着したと云われている。 |
||
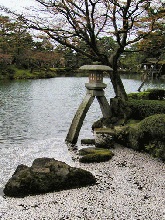 |
 |
 |
| 徽軫(ことじ)燈籠(春) | 噴水(春) | 雪吊り(春) |
| 金沢城跡の南側に兼六園がある。水戸・偕楽園 / |
||
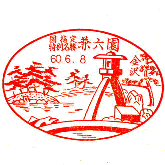 |
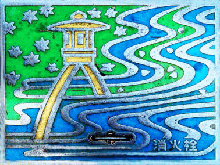 |
兼六園スタンプは、昭和60年(1985年)頃のもの。 市内に徽軫(ことじ)燈籠デザインの消火栓蓋がある。 |
| 兼六園スタンプ | 金沢市消火栓蓋 | |
 |
 |
兼六園の南側に隣接して成巽閣(せいそんかく)がある。文久3年(1863年)加賀藩13代藩主・前田斉泰が母・真龍院(12代斉広夫人)の隠居所として建て造営した。 |
| 成巽閣入口 | 成巽閣 | |
 |
兼六園から百万石通りを挟んだ西側に、天平年間(729年〜748年)創建と云われる石浦神社がある。金沢で一番古い神社 |
|
| 石浦神社社殿 | ||
|
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆元禄2年(1689年)3月27日 深川の杉山杉風の採荼庵(さいとあん)から出立して3ヶ月半、金沢で曾良は体調不良になる。体調不良は腹の具合と云われ、伊勢国長島の親戚のところへ行って養生するために先に発つことになった。 |
||
| ■元禄2年(1689年)7月24日 金沢→小松 | ||
| 金沢から山中温泉を経て越前国松岡までの25日間、立花北枝が随行した。立花北枝は蕉門十哲の1人で、加賀国小松町研屋小路に生まれる。金沢に住み、兄・牧童とともに刀研ぎを業とした。 金沢を出発、小春・牧童・乙州らは町外れ迄 / 雲口・一泉・徳子 らは野々市町迄 / 竹意は小松迄 随行した。小松に到着語、近江屋に投宿した。芭蕉が訪れたときは、加賀藩金沢城の支城で前田佐渡孝貞が城代であった。城代と城番が併存、実質城番が支配していた。城番は2人づつ3組6名で、毎年3月15日に交代していた。 |
||
 |
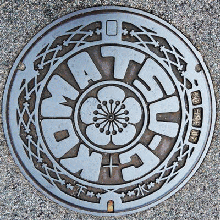 |
JR小松駅西口から25号線を渡ると、小松駅前郵便局がある。風景印は、弁慶と富樫泰家 / 歌舞伎殿 / お旅まつりの子供 の図柄になっている。 小松市マンホール |
| 小松駅前郵便局風景印 | 小松市マンホール |
|
| [寄り道]小松郵便局 | ||
 |
25号線を北に進むと、5分足らずのところに細工町交差点がある。細工町交差点を右折して360号線を東に進む。北陸線高架を潜り、5分足らずの左手に小松便局がある。風景印は、小松空港 / 安宅の関跡 / 弁慶 の図柄になっている。 | |
| 小松郵便局風景印 | ||
 |
 |
 |
| 細工町交差点まで戻り、直進して360号線を西へ進む。地子町交差点を右折して北へ進むと、城下町を思わせる町並みが続く。 | ||
 |
すぐのT字路が小松市役所前交差点で、小松市役所 / 芦城公園 / 石川県立小松高校 辺りが城域となっていた。小松市役所駐車場前に「七十間長屋跡」石柱がある。 [交通]JR北陸本線・小松駅-(徒歩約10分)-小松市役所前交差点 |
|
| 七十間長屋跡 石柱 | ||
| 小松城は、天正4年(1576年)加賀一向一揆方の若林長門守によって築城されたと云われている。 |
||
 |
 |
 |
| 芦城公園 | 土塁(芦城公園) | 三の丸石垣 |
 |
関ヶ原の戦い後、加賀藩初代・ |
|
| 本丸櫓台石垣 | ||
 |
芦城公園に、約2000万年前の珪化木(けいかぼく)が展示されている。木が火山灰に埋まって炭化、岩石の珪酸によって生成された化石。芦城公園の珪化木は巨大で、世界的にも珍しいと云う。 |
|
| 珪化木 | ||
 |
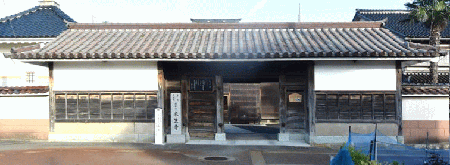 |
|
| 小松大川郵便局 |
来生寺山門 | |
| 芦城公園 |
||
 |
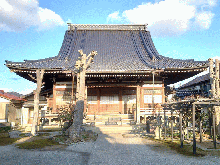 |
大川町交差点まで戻り、左折して南に進む。10分ほどの左手に興善寺寺がある。 |
| 興善寺山門 | 興善寺本堂 | |
| 興善寺は文明7年(1475年)大島村(現:小松市大島町)に創建されたのが始まり。寛永16年(1639年)小松城が2代藩主・前田利常の隠居城となったとき、城下町が町割りされて現在地に移転した。興善寺から更に南に進むと、15分ほどの左手にJR北陸本線・小松駅がある。 |
||
| ■元禄2年(1689年)7月25日 |
||
| 小松を出発しようとしたところ、多くの人たちに引き止められて予定を変更する。多田八幡神社を訪れた後、山王神社神主・藤井伊豆の宅に行き句会開催。この夜は藤井宅に泊る。 | ||
 |
 |
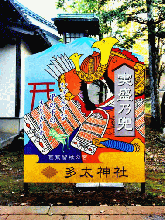 |
| 多田八幡神社鳥居 | 多田八幡神社社殿 | 多田八幡神社 記念撮影用看板 |
 |
 |
多田八幡神社はJR小松駅の南西方向、徒歩25分 |
| 芭蕉神社 | 芭蕉句碑 | |
 |
 |
 |
| 山王神社鳥居 | 山王神社社殿 | 金毘羅社 |
 |
山王神社はJR小松駅の南西方向、徒歩20分 |
|
| 日吉稲荷社 | ||
| ■元禄2年(1689年)7月26日 小松→片山津→小松 | ||
|
片山津は、JR北陸本線・加賀温泉駅からバスで10分余りのところにある。以前は大正3年(1914年)開業の北陸鉄道・片山津線が、動橋(いぶりはし)駅〜片山津駅を結んでいた。昭和40年(1965年)に廃止された。 |
||
| 承応2年(1653年)大聖寺藩2代・前田利明が鷹狩りのとき、柴山潟の水鳥の群れの様子を見て温泉が湧き出しているのを発見した。藩費で掘削に着手したが、湯源を確保することができなかった。何度も開発が試みられたが難航、明治15年(1882年)に源泉が確保され開湯した。 | ||
 |
 |
|
| 砂走公園あいあい広場 | 旧旅館 | |
| 片山津温泉街の中心部に砂走(すなはせ)公園あいあい広場があり、足湯が設けられている。古い建築物はほとんど残っていない。ソープランド街として知られ、9軒が営業している。 | ||
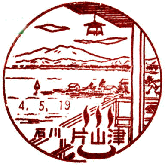 |
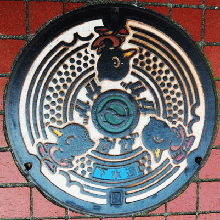 |
片山津郵便局の風景印は、白山 / 片山津温泉郷 の図柄になっている。 昭和33年(1958年)加賀市が発足する。平成17年(2005年)加賀市と山中町が合併して改めて加賀市が発足する。 |
| 片山津郵便局風景印 | 旧加賀市マンホール | |
|
■元禄2年(1689年)7月26日 夜に越前寺宗右衛門宅に招かれて句会。 |
||
 |
 |
 |
| 莵橋神社鳥居 | 莵橋神社鳥居 | 莵橋神社社殿 |
|
諏訪宮=莵橋(うはし.)神社は、JR小松駅から徒歩10分 |
||
| ■元禄2年(1689年)7月27日 小松→(山代温泉)→山中温泉 8泊 |
||
| JR北陸本線・ 加賀温泉駅からバスに乗車、15分ほどの山代温泉を経由して35分ほどで山中温泉に着く。 |
||
 |
 |
|
| 旅館群 | 町並み | |
| 山代温泉は神亀2年(725年)行基が羽を休める八咫烏(やたからす)を見つけ、手を浸したところ温泉を発見したと云われている。薬王院温泉寺は行基が温泉守護のため、薬師如来などを彫り、堂宇を建てたのが始まり。 | ||
 |
 |
|
| 旅館 | ||
 |
||
| 山代温泉古総湯 | 山代温泉総湯 | |
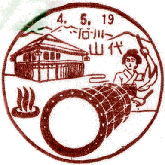 |
山代温泉古総湯の西方向に山代郵便局がある。風景印は、山代温泉古総湯 / 湯の華太鼓 の図柄になっている。 | |
| 山代郵便局風景印 | ||
| ■元禄2年(1689年)7月27日 小松→(山代温泉)→山中温泉 8泊 |
||
 |
JR北陸本線・ 加賀温泉駅からバスに乗車、15分ほどの山代温泉を経由して35分ほどで山中温泉に着く。以前は明治32年(1899年)開業の北陸鉄道・山中線が、
大聖寺駅-(8.9km)-山中駅を結んでいた。途中駅の河南駅で山代線(旧連絡線)が接続していた。昭和46年(1971年)に廃止された。 |
|
 |
奈良時代に行基が発見したと云われている。山中温泉は山に囲まれた街であり、大聖寺川の渓谷沿いなどに旅館が立ち並ぶ。山中漆器の産地で、土産物屋が多い。民謡・山中節は、江戸時代の元禄期から歌い継がれているとされる。 |
|
| 町並み | ||
 |
 |
|
| 旅館 | ||
 |
||
| 総湯・菊の湯 | 旅館 | |
| ■元禄2年(1689年)8月1日 黒谷橋 | ||
 |
鶴仙渓(かくせんけい)に掛かる黒谷橋は、古来から那谷寺(なたでら)に通じる橋として利用されていた。 橋から続く道は那谷道とも呼ばれ、峠を越えて那谷寺や小松に通じていた。 芭蕉はここが気に入り散策しながら、「この川の黒谷橋は絶景の地なり行脚の楽しみここにあり」と絶賛した。 |
|
| 黒谷橋 | ||
 |
 |
鶴仙渓遊歩道の黒谷橋のたもとに、明治43年(1910年)建立の芭蕉堂 / 茶店 がある。 |
| 芭蕉堂 | 茶店 | |
 |
芭蕉の館(有料施設)は、芭蕉が滞在した和泉屋久米之助宅に隣接の扇屋別荘を改築したもの。芭蕉が書き残した「やまなかや 菊は手折らじ ゆのにほひ」の掛軸真蹟などがある。 |
|
| 芭蕉の館 | ||
 |
 |
山中郵便局の風景印は、黒谷橋 / 鶴仙渓 の図柄になっている。 旧山中町マンホールは、こおろぎ橋 / 大聖寺川 / コサギ の図柄になっている。 平成17年(2005年)加賀市と山中町が合併して改めて加賀市が発足する。 |
| 山中郵便局風景印 | 旧山中町マンホール | |
|
■元禄2年(1689年)8月5日 山中温泉→黒谷橋→那谷寺(なたでら)→小松 |
||
| 加賀温泉駅から那谷寺を通る加賀周遊バスCANBUSが運休になっていた。 芭蕉と立花北枝は養老元年(717年)創建と云われる那谷寺へ行き、奇岩遊仙境の岩肌を臨み「石山の 石より白し 秋の風」と詠んだ。 |
||
 |
 |
那谷寺バス停から南に進むと、すぐ右手に那谷阿弥陀堂 / 那谷郵便局 と続く。風景印は、奇岩遊仙境 / 紅葉 / 石段 / 那谷寺本殿(重文) の図柄になっている。 |
| 那谷阿弥陀堂 | 那谷郵便局風景印 | |
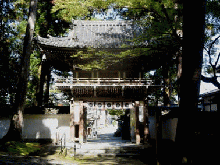 |
 |
|
| 山門 | ||
 |
||
| 金堂華王殿 | 奇岩遊仙境 | |
 |
 |
|
| 唐門 | ||
 |
||
| 唐門〜大悲閣の階段 | 大悲閣(本堂) | |
| 那谷寺(拝観600円)は養老元年(717年)創建の厳屋寺が始まり。寛和22年(986年)那谷寺と改称した。本尊の |
||
 |
駐車場にある御柱は、創建1300年の平成29年(2017年)御柱立柱祭で建てられたもの。 | |
| 御柱 | ||
| 芭蕉が那谷寺から小松に戻るとき、粟津温泉を通ったと思われる。 | ||
 |
那谷寺から小松に行く路線バスは、粟津温泉 / 粟津駅 を経由する。那谷寺から粟津温泉は徒歩50分の距離である。 |
|
| 粟津郵便局風景印 | ||
 |
 |
|
| 法師 | 黄門杉 | |
| 粟津温泉街の中心地にある法師は、養老2年(718年)の開湯から続く老舗旅館。北陸最古の旅館で、文化財指定の旅館になっている。法師の前に、道を塞ぐ様に樹齢約400年の黄門杉がある。加賀藩2代藩主・前田利常 水戸光圀も中納言に任じられており、水戸黄門と呼ばれていた。 |
||
 |
 |
|
| 旅館 | ||
 |
||
| 昭和8年(1933年)竣工の粟津演舞場 |
旅館 | |
 |
 |
400年も前から地元で語り継がれている恋物語・おっしょべ恋物語は、恋人の聖地になっていると云う。旅館の奉公人として働いていたお末と竹松の恋物語。 |
| おっしょべ公園 | お末と竹松の像 | |
| 芭蕉は7月24日に金沢から小松に到着、山中温泉の8泊を経て8月5日に小松から大聖寺に向かった。小松滞在中、源義経を慕う芭蕉が安宅の関(あたかのせき)を訪れているか気になるところである。 | ||
 |
||
| 梯川 | ||
 |
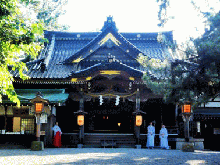 |
安宅の関にはJR北陸本線・小松駅より安宅線に乗車、関跡前バス停で下車する。日中は概ね2時間毎の運行(2023年8月)である。関跡前バス停からバスの進行方向に進むと、すぐに交差点がある。直進して梯(かけはし)川沿いに進むと、すぐ左手に安宅の関があったとされる安宅住吉神社がある。 |
| 安宅住吉神社鳥居 | 安宅住吉神社社殿 | |
| 安宅は古代の安宅駅の地とされ、海陸交通上の要地であった。中世には日本海海運の中継ぎ港として商品流通の拠点であり、北前船の寄港地 / 小松城下の外港
として船問屋の倉庫が林立して賑わっていた。 寛正6年(1465年)に成立したと云われる謡曲・安宅 / 元禄15年(1702年)成立の勧進帳 の舞台として知られている。寿永3年(1184年)加賀守護に任ぜられた富樫氏6代・富樫泰家は、文治3年(1187年)源義経や武蔵坊弁慶を見逃したとされる創作。 史実でないが安宅住吉神社は関所跡とされ、観光バスも立ち寄っている。 |
||
 |
 |
 |
| 住吉橋から河口方面を望む |
安宅郵便局風景印 | 小松市マンホール |
| 交差点まで戻り梯川に架かる住吉橋を渡ると、安宅の町並みになる。2本目の十字路を左折すると、すぐ右手に安宅郵便局がある。風景印は、勧進帳の巻物の変形外枠 / 勧進帳・安宅の関 の図柄になっている。小松市のマンホールには、勧進帳の弁慶 / 巻物に「清き水となり 台地をうるおせ」の図柄になっているものがある。 | ||
| ■元禄2年(1689年)8月6日 小松→大聖寺(だいしょうじ)2泊 | ||
 |
 |
JR北陸本線・大聖寺駅スタンプは、「加賀百万石の支藩・大聖寺藩城下町の駅」の文字 / 長流亭 / 時鐘堂 / 大聖寺流し舟 の図柄になっている。大聖寺駅1番ホーム(金沢方面)に、山中温泉で詠んだ「やまなかや 菊はたおらし ゆのにほひ」芭蕉句碑がある。 |
| 大聖寺駅スタンプ | 芭蕉句碑 | |
 |
元禄2年(1689年)当時は、加賀藩支藩の大聖寺藩2代藩主・前田利明が治めていた。 JR北陸本線・大聖寺駅より北に進む。5分ほどの大聖寺南町交差点を左折して、305号線を西へ道なりに進む。すぐの図書館前交差点を過ぎると、すぐ左手に大聖寺聖南通郵便局がある。 |
|
| 大聖寺聖南通郵便局風景印 | ||
 |
大聖寺聖南通郵便局からすぐの十字路を左折して南西に進むと、突き当りに天正4年(1576年)創建の全昌寺がある。大聖寺城主だった山口玄蕃頭宗永の菩提寺。
芭蕉は全昌寺に8月6日から2泊している。芭蕉到着前の前日、曾良も泊まっている。「終宵(よもすがら)秋風聞や うらの山」曾良 |
|
| 全昌寺 | ||
| 305号線まで戻り、西に進む。大聖寺関町交差点交差点を右折して北へ道なりに進むと、左手に錦城山公園がある。 [交通]JR北陸本線・大聖寺駅-(徒歩15分)-錦城山公園 |
||
| 大聖寺城(錦城)は、鎌倉時代に狩野氏によって築城される。建武2年(1335年)に中先代(なかせんだい)の乱に呼応した名越時兼が南下してきたとき、大聖寺城で迎撃したと云う。中先代の乱は、鎌倉幕府14代執権・北条高時の遺児・時行が鎌倉幕府再興のため挙兵した反乱。建武4年(1337年)新田義貞に荷担した敷地伊豆守、山岸新左衛門らが津葉清文の守る大聖寺城を攻略している。戦国時代には日谷城などとともに一向一揆の拠点となっていた。天文24年(1555年)越前国・朝倉宗滴が加賀に侵攻、大聖寺城は落城する。永禄10年(1567年)堀江景忠が一向一揆とともに朝倉義景に反乱する。足利義昭の斡旋により和議が成立するが、大聖寺城は焼払われる。天正3年(1575年)越前を平定した織田信長軍は加賀に侵攻、柴田勝家に命じて大聖寺城を修復させる。天正4年(1576年)佐久間盛政が城主となる。天正8年(1580年)柴田勝家は本願寺勢力の金沢御堂を攻略、拝郷家嘉が城主となる。天正11年(1583年)賤ヶ岳の戦い後は溝口秀勝 / 慶長3年(1598年)小早川秀秋の家臣・山口宗永(玄蕃)が城主となる。翌年に小早川秀秋は転封となるが、山口宗永(玄蕃)は豊臣秀吉直臣となり当地に留まった。慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いで山口宗永(玄蕃)は西軍に組したため、東軍の前田利長に攻められて大聖寺城は落城する。山口宗永(玄蕃)は嫡男・修弘と共に自刃した。その後は前田家の家臣が城代を務めたが、元和元年(1615年)の一国一城令での廃城となった。寛永16年(1639年)加賀藩3代藩主・前田利常の三男・前田利治が7万石を分地され立藩、大聖寺城跡地に大聖寺陣屋を設けた。 | ||
 |
 |
 |
| 本丸への登り坂 | 贋金造りの洞穴 | 土塁 |
| 錦城山公園入口から標識に従い、本丸へ進む。すぐに本丸と東丸との分岐があり、すぐ左手に“贋金造りの洞穴”がある。明治政府に武器弾薬の供出を命じられた大聖寺藩は、必要な資金を贋金を作り賄った。1分銀に金メッキを施す方法であるが、光沢があり過ぎた。このため山代温泉の湯に数日間浸けて、古い金貨と見分けが付かない様にした。以降も金貨偽造を続けたが、明治2年(1869年)に露見する。贋金作りを命じられた市橋波江は、切腹させられた。大聖寺藩は、継嗣に旧禄高の2倍を与えて跡を継がせている。 | ||
 |
 |
 |
| 本丸跡 | 東屋 | 山口玄蕃頭宗永公碑 |
| 錦城山公園入口から10分ほどすると、本丸跡に辿り着く。夏草に覆われた東屋や案内板 / 北側に山口玄蕃頭宗永公碑 がある。西の丸方向に、夏草に覆われたところを進む。方角が解らなくなり、泥だらけになる。忠霊塔に下る階段が現れ、安堵する。 | ||
 |
 |
 |
| 長流亭 | 江沼神社鳥居 | 江沼神社社殿 |
| 錦城山公園入口を北へ進むと、すぐ右手に茶室・長流亭(重文)がある。大聖寺藩3代藩主・前田利直の休息所として、小堀遠州の設計により宝永6年(1709年)に建てられた数寄屋造りの建築。隣接して宝永元年(1704年)創建の江沼神社がある。大聖寺藩3代藩主・前田利直が邸内に天満天神社を創建したのが始まり。松嶋神社が明治10年(1877年)に江沼神社と改称、明治12年(1879年)天満天神社を合祀する。 | ||
 |
 |
 |
| 福田橋 | 山口玄蕃頭宗永公御堂 | 山口宗永首塚 |
| 慶長5年(1600年)山口宗永(玄蕃)と嫡男・修弘は、新町で共に自決した。昭和10年(1935年)に架け替えられた旧大聖寺川に架かる福田橋を渡った右手に、山口宗永首塚がある。嫡男・修弘は山口宗永の菩提寺・全昌寺に葬られている。 | ||
 |
旧大聖寺川に架かる福田橋から南へ進むと、5分足らずの右手に吉田屋薬舗がある。吉田屋は酒造業 / 薬種業 を本業としていた豪商で、大聖寺藩に火薬を納める御用商人でもあった。文政7年(1824年)4代・吉田屋伝右衛門は、古九谷再興のため九谷村に吉田屋窯を開いた。九谷村は山奥で不便なため、文政9年(1826年)山代温泉に移された。吉田屋窯の作品は、緑 / 黄 / 紫 / 紺青 の四彩を用いた色絵が多く“青九谷”と称されている。古九谷再興の資金負担は膨大で、吉田屋の財政を圧迫し続けた。文政10年(1827年)伝右衛門が死去、文政13年(1831年)財政難で僅か7年で終えることになる。衰退していた九谷焼を再興したことで高く評価されている。大半の家屋敷と酒造業の株(藩の酒造業免許)を売却、以後薬舗の取り扱いを専業とする様になった。 | |
| 吉田屋薬舗 | ||
 |
 |
 |
| 深田久弥生家 | 深田久弥生誕之地 石柱 | 時鐘堂 |
 |
 |
 |
| 深田久弥文学碑 | 八間道船乗場 | 深田久弥 山の文化館 |
|
日本百名山で知られる深田久弥(ふかだ きゅうや)は、石川県大聖寺町(現:加賀市)生まれの小説家(随筆家) / 登山家。大聖寺中町通りにある深田久弥生家前には、“深田久弥生誕之地”石柱がある。深田久弥生家から北へ進むと、すぐ右手に平成14年(2002年)再建された旧藩時代の時鐘堂がある。江沼神社の鳥居を潜ると、右手に「山の茜を顧みて 一つの山を終りけり 何の俘のわが心 早も急かるる次の山」深田久弥文学碑がある。江沼神社の北東側に“大聖寺川流し舟”の八間道船乗場があり、旧大聖寺川を渡った右手に深田久弥山の文化館がある。明治43年(1910年)に建てられた絹織物工場・山長の事務所 / 石蔵 / 門 を修築したもので、国登録文化財になっている。石蔵はかつて生糸の保管庫として使われていた木骨石造りで、1階は深田久弥遺品を中心とした展示室 / 2階は資料の収蔵庫として使用している。 |
||