| ■元禄2年(1689年)5月13日 一ノ関→平泉→一ノ関 / 5月14日 一ノ関→岩出山 | |||||
 |
岩出山は岩出山要害の城下町で、岩出山伊達家が領していた。 | ||||
| 城下の町並み | |||||
| 応永年間(1394年〜1428年)奥州探題であった大崎氏の家臣・氏家直益が築城した。 岩出山城跡は、城山公園 / 有備館 / 宮城県立岩出山高等学校 / 大崎市立岩出山小学校 となっている。 |
|||||
 |
 |
 |
|||
| 本丸跡 | 西の腰曲輪 / 伊達政宗像 | 伊達政宗像 | |||
| JR岩出山駅から164号線を西へ道なりに進むと、城山公園がある。西の腰曲輪跡に伊達政宗像がある。仙台城跡に置かれていたもの。仙台城跡の銅像は第2次世界大戦における金属類回収令で失われ、コンクリート造りになっていた。昭和37年(1962年)に移設された。 | |||||
 |
 |
||||
| 有備館(ゆうびかん)は、元禄4年(1691年)頃に岩出山伊達氏3代・伊達敏親により城内の隠居所・下屋敷の敷地内に開設された仙台藩の学問所(春学館)。元禄4年(1691年)城の北麓にあたる現在地に移転、有備館と改称される。 |
|||||
 |
 |
有備館の南東側に阿部東庵記念館がある。長崎で蘭学、京都で茶道 / 歌道 / 医学 を学んだ。 |
|||
|
■元禄2年(1689年)5月15日 岩出山→鳴子町(通過)→堺田 2泊 / 5月17日 堺田→笹森関所→山刀伐峠(なたぎりとうげ)→尾花沢 10泊 5月25日夜、庚申待に招待される。 |
|||||
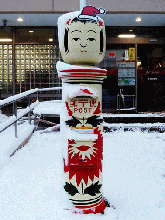 |
 |
鳴子温泉は、古代から中世にかけては“玉造湯(たまつくりのゆ)”と呼ばれていた。福島・飯坂温泉 / 宮城・秋保温泉 とともに奥州三名湯に数えられた。鳴子こけしは、文化・文政年間(1804年〜1830年)頃が始まりと云われている。 鳴子郵便局風景印は、荒雄岳 / 鳴子ダム / 鳴子こけし の図柄になっている。 |
|||
| 鳴子こけしポスト | 鳴子郵便局風景印 | ||||
| 庚申待(こうしんまち) | |||||
|
人の体には三尸(さんし)という虫がおり、60日周期で訪れる庚申の日の夜に人の罪状を天帝に告げに行くとされる。罪状により寿命が縮められる。三尸は起きていれば告げに行くことがないので、この晩は夜通し騒いで寝ずに過ごすのである。室町時代の中頃から庚申待が行われる様になり、さらに講集団が組織された。江戸時代になると各地に庚申講がつくられ、供養のため庚申塔が造立される様になった。 |
|||||
| ■元禄2年(1689年)5月27日 尾花沢→立石寺 |
|||||
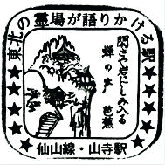 |
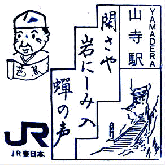 |
JR仙山線・山寺駅より北に進み、すぐの突き当りを右折する。すぐの十字路を左折して、すぐに立合川に架かる山寺宝珠橋を渡る。すぐのT字路を右折すると、左手に登り口がある。 |
|||
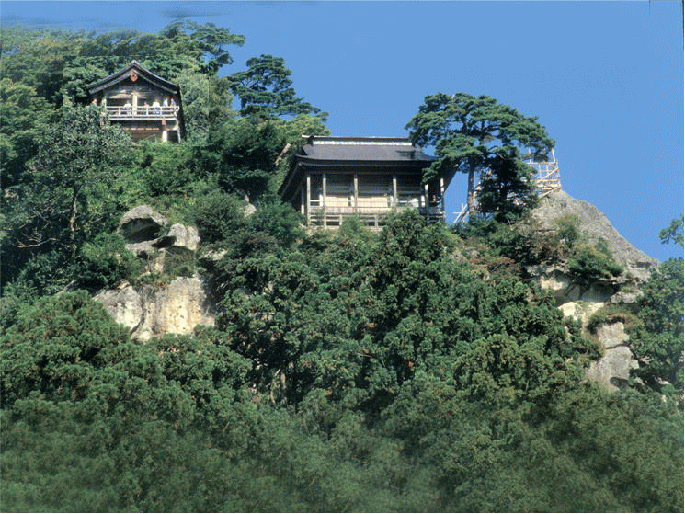 |
|||||
| 五大堂 / 開山堂 | |||||
 |
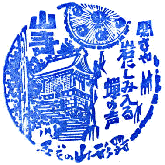 |
 |
|||
 |
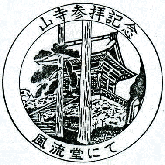 |
||||
 |
宝珠院立石寺(りっしゃくじ)は貞観2年(860年)に清和天皇の勅命で慈覚大師円仁が創建したと云われ、山寺(やまでら)の通称で知られている。 | ||||
 |
 |
||||
| 地蔵群 | 弥陀洞からの仁王門 | ||||
| 芭蕉は人々が勧めるので、尾花沢から立石寺を訪れた。約30kmの道のりで、到着後はまだ陽が残っていた。麓の坊に宿を借りて、山上の御堂に登った。弥陀洞(みだほら)辺りで、「閑さや岩にしみ入蝉の声」が詠まれたと云われている。 | |||||
 |
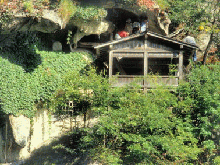 |
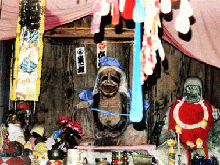 |
|||
| 立石寺には雨風に削られた風化した洞窟が多く、祠が置かれているところもある。 | |||||
 |
|||||
| 開山堂 / 五大堂 | |||||
 |
眼下に立合川に架かる山寺宝珠橋 / 山裾を通るJR仙山線と山寺駅 が見える | ||||
|
■元禄2年(1689年)5月28日 立石寺→天童→最上川中流に位置する船着き場である大石田 3泊 / 6月1日 大石田→舟形町→新庄 2泊 |
|||||
 |
 |
||||
| JR奥羽本線・新庄駅スタンプ | |||||
 |
|||||
| JR奥羽本線・新庄駅構内展示の山車 | 新庄城の本丸南西隅にある天満宮 | ||||
|
毎年8月24日〜26日に開催される新庄まつりは、天満宮の例祭で東北三大山車祭とされる。天満宮は応永年間(1394年〜1428年)角館時代から続く戸沢氏の氏神で、転封に伴い移転してきた。元和8年(1622年)新庄藩に転封になると新庄城下へ移転、新庄城が完成すると寛永5年(1628年)戸沢氏の氏神と城の鎮守社として新庄城の本丸南西隅に移転した。 |
|||||
 |
新庄は山形県北東部に位置する盆地で、国内有数の豪雪地帯として知られている。 |
||||
| 家屋の雪囲い | |||||
|
■元禄2年(1689年)6月3日 新庄→川舟にて東田川郡立川町を経由して羽黒町 |
|||||
|
出羽三山 / 五重塔 / 鏡池 は、歌枕として数多く登場している。江戸時代に参拝した方により造立された出羽三山供養塔は、各地で見られる。 |
|||||
 |
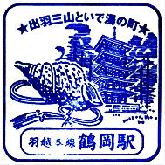 |
出羽三山の入口は、羽越本線・鶴岡駅になる。羽黒山は鶴岡駅前-(バス約35分)-羽黒随神門-(徒歩約10分)-五重塔-(徒歩60分〜90分)羽黒山頂 |
|||
| 山伏がいる出羽三山の駅。羽黒山 / 月山 / 湯殿山 / 山伏 の図柄になっている。 | 出羽三山といで湯の町。法螺貝 / 羽黒山五重塔(国宝) の図柄になっている。 | ||||
 |
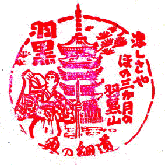 |
羽黒山 / 月山 / 湯殿山 は出羽三山と呼ばれ、古くから山岳修験道の山岳信仰の山として知られている。羽黒山は標高414mの山で、出羽三山の主峰である月山の北西山麓に位置している。羽黒山には、三山の神を祀る出羽三山神社・三神合祭殿 / 五重塔(国宝) がある。 | |||
 |
羽黒山五重塔は、承平年間(931年〜938年)平将門によって建立されたと云われている。現存する五重塔(国宝)は、応安5年(1372年)に羽黒山の別当・大宝寺政氏が再建したと云われている。 |
||||
  |
|||||
| 杉木立の2446段の羽黒山参道 | |||||
 |
|||||
| 出羽三山神社・三神合祭殿 / 鏡池 | |||||
 |
|||||
| 鏡池に映る出羽三山神社・三神合祭殿 | |||||
| 文政元年(1818年)再建の出羽三山神社・三神合祭殿前に鏡池がある。古くは“羽黒神社”を“いけのみたま”と読ませており、信仰の対象となっていた。古くから奉納された銅鏡が埋納されているので鏡池と呼ばれている。 | |||||
 |
 |
||||
| 鐘楼 | 蜂子神社などの境内社 | ||||
| 鐘楼は元和4年(1618年)出羽山形藩2代・最上家信によって建立されたもの。 | |||||
| ■元禄2年(1689年)6月10日 羽黒町→鶴岡 3泊 「珍しや山をいで羽の初茄子び」 |
|||||
 |
 |
 |
|||
| 日枝神社 | 町並み | 内川沿いの 家並み | |||
|
鶴岡は亀ヶ崎城の城下町。元和8年(1622年)出羽山形藩3代・最上義俊はお家騒動(最上騒動)により改易となる。 |
|||||
| ■元禄2年(1689年)6月13日 鶴岡から川舟に乗って酒田 2泊 「暑き日を海にいれたり最上川」「あつみ山や吹浦かけて夕すヾみ」 |
|||||
 |
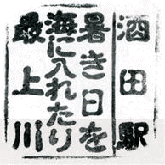 |
JR羽越本線・酒田駅スタンプは、飛島 / 山居倉庫 の図柄 と「暑き日を海にいれたり最上川」がある。 | |||
 |
|||||
| 最上川河口 / 木造六角灯台 | |||||
| 酒田は平安時代初期には出羽国の国府が置かれていた地で、最上川が日本海に注ぐ河口に位置している。古くから日本海沿岸や内陸河川交通の要地として、多くの豪商が軒を並べていた。寛文12年(1672年)西回り航路(北海道〜北陸 〜山陰〜下関〜瀬戸内海〜大坂〜江戸)が開拓され、北前船が往来した。江戸時代中期の酒田は、戸数3800軒 / 酒屋20軒 / 染屋18軒 / 鍛冶屋58軒 / ローソク屋17軒 / 油屋33軒 / 研ぎ師2軒 / 桶屋42軒 / 大工122軒 / 木挽き26軒 / 回船問屋97軒 / 川舟(2〜5人乗り)218艘 / 川舟(1人乗り)255艘 / 漁舟39艘 の記録がある。酒田の代表的な産物は刃物 / 木工品 / 酒 などで、蝦夷地(現:北海道)で使用された打刃物のほとんどは酒田産であった。 | |||||
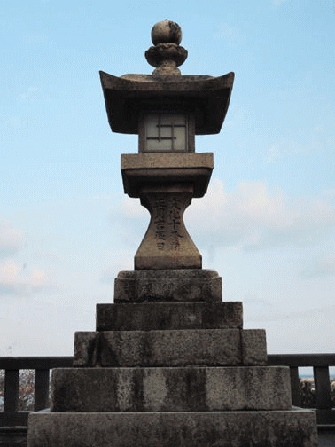 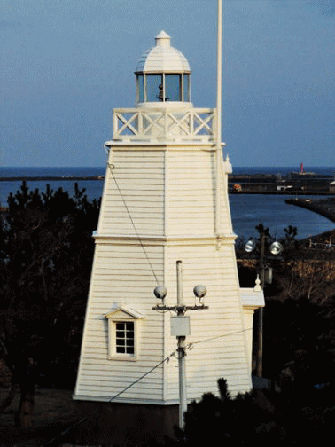 |
|||||
| 常夜燈 木造六角灯台 | |||||
 |
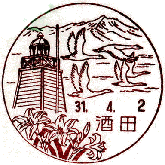 |
日本海 / 酒田港 / 最上川河口を一望できる日和山公園に、文化10年(1813年)造立の常夜燈 |
|||
| 千石船 | 酒田郵便局風景印 | ||||
 |
酒田は亀ヶ城の城下町でもあった。 元和8年(1622年)出羽山形藩3代・最上義俊は改易となり、酒井忠勝が庄内藩13万8000石で入封、鶴ヶ岡城を居城とした。 |
||||
| 酒田東高と八幡神社の間にある土塁 | |||||
  |
|||||
| 本間家旧本邸 本間家別館 | |||||
| 酒井本間家は 本間家旧本邸 宝暦5年(1755年)〜宝暦6年(1756年)宝暦の大飢饉で多くの農民が餓死したことから、豊作のときには米を庄内藩の米倉に貯蔵しる備蓄計画を起案した。この計画は昭和20年頃まで維持された。 |
|||||
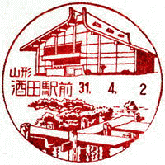 |
酒田駅前郵便局風景印は、本間美術館本館 / 庭園・鶴舞園 の図柄になっている。 | ||||
 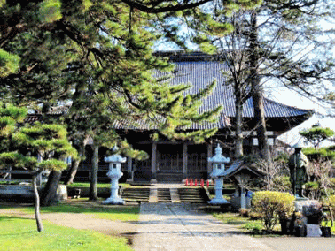 |
|||||
| 浄福寺唐門 |
|||||
| 浄福寺は |
|||||
  |
|||||
| 日枝神社随神門 日枝神社拝殿 | |||||
|
日枝神社 |
|||||
|
|||||
  |
|||||
| 宿泊ホテルからの眺望 山居倉庫 | |||||
  |
|||||
| ケヤキ並木 / 山居倉庫 三居稲荷神社 | |||||
| 山居(さんきょ)倉庫 |
|||||
|
■元禄2年(1689年)6月15日 酒田→吹浦 / 6月16日 吹浦→象潟(きさがた)2泊 |
|||||
|
象潟は松島と並ぶ風光明媚な歌枕で、芭蕉は「俤(おもかげ)松島に通ひて、また異なり。松島は笑ふが如く、象潟は憾む(うらむ)が如し。寂しさに悲しみを加へて、地勢 魂を悩ますに似たり。」と形容した。 |
|||||
 |
JR羽越本線・象潟駅から西に進む。 [交通]JR羽越本線・象潟駅-(徒歩約10分)-熊野神社 象潟駅スタンプは、鳥海山 / 蚶満寺(かんまんじ)/ 九十九島 の図柄になっている。 |
||||
| 象潟駅スタンプ | |||||
 |
熊野神社は神明の森と呼ばれる小高い丘にあり、芭蕉や江戸時代後期の旅行家・菅江真澄らが訪れている。往時は鳥海山と九十九島(つくもじま)が一望出来たと云われている。 |
||||
| 熊野神社 | |||||
 |
 |
 |
|||
| 蚶満寺山門 | 蚶満寺本堂 | 蚶満寺鐘楼 | |||
| 熊野神社鳥居から東へ進む。すぐの中橋を渡り道なりに進むと、7号線と斜めに交差する。交差点を東方向に進み、JR羽越本線の踏切を越える。すぐのT字路を左折して北に進むと、すぐにJR羽越本線沿いの道となる。すぐ右手に仁寿3年(853年)創建の蚶満寺(かんまんじ)境内が広がる。 [交通]JR羽越本線・象潟駅-(徒歩約15分)-蚶満寺 |
|||||
 |
 |
||||
| 蚶満寺境内からの眺望(左:駒留島) | にかほ市象潟町マンホール | ||||
| 紀元前466年に鳥海山が噴火、山体崩壊により浅い海と多くの小島できた。やがて砂丘によって仕切られて潟湖となり、小島には松が生い茂り風光明媚な象潟の地形ができあがった。古来より歌枕の地として知られ、古今和歌集や新古今和歌集などにも登場する。江戸時代には、東の松島
/ 西の象潟 と称された。芭蕉は西行を偲んで訪れ、芭蕉を偲んで与謝蕪村や小林一茶が訪れている俳人の巡礼地。 元禄2年(1689年)6月に松尾芭蕉が奥の細道で訪れ、九十九島(つくもじま)と呼ばれた象潟の景観を絶賛している。芭蕉は中国の悲劇の美女西施を思い浮かべ、「象潟や 雨に西施が ねぶの花」と詠んでいる。 |
|||||
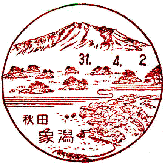 |
蚶満寺境内から線路沿いに南に進み、JR羽越本線の踏切を渡る。すぐに左折して7号線を南に進む。 象潟駅前交差点から5分ほどの左手に秋田象潟郵便局がある。風景印は、鳥海山 / 九十九島(つくもじま) / 小砂川海岸 の図柄になっている。 | ||||
| 秋田象潟郵便局風景印 | |||||
