| ■元禄2年(1689年)4月2日 鉢石宿→日光裏見の滝→鉢石宿-(日光街道)-今市宿(現:春日町交差点)-(日光北街道)-玉生(たまにゅう)宿 曽良日記「同晩 玉入泊 宿悪故 無理ニ名主ノ家入テ宿カル」 玉生宿の宿籠は最悪だった様である。 |
||
| 日光北街道は、日光街道・今市宿と奥州街道・大田原宿を結ぶ約40kmの脇街道。宿場は、今市宿 / 大渡(おおわたり)宿 (栃木県日光市) |
||
| ■元禄2年(1689年)4月3日 玉生宿-(日光北街道)-奥州街道・大田原宿-(黒羽街道)-黒羽 曽良日記「太田原ヨリ黒羽根ヘ三リト云ドモ二リ余也」 |
||
 |
 |
 |
| 忍精寺 | 愛宕神社 | 薬師堂 |
| 日光北街道は大田原市の神明町交差点で奥州街道に合流、すぐ右手に忍精寺 / すぐ左手に愛宕神社 / すぐ左手に寛正5年(1793年)に再建された薬師堂 と続く。愛宕神社社殿には、神明町公民館の表札が掛っている。 | ||
 |
||
 |
||
| 那須与一像 | ||
 |
||
| 正法寺 | 金灯籠 | |
| 薬師堂から5分ほどすると、左手に那須与一像 / すぐ左手に正法寺 / すぐの金燈籠交差点を渡る手前左手に金灯籠(かなどうろう) と続く。文政3年(1820年)造立の金灯籠 元禄2年(1689年)当時、金灯籠は未だなかった。 |
||
 |
金燈籠交差点から旧奥州街道を北東へ進む。旧奥州街道は次の交差点を左折して、ビジネスホテル手前を右折する。桝形を通り道なりに進むと、461号線に合流する。金燈籠交差点から10分ほどになる。すぐ左手に太田原神社がある。天文12年(1543年) |
|
| 太田原神社 | ||
 |
奥州街道(461号線)を挟んだ反対側に、大田原城跡がある。太田原神社からは461号線横断架橋で行ける。大田原城は、天文12年(1543年)大田原資清によって築城された平山城。明治維新まで大田原氏が居城した。龍城 / 龍体城 / 前室城 の別名がある。戊辰戦争のとき、大田原城は会津攻めの重要拠点とされた。慶応4年(1868年)旧幕府軍による攻撃を受け、三の丸が炎上した。明治6年(1873年)廃城令により廃城となる。現在は龍城公園(城山公園)になっており、土塁 / 堀 が残る。 | |
| 大田原城本丸跡 | ||
 |
461号線横断架橋下からすぐに、蛇尾(さび)川に架かる蛇尾橋を渡る。当初は橋渡しで、橋が流失した時は人足による徒歩渡しだった。天保3年(1832年)からは舟渡しになった。 |
|
| 蛇尾川 | ||
| ■元禄2年(1689年)4月3日 余瀬の翠桃宅に着く。 |
||
| ■元禄2年(1689年)4月4日 芭蕉と曾良は浄法寺高勝邸に招かれ歓待され、11日まで滞在した。 |
||
 |
大雄(だいおう)寺は応永11年(1404年) |
|
| 大雄寺山門 | ||
  |
||
| 大雄寺総門 / 廻廊 大雄寺本堂 | ||
 |
大雄寺参道を戻ると、隣接して虚空蔵堂がある。 | |
| 虚空蔵堂 | ||
 |
 |
 |
| 芭蕉句碑 | 浄法寺邸跡 | 大雄寺方向 |
| 虚空蔵尊堂から北に進むと、左手に案内板 / 芭蕉句碑「行く春や鳥啼き魚の目は泪」がある。ここから芭蕉の道に入ると、黒羽城三の丸の南にある浄法寺邸跡に行ける。西方向に、堀を挟んで木々の間から大雄寺の建物が見える。 浄法寺高勝は黒羽藩の城代家老で俳人、芭蕉の門下で俳号は桃雪 / 秋鴉。ここで芭蕉は「山も庭もうこき入るや夏座敷」と詠んでいる。 |
||
 |
 |
|
| 黒門跡 | ||
 |
||
| 那珂川 | 三の丸跡 | |
 |
 |
|
| 真先寶壽両社稲荷神社 | ||
 |
||
| 本丸跡 | 本丸堀 | |
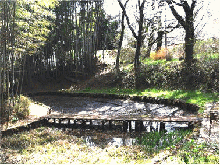 |
黒羽城は那珂川に沿って南北に延びた丘陵に築かれている。南北1.5kmにも及ぶ山城で、本丸の北に二の丸 / 南に三の丸 があった。本丸は黒羽城址公園 / 北城とも呼ばれる二の丸に黒羽体育館 / 三の丸は芭蕉公園 になっている。本丸は周囲を土塁が巡り、南には深い堀がある。黒羽城を築城したとき、城守稲荷として真先(まさき)稲荷神社を創建する。戦場の先駆けたらんことを祈願した神社で、後に寶壽(ほうじゅ)院の稲荷社を合祀して真先寶壽両社稲荷神社になった。 | |
| 池 | ||
| 黒羽城は天正4年(1576年)大関高増が築城した。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐とき、主家の那須資晴は小田原へ参陣しなかったために改易された。大関高増は大田原氏や芦野氏など那須衆と談合して参陣、所領を安堵された。廃藩置県により明治4年(1871年)廃城となった。 | ||
| ■元禄2年(1689年)4月16日 那須湯本に行くため余瀬から出立する。 余瀬(現:大田原市蛭田)は関街道・粟野宿があったところで、天正4年(1576)大関高増が白旗城からが黒羽城に移ってから寂れた。元禄2年(1689年)当時は、寂れたところになっていた。 この日は雨が降り始めたこともあり、高久の角左衛門家に2泊する。角左衛門は高久の名主であった。 |
||
高久の角左衛門邸-( |
||
 |
 |
 |
| 石塔群 | 永代常夜燈 | 旧奥州道中 練貫 |
|
栃木県大田原市市野沢 |
||
 |
 |
石塔群から10分足らずの左手に、明治天皇御駐輦紀念碑がある。さらに20分ほどすると、左手に馬頭観音がある。 |
| 馬頭観音 | 社 | |
 |
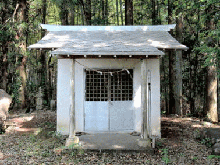 |
 |
| 不動堂 | 樋沢神社 | 葛籠石 |
| 社から15分足らずの左手に、不動堂 / 堂内に明暦2年(1656年)造立の不動明王 |
||
 |
 |
|
| 鍋掛愛宕峠 | 鍋掛一里塚 | |
 |
樋沢神社から5分ほどの左手に、鍋掛神社 / 鍋掛一里塚 がある。往時は鍋掛愛宕峠だったところで、現在は72号線から高い所に位置している。 |
|
| 鍋掛神社 | ||
| 鍋掛一里塚から5分足らずの鍋掛交差点を越えると鍋掛宿に入る。鍋掛宿は難所・那珂川対岸の越掘宿との合宿。川留めになると賑わったと云われている。鍋掛の地名は、川留めにより旅人が溢れ宿場住民が総出で鍋を出し炊き出しを行ったことに由来している。本陣:1 / 脇本陣:2 / 旅籠:23 だった。正保3年(1646年)以降は幕府天領になっている。 | ||
 |
鍋掛交差点から北西へ進む。 |
|
| 清川地蔵 | ||
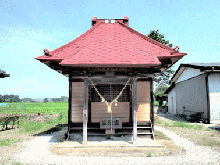 |
 |
 |
| 八坂神社 | 神号碑「初市神」 | 芭蕉句碑 |
| 鍋掛交差点から5分足らずの左手に八坂神社がある。境内に、神号碑「初市神」 / 文化5年(1808年)鍋掛宿の俳人により造立された「野を横に 馬牽きむけよ
ほとゝぎす」芭蕉句碑 がある。 |
||
 |
 |
隣接して明応年間(1492〜1500年)創建の正観寺がある。山門は鍋掛宿本陣の門と云われている。 |
| 正観寺山門 | 正観寺 | |
| 芭蕉は奥州街道・鍋掛宿から那須湯本に向かった。奥州街道を歩いたときは鍋掛交差点で区切り、黒磯駅に向かっている。芭蕉が那須湯本に向かった道だったかも知れない。 | ||
| ■元禄2年(1689年)4月19日 温泉神社に那須与一を偲び、殺生石(せっしょうせき)を訪ねる。 那須余一は、那須地方の豪族である那須太郎資隆の11男として生れた。11は10余り1から余一と名付けられ、後に与一に改名する。源義経の参陣のときに従い、騎下となって源平戦を戦った。元暦2年(1185年)の屋島の戦いでは、平氏方の軍船に掲げられた扇の的を射落とすなど功績を挙げた。源頼朝より20万石を与えられた。 |
||
 |
 |
 |
| 温泉神社鳥居 | 那須与一寄進の鳥居 | 温泉神社 |
| 温泉神社は延喜式神名帳に記載のある式内社で、那須与一が戦勝を祈願したことで知られている。文治2年(1186年)凱旋後に社殿 / 鳥居 を寄進、鏑矢
/ 蟇目矢 / 征矢 ./ 桧扇 を奉納した。 |
||
 |
||
| 殺生石園地遊歩道 | ||
 |
 |
 |
| 殺生石園地 | 殺生石残骸 / 殺生石標識 | 殺生石残骸 |
| 「石の香や 夏草赤く 露あつし」元禄2年(1689年)芭蕉が訪れてから333年後の2022年3月15日に殺生石(せっしょうせき)は割れて崩壊、残骸が空しく残る。 殺生石園地には、温泉神社社殿みぎてからも行ける。 |
||