| サグラダ・ファミリア | |
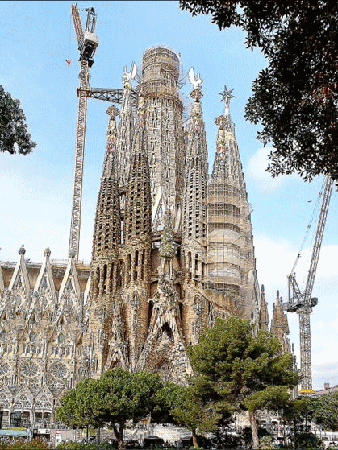 |
|
|
スペインのバルセロナにあるサグラダ・ファミリアの正式名称は、聖家族贖罪(せいかぞくしょくざい)教会である。サグラダ・ファミリア(Sagrada Familia)とは、スペイン語で「聖家族の聖堂」という意味になる。贖罪教会とは信者の寄付で建設する教会のこと。 |
|
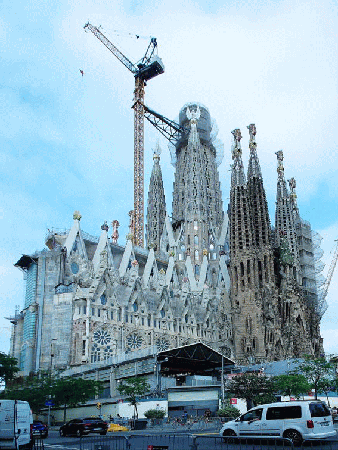 |
|
| アントニ・ガウディの死後の1936年に始まったスペイン内戦により、ガウディが残した設計図や模型 / ガウディの構想に基づき弟子たちが作成した資料のほとんど
が散逸した。 |
|
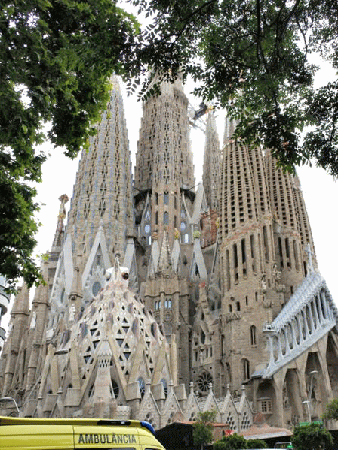 |
|
| 2005年にユネスコの世界文化遺産に登録された。 |
|
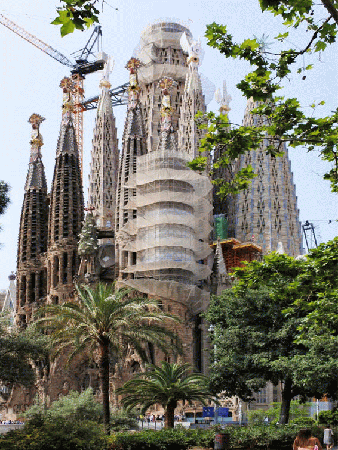 |
|
 |
|
| 西側の受難のファサード | |
| サグラダ・ファミリアを中心に周辺を2回徘徊するが、全体の調和が取れているとは到底思えない。イタリアやドイツで大聖堂を見ているが、いずれも調和が取れている。特に西側の受難のファサードなど、東側の生誕のファサードと比べるとアントニ・ガウディの設計とは思えない。 | |
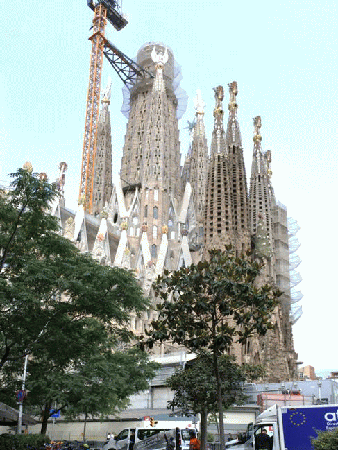 |
|
| さらに驚くべきことは、世界で唯一の建設途中の世界遺産となっていることである。スペインが観光地にするための政治力と、カトリック教会の思惑が見え隠れしている様に思える。 |
|
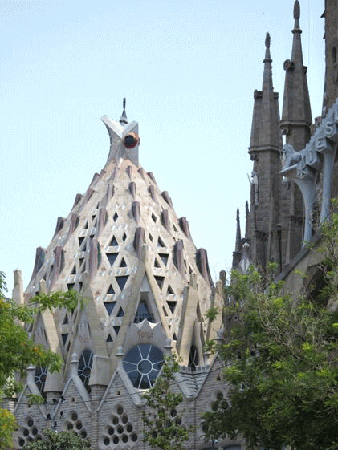 |
|
|
サン・ホセ教会の大聖堂であるので、祀るのは聖(サン)・ホセになる。しかしサグラダ・ファミリアの地下礼拝堂には、アントニ・ガウディの墓がある。 |
|
 |
|
| ツアー観光客 | |
 |
 |
| サグラダ・ファミリア周辺にあった電話用マンホール | |
 |
|
| サグラダ・ファミリア周辺にあったゴミ箱 | |