 |
|
| 郡上八幡の神社 |
|
 |
 |
 |
| 愛宕(あたご)神社 |
稲荷神社 |
岸剱(きしつるぎ)神社 |
| 慶長5年(1600年)創建 |
|
慶長19年(1614年)創建 |
| 郡上八幡駅から北へ進み、城南交差点を右折して256号線を東へ進む。枡形地蔵や乙姫トンネルを過ぎると、右手に見えてくる愛宕公園の西側にある。拝殿は急な階段の上にある。円通閣(慈思寺観音堂)
/ 遍照殿 / 五人塚 / 花鳥塚 / 宝暦義民碑 / 忠霊塔が点在する。 |
郡上市八幡町上桜町の山側にある。 |
山内一豊と妻の像から東へ進むと、岸剱神社と悟竹院がある。7月中旬から郡上踊りが開催されるが、7月28日には岸劔神社川祭が行われる。 |
|
|
郡上市八幡町柳町438 |
|
 |
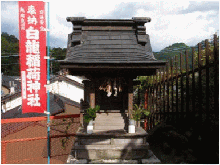 |
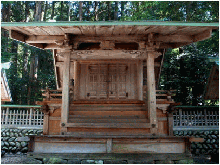 |
| 左京(さきょう)稲荷神社 |
白龍(しらたき)稲荷神社 |
神明(しんめい)神社 |
| 郡上八幡旧庁舎記念館の西を流れる乙姫川沿いに南へ進むと、右手に見えてくる。稲荷神社は金森左京家の屋敷にあったもの。金森家二代目藩主・金森可重の五男・重勝が初代金森左京家となる。郡上一揆により本家の郡上藩主・金森頼錦が改易となるが、金森左京家は旗本として幕末まで存続する。 |
吉田川に架かる宮ヶ瀬橋北側の岩山にある。疫病を鎮めるために創建され、神の使いである白蛇の修行場と云われている。祭礼は4月中旬の八幡まつりの時に行われる。 |
郡上八幡駅から327号線を北へ進む。城南交差点を直進して156号線をさらに北へ進む。郡上大橋を越え、五町交差点を右折する。T字路を左折して、Y字路を右へ進む。近くに楊柳寺がある。 |
|
 |
 |
 |
| 日吉(ひよし)神社 |
八坂(やさか)神社 |
八幡(はちまん)神社 |
| 天正年間(1573年~1591年)創建 |
明暦2年(1656年)創建 |
永禄2年(1559年)創建 |
| 郡上八幡駅から北へ進み、城南交差点を右折して256号線を東へ進む。枡形地蔵から日の出町の小道を東へ進むと、願蓮寺 / 日吉神社 / 最勝寺と続く。 |
浄因寺から北へ進み、中坪1丁目交差点を右折すると、右手に見えてくる。祀られている牛頭天王(ごずてんのう)は祇園精舎の守護神と云われている。疫病を撒き散らす怖い神であるが、親切に迎え入れた農民に対しては万病に効く術を授けたと云われている。医療技術が乏しかった時代は、疫病を防ぐ強い力を持つ牛頭天王信仰が広まっていった。7月中旬から郡上踊りが開催されるが、7月16日には八坂神社天王祭が行われる。 |
郡上八幡旧庁舎記念館から新橋を渡り右折、吉田川に沿って進むと左手にある。
主な行事
1月第4日曜日…天満宮祭
4月第3土曜日…八幡神社春祭
7月15日………若宮神明祭
8月25日………天満宮夏祭
水神風鎮祭 |
| 郡上市八幡町島谷683 |
|
|
|
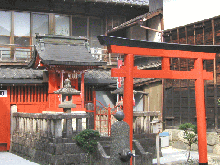 |
|
|
| 野中(やなか)稲荷神社 |
|
|
| 新町から“やなか水のこみち”を進むと右手にある。 |
|
|
|
| 郡上八幡の寺院 |
|
 |
 |
 |
| 安養寺(あんにょうじ) |
願蓮寺(がんれんじ) |
悟竹院(ごちくいん) |
| 遠郷山 / 真宗大谷派 |
竹林山 / 真宗大谷派 |
香厳山 / 曹洞宗 |
| 康元元年(1256年)創建 |
明応3年(1494年)創建 |
天文3年(1532年)創建。 |
| 郡上八幡旧庁舎記念館から吉田川に架かる新橋を渡り、左折して直ぐ右折すると。右手に見えてくる。天文8年(1539年)に郡上に移転、郡上御坊として栄える。明治14年(1881年)郡上八幡城三の丸跡に移転する。 |
郡上八幡駅から北へ進み、城南交差点を右折して256号線を東へ進む。枡形地蔵から日の出町の小道を東へ進むと、願蓮寺 / 日吉神社 / 最勝寺と続く。 |
山内一豊と妻の像から東へ進むと、岸剱神社と悟竹院がある。境内に威徳堂 / 豊川堂 / 太子堂 / 地蔵堂がある。 |
| 郡上市八幡町柳町217 |
郡上市八幡町島谷825 |
郡上市八幡町柳町410 |
|
 |
 |
 |
| 弘法堂 |
弘法堂 |
最勝寺(さいしょうじ) |
|
|
妙高山 / 浄土真宗本願寺派 |
|
|
寛永元年(1624年)創建 |
|
郡上八幡駅から北へ進み、城南交差点手前を右へ進む。5分足らずのところを右折して坂を登る。右手にある階段を登り道なりに進むと、左手の高台にある。
|
郡上八幡駅から北へ進み、城南交差点手前を右へ進む。256号線と合流する手前右手にある。 |
郡上八幡駅から北へ進み、城南交差点を右折して256号線を東へ進む。枡形地蔵から日の出町の小道を東へ進むと、願蓮寺 / 日吉神社 / 最勝寺と続く。 |
|
|
郡上市八幡町島谷672 |
|
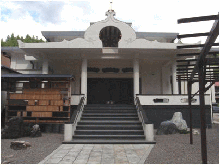 |
 |
 |
| 浄因寺(じょういんじ) |
慈恩禅寺(じおんじ) |
慈恩禅寺(じおんじ)円通閣 |
| 千躰山 / 真宗大谷派 |
鍾山 / 臨済宗妙心寺派 |
鍾山 / 臨済宗妙心寺派 |
|
慶長11年(1606年)創建 |
|
|
郡上八幡駅から北へ進み、城南交差点を右折して256号線を東へ進む。枡形地蔵から日の出町の小道を東へ進むと願蓮寺・日吉神社・最勝寺と続き、乙姫川を渡ると慈恩禅寺がある。荎草園(てつそうえん/有料施設)は室町様式の庭園である。花園天皇の御宸翰(ごしんかん/重文)がある。御宸翰とは天皇が自ら書いた文書のことである。
7月中旬から郡上踊りが開催されるが、30日には慈恩禅寺弁天祭が行われる。 |
飛地の愛宕公園の一角にある観音堂。郡上八幡駅から北へ進み、城南交差点を右折して256号線を東へ進む。枡形地蔵や乙姫トンネルを過ぎると、右手に見えてくる愛宕公園の東側にある。付近には愛宕の弘法堂と呼ばれている遍照殿、西側には愛宕神社がある。 |
| 郡上市八幡町殿町49 |
郡上市八幡町島谷339 |
|
|
 |
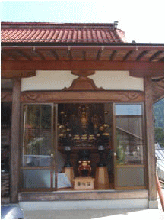 |
 |
| 善光寺(ぜんこうじ) |
善光寺(ぜんこうじ)およし稲荷 |
大乗寺(だいじょうじ) |
| 鞍馬山 / 天台宗 |
|
清水山 / 日蓮宗 |
|
|
慶長8年(1603年)創建 |
| 郡上八幡旧庁舎記念館から吉田川に架かる新橋を渡り、左折して直ぐ右折する。安養寺の手前を右折すると、郡上八幡城への坂の右手にある。白鳥町長滝にあった長滝寺の持善坊が明治30年(1897年)に移転。 |
郡上八幡城の石垣の崩壊を防ぐために人柱にされたと云われる“およし”を祀る。 |
古い町並みが残る職人町・鍛治屋町から小駄良川を大乗寺橋で渡る。尾壺城跡にあり、山門は享保4年(1719年)再建。 |
| 郡上市八幡町柳町370 |
郡上市八幡町柳町370 |
郡上市八幡町向山389 |
|
 |
 |
 |
| 長敬寺(ちょうきょうじ) |
洞泉寺(とうせんじ) |
遍照殿(へんしょうでん) |
| 光耀山 / 真宗大谷派 |
松峰山 / 浄土宗 |
愛宕山 / 真言宗 |
| 慶長6年(1601年)創建 |
|
|
| 古い町並みが残る職人町・鍛治屋町の突き当たりにある。八幡城主遠藤家の菩提所。 |
本町から小駄良川を洞泉寺橋で渡る。青山家の国元における菩提寺。7月中旬から郡上踊りが開催されるが、8月7日には洞泉寺弁天七夕祭が行われる。 |
郡上八幡駅から北へ進み、城南交差点を右折して256号線を東へ進む。枡形地蔵や乙姫トンネルを過ぎると、右手に見えてくる愛宕公園の東側にある。西側には愛宕神社、慈恩寺飛地には円通閣がある。愛宕の弘法堂と呼ばれている。 |
| 郡上市八幡町職人町742 |
郡上市八幡町尾崎町417 |
郡上市八幡町島谷102 |
|
 |
 |
|
| 楊柳寺(ようりゅうじ) |
蓮生寺(れんしょうじ) |
|
| 瑞宝山 / 曹洞宗 |
玉井山 /真宗大谷派 |
|
| 郡上八幡駅から327号線を北へ進む。城南交差点を直進して156号線をさらに北へ進む。郡上大橋を越え、五町交差点を右折する。T字路を左折して、Y字路を右へ進む。近くに神明神社がある。 |
古い町並みが残る職人町・鍛治屋町にある。 |
|
| 郡上市八幡町五町292 |
郡上市八幡町職人町739 |
|
|
| 郡上八幡の地蔵・庚申etc. |
|
 |
 |
 |
| 愛宕の地蔵 |
犬啼(いぬな)水神 |
延命地蔵 |
| 愛宕神社の鳥居の傍にある。 |
郡上八幡旧庁舎記念館前にある。7月中旬から郡上踊りが開催されるが、7月20日には犬啼水神祭が行われる。 |
洞泉寺と大乗寺の間にある。 |
|
 |
 |
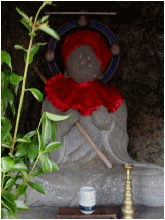 |
| 大滝観音 |
大滝不動 |
尾崎延命地蔵 |
| 大滝鍾乳洞入口近くにあった観音。 |
大滝鍾乳洞の大滝滝壷右手に刻まれている。 |
洞泉寺から南へ進む。道なりに西へ、吉田川沿いに156号線方面に進む。 |
|
 |
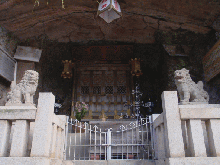 |
 |
| 小坂歩岐馬頭観音 |
神濃(しんのう)薬師 |
常盤電気地蔵 |
| 交通の難所であった小坂歩岐付近にあった観音が合祀されている。歩岐とは川に岩崖が落込んでいる地形。 |
郡上八幡旧庁舎記念館から吉田川に架かる新橋を渡り、左折すると直ぐ右手にある。7月第3土曜日が祭日。 |
八幡小学校端の常盤町にある。明治26年(1893年)に洪水で流されるが、八幡水力発電所の工事中に発見される。 |
|
 |
|
|
| 枡形(ますがた)地蔵 |
|
|
| 郡上八幡駅から北へ進み、城南交差点を右折して256号線を東へ進むと右手に見えてくる。城を防備するために、城下には見通しの悪い“枡形”や“鉤型”などを通りに配した。郡上八幡には城下町の出入口4ヶ所に見通しの悪い“枡形”が造られ、その1つの場所にあるのが桝形地蔵である。“桝形延命地蔵”“南無阿弥陀仏““南無妙法蓮華経碑”が合祀されている。8月24日に枡形地蔵祭が行われ、郡上踊りが奉納される。 |
|
|
|
| 郡上踊り |
 |
盆踊りは踊念仏が起源と云われている。平安時代に空也が始めたとされるが、定着したのは鎌倉時代からである。時宗の開祖である一遍は、生涯を諸国遊行で過ごし踊念仏を行なった。時宗は信心がなくとも等しく救われると説き、踊念仏により人々の心を捉え広まっていった。室町時代には、太鼓などを叩いて踊るようになったと云われている。盆踊りは村落社会において娯楽と村の結束を強める役割を果たす様になり、地域独特の音頭と踊り方が生まれた。郡上踊りは7月中旬から9月上旬まで開催されている。盆の4日間は徹夜踊りとなる。「郡上の八幡出てゆく時は、雨も降らぬに袖しぼる」と詠われる郡上踊りの始まりは定かでない。慶長5年(1600年)関が原の戦い後に郡上藩の藩主となった遠藤慶隆が、民心の融和を図るために盆踊りを城下で踊ることを奨励したのが始まりとも云われている。享保年間(1716年~1735年)飛騨国代官を務めた長谷川忠崇によって書かれた「飛州志」には、川崎の原歌と考えられる民謡が記載されていると云われる。古調川崎は、無形文化財に指定されている。明治に入って禁止令が出され途絶えたが、大正期に復活して続いている。 |
| |
| 大滝鍾乳洞 |
 |
郡上八幡近郊には大滝鍾乳洞と美山鍾乳洞があり、ともに2億年以上前にできた堅穴式鍾乳洞である。大滝鍾乳洞は東西270m / 南北40m / 深さ100m
/ 八層、美山鍾乳洞は東西160m / 南北130m / 深さ80m / 6層段の規模である。附近一帯の洞穴からはナウマン象 / ヘラ鹿 /
ヒョウ / 大角鹿などの化石が発見されている。大滝鍾乳洞の入口まではケーブルトロッコで登る。最深部にある落差30mの大滝は水量も豊富で圧巻だ。車で5分程のところに、縄文時代の住居跡が発見された縄文鍾乳洞がある。美山鍾乳洞は大滝鍾乳洞に比べると賑わいは劣る。交通の便が悪く、最寄りのバス停から徒歩30~40分は掛かる。夏季に郡上八幡駅から大滝鍾乳洞まで臨時バスが運行される。
[交通]郡上八幡駅-(タクシー/15分)-大滝鍾乳洞-(タクシー/20分)-美山鍾乳洞-(タクシー/20分)-郡上八幡駅 |
|
 |