| 営団地下鉄 |
|
| 日本の地下鉄は、昭和2年(1927年)東京地下鉄道によって浅草駅〜上野駅が開通したのが始まり。昭和9年(1934年)浅草駅〜新橋駅が全通した。新橋駅〜渋谷駅は、昭和14年(1939年)東京高速鉄道により全通した。昭和14年(1939年)から直通運転が始まり、昭和16年(1941年)帝都高速度交通営団(営団地下鉄)に譲渡された。 |
|
| 銀座線 |
|
 |
| 2085 |
|
|
銀座線の画像は、昭和43年(1968年)頃に赤坂見附駅で撮影している。ASA400のアグファ・イソパンウルトラで撮影したもの。ASAは現在ISO表記に変更されている。コダック・トライXより諧調が出ると、同級生から譲り受ける。長尺巻を裁断したフィルムで、40枚以上撮れる筈と云われる。ハーフサイズのPEN-Fでは80枚以上になる。フィルムは巻き上げて使用するが、上巻きスペースに限界がある。80枚手前で巻き取れなくなり、パトローネに撮影できるフィルムを残して終わる。露出計を買えない時期でもあり、使えない画像が多い。
|
|
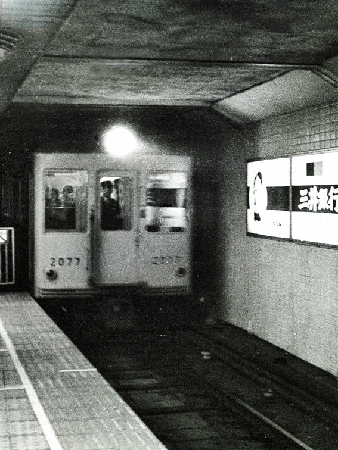 |
| 2077 |
|
|
2000形は、昭和34年(1959年)から製造された車両。昭和43年(1968年)頃は新型車両で、先頭の車両で運用されていた。
|
|
 |
| 100形 |
|
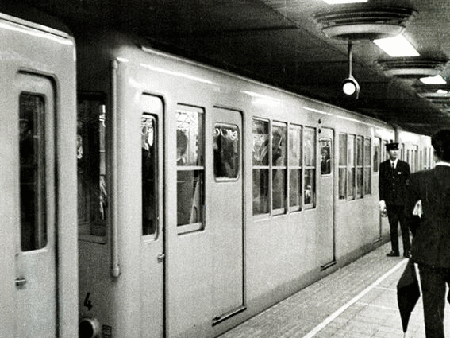 |
|
|
東京地下鉄道開業時に運用の1000形 / 東京高速鉄道開業時に運用の100形 も中間に組み込まれて運用されていた。100形はリベット接合の鋼製車であった。当時は駅や分岐の前後にデッドセクションが存在、室内灯が消えて非常灯が点灯した。
|
|
| 丸の内線 |
|
 |
| 687 / 中野坂上駅 |
|
| 昭和29年(1954年)池袋駅〜御茶ノ水駅が開通、昭和37年(1962年)荻窪駅まで全通した。中野坂上駅から分岐する方南町支線も開通、途中に中野車両基地がある。池袋駅〜東京駅〜新宿駅は山手線内、新宿駅〜荻窪駅は青梅街道を通る路線。 |
|
 |
| 653 / 茗荷谷駅付近 |
|
| 茗荷谷駅〜後楽園駅は地上に線路が敷設され、茗荷谷を埋め立てた車両基地(現:小石川車両基地)があった。台地に都電が見える。 |
|
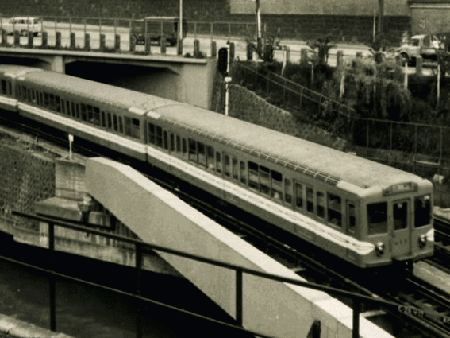 |
| 聖橋からの神田川を越える丸ノ内線。 |
|
 |
| 109 / 中野坂上駅 |
|
| 昭和37年(1962年)開通した方南町支線。当時の方南町支線は、 東京高速鉄道開業時の100形が、2両編成で使用されていた。リベット接合の鋼製車で、塗装は本線と同様に赤に白帯になったが装飾はなかった。銀座線の車両ではドアとホームの間に隙間が開くため、ドアにテップが設置されていた。当時の地下鉄は冷房されていなかったが、暑く感じることはなかった。方南町支線に乗車すると、夏でも涼しくすら感じた。 |
|
| 中野車両基地 |
|
 |
|
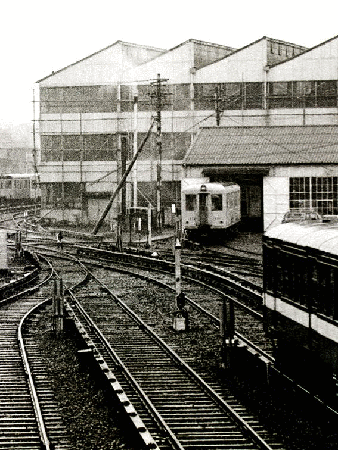 |
|
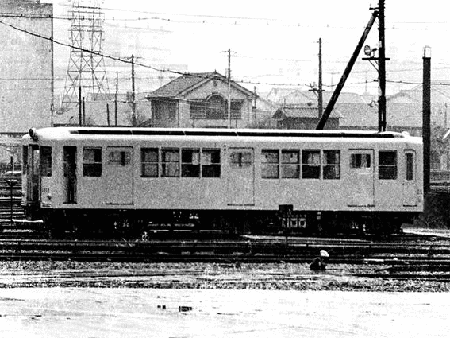 |
|
|
南町支線の途中に中野車両基地があり、銀座線車両も見かけられた。
|
|
 |