| 日光例幣使街道・静和駅-(約10km)-栃木駅 |
|
 |
東武日光線・静和駅より西へ道なりに進む。5分ほどすると静和交差点で36号線に合流する。すぐの岩船和泉郵便局の先を右折して、日光例幣使街道を北へ進む。5分ほどすると、左手に和泉天満宮がある。 |
| 和泉天満宮 |
|
 |
左折して和泉天満宮境内沿いに北へ進む。5分ほどの11号線を越え、斜めに弧を描く様に進む。10分ほどすると11号線と斜めに交差、コンビニ南側の道を進む。5分足らずの左手に「例幣使街道」標識があり左折する。 |
| 例幣使街道標識 |
|
| すぐに右手からの道と合流する辺りに、富田宿の木戸が設けられていたと云われている。 |
|
|
富田宿
日光例幣使街道が整備される前から存在した宿場。正保3年(1646年)幕府から正式に伝馬宿として指定された。12町12間の長い宿場通りであった。飯盛り女が置かれ、富田女郎衆として知られていた。往時の面影はほとんど残っていない。本陣:1
/ 旅籠:28 があった。
|
|
 |
 |
 |
| 馬頭観音 |
勝善碑 |
馬頭観音 |
|
 |
「例幣使街道」標識から5分足らずの左手に馬頭観音 / すぐ左手に勝善碑 / すぐ左手に馬頭観音 / すぐ左手に玉正寺看板 / すぐ左手に軍馬観音
と続く。玉正寺の境内は11号線を越えたところにある。
|
| 軍馬観音 |
|
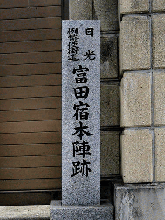 |
軍馬観音からすぐの富田交差点を左折すると、すぐ右手に「富田宿本陣跡」石柱がある。
|
| 富田宿本陣跡 |
|
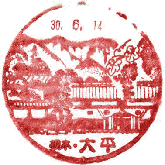 |
富田交差点まで戻り北へ進む。すぐの十字路を左折すると、すぐ右手に大平郵便局がある。風景印は、大平山 / 郷土資料館・戸長屋敷 / 葡萄 の図柄になっている。
|
| 大平郵便局風景印 |
|
 |
 |
十字路まで戻り北へ進む。すぐ左手に八坂神社がある。永享年間(1429年〜1440年)に築城された富田城内に牛頭天王社と創建され、寛永17年(1640年)に現在地に移された。
|
| 町並み |
八坂神社 |
|
|
|
| 「寄り道」富田城跡 |
|
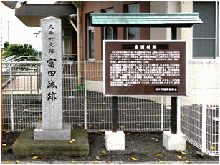 |
八坂神社からすぐの交差点を左折して西へ進むと、すぐに冨田バイパスと交差する。越えるとすぐ左手の大平西小学校門横に富田城跡石柱 / 案内板 がある。大平西小学校付近一帯が富田城跡で、東西400m / 南北500m の城域であった。
嘉吉元年(1441年)富田成忠によって築かれたと云われている。富田氏は皆川氏の一族であるが、弘治3年(1557年)富田信吉は皆川俊宗に攻められ落城する。富田信吉の父・富田秀利が佐野氏と結んだ為と言われている。以後、富田城は皆川氏の支城となった。 |
| 富田城跡石柱 / 案内板 |
|
|
天正18年(1590年)皆川城は豊臣秀吉の軍勢によって落城する。天正19年(1591年)〜慶長2年(1597年)富田秀重が富田城主であった。慶長18年(1613年)北条氏重が下総国岩富より1万石で移封、富田城跡に陣屋を構える。北条氏重は、小田原北条氏の一門・北条綱成の孫・氏勝の養子となった人物。元和5年(1619年)遠江久野に移封となり、富田陣屋も廃された。
|
|
|
|
 |
 |
 |
| 旧早乙女醫院 |
旧大平下病院 |
旅籠・島田屋跡 |
|
|
交差点まで戻り、日光例幣使街道を北へ進む。すぐ左手に旧早乙女醫院 / すぐ左手に旧大平下病院 / すぐ右手に旅籠・島田屋跡 と続く。
|
|
 |
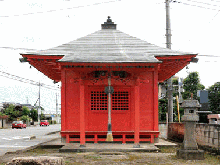 |
旅籠・島田屋跡からすぐの交差点手前右手に、永正2年(1505年)創建の宗光寺がある。この辺りで富田宿が終わる。
|
| 宗光寺本堂 |
宗光寺地蔵堂 |
|
 |
宗光寺から5分ほどの左手に樋下稲荷神社がある。 |
| 樋下稲荷神社 |
|
 |
 |
樋下稲荷神社からすぐに11号線に合流する。すぐに右方向に進むと、すぐ左手に大日如来 / 上部が欠落している文政2年(1819年)造立の常夜燈
がある。
|
| 大日如来 |
常夜燈 |
|
 |
この辺りからは耕地になって、日光例幣使街道は途絶えている。現在は住宅街となり道があるが、往時の日光例幣使街道ではない。道なりにのんびり15分ほどすると、11号線に合流する。11号線を横断、左斜め方向に進む。交通量が多く、南側にある交差点から迂回する。左斜め方向に進むと、すぐに永野川に架かる永久橋を渡る。
|
| 永久橋 |
|
 |
永久橋を渡った辺りからの日光例幣使街道は、永野川に沿っていたと云われている。土手道を10分ほど進むと、川連交差点を渡る手前右角に天正年間(1573年〜1592年)創建の川連天満宮がある。
|
| 川連天満宮 |
|
|
この辺りは広大な城域の川連城南端となる。応仁年間(1467年〜1469年)川連仲利によって築かれたと云われている。川連城は皆川氏と佐野氏の領地が接するところにあり、争奪戦が繰り広げられている。永禄6年(1563年)皆川俊宗に攻められ皆川城の支城となる。天正6年(1578年)佐野氏家臣・平野久国に攻められ、粟野城の支城となる。天正16年(1588年)皆川氏に攻められ粟野城が落城、川連城は再び皆川氏の支配下となる。天正18年(1590年)小田原征伐のとき、皆川広照は小田原城に篭城する。皆川城は上杉景勝に攻められ落城する。皆川広照は小田原城包囲直後に脱出、徳川家康の取り成しによって所領を安堵される。天正19年(1591年)皆川広照は本拠を栃木城に移し、皆川城とともに川連城も廃城となる。
|
|
 |
 |
川連交差点で11号線を越え、東に進む。5分ほどの栃木翔南高校入口交差点を左折する。10分ほどすると、JR両毛線を潜る。すぐの交差点を越えると、すぐに突き当たる。左折すると31号線に突き当たり、蔵の遊歩道標識 / 蔵の遊歩道案内板
がある。
|
| 町並み |
蔵の遊歩道標識 |
|
| [寄り道]栃木蔵の街 |
|
  |
| 巴波川 / 白壁土蔵 |
|
 |
蔵の遊歩道標識から左に進む。道なりに巴波川(うずまがわ)沿いに北へ進む。船頭の舟歌が聞こえてくると、蔵の街遊覧船がやってきた。江戸川に通じる巴波川は、舟運の盛んだった。物資の集散地として、往時の蔵造り建造物が多く残っている。徳川家康の霊柩を久能山から日光山に改葬したとき、日光御用の荷物を陸揚げしている。 |
| マンホール |
|
 |
 |
蔵の遊歩道標識まで戻り、31号線を東へ進む。すぐに「日光例幣使街道」標柱があり、例幣使街道は左折して北へ進む。左折せずに直進、すぐの境町交差点を右折する。すぐも突き当りにJR両毛線 / 東武日光線・栃木駅がある。
|
| 蔵の遊歩道標識 |
日光例幣使街道標柱 |
|
 |
JR両毛線・栃木駅と東武日光線・栃木駅は、隣り合わせにある。東武日光線・栃木駅ホームで列車を待っていると、JR253系1000番台車両の「きぬがわ4号」新宿行が到着する。解っていても奇妙な感じがする。栃木駅-(東武鉄道)-北千住駅-(JR常磐線)-日暮里駅-(JR山手線)-池袋駅で帰宅する。
|
| きぬがわ4号 |
|
 |