| 日光例幣使街道・八木宿-(約15km)-天明宿 |
|
 |
 |
東武伊勢崎線福居駅から線路沿いに南に進む。すぐに左折して東武伊勢崎線の踏切を越え、128号線を南東へ進む。5分ほどすると、左手の公園に地蔵 / 背後に石仏石塔群 がある。
|
| 地蔵 |
石仏石塔群 |
|
 |
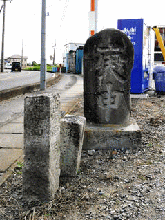 |
5分ほどすると、Y字路がある。三角地帯に「東 梁田ヲヘテ 佐野方面ニ到ル」道標 / 庚申塔 がある。日光例幣使街道は左方向に進む。 |
| Y字路 |
道標 / 庚申塔 |
|
 |
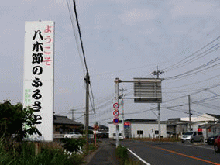 |
Y字路から5分足らずの右手に、常夜燈が数基並んでいる。すぐ右手に、八木宿入口近くにあったのと同じ「ようこそ 八木節のふるさとへ」看板がある。画像は逆方向から撮影したもの。
|
| 常夜燈 |
街道寸景 |
|
 |
看板からすぐに上渋垂町交差点を越える。10分足らずの梁田町交差点を越えると、左手に南国ムードが漂う情景がある。
|
| 南国ムードが漂う情景 |
|
 |
梁田町交差点から5分余りのT字路を左折すると、梁田宿に入る。事前にチェックした目印のコンビニは、更地になっていた。
|
| 町並み |
|
|
梁田宿
渡良瀬川の渡しがあった宿場。八木宿同様、飯盛女が置かれていた。慶応4年(1868年)新政府軍と幕府軍が戦った梁田戦争(梁田の役)があったところである。東武鉄道敷設の折に反対したため、衰退した。本陣:2 / 旅籠:32 があった。静かな町並みになっている。
|
|
 |
 |
梁田宿に入るとすぐ左手に、道路標識が邪魔をして正面から撮影できない「旧日光例幣使街道梁田宿」石柱がある。左折すると長福寺がある。
|
| 旧日光例幣使街道梁田宿石柱 |
長福寺 |
|
 |
すぐに渡良瀬川に突き当たり、宿場は終わる。渡良瀬川の渡しは、この辺りから右斜め方向への渡船だった。
|
| 渡良瀬川河川敷 |
|
 |
 |
 |
| 渡良瀬川 |
川崎天満宮 |
|
|
ここからは迂回路になる。右折して渡良瀬川の土手を進む。10分足らずで渡良瀬川に架かる川崎橋を渡る。5分ほどで川崎橋橋を渡り切り、すぐに左折して土手道を進む。 すぐに3本の道が交わるところ辺りが対岸だった様である。鋭角に右折して逆方向に土手道を下ると、すぐ左手に川崎天満宮 / 境内に案内板 がある。例幣使は必ず立ち寄って参拝した / 例幣使の残した短冊3枚が残されている ことなどが記載されている。
|
|
 |
 |
 |
| 地蔵 / 不動明王 |
石仏石塔群 |
庚申塔 |
|
|
川崎天満宮から東へ進むと、すぐに川崎橋から延びる道を潜る。5分足らずで渡良瀬川の土手が近くなるところがあり、その先を左折する。すぐの変則十字路の正面に、地蔵 / 不動明王 がある。右折すると、すぐ右手の公民館脇に石仏石塔群がある。道なりに進むと、すぐ左手に庚申塔がある。
|
|
|
すぐの十字路を右折する。すぐに工場に突き当たり、日光例幣使街道は途絶える。 ここからは迂回路になり、左折して北へ進むと128号線と交差する。左折して128号線を東に進む。5分足らずの交差点を過ぎると、左方向に曲がるところがある。この辺りから日光例幣使街道が復活している様である。
|
|
 |
15分ほどの出流川を渡り、交差点を左折する。10分足らずの右手に「寺岡山 厄除元三大師」看板がある。さらに参道入口の看板があり、右折する。すぐの十字路を左折して北へ進む。
|
| 十字路から北に進む道 |
|
 |
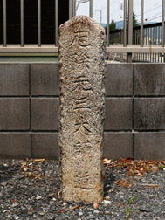 |
十字路から5分ほどすると、67号線に突き当たる。手前左手に、道標2基 / 「厄除元三大師道」道標 がある。左側は元文5年(1740年)造立で、正面に「佐野道」
右側面に「足利道」 左側面に「太田道」と彫られている。右側は寛政3年(1791年)造立で、正面に「日光道 道祖神 佐野道」 左側面に「江戸道
館林道」と彫られている。
|
| 道標 |
「厄除元三大師道」道標 |
|
 |
右折して67号線を東へ進む。と、すぐ左手に両社神社がある。
|
| 両社神社 |
|
 |
 |
両社神社から5分足らずの白旗橋の手前を左折する。すぐに旗川に突き当たる。往時はここが渡河地点であった。
|
| 街道寸景 |
古民家 |
|
 |
67号線に戻り、旗川に架かる白旗橋を渡る。足利市から佐野市へ入る。 |
| 旗川 |
|
 |
すぐの交差点を左折、すぐの十字路を右折するのが日光例幣使街道になる。十字路の西方向が渡河の対岸になる。
|
| 町並み |
|
 |
 |
 |
| 芦畦の獅子舞収蔵庫 |
古民家 |
常夜灯 |
|
 |
 |
十字路から5分ほどのY字路は道なりに左へ進む。すぐに斜めに合流、両毛線の踏切を渡り斜め右方向に進む。 すぐ左手に「芦畦の獅子舞」の収蔵庫と案内板がある。約700年も前に始まったという獅子舞で、三頭の獅子が町内を練り歩くと云う。すぐ左手に柵で囲われた常夜燈
/ すぐ左手に「日光例幣使街道」石柱 と続く。
|
| 町並み |
日光例幣使街道石柱 |
|
 |
 |
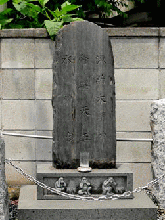 |
| 古民家 |
地蔵 / 日光例幣使街道石柱 |
神号碑 |
|
|
5分ほどすると両毛線の「第一足利街道踏切」を越え、斜め右方向に進む。5分ほどすると、街道歩きには不親切な大橋町歩道橋を越える。5分ほどすると、左手の石材店に地蔵と「日光例幣使街道」石柱が並んでいる。すぐに秋山川に突き当たる手前左手に「水神宮 帝釈天王 諏訪大明神」と彫られた神号碑があり、台座には三猿が彫られている。往時は猿橋が架かっていた。
|
|
|
右折してすぐの中橋を渡る。すぐに左折すると、往時は猿橋が架かっていた対岸になる。T字路を右折すると、すぐに突き当たる。日光例幣使街道はここを左折して北へ進む。
|
|
| [寄り道]惣宗寺(佐野厄除け大師) |
|
 |
 |
突き当りを右折して南へ進む。すぐ右手に神明宮がある。中橋から延びる交差点を越えると、すぐ右手に涅槃寺日限地蔵堂がある。日限地蔵は人の形をした地蔵で、天和2年(1682年)江戸・松秀寺より勧請した。日を決めて願をかければ叶うと云われている。 |
| 神明宮 |
涅槃寺日限地蔵堂 |
|
 |
 |
すぐの交差点左方向に、天慶7年(944年)藤原秀郷が春日岡に創建したのが始まりと云われる惣宗寺(佐野厄除け大師)がある。慶長7年(1602年)佐野信吉が春日岡に佐野城を築くため、現在地に移転する。厄除け大師は、平安時代の僧・良源(りょうげん)のことである。慈恵大師(じえだいし)としても知られるが、通称の元三大師(がんざんだいし)の名で知られる。境内に東照宮がある。徳川家康の遺体を久能山から運ぶ途中、天明宿に2泊したため文政11年(1828)に造営された。久々であるが、混雑している正月にしか訪問していなかった。山門は佐野城城門を移築したもの。 |
| 惣宗寺山門 |
惣宗寺本堂 |
|
 |
 |
| 東照宮 |
|
 |
惣宗寺(佐野厄除け大師)の東に隣接して、大永年間(1521年〜1528年)創建と云われる観音寺がある。
|
| 観音寺 |
|
| 道を戻り、日光例幣使街道を北へ進む。すぐ67号線と交差、右折して67号線を東へ進む。すぐに天明(てんみょう)宿に入る。 |
|
|
天明宿
天明宿は佐野市の中心部に位置している。平安時代の延長5年(927年)藤原秀郷によって唐沢山城が築城され、天明の集落が形成された。天慶2年(939年)藤原秀郷が連れてきた鋳物師(いもじ)によって鋳物産業が発展、茶の湯の流行などでその名を京都にまで知られた。藤原秀郷の子孫は佐野周辺を領して佐野氏を称した。慶長4年(1599年)江戸20里四方の山城法度による禁令により、唐沢山城は廃城となる。慶長7年(1602年)佐野信吉によって、佐野駅の北側にある丘陵に佐野城が築城される。この頃には、既に東山道の宿駅になっていたと云われている。佐野信吉によって整備された町並みは、例幣使街道の開通により宿場町としても発展した。例幣使一行は天明宿泊まりを習わしとしていた。本陣:1 / 旅籠:8
と、宿場の規模として旅籠数は少ない。
|
|
 |
 |
 |
| 古商家 |
星宮神社鳥居 |
星宮神社社殿 |
|
| すぐ左手に星宮神社の参道がある。予定していた行程の終着が近くなると、迷う距離である。さらに鳥居を潜ると、登るか迷う石段がある。銅造鳥居は享保20年(1735年)の建立で、鋳物師棟梁大工職刻銘がある。社殿は天和3年(1683年)に再建されたもの。 |
|
 |
 |
67号線まで戻り東に進む。すぐに本町交差点を越える。5分足らずの佐野駅入口交差点の手前左手の群馬銀行の辺りに本陣があった。佐野駅入口交差点を左折する。5分足らずの突き当りに、JR両毛線 / 東武佐野線・佐野駅がある。
|
| 古商家(2010年9月撮影) |
古商家 |
|
| [寄り道]佐野城 |
|
 |
 |
 |
| 史跡 佐野城址 石柱 |
本丸跡 |
埋め戻された石畳と石垣 |
|
|
佐野駅北側の城山公園にある平山城。佐野氏は延長5年(927年)藤原秀郷によって築城されたと云われる唐沢山城を居城としていたが、江戸20里四方の山城法度による禁令により廃城となる。惣宗寺(佐野厄除大師)を移転させ、慶長7年(1602年)佐野信吉によって築城される。慶長19年(1614年)佐野信吉は改易となり、廃城となる。曲輪
/ 堀切 / 土塁 が残る。本丸虎口の石垣と石畳が発掘されるが、保存のため埋め戻されている。 城門が惣宗寺(佐野厄除大師)山門としてとして移築され現存する。 |
|
 |