| 日光例幣使街道・倉賀野宿-(約21km)-境宿 |
|
 |
 |
倉賀野駅南口から、Y字路を左へ173号線を南へ進む。5分足らずで121号に突き当たり、中町交差点を左折して旧中山道を東へ進む。中町交差点〜下町交差点は、旧中山道で歩いた道のり。中町交差点から5分足らずの下町交差点は、旧中山道と例幣使街道の追分である。 |
| 町並み |
追分 |
|
 |
 |
 |
| 閻魔堂 |
道標 |
常夜燈 |
|
 |
三角地帯に、閻魔堂 / 道標 / 文化11年(1814年)造立の常夜燈 / 石仏石塔群 がある。閻魔堂は新しくなっている。道標は正面に「是従
右 江戸道 左 日光道」 裏面に「南無阿弥陀仏 亀湧水書」と彫られている。常夜燈は正面に「日光道”」 右側面に「中山道」 左側面に「常夜燈」と彫られている。閻魔堂の日光例幣使街道側の石仏石塔群は、旧中山道のときに見逃している。 |
| 石仏石塔群 |
|
 |
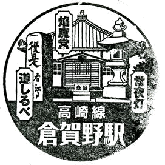 |
「参考」2011年6月に撮影した閻魔堂。
JR高崎線・倉賀野駅のスタンプは、この場所をイメージしたもの。
|
| 閻魔堂(2011年6月撮影) |
倉賀野駅スタンプ |
|
 |
 |
例幣使街道を北東へ進む。5分足らずでJR高崎線の踏切を渡る。交直両用を直流に改造した JR特急列車651系1000番台車が通り過ぎる。5分ほどすると、金属工業団地交差点がある。すぐに例幣使街道標識がある。さらに5分足らずのところにも同じ標識がある。 |
| 特急列車651系1000番台車 |
例幣使街道標識 |
|
 |
街道沿いは工場地帯で、大型トラックの往来が多い。コンテナを搭載したトラックが通ると、落下してこないかと恐怖を感じる。金属工業団地交差点から10分ほどすると、綿貫町南交差点で13号線と交差する。綿貫町南交差点からすぐの十字路左手手前に、不明の台座
/ 道標らしき石柱 がある。すぐに高崎量子応用研究所の敷地に突き当たり、例幣使街道は途切れる。 |
| 不明の台座 / 道標らしき石柱 |
|
 |
 |
綿貫町南交差点まで戻り、迂回する。13号線を北へ進み、すぐの綿貫町交差点を右折して東へ進む。5分ほどすると、左手に不動山古墳 / 古墳の上に不動堂
がある。 何処で例幣使街道が復活しているのか、よく解らない。 |
| 不動山古墳 |
不動堂 |
|
 |
不動山古墳から10分足らずで、井野川に架かる鎌倉橋を渡る。往時は土橋で30mほど下流に架けられていたと云われている。 |
| 井野川 |
|
 |
 |
鎌倉橋を渡り10分ほどすると、関越自動車道を潜る。さらに10分足らずで玉村宿に入り、すぐ左手に萬福寺 / 隣接して稲荷神社 がある。
|
| 萬福寺 |
稲荷神社 |
|
| 玉村宿は慶長10年(1605年)から代官・伊奈忠次によって新田が開発され、付近の住民を移した。寛永13年(1636年)日光東照宮が整備され、街道一の宿場町になった。本陣:1
/ 旅籠:36 があった。慶応4年(1868年)の大火で、往時の面影はあまり残っていない。 例幣使は毎年京都を旧暦4月1日に出発、4月11日に倉賀野宿を通過して玉村宿に宿泊した。翌日に、次の宿泊地である天明(てんみょう)宿を目指して出発した。4月15日に日光に到着している。 |
|
 |
稲荷神社から10分足らずの左手に、造り酒屋・泉屋がある。問屋場だったところで、慶応4年(1868年)の大火を免れた建物が残る。 |
| 造り酒屋・泉屋 |
|
 |
 |
 |
| 玉村八幡神社鳥居 |
玉村八幡神社随神門 |
玉村八幡神社拝殿 |
|
 |
造り酒屋・泉屋からすぐ左手に、建久4年(1193年)鶴岡八幡宮を勧請して角渕に創建したのが始まりの玉村八幡神社がある。江戸時代初めに代官・伊奈忠次によって現在地に移転したと云われている。随神門は慶応元年(1865年)建立
/ 拝殿は18世紀末頃の建立 / 永正4年(1507年)建立の本殿は重文。境内に、人形神社 / 加恵瑠神社 がある。玉村八幡神社駐車場に、玉村宿散策マップがある。
|
|
人形神社 / 加恵瑠神社
|
|
 |
すぐに例幣使道玉村宿交差点がある。すぐの交差点の南西側にある町田酒造は、以前は煉瓦造りだったと云われている。 |
| 町田酒造 |
|
 |
交差点に木島本陣跡歌碑標識があり左折する。すぐの玉村町商工会館前に標識があり右折すると、すぐ右手に木島本陣跡歌碑がある。本陣の建物は慶応4年(1868年)の大火で焼失している。天保14年(1843年)に帰路も中山道を利用した例幣使・参議有長の歌碑がある。
|
| 木島本陣跡歌碑 |
|
 |
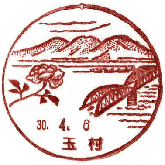 |
交差点まで戻り、例幣使街道を東に進む。10分足らずの下新田交差点を越えた左手に、玉村郵便局がある。風景印は、赤城山 / 利根川 / 町の花・薔薇 / 福島橋 の図柄になっている。
|
| 町並み |
玉村郵便局風景印 |
|
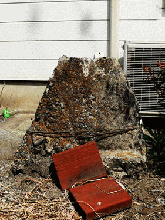 |
 |
 |
| 不明の石塔 |
石仏石塔群 |
毘沙門堂の石灯篭 |
|
|
玉村郵便局から5分ほどの左手に、上部が欠けた不明の石塔がある。すぐ左手に九丁目住民センター看板があり、石仏石塔群がある。鎖で囲われている「玉村町新田9丁目毘沙門堂の石灯篭」は、日光例幣使道の目印として置かれていたと云う。
|
|
 |
 |
 |
| 日露戦役紀念碑 |
日清戦役紀念碑 |
聖蹟記念碑 |
|
|
石仏石塔群からすぐの上飯島交差点付近に下木戸があったと云われ、玉村宿は終わる。40分ほどすると、旧例幣使街道は左方向に進む。左手に、日露戦役紀念碑 / 日清戦役紀念碑 / 聖蹟記念碑 がある。
|
|
 |
 |
 |
| 常楽寺山門 |
常楽寺本堂 |
町並み |
|
|
10分ほどの五料交差点手前左手に、千代寿丸が柴渡船転覆により溺死した「千代寿丸伝説」ゆかりの常楽寺がある。五料交差点を越えると、五料宿に入る。
|
|
|
慶長6年(1601年)関所が設けられ、数軒の旅籠ができて五料宿が整備された。天明3年(1783年)浅間山噴火で大被害を受け、関所の復旧のときに街道が付け替えられている。地名の由来は、朝廷の御料 / 千代寿丸伝説の御霊信仰 などと云われている。
|
|
 |
宿場通りは、すぐに利根川に突き当たる。利根川の渡しは少し下流にあった。鋭角に左折して、すぐに右折して利根川に架かる五料橋を渡る。 |
| 利根川 |
|
 |
 |
五料橋から10分足らずの芝町交差点を越えると、すぐに柴宿の町並みになる。すぐ右手の柴町住民センター前に案内地図 / すぐ右手に柴宿本陣門 がある。 |
| 柴宿の町並み |
柴宿本陣門 |
|
|
柴宿は利根川の対岸にあった宿場で、規模は小さかった。中町と堀口が加宿となっており、合わせるとかなりの規模になっていた。本陣:1 / 脇本陣:1 / 旅籠:17 があった。天明3年(1783年)浅間山噴火までは、中町の雷電神社へ直線的に延びていた。例幣使は柴宿本陣で休憩することが慣わしとなっていた。
|
|
 |
 |
 |
| 雷電神社 |
曰くがありそうな門 |
満善寺仁王門 |
|
 |
柴宿本陣門からすぐの交差点を越え、すぐに右折して小川沿いの道を南に進む。5分足らずで142号線に合流、右手に雷電神社がある。雷電神社から道は東に進路を変える。すぐ右手に、曰くがありそうな門がある。5分ほどの左手に、勝道上人によって創建されたと云われる満善寺がある。
|
| 満善寺本堂 |
|
 |
 |
満善寺から10分足らずの左手に、昌雲寺がある。さらに10分足らずで韮川に架かる道満橋を渡ると、旧日光例幣使道標識がある。
|
| 昌雲寺 |
旧日光例幣使道標識 |
|
 |
 |
旧日光例幣使道標識から10分ほどすると、豊武神社 / 左手の大正寺公民館敷地に石仏石塔群 と続く。 |
| 豊武神社 |
石仏石塔群 |
|
 |
 |
石仏石塔群から10分足らずの右手に「伊勢崎織物 大絣発祥の地」碑がある。伊勢崎市は桐生市と並ぶ絹織物生産地だった。すぐ左手に「遺跡 三ツ橋」石柱 / 庚申塔の祠 がある。建仁2年(1202年)栄朝禅師が三ツ橋を通り掛ったとき、麻疹(はしか)により苦しむ子供に出会う。経文を唱えると、たちまち麻疹が直ってしまった逸話。
|
| 伊勢崎織物 大絣発祥の地碑 |
遺跡 三ツ橋 |
|
 |
 |
 |
| 飯玉神社 |
延命寺 |
石仏石塔群 |
|
|
「遺跡 三ツ橋」から5分ほどすると、左手に飯玉神社 /
隣接して延命寺 がある。延命寺は例幣使の御小休所であった。5分ほどすると、右手に石仏石塔群がある。
|
|
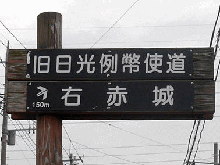 |
 |
 |
| 旧日光例幣使道標識 |
旧日光例幣使道標識 |
右赤城案内板 |
|
 |
 |
 |
| 旧日光例幣使道標識 |
不明の石柱 |
道標 |
|
|
石仏石塔群から10分ほどすると、旧日光例幣使道標識があり右折する。道路にも描かれている。すぐ右手に、右赤城案内板がある。これまで左に見えていた赤城山が右後方に見えるところであるが、見えなかった。すぐのY字路にも道路に標識が描かれており、左方向に進む。5分足らずで296号に突き当たるが、手前左手の空き地に不明の石柱がある。突き当たる296号を左折するところに、「右
五りょう 東 日光道 左 ほんじやう」と彫られている道標がある。文字は摩滅して判読できない。
|
|
 |
すぐの下蓮町交差点を直進、142号線を北東に進む。 10分足らずで、142号線は大きく右に曲がる。旧日光例幣使街道は直進する。5分足らずで広瀬川に突き当たり、道なりに右方向に進む。すぐ左手に、竹石の渡し案内板 / 案内地図 がある。竹石の渡しは武士橋の50m程上流いあった。
|
| 竹石の渡し案内板 |
|
 |
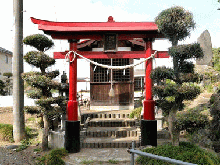 |
 |
| 広瀬川 |
稲荷社 |
御嶽山座王大権現 |
|
|
すぐに142号線に突き当たり、武士橋西詰交差点を左折して広瀬川に架かる武士橋を渡る。すぐの交差点を左折、さらに右折して復活した旧例幣使街道を北東に進む。すぐ右手に、乳母の懐案内板がある。輿に揺られ居眠りした勅使が起こされたとき、「乳母の懐に抱かれていたようじゃのう」と言ったこと
/ 実際の場所は境萩原だったこと が書かれている。すぐ左手に稲荷社 / 八海山と呼ばれる築山に御嶽山座王大権現 がある。高札場があったところで、日光例幣使街道の一里塚であったとも云われている。
|
|
 |
 |
5分ほどすると142号線に合流する。三角地帯に、旧例幣使街道標柱がある。鋭角に右折して142号線を西に進むと、すぐ右手に境郵便局がある。風景印は、赤城山
/ 渡し舟 / 町の冬の花・水仙 の図柄になっている。
|
| 旧例幣使街道標柱 |
境郵便局風景印 |
|
 |
旧例幣使街道石柱まで戻り東に進むと、すぐに社会体育館入口交差点がある。すぐに旧例幣使街道は右方向に進む。 |
| 旧例幣使街道分岐 |
|
| すぐに境萩原交差点で142号線に合流、南東へ進む。境宿に入る。 |
|
|
境宿は立場・間宿だったところで、文久3年(1863年)宿場になった。広瀬川東岸の舟着場として、室町時代から集落があった。那波と新田の境というところから境と呼ぶようになった。本陣:1 / 旅籠12 の規模であった。
|
|
 |
境萩原交差点からすぐの右手に、織間本陣跡がある。 / |
| 織間本陣跡 |
|
| すぐに境町駅入口交差点がある。左折して北へ進むと、5分足らずの突き当りに東武伊勢崎線・境町駅がある。 |
|
 |